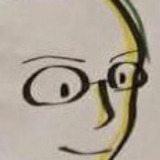コーダ あいのうたのレビュー・感想・評価
全733件中、461~480件目を表示
ただただ感動しました。
耳の不自由な家族と歌の才能に恵まれた娘の葛藤の物語。フランス映画『エール』のリメイクで、フランス映画は両親が漁師ではなく畜産をやっていたり多少の違いはあるものの原作の良さを残しつつ迫力では原作?を上回っているように感じた。
素晴らしい主人公の歌声と、音の聞こえない家族、そして静寂と下ネタのオンパレード。
そして全ての音が消えるあのシーンは圧巻。
もう映画の途中から泣きっぱなし。
あまりの迫力に手話を習おうかと思ったくらいで、アカデミー賞ノミネートは伊達じゃないですね。
私の感性が錆びついているのかも。
5つ星、4つ星の評価が多く、また泣ける作品とあったので、ものすごく期待して鑑賞した。結果はまぁ合格点は与えて当てもいいかなと思える作品だ。合格点とは、映画代金を払う価値があるかだ。
サンデンス映画祭で4部門の賞を獲得しているので、私の感性が錆びついているのかもしれない。聾唖者の家庭に生まれた健常者の苦労が描かれ、障害のない者にとっては知らない世界を垣間見ることができる。だが、私が好ましいと思ったのは、家族の犠牲になっている妹を思う兄の姿だ。結末はご都合主義だ。免許を取り上げられ、通訳もいないのに漁業の操業ができるのだろうか。
戦後ドイツを代表するバリトン歌手、フイシャーデスカウが音楽学校を受験した際、審査員がそのあまりの美声に驚愕したエピソードがある。それを知っているだけに、バークリー音大にあの声、歌唱力で合格するのも、ご都合主義だ。
嬉しかったのは、「青春の光と影」を聴けれたこと。50年以上も前に、深夜ラジオでよく流れていた。久しぶりに耳にして、懐かしかった。
心温まる作品
今の世の中
愛が溢れるファミリー!
最初jは、ラブストーリーメインかなと思っていました。
生まれながら共依存状態の家庭に育ったルビーが、家族との関係性を考え直し、自分の人生を選択する物語。
18歳という年齢でこれをできるのは、個人主義のアメリカならではなのかな。
素晴らしい歌声とキャスト、お涙頂戴のストーリーではないのに、自然と涙が溢れました。
合唱のシーンでの数分間の演出は、鳥肌がたちました。
ルビーの家庭状況は、両親・兄が聾唖であるという特殊な状況ですが、この身動きできない関係性はどの家庭でも起こりうるものです。
子どもが大人になる時期に、どう新しい家族関係を創るか・・・非常に大切なステップですね。
昨年末母を亡くし、この春2人の子どもたちが一人暮らしを始める私にとっては、とても良いタイミングの鑑賞でした。
ルビーの家族のように、笑顔で子どもたちを送り出します(*^-^*)
じんわり感動
素直に感動できる良作
フランスで大ヒットを記録した感動作「エール!」のリメイク作。
基本的なシノプスはオリジナル版と一緒で、演出やセリフ、場面構成まで同じ個所もあり、オリジナリティという点では「エール!」に劣るが、それを差し引いても前作同様、このリメイクも良作である。
ただ、本作はオリジナルとは設定が色々と変更されている。ハリウッドでリメイクされる場合、往々にしてこの設定改編で失敗してしまっている印象があるのだが、本作はそこが上手くいっている。
最も大きな変更はルビーの家の家業が酪農業から漁業に変わった点である。これによってオリジナル版にあった父親の選挙戦のエピソードは、苦しい立場に立たされる漁師たちの漁業組合への反発というエピソードに書き換えられている。両作品を見比べてみると分かるのだが、この改変は実に上手くいっている。正直オリジナル版の選挙戦にはどうしても唐突な印象が拭えなかった。平凡な酪農一家の男にとっては余りにも無謀な出馬であるし、それに賛同する家族の浅はかさな思考にも無理がある。それに対してこちらの反組合活動というのは、日々の経済的利害が直接絡んでくる話なので吞み込みやすい。
もう一つ大きな変更点は、弟のキャラが本作では兄に変更されたことである。オリジナル版の弟はどちらかと言うとマスコット的な存在で所々でユーモラスなエピソードをまき散らしていたが、本作の兄はコーダの進路を後押しするような頼もしさがあり、存在感という点ではかなり大きくクローズアップされている。これも上手くアレンジされていると思った。
他に、コーラス部の男子生徒とのロマンスも、オリジナル版は中途半端な描かれ方をしていたが、こちらはより明確な形で描かれていて観てて非常に気持ちが良かった。
このように本作はオリジナル版で足りなかった所、余り上手くいっていなかった所が見事にブラッシュアップされており、リメイク作品としてはかなり成功している方だと思う。得てしてこの手のリメイクは失敗することが多いが、今回はオリジナル版の良い所はそのままに、改良の余地がある所は大胆に改善しながら元々の作品のトーンを崩すことなく上手く作られていると感じた。
キャストではルビーを演じたエミリア・ジョーンズの好演が印象に残った。手話を使った難役を堂々と演じきって見せている。今後の活躍が楽しみな若手女優である。
また、母親役のマーリー・マトリン以外の家族は本物の聾唖者が起用されているというのも大きな見所である。手話のことは詳しく分からないが、父親と兄はそれぞれに好演していると思った。
ちなみに、マーリー・マトリンを言えば「愛は静けさの中に」で華々しく映画デビューを飾り、その後もテレビドラマを中心に長く活躍し続けている女優さんである。ただ、デビュー作以降今一つパッとした活躍を果たしておらず、少し寂しく感じていたが、それが本作で久々に見ることが出来て嬉しかった。
後でわかったのだが、彼女は女優業の傍らで聾唖の子供たちのために慈善団体の活動しているということだ。本作で本物の聾唖者をキャスティングするよう働きかけたのも彼女だったということである。
思えば、マトリンが出演した「デッドサイレンス」は中々良く出来たサスペンス映画だったが、その中で彼女は聾唖学校の女性教師役を印象的に演じていた。もしかしたら、その頃から彼女はこうした慈善活動の意識を持っていたのかもしれない。
可笑しくも素晴らしい家族と、躊躇しながらも思い切って外へ踏み出そうとする少女の一時を追った人間賛歌。
オリジナルのフランス映画『エール!』は未観賞。
両親と兄は聴覚障がい者で、主人公の歌を聴くことができない。
映画の終盤、合唱クラスの発表会に出向いた彼らは、主人公がステージで歌う声を周囲の観客たちの表情から想像する事しかできないでいた。
帰宅後、父は自分のために歌ってくれと娘に頼む。歌う娘とその頬や喉に触れて歌を感じようとする父。ここまでに両親の破天荒ぶりを見てきたので、このギャップある父の姿には胸が熱くなる。
このシークェンスは、音楽大学のオーディションというクライマックスへ物語を展開させる重要なターニングポイントだ。
主人公は、そのオーディションで家族のために圧巻の歌唱を披露するのだ。
この映画は、特殊な家庭環境にある少女と、それゆえの障壁の物語ではある。
だが彼女が、恋に憧れ、家族の無理解に悩み、周囲の誹謗中傷に憤り、好きなことに情熱を傾け、夢に向かって進もうとする普通の女子高生なのだ。
主演のエミリア・ジョーンズが、この多感で逞しい少女ルビーを瑞々しく演じていて、輝いている。歌も吹き替えなしのようだ。
ルビーの家族を演じているのは実際に聴覚障がいのある役者たちだという。凄い人たちがアメリカの芸能界にはいるものだ。
母親役はマーリー・マトリンだった。『愛は静けさの中に』以降も女優を続けていたとは、知らなかった。
父親が家族団らんの食卓で、母親が若い頃ミスコンで健聴者を押し退けて優勝したと自慢する。そりゃそうだろう、20歳の頃のマーリー・マトリンは本当に綺麗だった!
「また始まった」と、ルビーは呆れる。
ルビーが音楽教師の個人授業を受けるようになったことを家族は知らず、両親がルビーに頼み事をしたために個人授業に遅刻してしまう。教師からは二度と遅刻するな、時間を無駄にするな、と厳命されていたにも拘らずだ。教師に厳しく突き放された時、ルビーが「家族と共にいなかった経験がない」と吐露する場面が切ない。彼女の行動基準は常に家族だったのだ。
また、家族の漁船がトラブルに見舞われ、ルビーが通訳として乗船しなかったことを原因の一つにされた時の「私の所為なの?」という主人公の叫びも切ない。父親は「来られないといってくれれば通訳を他に頼めたのに」と言う。正論だ。親に断らずに遊びに行く、ハイティーンならごく普通の行動を今までの彼女はしてこなかったのだろう。
ルビーは発音がおかしいと同級生たちから笑われた経験を持つ。
歌が好きだが、一番身近な家族から評価を聞いたことがないので、人前で歌うことが怖い。
そのガチガチの殻を剥がしていく音楽教師の指導がユニークで熱い。
幼い頃から家族の通訳を務めることが当たり前として育った少女に、家族も頼ってきた。
だが、この家族は互いに支えあうと共に思いやって生きている。ふざけあって、いがみあって、恥ずかしい思いをしても、強い絆で結ばれた家族の姿は美しい。
夢を諦めようとするルビーに、兄が「家族の犠牲になるな!」と言う。
母親が、ルビーが生まれたとき“聞こえる”ことが分かって悲しかったと言う。「解り合えないと思ったから」
今思い出しても目頭が熱くなる…
すみません,嫌らしい観方をしたレヴューになっちゃった,高い評価をされやすい題材⁉︎
中途半端
心が暖かくなる作品
勉強になった
作中、聾唖の方が感じてる世界を感じる場面があったけど、想像すれば分かることなんだろうけど、驚いてしまった。
自分の知らない世界がまだまだたくさんあるんだと思いました。
歌声はすごいかっこいいし、V先生がとっても良かったです。
終わったときに覚えてるメロディーはなかったけど(記憶力のせいかも)。
最後の方、家族の問題がなぜ解決したのか分からなかったです。
なんで主人公がいなくても家がうまくいったのかな?
周りが聾唖者に歩み寄ったりしてる場面あったかな?
先生の手話のところかな??友達の子かな?私の理解不足か。。
あと、お父さんとお母さんが仲良しなのはいいけど、子供に下品な発言させたり、お兄ちゃんと友達との場面もあったり、性的表現あんなに必要だったかな。
映画館で笑ってる人何人かいたけど、私は笑えませんでした。
でも、全体的にはいい話だったと思います。
主人公の将来が楽しみです。
理解し合うって素晴らしい
ライブのシーンで全く音がせず…聴こえない世界って…聴こえない人は…って、想像するしかないんだけど。どちら側でもなく。
理解しよう、理解したい、と葛藤し続けたい。分断とか区別するのはそりゃあ簡単だ。
理解しようとしなくなったら、そこで終わり。
デュエット相手の男の子と理解しあっていく過程もよかったし、両親や兄貴の個性もたまらなく愛おしい。
惜しい
やがて聴こえる“饒舌な歌声”
映画を見終えてこれほど爽やかな気分を味わったのは久々ではないだろうか。自分の夢と家族の板挟みになりながらも、ひたむきに努力する物語は数あれど、“よくある映画”の一言で説明するにはあまりにも勿体ない作品だ。
聴覚障害というハンディキャップのある一家で一人だけ耳が聞こえる主人公・ルビー。彼女が持つ才能というのが歌という巧みなプロット。当然、家族に自分の才能を聞かせることはできないし、理解してもらうことも困難という物理的な壁が家族との間に生じてくる。
天邪鬼な私からすれば、これはお涙頂戴映画として斜に構えて見てしまうところだが、家族一人ひとりが曲者でありながらも、どこか憎めないキャラクターというのが地に足の付いた人物に見えて嫌味がない。家族劇はユーモアたっぷりで描かれ、娘の夢を応援できないのも、自分たちの生活の中で耳の聞こえる娘が家族にとって必要であるからこそ、というのも説得力が生じてくる。
しかし、次第に彼女が持つ才能を家族が理解し出す出来事が訪れる。自分の才能をどう伝えるか?どう理解してもらうか?その描き方、表現力にこそ、本作の映画としての魔法が宿っている。特に終盤のルビーの歌唱シーンは正に本作の白眉。どんなシーンかは是非ご覧になって頂きたいが、彼女があることに気づいた瞬間に、それは“饒舌な歌声”となって、家族を通り越して、スクリーンの向こう側にいる我々観客の琴線を優しく撫でてくる。ここで歌われる曲のチョイスがなんとも絶妙だ。
コロナ禍で閉塞感の拭えない世の中であるからこそ、こんなに純粋に夢を追う映画があって良いじゃないか、と思えるほどの爽快感。特にステイホーム、オンライン学習などで対面で授業できないと嘆いている若い学生たちにこそ、本作をオススメしたい。夢を追うことはこんなにも気持ちが良い。
ベるるるるるるナるるドゥ
最高だったなぁMr.V。リメイクなので少し抑えましたが、個人的には刺さりまくりで、終わった後も脳内が痺れてました。シンプルさが素晴らしい。お陰で、イラッとする人物の立ち位置(考え方)に入り込む隙間もあるので、色々と考えさせられましたね。邦画だったら引っ張りそうなクラスメイト関係があっさりなのも好印象。だもんで、お願いだから和製リメイクは踏み止まって頂きたいと切に願います。
あれこれ言ってますが一番心を掴まれたのは、気になる彼の序盤のTシャツでした。「キングクリムゾン!!しかもディシプリン!!」ってなり、危うく脳内脱線する所でございました(多少したけれど)。誰の趣味(チョイス)だったんだろうなぁ、良いよねキングクリムゾン。しかも評判的には今ひとつのディシプリンって辺りが、もうたまらん!…物語には全く絡みませんけどね(笑)。
泣けました泣けました。ただ…
CODA=child of deaf adult、親がろう者である子ども[健聴児]だと最初に説明される。
「生まれてきたあなたが耳が聞こえると知って、わかりあえない気がして不安だったわ。(健聴者の)母と(ろう者の)私がわかりあえなかったように」という母の言葉。
でも、主人公ルビー(健聴者とその両親、兄(ろう者)はわかりあって幸せにやってこれた。父と兄の漁業で、貧乏だけど一家なんとかやってこれた。話せないから魚を安く買い叩かれている気はするけれど。
ただ、家族には、ルビーが大好きな歌は、聞こえない。聞こえないからわからない。歌が上手だから、才能があるから家を離れて音楽大学へ行く道があり、ぜひセレクション受けるべきだ、と先生が言ったって、わからない。だって、聞こえないんだから。
家だって、思い切って始めた直接販売組合で大忙しだ。手話通訳ができるルビーがいなくなったら、どうなることか。
主人公ルビー本人も迷いに迷う。兄ちゃんは「家に縛られるな。俺に任せろ。これでも兄貴なんだから」と言ってくれる。でも市場に買い叩かれてるのを毎日見てきたし。母親を心配させたくもないし…
さあ、どうなるか?という話。とにかく、後半を観てほしい。学校で行われたコンサート。そしてはたして大学で行われるセレクションには行くのかどうか?!
まずコンサートで、無音になるシーンを堪能してほしい。そう、これがルビーの家族がいる世界なんだ。これを経験したら、俺たちも「わかってやれよ」とか安易に言えない。だって、聞こえないんだから。とにかく、ここ。そこで初めて俺たちは、主人公の家族たちを理解できる。
…そして、その夜の父親とのやりとり。
最後は書けないけど、夫婦でのSEX大好きな父ちゃん、あんた、最高だよ!
というわけで、ちゃんと泣けました!それはもう。
------
本作、作品賞候補に入っているけれど、自分としては脚本少し弱く感じる。オリジナルのフランス映画「エール」の農業を漁業に変えた舞台設定でのリメイクだけれど、"大いなる課題だと言ってきたことをほっぽらかし気味のままで結末" ってのは、やはりいまいちだと思う。そこは同じ課題でも畜産業のがまだなんとかなりそうで、「エール」のがましだったかな。
おまけ(妄想)
自分には、「最初に監督が描いたエンディングはこんな感じだったんじゃないかな」と思えるストーリーがあるけれど、「それじゃあ、最後に運良く人に押し付けただけに見えちゃうだろ」といった理由でNGとなった、と予測してます。
-----
2022/7/29追記。
「コーダ」と「エール!」 どちらも聾唖者と音楽。
娘が歌うことの道を進むと自分達は不便になる。歌うことの素晴らしさは、聴こえないので全く知ることはできない。体感できない。つまり自分たちには、娘がその道を選ぶことを肯定する要素は一つもない。
だけれど、娘がやりたい道を進むことを(納得し)祝福する。これって、けっこうすごいな。愛ってこんな感じなんだな、と思いました。
俺が「コーダ」に若干冷たいのは、「組合を立ち上げて直接売る。聾唖者の自分たちでやる」という取組みがいかに大変か、主人公なしでそれを続けられるか真剣に悩んでるという両親の不安をさっきまで描いていたのに、決断の後は、エンディングで「でも大丈夫でした」的な映像が流れるだけって、さすがにご都合主義過ぎないかなあ、と感じたためです。
「エール」より「コーダ」では、両親と兄の取組みが大規模化したので、違和感もだいぶ大きくなっちゃったんですね。映画の主題にはコンサート、オーディションの演出含めとても感動しています。あくまで個人の感想です。
全733件中、461~480件目を表示