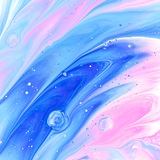コーダ あいのうたのレビュー・感想・評価
全733件中、1~20件目を表示
言葉が汚い彼ら、美しい音色を奏でる生活
聴覚障害者の彼らが聖人として描かれることなく、言葉は汚く、性的な人間として描かれているのがよかった。
過度に障害/障害者像を脚色することなく、普遍的なヒューマンドラマに翻案したからこそ、アカデミー賞で作品賞、脚色賞、助演男優賞を受賞したのだと改めて思う。
秋の学内コンサートのシーンで、ルビーの歌声を掻き消し、彼女の家族の音が聴こえない世界を表現していることはやっぱりいいと思った。しかもこの視聴覚経験は映画館で観たからこそより際立つものであった。
他にも彼らがルビーを搭乗させず漁をすることで取り締まりを受けるシーンとルビーが気になっている彼と遊泳禁止の海で戯れるシーンが編集で繋がっている。
家族が法を破って罰則を受けることとルビーが法を破って恋を成就させることが見事な非対称性を帯びていてそれもよかった。
そして音楽の力も凄いなと。
音は振動する波である。それらが合唱で共振する時、共通感覚が生み出され、美しい作品になる。また例え音色として誰かに届かなくても、音の波が聴いた者の心にしっかり届くのである。ルビーに触れて父が歌声を享受するように。
魚の不当な搾取に抵抗するために協同組合を組織することーしかもルビーの家族が当たり前にトップを務めているーも示唆深く、みてよかったです。
「伝わらない」もどかしさ、苛立ち、諦め「伝わる」喜び、希望、温かさ、繋がり
いろんな考察や感想が頭のなかで渦巻いているんだけど、何を言ってもきれいごとになってしまう。私はルビーの葛藤を理解できても共感することはできない。ルビーは幼い頃から健聴の「CODA」として役割を担い、その役割を果たさないと親兄弟が家族として機能できない。
言い方は悪いが「親」を人質に取られているようなもんだ。親として機能してもらうには自分がいなくてはならない。
ルビーの両親だって、愛のない人たちではない。精いっぱいの努力で地域で子育てをしてきて、聴こえない分の情報の少なさもどうにか補って生きてきたたくましい人た ちだ。ただ、自分たちが知らない世界に娘を送り出すって誰だって怖いよね。
本作では「歌」を家族の役割再編成のツールとして効果的に使っている。
もうひとつの「coda」へと向かって。
最後にマイルズも言ってたけど、ルビーはもう実家に帰って来なくていいと思うんだ。両親と兄貴もルビーがいたから考えなかったことを考えるときが来たんだよ。いくら親子だからって誰かが犠牲を払って成り立つことはホントはちゃんと成り立ってない。だからルビーはルビーの人生を歩くべきなんだ。
まとった鎧を脱ぎ去って
○作品全体
高校卒業という子供から大人へと変わっていく象徴のような時期に、家族全体が変わっていく…そんな大きな括りで見るならば、ああいう作品があったな、といくつか浮かんでくる。
しかし、家族のハンディキャップによって「大人」でいなければならなかった環境から子供や大人といった区切りを超えて等身大の自分に変わっていく…そんな本作は新鮮な気持ちで見ることができた。
主人公・ルビーに「大人」でいるという鎧を身に付けさせた家族が、その鎧を脱ぎ捨てさせる描写がまず良かった。
ルビーは最初からずっと大人でいることを脱ぎ捨てたかったわけではない。幼少期から父母のビールを頼んでいたのは、健聴者であるからという理由もあるだろうが、そうすることで家族唯一の健聴者、という疎外感を取り除こうとしていたルビーの望みもあったはずだ。コンサート前に母と話すシーンではその点核心をついていて、互いにルビーの疎外感を感じていたことを打ち明けている。打ち明けられる関係性になったからこそ、「大人」でいることをやめて、試験会場にも向かうこともできたのだろう。
父と兄はルビーが「大人」として振る舞っていることをそれぞれの立場で理解し、それぞれのやりかたでルビーを応援している。ルビーに対する兄の振る舞いは特に面白かった。妹の方が仕事や家族に貢献をしているけれど、その役割を奪うことができない。そんな妬みを抱えながらもルビーを認めている気持ちもあるし、やりたいことができないルビーの姿をもどかしくも思っている。妬みという負の感情があるからこそ、終盤の兄とのシーンはルビーに鋭く刺さる場面になっていて、自分のやりたいことに進んでいくきっかけにもなっている。こうした登場人物の行動の説得力が綺麗事な感情だけじゃないところに、人間味を感じてグッときた。
家族という一括りではなく、それぞれが考えるルビーへの気遣いがルビーを「大人」から卒業させていく。この見せ方が素晴らしい。
そしてルビーの中で隠していた「やりたいこと」を掬い取るマイルズとV先生の役割は、家族の距離感ではなし得ない、大切な役割だった。
特にV先生の指導シーンはどれも良かった。独特でありながら力づくでルビーの本心を引っ張り出そうとする指導が、ルビーを「大人」でもなく「シャイな10代女子」でもない、歌が好きな女の子にさせていく。この過程の描き方がすごく良かった。
「障害者の家族」ということがルビー自身を束縛するが、だからこそ手話を用いて特別な家族に届けることもできる。歌が好きな自分を見つめることができたからこそ、自身の置かれた環境を見つめ直すこともできた。鎧を脱ぐだけでなく、その鎧も自分自身だと消化したルビーの姿は、爽快感に満ちていた。
○カメラワークとか
・ピン送りが多い。「伝える」が難しいことを演出しているのかも。
○その他
・家族の対立を描く中盤の描写は少しステレオタイプな対立だなあと思ったりした。取材の日を伝えない母や監査の日に遊びにいってしまうルビーとか、行き違いのシチュエーションが急に出てきたような印象があって対立の作り方が粗く感じた。
母と朝食を摂るシーンでルビーが母は自己中だと話すシーンもあったから、それを伏線としているのだろうか。
最後の手話の意味は?
以前、同じようなシチュエーションの映画を観た記憶があるけど、それよりも判りやすく美しく、面白みのある映画だったと思います。開始して数分で世界観を全て描ききる明解さ、「ろうあ者の家族に囲まれ、話相手はラジオの音楽だけ、だからヒロインは歌が好き」という説明書きが一瞬で説明されていて、そこからスイスイと没入していきました。障害者の映画だからと云って、決して何とかポルノじゃない、下品な手話もシーンも満載w そして歌好きにもちゃんと見応え聞き応えのあるシーンも満載。
といって、ただ綺麗な歌声を流すだけじゃ無い、「ろうあ者にはどのように聞こえる(見える)のか」を再現するため、途中で音を消すという、ちょっと骨太い演出に関心。そして、最後のオーディションのシーンにも感動しました。それは手話というのは単なる言葉の代わりだけじゃない、言葉にならない想いを伝える手段にもなり得ると云うこと。ろうあ者にとって唯一の言語かも知れないけど、ヒロインの彼女にとって、小さい頃から家族とやり取りしてきたもう一つの言葉、もう一つの思い、彼女の体には私達と比べて二倍の厚みの辞書が埋め込まれていて、思わず言葉だけじゃ無く手話が出てしまう。だから、劇中で先生に想いを伝えられず手話で表現せざるを得なくなった。だから、最後のオーディションで想いが募り、思わず歌声と共に手話で表現してしまった。あの場に家族が来ていたからでは無いと私は想います。彼女はもはや、独り言すら手話で出てしまう、思わず手話で思いを語る人ではないのかと――。
最後の手話の意味は「あいしてる」なのだそうです。そして、エンドロールと共に流れる歌は彼女自身の生い立ち、家族と共に夜明け前から漁に出ていた頃を表した彼女自身の歌なのに気が付き、最後の最後まで聞き入り、字幕を読み込んでしまいました。また、タイトルのコーダが音楽用語でも有り、「Children of Deaf Adults」→「耳の聞こえない親のもとに生まれ、手話を第一言語とする人」という意味でも有るというのが面白いですね。
好感度満点の家族たちに魅せられる。
実際のろう者やCODAの人たちのこの映画に対する批判や違和感についての記事やコメントをいくつか読んだ。聴者である自分なりに想像して、納得のできることがほとんどだが、それでもどこまで理解が及んでいるのかは自信がないし、この映画を手放しで賞賛するのは、確かに聴者の特権かも知れないとも思う。
ただ、自分自身の感じ方を優先させてもらうと、ろう者の俳優が本当に生き生きと芝居をしている映画を初めて観た気がするし(『サウンド・オブ・メタル』の場合はむしろドキュメンタリー的な演出が光って見えた)、とにもかくにもあのやかましい家族たちへの愛着が湧いてくる作品に仕上がっていた。
終わりどころを見失いかけたように感じたり、恋人役の男の子が笑うくらい添え物感があったり、完璧な映画ではないが、好感度の高さでは2022年のアカデミー賞候補作ではピカイチかも知れない。
明るくてユーモラスな家族の風景が物語るものとは
今年のアカデミー作品賞候補作の中でも、見終わった後の感触の良さではピカイチ。家族の中で唯一健聴者である娘が、生まれながらに恵まれた美しい声と音楽の才能を武器に羽ばたこうとした時、家族それぞれがしがらみや常識にとらわれない自由な生き方を受け入れ、肩を押す。その過程で、なぜ、自分がそんな家族の言葉となって他者との橋渡し役を請け負わなければならないのか?と言う娘の不満や、彼女を引き止めたい母親の思いや、聞こえないことのハンデそのものが描かれるが、なぜか、それほど悲劇的な雰囲気はない。すべては、めちゃめちゃ明るくてユーモラスで、時々"奔放な"家族の風景にあると思う。この種の突き抜けたユーモアはアメリカ映画ならではだろう。
結果、この家族が持つハンデの大きさが逆説的に伝わり、一方で、我が子が年頃を迎えて自立しようとした時、世の親たちはいかにエゴを捨て、子供の未来を信じられるかというテーマが浮かび上がる本作。聴覚障害者の父親を豪快に演じるトロイ・コッツァーは助演男優賞を本命だが、惜しくも候補から漏れたものの、エミリア・ジョーンズ演じるヒロインと絶妙の掛け合いで笑わせる兄役のダニエル・デュラントの好感度が抜群だ。もし、興味があれば、YouTubeにアップされている撮影の舞台裏を映した映像の中で、撮影最終日を迎えたデュラントが号泣しながら共演者たちと抱き合うシーンがあるので見てみて欲しい。そこには、製作の過程で彼らの中に生まれた絆の強さがしっかりと残されていて、もう一度感動が蘇って来るはずだから。
あざやかなリメイク
フランス版『エール!』の精神はそのままに、いくつかのアレンジを加えてより洗練された家族ドラマに仕上がっていた。フランス版では畜産農家だった一家を漁師になっており、一家の息子は主人公の少女より年上に設定し直されている。物語の根幹に変化はないが、色々なアレンジが物語の深度を深めている。
朝早くからの仕事で疲れて、授業中に寝てしまった主人公が教師に起こされるシーンが印象的だ。急に起こされた主人公は、とっさに無意識で手話を繰り出す。彼女にとって手話は自然言語であることがよくわかる、さりげなく重要なシーンになっている。
家族で唯一健聴である主人公は、家族と世間の媒介役とならねばならない。聾唖の世界はそれ自体が1つの文化であり、『サウンド・オブ・メタル』ほど強く打ち出していないが、ある種の異文化衝突的な側面が描かれる作品でもある。
主人公の合唱を会場で見る家族は聞こえないがゆえに疎外感を体感させる演出は、フランス版でもあった。フランス版はわずかに風が吹いているみたいな音を残していたが、こちらは完全に無音を作った。どちらがリアルに近いのかはさておき、完全無音はより強いインパクトを残すなと思った。
人生を潤わせ、力強く後押ししてくれるもの
そうきたかと何度も笑い、心揺さぶられた。歌や家族やハンディキャップや自己確立などの要素を織り交ぜ、やがて無二のハーモニーへ昇華させていくひととき。観ている序盤はこの映画をなんらかの既存の枠組みに当てはめようとする自分がいたが、途中からそんなことは何の意味も持たないことに気づいた。本作を介すと、これまで見えてなかったものが見えてきて、聞こえてなかったものが聞こえてくる。最たるものと言えば、思いがけない手法で描かれるコンサートの一場面か。その瞬間、眼から鱗が落ちたというか、ああ、この映画を観てよかった、大きな気づきをもらえたと、感じた。何かが欠けてるとか、秀でているとかではない。あらゆる人々が各々のやり方で懸命に人生を奏で、なおかつ大切な人のハーモニーを全身で受け止め、応援したいと願っているーーー。家族というかけがえのない存在を抱きしめ、己の人生を前進させようとするバイタリティに満ちた秀作だ。
説得力ある伸びやかな歌唱。名曲『青春の光と影』の選曲も秀逸
主演の英出身女優エミリア・ジョーンズ、あまり記憶に残っていなかったのだが、プロフィールを見たら「ゴーストランドの惨劇」(2018)に若い時のベス役で出演していた。同作では黒髪だったこともあってか、10代後半の約3年でずいぶん印象が変わるものだと驚かされる(現在19歳)。そしてその柔らかな声質と表現力豊かな歌唱にも感心したが、8歳で子役としてキャリアをスタートさせ、9歳でミュージカルの舞台に立っていたとか。なるほど納得のパフォーマンスで、彼女が歌う映画をもっと作ってと切に願う。
両親と兄がいずれも聴覚障がい者で、家族で唯一健聴者の高校生ルビーが、合唱部顧問に歌の才能を見出され、バークリー音楽大学を目指す話。家族同士の会話や罵り文句に性的な表現をよく使う両親など、聴覚障がいのある3人を個性豊かなキャラクターとして描いているが、家業の頼りにされ夢を追うことを反対される子の悩みといった普遍的なテーマもわかりやすくストーリーに織り込まれている。基本的にルビーの視点で進むのだが、父兄を招いた高校の発表会、ルビーがボーイフレンドとデュエットして他の聴衆が盛り上がる場面で、無音になり家族3人の“聴こえない感覚”を疑似体験させる演出は胸に迫るものがあった。
ルビーが入試で歌うのは、ジョニ・ミッチェルの名曲『青春の光と影』(Both Sides, Now)。「若い頃の楽しい体験と、苦労や悲しみといった両面も、振り返ってみると幻のよう、人生なんてわからないもの」といった内容の曲で、映画のストーリーにもぴたりとはまっている。ほかにも合唱部で歌うデビッド・ボウイの『スターマン』など、選曲のセンスもとてもいい。
題名の「CODA(コーダ)」が「Children of Deaf Adults=“耳の聴こえない両親に育てられた子ども”」を指すというのは初めて知ったが、もちろん音楽用語で終結部を意味する「coda」にもかけたダブルミーニングだろう。唯一の健聴者として家族を支えた子供時代の終わりを描く本作は、ひとり立ちして大人の時代へと歩き出すすべての若者を祝福する応援歌でもある。
歌と脚本が良い作品は、かなりの確率で名作! 少しでも気になる人は是非見てほしい作品!
私が一番相性の良いと思っている映画祭にサンダンス映画祭があります。特に観客が選ぶ「観客賞」は割と名作が多い印象です。
本作は、数々の名作を送り出してきたサンダンス映画祭において、2021年に「観客賞」「審査員賞」「監督賞」「アンサンブルキャスト賞」という史上最多となる4冠に輝いているのです!
そして、配給権がサンダンス映画祭史上最高額の約26億円で落札されています。
これは分かりやすい事例では、2006年の「リトル・ミス・サンシャイン」があります。2006年にサンダンス映画祭で上映され、フォックス・サーチライト・ピクチャーズが当時のサンダンス映画祭史上最高額で配給権を獲得しています。
その後「リトル・ミス・サンシャイン」はアカデミー賞で作品賞、助演男優賞、助演女優賞、脚本賞の主要4部門でノミネートされ、助演男優賞と脚本賞を受賞。
本作「コーダ あいのうた」は、私の中では「リトル・ミス・サンシャイン」に近いイメージがあります。
特に物凄い事件が起きたりはしませんが、家族などの日常をユーモアを交えながら丁寧に描いているのです。
そして、本作は何といっても歌が良い。しかも、その演出手法も独自性があって上手いのです。
タイトルの「CODA(コーダ)」は、「Children Of Deaf Adults= “⽿の聴こえない両親に育てられた⼦ども”」を意味しています。
もっと具体的に言うと、父・母・兄との4人家族の中で、主人公の女子高生ルビーだけ耳が聞こえます。
そのような設定のため、「割と暗めな作品?」と思う人もいるでしょう。
ところが、脚本やキャストの演技が最高で、決して嫌な暗さは感じさせません。
本作は現時点ではアカデミー賞の前哨戦であるゴールデングローブ賞で作品賞(ドラマ部門)、助演男優賞にノミネートされています。
「リトル・ミス・サンシャイン」のようにアカデミー賞にも期待がかかりますが、もう本作は賞レースとかどうでも良いとさえ思えるくらいの「名作」だと思います。
なので「リトル・ミス・サンシャイン」が好きな人など、本作が少しでも気になる人には是非とも見てほしい作品です。
Another Welcome Drama on Deaf Community
Coda is the story of a a deaf family's hearing daughter. The father is a fisherman, and when the local feudal lord toughens working conditions, her service is needed. But her pursuit for a music academy becomes an obstacle. It sounds like a Disney movie, but it's more like Sound of Metal mixed with Manchester by the Sea. A welcome film for exploring society's inclusion of the deaf community.
心の障害をテーマにした映画作りは難しいが、身体の障害であれば精神は...
心の障害をテーマにした映画作りは難しいが、身体の障害であれば精神は健常だからまた違ったアプローチができる。これは4人のうち娘だけがろう者に生まれなかった家族の物語。街の人々は家族の存在は知っている前提で話は進む。障害を強調する描写はなく、でも当事者にしかわからない悩みを日常の映像で切り取っていく編集が上手い。そして健聴者の娘には「歌」の才能があった。ドラミ先生なら開始10分でエンディングまでお見通しの王道ストーリーながら、合唱部コンサートのエモ演出あたりからラスト30分は泣きっぱなし。映画はやっぱり演出なんだよな~。むしろこの演出でちゃんと泣ける自分がうれしかったまである。異例尽くしのアカデミー作品賞授賞も納得の秀作。
”ぼんやり”とした内容の映画
「聾」と「声楽」を題材にした青春映画。
主人公以外は聴覚に障害を持つ家族愛とその家族のせいでクラスメイトから奇異な視線で見られ、学校内でも自分を主張することができない聡明なヒロイン。
聴覚が原因で健常者から不当な扱いを受ける家族を助けるヒロイン。
実際に聾の唯一の「手話」のシーンでは無音になり、逆に登場人物の表情とジェスチャーを注視する斬新な手法に驚く。
ただ家族の知的レベルの低さ(未来を想像できない)や下品な台詞は実際に業務上従事したことがあるので「万国共通なんだな...」とは感じた(夫婦の営みや兄貴のS0Xシーンはいらん!)
音楽教師にその素質を見出され、トレーニングに励むも、少し身勝手な両親との板挟みにあい次第に苦悩するヒロインを見て少し胸が痛む。
最初に出てきた音楽系クラスメート(ゴボウ)の一体どこに惹かれる要素があったのか?
少し理解に苦しむ。
仲良くなった主人公のプライベート(両親のSEXを目撃して)をクラスメートに喋り、主人公はクラスの笑いモノにされてしまう。
ヒロインが賢く利発な分、クラスメートの思いやりの欠如が余計際立つ。
娘の将来を案じ、快く送り出すところはまあ、よいが脚本が音楽をモチーフにする以上、もう少し練った方がよかったかも。
素晴らしい作品
俳優陣うますぎる
脇役の演技がすごい
女主人公は可愛くて声が良いくらい。けれど、父親役の演技が凄い。手話で「戦士はヘルメットが必要だ」とかは爆笑してしまった。
今の時代のCODAとは環境が違っているだろうが、幼い頃から通訳をさせられるという辺りは間違ってはいない。
友人が兄を誘惑する。交わる辺りの演技も凄い。勢いが違う。それに比べると主人公は目立たない感じかな。
高校の合唱部発表会で音を消したのはGOOD!両親からはこう見えているという映像。これがあっただけで映画が締まった。
やっと鑑賞
落ち着いてゆっくり見たいと思っていたら、なかなか時間が取れずやっと見ることができた。
合唱で無音になる場面があるが、耳が聞こえない様子を実体験している気分になり、こんなにも疎外感を味わって生きているんだなと泣けてくるシーンだった。
父親にだけ歌う場面で、何とか娘の声を感じ取ろうとするところ、コンクールで手話を交えて歌うところなどで号泣。
何度も見たくなる素敵な映画でした。
家族の愛が深い
全733件中、1~20件目を表示