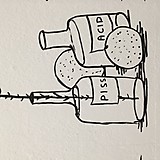コンパートメント No.6のレビュー・感想・評価
全92件中、41~60件目を表示
ロシア🇷🇺に、向かう列車は、暗い
ハラハラも、ドキドキも、湧いてこない。
暗く、重い、映画です
何も、事件も、起きなければと、思いながら、
見続ける
コンパートメント(閉ざされた空間のようだ)
無条件で、押し込められた感が半端ない
列車は、真冬のロシア🇷🇺の最北の街を目指す
それだけで、つらくなる
ハートフルな、話なんだけど
やっぱし、ホッコリはしなかった。
懐かしい風景そして時代!
ロシアの長距離列車の旅、幾度もしました。ムルマンスクまでは行ったことはありませんが、雰囲気も匂いも、ロシアの普通の人たちの温かさもそのまま伝わる映画でした。
予告見なくても、90年代初頭だってわかる仕掛けがあちこちに。
多分、今も変わらず運行され、飾らない素朴な人たちが暮らしているはずです。またロシアに行きたくなりました。この路線もいつか乗ってみたいです。
だんだん楽しくなってくる
初対面が最悪のリョーハ。粗野で無教養で酔っぱらい。こんなのと狭い客室で顔付き合わせた旅なんて!
それが、根は正直で悪気がないと分かってくる。と、顔がちゃんと映るんです。えっ、意外にハンサム?
あー、これ、カラシニコフの主役だった俳優さん。あちらはナイーブで真面目な役だったのに。
彼の背景は匂わせるだけで語られない。立ち寄るお婆さんはどういう関係なのか?彼が「友達ごっこ」とキレるのはなぜなのか。
でも、そんなことはどうでもいい。生まれた友情に、初めはずっとしかめ面だったラウラがいい笑顔でラスト。
それにしても、カセットのウォークマン、やや大きいビデオカメラ、携帯のない時代、ボロい建物、ガタガタしたドア等、いつの時代?80年代かな?と思ってたら、ラスト近くで「タイタニック見た?」って、90年代後半なの?と驚いた。
愛の告白がクソッタレ
モスクワから、北へ向かって一直線。世界最北の不凍港ムルマンスクまでの2,000kmの列車移動でございます。多分、今、賑わってると思うんですよね、ここ。ロシアへの制裁破りの諸物資輸送をするとしたら、ここが拠点だろうと。
男女の出逢いの物語です。Boy Meets Girlです。ちょっと歳は行ってます。いい大人の出会い系。ドキドキ要素ゼロ。萌え要素ゼロ。と言うか、北極圏の気温のごとく、むしろ (-)です。氷点下です。でも、なんかジワるロードムービー。
無骨なリョーハ。単純です。分かりやすい性格してます。ストレートです。女慣れしてません。口下手です。ついでに字も下手です。
第一印象はクソッタレ。徐々に惹かれていく女ごころが、やっぱり良く分からないんですが、ワタクシ的には。リョーハ画伯の、気持ちのこもった似顔絵に書き添えられた、愛の告白の言葉に。
そうだよ、最初、私は彼をクソッタレだと思ったんだよね。
なんで今は、チョメチョメなんだろ。可笑しい。笑っちゃうよ。
って言うオチにジワるという、四か国合作映画。いやー、なんか、このジワジワ来る感じが良いです。
好き。
結構。
結局、寝てしまった
頑張って最後の近くまで起きてたつもりだけど、二人が海岸に行ったあたりで寝てしまったのか、いつのまにか、リョーハがいなくなってた。
あんなに簡単にくっつくかな〜ってのが率直な感想。
この映画がそんなに評価される理由がよくわかりません。
あと、主人公の年齢も。
吹雪のち晴れ。
期待していたほどの内容ではなかった・・
タイトルなし(ネタバレ)
携帯電話はなく、テープによるビデオカメラ、ウォークマンなどが利用されるところから1990年代と思しき冬のロシア・モスクワ。
フィンランドから考古学を勉強するためにやって来た留学生ラウラ(セイディ・ハーラ)は、大学の文学専攻の女性教授のもとに身を寄せている。
周囲からは「下宿人」と揶揄される、いわゆる同性の恋人的存在だ。
そんなラウラは恋人の教授と一緒にロシア最北端・世界最北端のムルマンスクにあるペトログリフ(岩面彫刻)を見に行く予定だったが、恋人の教授が急に多忙を言い出し、ひとりで行くこととなった。
盛大な送別会のあとにラウラが乗り込んだ寝台車のコンパートメント6号の相席となったのは粗野なロシア人の青年鉱夫リョーハ(ユーリ・ボルソフ)。
リョーハの粗野で粗暴で失礼な態度に腹を立てうんざりするラウラは、途中駅で恋人の教授に電話をするが素っ気ない。
途中乗り合わせたフィンランド人男性は、人当たりは良かったが、思い出を記録したビデオカメラを盗まれてしまう。
挙句、ムルマンスクに到着したが、冬はペトログリフへの道路は封鎖されているという・・・
といった物語で、気の合わない男女が乗り合わせて・・・というのは『或る夜の出来事』から『恋人までの距離(ディスタンス)』までおなじみの趣向で、あらすじに書いたムルマンスクに到着するまでの寝台車でのエピソードや描写にはそれほど面白いところがありません。
(といって、まるっきりツマラナイわけではないですが)
俄然面白くなるのは、ムルマンスクに着いてから。
ペトログリフを観に行けなくなったラウラは、ホテルから紹介された別の観光ルートに出たりするのだが、思い断ち難く、結果、ムルマンスクの鉱山で働く喧嘩相手のリョーハを頼ることに。
そこからペトログリフを目指す行程が難儀で困難。
結果ふたりは、いわゆる「ハラハラドキドキを共にした男女は恋人になる」(by『スピード』)の格言どおり、豪雪の中のペトログリフ行の中で急接近することになります。
いやぁ、この終盤がいいんですよ。
なにがいいって、ペトログリフをカメラで写さない。
ペトログリフはあくまでマクガフィン。
こいつが素晴らしかろうが、素晴らしくなかろうが、そんなことはどうでもよいのよ。
重要なのは、雪投げ、浜に打ち上げられた廃船、そういう小道具。
生死は賭けないけれど、妙にハラハラしたりドキドキする、そういう類のもの。
最後の最後は、前半、ラウラがリョーハに教えた「くそったれ」というフィンランド語が「月がきれいですね(by夏目漱石)」となって現れるあたり、とっても微笑ましい。
なお、ラウラは30代後半の留学生という設定らしい。
どうりで、ちょっと薹が立っていると思いました。
北へと向かう列車に乗り海岸の岩に掘られた昔の絵を見に行く女性。乗り合わせた男との道行を描いたロードムービーです。
列車の旅・北国・出会い。…うん。
何かが起こりそうな予感。そんな雰囲気を
感じたような気がしたので鑑賞することに。
ですが…
正直なところ、
良く分からない内に終わってしまった感じです(…泣)。
最後まで理解できなかったのが
「行動の動機付け」 …う~ん
一緒に旅するハズだった恋人(?)に振られた女性。
自分一人でも行く と乗った寝台列車の部屋には
危なそうな雰囲気の漂う若い男。
タバコぷかぷか。酒をぐびぐび。
つまみが口からポロポロと落ちようがお構いなし。
(これと同室?)
速攻で車掌室に向かう主人公。「他の個室にして!」
しかし、他は全て埋まっていると言われ
仕方なく部屋に戻る。
男はロシア人らしい。エストニア人を嘲り
ロシアに無いものはない …と豪語するこの男
この列車の行き先の港で働いているようだ。
女性がフィンランド人と知り、話しかけてくる。
挨拶の言葉を聞かれたり、
「これを何という?」と尋ねてきたり。
何をしに行くのかを問われ、女性が答える。
「ペトログリフを見に行く」 と。
列車の行き先は「ムルマンスク」。
そこの海岸の岩に先史時代の「絵」が掘られていることで
有名らしい。ペトログリフとは、その画のことだ。
ただ、そこはロシアの中でも北に位置する極寒の地。
思い立ったら見に行ける そんな場所ではなさそうだ。
列車内や停車する駅の構内での場面が続く。
切符の無い旅の男を個室に入れてあげたところ
途中の駅でその男は立ち去っていくのだが
その男にビデオカメラを盗まれてしまっていた(らしい)
モスクワでの想い出が記録された大事なカメラを
盗まれて落ち込んでしまう彼女なのだが
ロシア人はそんな彼女を殊更に慰めるでもない…(んー)
いよいよムルマンスクに到着。
さあペトログリフへ …の流れかと思えば
「この季節(冬?)は通行止めだ」 …えっ?
行く手段が無いと言う …えっ?
となっているところに再びロシア男登場。
「車を手配した。一緒に行くぞ」 …えっ?
「連中は仕事をしない奴らだ」 …(そういう問題なのか?)
というわけで、 行けることになり …えぇぇ
目指すはブリザード吹き荒ぶ凍てつく海岸。
さあ、そこで見たものは…
とまあ、こんな感じなのですが、
何といいますか。達成感とか満足感とか。
そういったものが余り感じられない作品
との印象のまま終わりました。 ふぇぇ
ドラマと捉えるのではなく、
列車を舞台にしたロードムービーだった
…そう考えればいいのでしょうか。 はて
ロシア北端の海は寒そうでした。
◇あれこれ
作品の背景等も良く分からないまま鑑賞し
すっきりしないまま終わってしまったのが悔しくて
この作品のコトを少しだけ調べてみました。
■ペテログリフとは?
岩石や洞窟内部に掘られた文字や絵の彫刻こと。
ロシアに限らず、アメリカのユタ州やハワイなど
世界の各地にあるみたいです。海岸限定ではなさそう。
日本にもあるらしいです。
■ムルマンスクって?
フィンランドの北部と国境を接するロシアの州。
アイスランドよりも高い緯度にあります。寒いハズ。
港町です。接する海は北極海…ではなかった。
北極海はさらに一段北です。 凍えます。ぶるぶる。
■モスクワからムルマンスク
鉄道で1日半がかり。1,488㎞あるとのこと。
日本国内の場合、青森市から山口市まで
車での走行距離(日本海ルート)が 1,476㎞。
本州の端から端までの距離。
うーん。遠いです…。
座りっぱなしだと尻が痛くなりそう…。
◇最後に(…というか 願い)
2021年の制作で2023年の公開の作品。
制作が4か国の合作。
フィンランド・ロシア・エストニア・ドイツ。
…うーん。
政治と芸術は分けて考えれば良いのでしょうけど…。
「T34」を心から楽しめる時代に戻りますように。
☆映画の感想は人さまざまかとは思いますが、このように感じた映画ファンもいるということで。
恋人のドタキャンのせい一人でペトログリフ(岩面彫刻)を見に旅に出るロードムービーだが、汚れと暖房で曇った車窓から見える低層の灯りのように、作品全体がほんのりと懐かしい。
主人公ラウラの不機嫌な顔が、旅をすすめるにつれ和らいでいき、同室の粗暴な男との関係も変化してゆく。途中の珍入者や車掌なども含め、人は見かけではわからないという示唆も興味深い。
ロシアの古びた列車、サービスの行き届かないお国柄、極寒の地とは反対の意外と人懐こく優しい民族性など、さりげない表現で伝わる演出の上手さ。吹雪の中での雪合戦は撮影も困難を極めただろうが、クライマックスに相応しい熱を感じる。
オープニングでのパーティーシーンではラウラと恋人の関係性を映し出すが、この列車の旅は、高等教育を受けた知的階級への憧れを「愛」と錯覚していたラウラがそれに気づく旅でもあったのだ。
ウォッカ、ビデオカメラ、似顔絵、行き先、「愛してる」、など、たくさんのヒントをちりばめながら自然にそれらがつながってゆくストーリーに唸った。
この監督の前作「オリ・マキの人生で最も幸せな日」もそうだつたが、フィンランドの音楽事情はこういう感じなのか?それともカウリスマキを意識しているのか。これもまた楽しい。
いちばん映画らしい映画ですかね
言語化すると陳腐になる
映画館で鑑賞。
この映画が好きになりすぎて言葉にするのが難しいし、言語化すると陳腐になるだけな気がするような、すばらしく映画らしい映画だった。
ラウラとリョーハに生まれた絆を恋やラブストーリーとゆう言葉では表現してほしくなくて、あらゆる暗い問題に塗れた現代にとっての希望や人類愛のような、ひらけた明るい物に感じた。
この映画がウクライナとロシアの戦争の前に撮り終わっていて、公開されたときには
戦争が起こってしまっているのが悲しい。
描かれてる時代は違うが、この戦争に送り込まれている人はリョーハの様な人なのではと思わずにはいられない。
日常に絶望したときに、心の支えになるのが映画や本や漫画などの文化的な物だと思っている自分にとって心の深いところを揺さぶられる作品だった。
映画を観た映画の帰り今まで観た映画のあらゆる寂しいさや孤独なシーンをなんだか思い出してしまって、私はこうゆう孤独な映画が一番好きなのかもと思った。
好き嫌い分かれるかな。
あらすじとレビューでほぼほぼ全編を網羅。
起伏が少ないというか、だから?の先がない。他の方が何を見せらてるのかいう感想を述べていたが分からなくはない。もどかしいともまた違う…今みたいに直ぐにSNSでつながれる時代じゃないからこそ関係性。
ロードムービーでもあり青春映画でもある。
ウトウトしたけど嫌いじゃない。
ロシア人青年に感情移入するとダメージでかくなるストーリー
999を想起させるロードムービー&ラブストーリー
1990年代、ソビエト連邦が崩壊して現在のロシア共和国が誕生して間もない時代のロシアを舞台に、フィンランドからモスクワに留学していた主人公のラウラが、ロシア北部の街・ムルマンスクの郊外にある岩面彫刻であるペトログリフを観に行くため、何日も夜行列車に揺られて旅をするというロードムービー、かつラブストーリーでした。僅か20~30年前の時代設定なのですが、夜行列車はもう少し前の時代の雰囲気で、約1500キロ離れたモスクワ→ムルマンスクを、3~4日掛けて移動します。途中駅のひとつでは、列車が一晩駅に停車するため、ラウラは偶然同じ客室に乗り合わせたロシア人青年・リョーハと、リョーハの知り合いの家まで行って宿泊します。この辺りの雰囲気は、まさに「銀河鉄道999」そのもの。いろんな出会いがあり別れがあり、トラブルも発生する。「999」と違って、本作の車掌さんは当初かなり共産官僚的でサービス精神皆無でしたが、時間が経つにつれて徐々に人懐こさが現れて来たりして、もう「999」の世界を思い出さざるを得ない流れでした。
また特徴的だったのは、殆ど音楽が流れなかったこと。この辺りはゴダイゴやささきいさおの歌う名曲が象徴的だった「999」とは対照的でしたが、音楽がない替わりに、列車の動く音だったり、車のエンジン音だったり、吹雪や荒波と言った自然の音が、いわばBGMとして本作の骨格を創っていて、それがロシアの寒々とした冬の景色や登場人物たちの鬱屈とした心情と見事にマッチしていて、実に見事でした。
さらにラブストーリーとしても、美人の女性大学教授であるイリーナに実質的にフラれたラウラと、粗野で下品で子供っぽくて無教養なリョーハが、数日間の列車の旅と、さらには岩面彫刻・ペトログリフを見に行く過程で心を通わせていくに至るまで紆余曲折とした物語の流れは、非常に上質であり、唸らせる創りでした。
そして何より良かったのは、登場人物たちの表情や態度。心の内を、言葉だけでなく表情や態度で繊細に表しており、変にワザとらしいこともなく、自然とラウラとリョーハの心情の変化が伝わって来て、こちらも心揺さぶられました。
また、時折表現されるコメディチックな演出も、緊張と緩和という意味で大変効果的だったと思います。
ただこんな素晴らしい映画なのですが、残念ながら2022年2月にロシアがウクライナに侵攻し、今でも戦禍が続いています。本作は、フィンランド、ロシア、エストニア、ドイツの4か国の合作ということになっていますが、製作されたのが2021年だったことから、普通に完成したものと思われますが、時期が少しずれていたら、本作の製作は難しかったのではないかと思われます。ご存知の通り、ウクライナ侵攻後、従来中立国の立場にあったフィンランドはNATOへの加盟を申請しましたし、NATOに加盟しているドイツやエストニアは、ロシアと対立関係にあります。一日も早く、こうした作品が共同で製作できる平和が戻ってきて欲しいと願わずにいられません。
最後は少し映画の話から逸れてしまいましたが、本作は今年観た映画の中で一番面白かったので、評価も★5としたいと思います。
今は亡き………
凄く良かったわけではないけど退屈でもなく、なんだか誰かと語りたい!!って訳でもないけど、感想を言い合いたい映画かな。
彼女は自分を持った人が好きなのかな?同性愛者って訳でもないのかも。自分に自信がないから確固たる自分を持ってる人に惹かれてしまうのかも。リョーハは賢くないし幼いし粗野だけど、なんか確固たる自分を持ってそうだもんね。
バックパッカー羨ましい、と思った。
でも今の世の中あんな風に他人と交流できるかな。世の中のせいだけじゃなくて自分のせいでもあるけど、スマホいじって、イヤホン耳に入れて他人と交流しなくても楽しく生きていける世の中。
他人の部屋に堂々と居座る親子とか、親切にされたのにもの盗んでく男とか、なんか……酷いながらも酷すぎない人との触れ合いがある時代だったんだろうなぁ。と現代人?の私は思いました。
家テレビで見たらスマホいじってしまうのかも。映画館で見る映画。特別綺麗な景色が出てくるわけでもないのだけれど。静かに退屈にゆっくり観たい映画かな。
もはやリョーハがいなくなってからペトログリフどうでもよくなってるや...
全92件中、41~60件目を表示