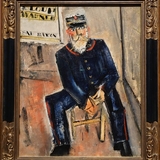コットンテールのレビュー・感想・評価
全98件中、1~20件目を表示
よく見れば、良い家族、良い映画
嫌味無く、とても良い家族の良い映画だったと思います。
実はあまり広告の説明を読まずに、丁度良い上映時間を選んだだけで映画館に飛び込みました。上映開始後、内容はすぐに理解。誰も居ない席のグラスにビールを注いで、万引きしたタコの寿司を食べる。それだけで、どんなお話は大体読める。とても判りやすい。思い出されるのは出逢った頃の妻の姿。とても愛らしい昭和美人。そして弔いのビールを飲み干して、息子に連れて行かれた、その妻の葬儀。
なんだか、うさんくさい駄目親父だと思ってたけど、出逢った頃の妻を未だに胸に抱くその姿。ぶつかり合いながらも、その父を見捨てない立派な息子。とても良い家族。とても良い話。悪い人は全く出てこない(電車で乱痴気騒ぎで絡んできたイギリス人も含めて)スムーズに理解出来る良い映画だったと思います。
誰にも任せられず、しっかりと胸に抱えた遺骨のバックも、散骨を終えれば、やっと肩の荷が下りたのでしょう。地面に下ろして息子夫婦や孫と一緒にウサギを追って駆けていくエンディングは素晴らしかったのですが、これは誰もが辿る物語。スタッフのエンドロールに強い重みを感じました。
リリー・フランキー演じる妻を亡くした男がとてもリリー・フランキーら...
リリー・フランキー演じる妻を亡くした男がとてもリリー・フランキーらしい役だと思った。
亡き妻(母)の遺言に導かれた先がイギリスの地で、 新たな一歩を踏み出そうとする夫と息子夫婦の物語。
主要な登場人物はみんな良かった。
↓引用
イングランド北西部に広がる湖水地方は、イギリスで最も風光明媚なリゾート地として知られる。その起伏に富んだ美しい自然の風景をカメラに収めた本作は、日本人キャストとイギリスの新鋭監督パトリック・ディキンソンがタッグを組んだ国際的な合作プロジェクト。東京からイギリスへと舞台を移しながら、家族の愛と再生を紡ぎ上げたロードムービー仕立てのヒューマン・ドラマである。ワールドプレミアとなった第18回ローマ国際映画祭では絶賛を博し、最優秀初長編作品賞に輝く快挙を達成した。
クソまみれ
途中までは大したことない物語だと思っていたのに、回想シーンになるとグサリときた。やはり認知症患者を扱った作品では自分の家族のことを思い出してしまうのです。失禁や思わぬ排便・・・まさしくクソまみれでした。映画の中では父親であるリリー・フランキーが息子錦戸亮に見せないようにしたけど、逆に息子の方が手厚く看護するシーン。ちょっとだらしない父親の姿が真に迫っていた。
もひとつ、入院してからの妻・木村多江の演技。認知症とはいえ、一瞬だけ正気に戻ったような表情が光っていた。あの段階では正気に戻る瞬間が何度もあるはず。その表情が父の脳裏に焼き付いているに違いない。そして忙しさのために面倒を見ることができなかったという後悔の念が彼をも病ませるのだろう。最初はリリー・フランキーが認知症を患ってるのかと思ったほど。
イギリスで迷子になって世話になったジョンと娘メアリーの優しさにも心打たれました。境遇が似ていたせいもあるけど、普通じゃそこまで優しくできないよなぁ。
勝手なじいさん
木村多江さん、認知症患者の役をされておられ、
やはり厳しい場面もありなかなか大変と感じました。
幼い頃からピーター•ラビットの絵本?
日本人ならもっと違う作品だと思うので違和感。
しかし、
あのお写真は子供の頃行った時のもの?
家族でイギリス🇬🇧に傾倒されていたら、
ピーター•ラビットも有りかも。
若い頃の初めての出会いを挟むあたり、
兼三郎が明子をずっと愛し続けていることがわかります。
でも、結婚して息子の慧ができてからの
慧との関わりが描かれておらず
直ぐに明子が亡くなった前後のシーンに
なっているので、慧との親子関係が不明。
ずーっと息子慧と疎遠で明子の逝去で再会したなら、
明子の手紙によりイギリス🇬🇧に行くという
父親に妻子連れて一緒に行くって、
なかなか理解しにくい。
ついて行くなら、慧一人でしょう、と思うけど。
この兼三郎じいさん、わがまま過ぎだし、
イギリス🇬🇧なのに、
日本🇯🇵のどこか片田舎ぐらいに行く感じで、
一人間違った列車に乗り、
なぜか親切なジョン&メアリー親子に依存。
ジョン父さん、正体不明な外国人のじいさんを
よく娘一人と一緒にして出かけるなぁ、と思った。
そして、兼三郎ずうずうしい。
だいぶお世話になったけど、
息子たちが来たらアッサリ別れて目的地へ。
雨降りの暗闇の中、わがままはるじいさん。
嫌がる慧と妻。
途中慧の妻に仕事の電話☎️、
何の効果を狙ってだろう。
だけど、湖の目的地見つけた兼三郎のあとを追い、
慧が来て二人でズボンを捲り上げることなく、
入って散骨したら、父子仲直り?
戻ると慧の妻も上機嫌?
この辺りついていけませんでした。
木村多江さんの患者の演技にはお疲れ様と言いたい。
迷子のコットンテール
リリー・フランキー演じる作家大島兼三郎は、おそらくノーベル賞作家大江健三郎がモデルになっている。長男の大江光は脳瘤(脳ヘルニア)のある障害者で、その実体験をもとに『静かな生活』などの小説を書いている。本作の兼三郎も妻の明子(木村多江)が認知症を発症自宅介護を選択するものの、責任を最期まで全うすることができなかったことを悔いていた。その贖罪からだろうか、息子慧(錦戸亮)家族とも疎遠になっている兼三郎だった。
この兼三郎、魚河岸で奥さんの大好物タコブツを無断で失敬したり、英国湖水地方のとある駅で放置されていた自転車をネコババしたり。手癖の悪いところがあの“ピーター・ラビット”にクリソツなのである。映画タイトル『コットンテール』はピーターに3匹いる妹のうちの1匹の名前であり、妹たちにたらふく野菜を食わせてやりたいと人間の耕す畑から無断で拝借する様子が面白おかしく描かれているそうで、やがて“自由”には“責任”が伴うことを学んでいくのである。
つまり、イギリス人映画監督が日本人俳優を使って撮りあげた長篇処女作は、家族が障害者を受容するにあたって生じる責任について言及した作品ではないのだろうか。途中兼三郎が迷子になってお世話になる英国人とその娘が登場するのであるが、娘の年齢からして母親が何かしら病気を患って早逝したらしいのだが、その介護生活にはあまり触れられていない。しかしながら本作は、障害者や認知症患者を受容する(万国共通の)家族の葛藤をテーマにした作品であろう。
兼三郎の場合、仕事に忙殺され家族をかえりみなかった疚しさをして、息子とその家族をわざと過酷な介護生活から遠ざけたようなところもあり、息子の慧としては(自分勝手に一人で責任を負うようなまねをせず)もっと自分に頼って欲しかったというのが本音ではなかったのだろうか。映画としては、原作者ビアトリクス・ポターよろしく湖水地方の美しい湖へ明子の遺灰を散骨するロマンチックストーリーになっているため、介護問題への言及が多少薄まってしまった気がする。
映画ラストは、草むらに逃げ込んだ“コットンテール”を家族で一緒に追いかけるシーンで閉幕する。ここ湖水地方では犬も歩けば必ずや遭遇する迷子のウサギちゃんらしく、徘徊して行方不明になりかけた明子をそれに重ねているのだろう。一人で湖を探そうとするから道に迷うのであって、みんなで仲良くウサギちゃん探しゲームを楽しむくらいのノリで介護に望めばいいのである。この世の不幸をすべて背負子んだかのような兼三郎の頑なな態度こそが、家族を破壊する元凶なのだろう。
ウィンダミア湖畔への旅‼️
妻を亡くした男が、妻の遺言でイギリスのウィンダミア湖への散骨に、疎遠になっていた息子夫婦と共に出かける・・・‼️要は家族再生の物語です‼️イギリスの美しい片田舎やウィンダミア湖を映し出した映像はホントに美しい‼️ただ少し人間ドラマというか、キャラ描写が雑に感じました‼️妻が「ピーター・ラビット」の大ファンで、かつて暮らしたことのあるウインダミア湖へのこだわりはイイとしても、直接の死因は何の病気だったのか⁉️主人公と息子はなぜ疎遠になってしまったのか⁉️そしてリリー・フランキーのキャラ‼️魚屋でタコの刺身を万引きするし、イギリスで明日の汽車を予約してるのに「今日出発しよう」と頑なに主張したり、夜遅い豪雨の中を息子夫婦の事などお構いなしに湖を探し続けたり・・・‼️めっちゃ自分勝手でイヤな奴、訳分からん奴‼️そう思わせるリリー・フランキーの演技はスゴいと思う‼️ただあまり主人公のキャラに感情移入出来ないまま映画も終わってしまった‼️上映時間も1時間30分と短いので、あと30分ぐらい時間をかけて、キャラの詳しい背景や人間関係を掘り下げたほうが良かったと思います‼️
愛妻を亡くした初老の夫の寂しさを切々と
それを形にして演じるリリー・フランキーがいました。
・・・髭が白くなったなぁ。
・・・不安げな表情、上手いなぁ、
と改めて感心する映画でした。
《ストーリー》
長年アルツハイマーを患っていた妻(木村多江)が亡くなった。
看病疲れと喪失感から茫然自失の夫・謙三郎(リリー・フランキー)
看病を一人で抱え込んでいた謙三郎は、葬儀の迎えに来た一人息子の
彗(トシ=錦戸亮)に喪服のネクタイまで形作って貰うほど疲れていた。
3年前までは意思疎通も出来た妻。
その明子の遺書を住職から渡される。
そこには「遺骨をピーターラビットの里、
・・・ウィンダミア湖に散骨して・・・」と
書いてあった。
1966年に撮影した明子が若かった頃に一度だけ訪れた際に写した
一枚の写真。
それを頼りに、息子と嫁(高梨臨)孫娘の4人で
謙三郎はイギリスに向かった。
異国の地で謙三郎は自分の無力をまざまざと思い知る。
息子任せにしたせいでウインダミア湖の正確な位置も頭に
入れてこなかった。
ロンドンのホテルで、気持ちばかりせいて、若い人のペースに
乗れない。
単独行動で湖水地帯を目指すものの、反対方向の電車に乗っていた。
慌てて電車を降りて、とある駅で夜明かしすることになる。
ここで謙三郎がユニークなのは、自転車で闇雲に走り出すこと。
川崎では値札の付いてないタコのぶつ切りを、持って来たり、
英国でも誰かの自転車に勝手に乗り、どこかで乗り捨てる。
朝から缶ビール、今時なのに、歩きタバコ、くわえタバコ・・・
常識が無くて、なんかハラハラする。
英語教師をしていた過去(いつまでだろう?)
発音がめちゃめちゃカタカナの棒読み。
(日本語を封印されたリリーさんは、手足がもがれたように
心もとない)
おまけにガラケーときている。
(いつの時代の話なんだろう?)
やはり高齢で地域社会から孤立していると情報から取り残されている
姿が浮かび上がる。
湖水地帯から300マイルも離れた場所で雷雨に濡れて途方に暮れていたら、
牧場主の父娘に親切にされる。
(お風呂まで入れるなんて、私にはとても出来ないよ)
(そうでもないかな?人畜無害そうだから、もしかしたら出来るかな?)
謙三郎は息子が書いたくしゃくしゃにした電話番号メモに、
なんとか公衆電話から連絡をする。
良く巡り会えたものだよ。
レンタカーにカーナビがついていたってどうやって
探したんだろう?
奇跡のように思える。
一枚の写真から、場所を特定するなんて不可能だ。
地形も変わる、樹木なんか生え茂ったり朽ち果てたり流動的だ。
ウィンダミア湖地域は2017年に世界遺産に登録されたという景勝地。
ピーターラビットの作者ビアトリクス・ポーターが、こよなく愛した
湖水地帯だ。
【安堵】
息子とも再会して、謙三郎がここで良いと満足した地に遺灰を静かに
撒いて沈める。
嫁と孫はピーターラビットそっくりの兎を見つけて、はしゃいだ声を
あげている。
好むと好まざるに関わらず、優しい息子の側を、離れないで、
「老いては子に従え」
この言葉は真理である・・・そう謙三郎も思っただろう。
(寡黙な映画でしたので、心情を推測しました)
鑑賞後1時間は続く
ほのぼのロードムービーかと勘違い
いつも通り前情報なしでみましたら、完全に勘違いしておりましたが、勘違いして観に行ってよかったです。こんなにシリアスだと知っていたら観に行かなかった。
喪失感にまみれた兼三郎の表情に続き、明子とのみずみずしいはじまりの時が散りばめられ、子育てが終わり穏やかな二人の日々。明子の病気が発症し、病院の帰りに二人で入った喫茶店で見せる明子の不安。
「迷惑をかけるだけの存在になっても、生きていかなくちゃいけないのかなあ。」
残酷なことにその不安は現実となり、介護の日々は時に家族にとっては辛いものとなる。辛いを通り越して惨たらしいまでに感じられたのは、鬼気迫る演技のせいか。
怖かった。きっと当事者の家族と同じ、怖かった。
明子の最後の願いを、紆余曲折ありながらも家族で叶えたのちに見つけた「Rabitt」は、明子のありがとうだったのか。夕焼けはいつだって美しいけど、大雨の後の夕焼けは尚更美しい。
認知とは
there were four little Rabbits,and their names were-Flopsy,Mopsy,Cotton-tail and Peter
ビアトリクス・ポターの「The tale of PETER RABBIT」の冒頭の一節である。(この映画にも出てくる)コットンテールはここから。
ポターは世界中で知られた作家であるが特に日本に熱狂的なファンがいて屋敷があったウィンダミア湖は聖地巡礼の場所になっているそうだ。彼女は亡くなった後、遺言で湖水地方の何処かに散骨された(場所は非公開)木村多江演じる明子はポターのファンという設定で散骨もそこから連想したということなのだろう。
長く連れ添った夫婦というものは不思議なもので互いにかばい合い、自分たちの子供であっても間に入ってこられることを嫌がるようなところがある。オムツを外してしまった明子を兼三郎が風呂場で洗ってやるところ、たまたまやってきた息子のトシを憲三郎がなかなか部屋に入れない。私の亡くなった両親もあんなふうだった。
一方で、この映画では兼三郎を中心とした人と人の関係がなにか独特な感じがした。ベタベタはしていないし、かといっても乾ききってもいない。微妙な距離感があるというか。兼三郎からみた息子夫婦との関係については、トシとさつき、孫娘のエミまでがみんな美男美女であることがその印象を強めているような気がする。兼三郎が旅先で助けてもらう農園の親子との関係も不思議。ありえないほど親切にしてもらったのに別れ際はあんなにあっさりしてて良いの?と思った。こころなしかリリーさんもいつになく無頼な印象がない。
イギリス人の監督だからですかね。悪くはないけど。このあっさりした感じも。
最後に一つ。明子の両親は湖バックの写真にしか登場しないのだけどエンドロールでは母親役が真矢ミキとクレジットされていたように見えた。見間違いかしら。
ロードムービーの形を取っているが…
出掛ける際、隣人に挨拶されても返事もしない兼三郎。電車では肩がぶつかった乗客に謝りもしないし、市場では店主の目を盗んで蛸を万引きする。こうした冒頭からのシーンで、主人公がかなり自分本位の偏屈な男だという事が伝わってくる。しかし馴染みの寿司屋に入ったあたりで、彼が妻を亡くしたばかりで平常心を失っていたことが分かる。ここまで台詞は少ないが、兼三郎の置かれた状況と明子への愛情の深さが窺い知れる良い導入だ。そしてイギリスで迷子になってしまっても、彼ならさもありなん、というエクスキューズにもなっている。
途中、何度か回想シーンも挿入されるが、過去は過去で出会いから死までが時系列に沿って語られるので、混乱することはない。ロードムービーの体をとっているが、本質的には避けていた息子といかに向き合い、妻の死をいかに受け入れるかという家族の再生の物語であり、特に後者の比重が大きい。
象徴的なシーンがある。明子の臨終の際、病室のドアは完全に閉まってはいない。医者や看護師に声を掛けようとすれば可能なのである。しかし、兼三郎はそうしなかった、と言うよりも部屋の外は関係なかった。彼にとって妻との関係が唯一無二の物であり、外界とは(たとえ、それが息子であっても)積極的に関わるつもりはなく、ましてや明子の死後は閉ざされた世界にひとり住んでいたに違いない。だから、言語が異なり意思の疎通が取りづらい異国において、初めて自分と向き合うことが出来たのだ。
他人に触られることを拒んでいたバッグは妻への執着を表しているのであり、見つかった写真の湖は過去のメタファー。そう考えると、その湖を見下ろし、あれほど手放さなかったバッグを置いて、家族の呼びかけに応じて丘を登った兼三郎は、新たな一歩を踏み出す勇気が持てたのだろう。切なくも愛おしいラストシーンだ。
確かに、別に舞台が湖水地方でなくても成立する物語ではある。しかし、よく見ると監督はイギリス人。おそらく、洋の東西を問わず共通な家族の和解というテーマ(高齢者大国日本を象徴する介護問題も含んでいるが)に、自分自身のアイデンティティでもあるイギリスの田園風景を盛り込んだのではないか。それも納得の美しい映像と、出演者の演技が心に沁みる作品だった。
父と息子はわかりあえるか?
健三郎が愛おしい
イギリスに期待し過ぎた
キャスティングが良かった
全98件中、1~20件目を表示