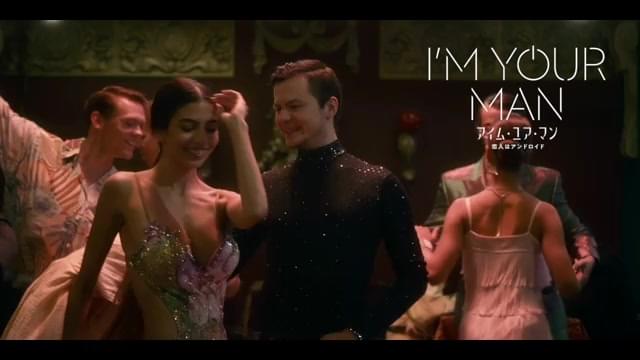「超真面目なドイツ人」アイム・ユア・マン 恋人はアンドロイド R41さんの映画レビュー(感想・評価)
超真面目なドイツ人
解説にはラブストーリーとあったが、この作品をジャンル分けすればSFになるように思う。
そしてこの作品は、様々なモチーフを使いながら、人型ロボットと人間とは「伴侶」になれるのかどうかを視聴者に問うている。
問うているので物語は多義的に感じるし、そのように作られている。
冒頭 主人公であるアルマがとある会社に選ばれ、こことについて意見報告を求められることになる。
アルマのほかにも「博士」とか「ドクター」と肩書きのある人物たちがこの実験に参加している。
近未来SF
そして少し前に言われたシンギュラリティ
そして昨今身近になってきたAI
当然ロボットなので、その技術はAIとブレインマシンインターフェイスのようなものだろうか。
これを開発した会社の意図は不明だが、表面上描かれているのが人間とロボットが伴侶として生きていく未来。
その根拠として、アルマの実家にいる認知症の父の介護の問題が設定されていた。
このSFが秀逸なのは、この近未来の技術と考え方を受け入れられるのかどうかということを映画の力を使って、アルマの過去現在、そして来るべき未来を想像しながら「考えさせる」構造になっていることだろう。
だからこれに関する答えは、視聴者個人が持てばいいということになる。
そして私は、アルマのケースを想像する。
アルマはトムを追い返した。
それがどうしてもできないという理由から、「私のために去って」と言った。
おそらくトムには360度にセンサーがあるのだろう。
トムにはアルマがどこにいるのかわかる。
これは元カレユリアンが大きな絵を取りに来た後、車にその絵を運ぶシーンでわかる。
つまりトムは去った後も、上からアルマが見ているのを知っていた。
それ故、パフォーマンスとしてゴミ箱に腕を突っ込んで「私はゴミになった」というメッセージを彼女に送った。
このシーンは重要で、感情というものがないロボットは、常に人間の心情を学習しながら読み、先回りして行動するプログラムになっている。
そもそもアルマを幸せにするためにプログラミングされているので、彼女の気持ちが動くように行動している。
アルマは、この会社が開発した人型ロボットについて報告書をまとめた。
「人間以上の存在」と評価する半面、「ボタン一つで人間の心を満たしていいのか」という疑問
そして「私は反対する」という強い意見
葛藤しながらようやく導き出した答えと、ボタン一つで思い通りになってしまうことへの怖さ。
それの答えは正しいのかという疑問。
この彼女の報告書にたどり着くまでのアルマの過去 初恋と恋人ユリアンと妊娠と、3年間もの研究が他の研究機関に先を越されてしまったこと。
この満たされない気持ちのオンパレード
不条理で理不尽なこの世界への不満
ユリアンの新しい伴侶 彼女の妊娠 もうやり直すことも敵わなくなってしまった「現在地」に立つアルマ
そして、その代用としてのロボットという考え方
アルマの思考 研究者としての論理的思考
この割り切れない思いがある事実
最後に会社の女性(ロボット)が訪ねてきて、おそらく失踪してしまったトムを見つけたのだろう。
そこへ向かったアルマ
「あなたがいないとただの人生になる」
ここに隠された人間の本心 満たされたい想いが描かれていた。
「君が見つけてくれるまで」
そう語ったトムの「作戦」
それを作戦とはどうしても思えない人間の「想い」という感情
アルマが思い出した初恋相手のこと
人は皆、そんなころからずっとずっと満たされない気持ちを抱え込んだまま生きてきた。
大人になって、キャリアを見つけ、そのころに出会う恋人
妊娠がきっかけで結婚を約束したけど、おそらく流れてしまい、それがきっかけで二人は別れることになったのだろう。
同時にキャリアでは世界で最初の文字を持ったシュメール文化と、その後に文字を持ったペルシャやアッカド
彼らが文字として残した「詩」と隠喩という概念の研究調査
文字の余白
この隠喩に例えられるこの作品の余白はとても重要な部分だと思う。
アルマという人物の人生は、決して不幸ではないものの、いつも肝心な部分が満たされないという思いで一杯になっているように感じる。
それでも大学で教鞭をとるように、彼女は生きているからこそ前を向いている。
父の認知症と徘徊というリアルな現実
妹に面倒を押し付けている感覚も否めないのだろう。
このどうにも満たされない状態が限界に来た時、あるいはロボットの存在が必要になるのかもしれない。
論理的思考は、本当に正しい答えを導き出すのか?
恋人と別れ、競争に負け、それでもなぜ立ち続けなければならないのか?
何もかもが八方塞になったとき、ロボットに頼るのは間違いなのだろうか?
満たされない心を少しでも満たすためにロボットを使うのは間違いなのか?
これらの問いに対する答えを、常に自分と向き合って、自分自身が出さなければダメなのか?
このような疑問がアルマの頭を駆け巡ったのだろう。
力を抜いてもいい場所が、いつの間にかなくなっていた現代社会
どこにいてもそうあるべき自分像を「演じ続けている」
この苦痛に気が付けば、その演じていた自分が足元から崩れ落ちてしまうのかもしれない。
さて、
このSFが現実になったとき、おそらくLGBT法のようにロボットに人権をという概念が登場するだろう。
この作品の余白のひとつとしてこの問題があるならば、まず貧困層を根絶することが優先されるべきだと主張したい。
ロボットを作った会社の思惑はわからないが、貧困層の人権を踏みにじっている連中がロボットの人権を主張することは今のところ許されないとおもう。
この作品を通して見るドイツ人は、うわさ通りに超真面目な人種だった。
R41さんのレビューを拝読して、この映画を見て、たくさん考えたことを強烈に思い出しました。考えることに関しては、ドイツ人は確かに真面目で感情に流されず抑制する人達が、とりわけ知識層には多いと思います。書いていらっしゃるように、ロボットが今後どのような思惑で作られ使用されるにせよ、貧困層に落とし込まれた人達、恣意的に差別され排除されようとされている人達の人権がまず優先されなければいけないと私も思います。素晴らしいレビューのおかげで、この映画のことをまた思い出させて頂きました。ありがとうございます