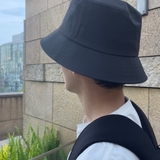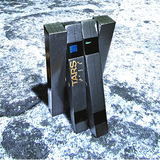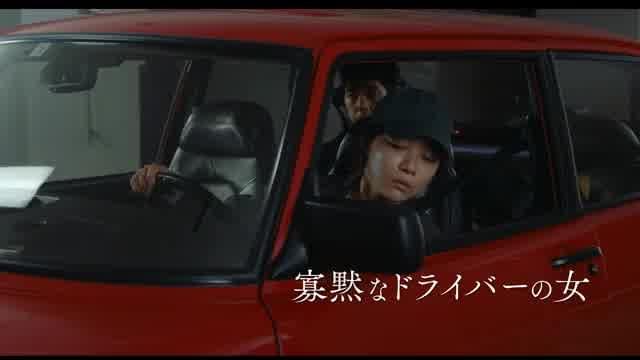ドライブ・マイ・カーのレビュー・感想・評価
全795件中、601~620件目を表示
あっという間の179分
静寂の中に圧倒されるような約3時間でした。最近の映画としては上映時間は長い作品ですが、最初から最後まで繊細に、大事な伏線がいくつもあるからこそ集中してしまいました。物悲しさと温かさの調和、背景の多くも東京ではなく洗練された中の情緒ある地方都市の風景もなんとも言えない美しさがあります。
原作はもちろん、監督、実力派の役者さんたちの創り出す世界は傑作でした。終盤のシーンは今の時代だからこそ考えさせられる言葉、所作の一つ一つが圧巻でした。
素晴らしい時間をありがとうございました。
次から次へと ようやく目的地に辿り着くドライブ
先に原作を読んだらどんな感想になるだろうという好奇心による原作既読。
30分で読める短篇がここまで、3時間の尺に発展させられるとは、一つの驚き。
村上の作った線画が、濱口の手によって色と背景を付けられ、具現化されたという喜びの発見だった。そしてその長い脚本に、無駄な力入れは一つもなかった。
映画は、小説と違って時間線に沿って物語を伸ばしていき、家福の視点から問題を投げ出し、またそれを解くドライブに観客を誘った。
後の工程は玉葱の皮剥きのように、芯までどんどん深まっていく。その鍵となる人物は、高槻とみさきだった。
家福と高槻の違いは、観客には分かりやすかった。高槻はたしかに自分のコントロールができなく、現実上、芝居と同様に人の深いところまで突き止める。家福はその反対。
高槻が車で言ったことは正直で、胸に響いた。小説で村上が書いたまんまだ。そして最後に警察に連れられたときまでも、彼の言ったように空っぽかもしれないけど偽りなかった。
そんな高槻の逮捕によって課題は家福に残された、家福は自分の問題に直面しなければならなかった。そしてオリジナルの北海道の旅は更なる救いで、もっと直接の答えになった。本当の自分と向き合えるのだ。そんな自分を持って人と向き合うのだ。演劇祭の人たちのように、言語がちがっていても。
最後の手話のシーンが良かった。声がでなくても、ちゃんと強く伝わったことがあるんだ、と思わせた、全編を収束した力強いシーンだった!
最後に言及しなければならない二つのメタファーは観客の助けにもなった。音のミツメウナギの話と劇中劇...前者は音にまつわる伏線、後者はストーリーを貫通する家福の心理劇....どっちも表現が素晴らしかった。
芸術性を追求する一方の分かりにくい映画より、このような誰にとっても大事な心得を誰でも分かるようで、また吟味させられて考えさせられるような面白い表現で伝えた方がずっとテクニカルだと思う。振り返って見ると、ちょっとの遠回りかもしれないが、いい景色だった。
秋の映画って感じ
芸術的な作品です。
これから深まる秋にふさわしい映画だと思いました。
最近、立て続けに娯楽映画を鑑賞していたのでより新鮮に感じました。。「ブラックウィドウ」「フリーガイ」「スペースプレイヤーズ」「チャンシー」「竜とそばかすの姫」ときてドライブマイカー。
観客層が全然違いました。自分を含めてお一人様のおじさま、おばさまが多かったです。見終えてからkindleで原作を読もうとあらかじめ買っておき、短編のはずだけどどこまでが原作なのか想像しながら鑑賞していましたが全体的に雰囲気が村上春樹っぽく見定めることができませんでした。3時間は長いなーと思いつつ、冒頭30分ほどで「あれ?これまだアバンタイトル?」と思った直後にほんとに「(主演)西島秀俊」と文字が出てきてそりゃ長いよねと納得。しかし、綺麗な景色と落ち着いた演技、先の読めない展開で意外にも娯楽作品にもなっているなーと感心。終わってみればあっという間でした。
見終わってしばらくして、そういえばこの俳優さん「ゼロの焦点」では秘密を持ったまま冒頭に消える役立ったけど今度は真逆で秘密を追う側になっているなーと思って妙に納得してしまいました。
悲しみの果てに
傷ついた魂の再生物語
長さは感じなかった。テンポよく場面が展開していく。
亡くなった妻の裏切りをきちんと受け止めなかったために前に進めなくなった男、家福と虐待された親を見殺しにしてそこから逃げた女、みさき。そして裏切り相手が目の前に現れたことで、物語が大きく展開していく。
家福は自分の分身のような車に長く乗り続け、その中で聞く妻の声のテープでセリフを言うという習慣を変えることなく、過去に縛られ続けていた。そしてそこに初めて他人のみさきがドライバーとして加わったのだ。
この時、すでに物語は動き始めていたのだろう。
裏切り相手に妻のことを語られ、深く傷つく。この男は何のために家福の前に現れたのか。同じ相手を愛したことで思い出を語りにきたのか。
過去の痛みを抱えた2人がたどり着いた場所で、自分の気持ちに向き合う。そこで出た結論は2人の再生への予感となって、映画のラストを明るくしてくれた。
とてもいい話だったしインパクトも感動もあった。
ただ、村上春樹ファンとしては、ここまで全てを語らせる必要があったのかとちょっと引いてしまった。もう少し、余韻というか、観客に委ねる部分があってもいいかなぁと思った。
劇場版でしか成立しない作品
劇中劇がよい
様々な言語が飛び交う「ワーニャ伯父さん」は、普段われわれが同じ言語で言葉を交わしながらも、相手の真意が理解できていなかったり、会話が成立しているようで齟齬していることを象徴しているのだろう。この舞台に参加している俳優たち、それぞれがとても良いので見入ってしまう。
夫婦、親子でも意思疎通することの難しさ、それでも言葉を重ねることでしか歩み寄れないのが人というもの。
それを怠り、暴力という手段に訴えて破滅するのが岡田将生演じる若手俳優なのだろう。
三浦透子はこの先どんな演技を見せてくれるのか非常に楽しみな女優だ。この作品のために運転免許を取得したというのは驚き。
居心地の良い違和感
観に行くタイミングがなく、公開から3週経ってようやく鑑賞。
序盤の主人公・家福の奥さんの不倫や夫婦としてのセックスで創作を生み出している様子を見ると、刺激が欲しくてたまらないんだろうなと思い、生々しくもリアリティがあって感心しました。奥さんの突然のくも膜下出血での死も悲しい出来事だけに終わらず、後半に活かしてくるのでまた驚きました。
タイトル通り、今作は車に乗っているシーンが多めですが、その車に乗っている時間が観ている側からしてもとても居心地の良いもので、最初はドライバー・渡利がつくことを敬遠していた家福が、彼女の運転スキルを認めて、話の輪を広げたり、オススメの場所を教えて貰ったり、助手席に座ったり、車内タバコを許したりと、信頼していく描写を車内で表している魅せ方はグイグイと引き込まれるものがあり、凄いなと思いました。
役者陣の演技もとっても見応えがあり、西島さんの物語のテンポにビシッとハマる舞台上での演技や、カセットテープに合わせての語り、物語上殆ど激昂する場面はありませんが、様々な感情が飛び交っていました。三浦透子さんの淡々とした喋りもとっても心地が良くて、高槻演じる岡田将生さんの別人が憑依したかのような狂気的な部分も見ることができて良かったです。手話での会話で育んだ愛とメインストーリーではないものにもスポットが当たっており、バランス良く観ることができました。
高槻が喧嘩でボッコボコにした相手が死んでしまい、高槻が逮捕され、舞台が一度滞ってしまいますが、ここで何を思ったか家福が終盤で広島から北海道へドライブするというぶっ飛んだ流れを平然とやってのけるので笑ってしまいました。汚点という訳ではありませんが、急に現実味消えたなと思いました笑。北海道で語られる2人の過去の話は、殺しと同様に残されたものがずっと背負っていくものという描写には震えました。決して自分は悪くないのに、目に焼きつけた光景を背負っていくという生々しさが垣間見えました。
なんとか舞台も成功に導き、最後は家福の車を渡利が引き受けて終わりました。原作を読んでいないので最後はよく分かりませんでしたが、前向きに進んでいるんだろうなという感じに自分は捉えました。
179分という短い映画なら2本観れる長さですが、そんな長さを感じさせないくらいあっという間に終わりました。上映時間の長さで敬遠されている方がいたら、そんなこと気にせずに観に行って欲しいなと思いました。
鑑賞日 9/9
鑑賞時間 12:40〜15:50
座席 H-1
評判が良かったので
透子運転の車に揺られているような心地よさ
2021年劇場鑑賞18本目 傑作 75点
公開日に見にいったのにも関わらず、2週間近くレビューしていなかった作品。
私が一番好きな俳優さんである西島秀俊さん主演ということで、期待していましたが期待通りの作品でした。
平日の朝からの上映だったのにも関わらず、ほぼ満員で観客の年齢層が非常に高めで、国外で評価を受けているので聞きつけて足を運んだ人も多いのかなと思い、いち西島さんファンとして嬉しかったです。
作品についてですが、久しぶりに心地よい、近年の邦画に多い安っぽさを感じられないこれぞ映画だよねと思えた作品でした。
上映時間が3時間近くありますが、その長さを感じないほどの充実感で、表現の上でのゆとりが随所で感じられ、意味のある3時間だと思いました。
ドラマ上りや実写映画、キャストばかり豪華な作品のような、邦画特有の気質がある作品が増える中、こういった空気を感じられる作品もちゃんと残り続けてほしいです。
それでも生きていく
家福の演出方法は、感情を極力廃した本読みをひたすら繰り返すというもの。俳優陣もこれには少々焦れ気味なのだが、この本読みこそ、いざ実際に動きを伴う稽古に移った段階で効果を発揮する。この映画自体、観客も冒頭から家福の妻音による『ワーニャ伯父さん』のセリフの録音を繰り返し聞くことになるのだが、このセリフのひとつひとつがラストに向かってこの物語の中で大きく響いてくる。この映画の俳優陣も感情をむき出しにするシーンはほぼないが、これもラスト近くで家福とみさきが心情を吐露する場面で効いてくる。家福もみさきも自分の感情を押し殺してきたが故に苦しんできたが、お互いに相応しい相手に出会えたことでようやく心のうちを吐き出すことが出来たのだ。
西島秀俊、三浦透子の好演は勿論だが、この映画の中では唯一自らの行動をコントロール出来ない高槻を演じた岡田将生の演技も忘れがたい。
音から聞いたという前世がヤツメウナギの女の話のその後を語るシーン不気味さは、彼の中の闇を感じさせ絶品。
何よりも、原作『女のいない男たち』からの数篇、そしてチェーホフの『ワーニャ伯父さん』を融合させた脚本が素晴らしかった。
車の色はよいが、終止形か命令形かわからない。
※追記
長編映画賞というカテゴリーがそもそも気怠い。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
心理重視の独特の湿度のある作品。
場面場面に散見される間の取り方も綺麗で、あまり欠点は無いのだが、
如何せん映画全体の尺が長い。映画ちょい好きーポンポさんのいう適尺=90分の倍である。倍。
もう少しコンパクトに出来る部分があるようにも思える。本であれば途中でしおりをはさめるが、映画(館)ではそれが出来ないのである。
各場面だけではなく、全体の枠まで考慮してこそ、監督の真の実力と言えるだろう。
まあ長尺が平気な人には良いかもしれない。
寝たい人にも良いかもしれない。
物好きにも良いかもしれない。
湿度70%くらいが好きな人にも良いかもしれない。
良い点
・バイリンガル
悪い点
・話がにわかに分かりにくい
・タバコ多め
良い作品と言うことのステイタスみたいな...
ちょっと、良く解らないです。
以前から、村上春樹さんの描く女性像が苦手ですが、今回も同様。
なんだか、うわっつらの格好つけーに感じちゃうのです。
家福も、高槻も同様。
夢みる夢男さんみたいだった。
とにかく、演出なのでしょうが、日本の役者さんたちに、
リアル感が無さすぎて、まったく入り込めなかったな…。
その点、ユンさんのナチュラルさが際立って、ものすごーく良かった。
この方の出演されてる作品を、もっと観たくなったもの。
これ、海外の方がリメイクされたのが観てみたいな。
そちらの方が違和感なく観れそう。
日本人ということで、より近い現実の日常と比べてしまうのよね...。
この作品の主要な登場人物たち人たちは、セリフまわしとか行動とか遠過ぎて、
そんなアホな!って思っちゃって…。
しいて言うなら、音楽が良かったなー。
3時間、人間を観てきた。
観終わってから原作が読みたくなりすぐに読みました。原作は短編だった...
脚本も役者も素晴らしい!!ただ、少し難しい。
正直、まだこの映画を自分の中で消化できていない。
こんなに長く余韻に浸っているのは久々かも。
3時間、あっという間だった。
もう一度見たい、何度も見たい。
.
作中では、「演劇」が重要な役割をもつ。
劇中劇として「ワーニャ叔父さん」がでてくるが、この主人公が置かれている状況と家福(西島秀俊)の状況がだんだん重なってくる展開がおもしろい。しかもそれが自然なので違和感がない。
.
そして、心情の変化や本心の吐露は、ほぼすべてが車のなかで起こる。車の走行と感情の変化が相乗効果を為して、この映画のなんともいえないスピード感をつくりあげている。
.
自分が最も印象に残ったのは、イ・ユナ(パク・ユリム)の韓国手話でのお芝居のシーンである。
ユナの手話がすごく自分の心に届いた。
この映画は最初から最後まで「声」を大切にしている映画だと思うのだけれど、声を発さなくてもここまで心にセリフが届くんだというメッセージを感じた。
ふと、生き辛い世の中だなと感じることがある。生きていると、なんでかわからないけど苦しくなることがある。「ドライブ・マイ・カー」は、そんなときにそばにいてほしい映画だなと思う。
演劇を中心にすすんでいくので、演劇の知識がない私は、正直途中でついていけないところもあった。
演劇に精通しているともっともっと楽しめる作品なのだと思う。
『 トニー滝谷 』の続き
やはり原作は村上春樹さんの『 トニー滝谷 』という映画でナレーションをされていたのが西島さんでした。なんの予習もなしに続編を見るつもりで、映画館の座席に座ると配給会社がビターズ・エンド!ハッピーエンドが安心な私には不安な滑り出しでした。
海外で評価の高い映画を見れば、その時代の日本の良いところや悪いところそして当たり前だと気づかずにいること、それらが目の前に現れてそれだけでも面白いのですが、今回は野心的な監督とスタッフの皆様の試み、そして心地良い音楽が包んでくれる素晴らしいひと時を過ごすことができました。
そういえば、先週から練習しているピアノ曲で、先生から言われたことを思い出しました。「 風船が床に落ちて跳ね返る時の、あのふんわりとしたイメージで鍵盤を叩いてみて 」
感情の揺れはそんな優しさで丁寧にくるまれ届けられます。
ワーニャおじさん、生きていきましょう。長い人生を生き抜いていきましょう。そして最後の時が来たら、おとなしく死んでいきましょう。
全795件中、601~620件目を表示