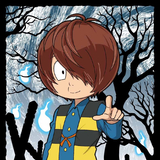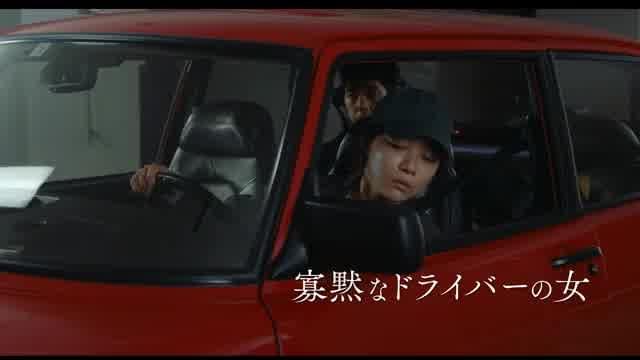ドライブ・マイ・カーのレビュー・感想・評価
全795件中、501~520件目を表示
じんわりと心に響く作品でした。 派手さは無い3時間の長尺ですので、...
喪失感、後悔…自分自身の感情と向き合い、折り合いをつけて生きていく
西島秀俊さん、三浦透子さん、岡田将生さんの演技が素晴らしいです。長い映画だし、多言語の劇中劇があるのですが、劇中劇はなかなか良かったです。
車内のシーンはセリフも動きも少ないのに、感情の移ろいが伝わってきて退屈では無かったです。
印象的なシーンも幾つかありましたが、全体としては私は感動する程では無かったです。
多言語の舞台と言うのは実験としては面白かったけど、家福が以前からそういう演出をするのだとしたら、それにこだわるのはなぜなのかと思いました。高槻は結局何がしたかったのか良く分からなかったです。
「彼女は高貴なヤツメウナギだったから、他のヤツメウナギのように寄生したりせずに、ただ石にへばりついてゆらゆらと揺れていた」というのはつまり、ヤツメウナギは浅ましく、人間は高貴である、と言っているわけですよね。
夫を深く愛しているのに夫だけでは満足できない、という人は居るのかもしれませんが、その妻を深く愛せる夫の気持ちは解らないです。
音は元女優の設定なのに、録音のセリフは感情を込めないというより何だか暗くて、駄目出ししなくて良かったんでしょうか。
共感する夫婦間
村上春樹さん作品にはよくある 本編には関係ない”こだわり”=ザ・ビートルズ
原作は読んでいないし、劇中劇である戯曲「ワーニャ伯父さん」も知らないが、
本作は村上春樹さんの小説を1字1句残さず、セリフの間さえも的確に描写している"ザ・村上文芸作品"の匂いがした。
キャスティングもイメージどおり。
2時間程度の短絡的な作品が多い現代映画界である甲子園にプロのピッチャーが投げてしまった映画。
原作・脚本力はピカ一だ。
人と人は「言葉に関係なく、うまくコミュニケーション=和をもつことができる」という表現目的である多言語演劇の
劇中劇では舞台頭上に長々と字幕が出る。
これは形だけの説明であり、こんな長文をいちいち読んでいては 劇を真剣にみることはできない。
あくまで多言語演劇を観るには予習が必要で、
その予習を確認しながら この劇を観る事を 演出家は期待している。
同じように、変化を嫌い 繰り返しを好む主人公は 車の中で元妻のカセットを何度も繰り返して聞く事で、いつも安堵する。
舞台練習に対しても、机に座った本読みばかりを行い、セリフを繰り返し繰り返す事で、言葉を体に沁み込ませる手法をとる。
これは予測されている事を確実にこなす事を重視するのであって、予期しない変化は断じて認めない事でもある。
だから主人公は妻の不貞=変化も観て見ぬふりをし続け、役者として気づかない演技をし続けてしまった。
この映画は長い。重要なのは 時間だけではない
これを理解できないと この映画は苦痛になってしまうかもしれない。
途中であきたのか? 隣のおじさんが 途中「あーーー、うーーーー」と煩かった。
情熱的な色をした車は主人公の妻=音(おと)であり、
それは主人公だけのもの
主人公 家福(かふく)は自分でその車を運転する事にこだわるが、
演劇主催者により、運転席の座は強引に取り上げられてしまった。
最初は車と主人公の間に入ってきた運転手である"みさき"との間に壁を作っていた主人公も、
ある日、心を落ち着かせる為に、いつもより長くカセットを聞きたかっただけのドライブをとおして、副産物として、みさき を理解出来るようになり、同化さえしていく みさき に車を託して、共有する気になる。
それは2年という単なる時間の消費だけでは解決できなかった想いを
ただ時間をかけるだけでなく、
相手を理解する事の大切さを知る事。
故に車で座る席も、傍観者的であった後部座席から、助手席に代わり、主人を待つ間にもその席に座る事を許す事になる。
自分の車は自分だけが、運転するものではなく、「他の誰かにも運転させる」 そう言うもの そう理解する。
同時に舞台では、自分の立場に近かった役を演じられないとしていたが、
妻との間に入ってきた男を理解することで、
同じように妻を理解でき、その役も演じる事ができるようになった。
そして妻の象徴でもあった車さえ、最後は みさき に完全に託す事ができるようになる。
呪縛から解放されたのである
なぜ みさき の故郷が北海道なのか、監督に聞いてみたい。
広島ならば、距離的には新潟あたりがよいのではないだろうか?
それ以上に 家福さんが住んでいた 東京の手前で高速を曲がるような場所である 山梨とかの方が、主人公の心の整理と葛藤を裏表現できて、的確なのではないだろうか?
答えを求めていた恋敵である高槻は現実と似た役柄である"妹の元旦那”を求めていたのに、
主人公は現実には自分と似た立場である"妹の兄(叔父)"をやらせたのだろうか? 脚本家に聞いて確認してみたい。
帰り際によく見ると、隣の席ははおばさんだった。
この映画を観たら「ノルウェイの森」を やはり観る冪なのだろう。
また、文芸作品としては何度も映画化されている「伊豆の踊子(1974年他)」もそれぞれ比べてみると良いと思う。
世界観にゆっくり浸るのにオススメ
あの短編小説を、どうやって3時間の長編に??と思いましたが‥
チェーホフの『ワーニャおじさん』の演劇製作と並行しながらの、ストーリー展開には引き込まれました。
劇中劇の対話、家福とみさき、高槻との対話、音から紡ぎ出される語り。
印象的だったのは、高槻が、「他人の心をそっくり覗き込むことはどんなに愛している人でも無理。でも、自分の心はしっかり覗き込むことができる」とゆうところ。それから、みさきが、夫以外の男性と関係を持っていた音のことについて、「謎ではない、ただそういう人だった」みたいにゆうところ。なんか、ちょっと、救われるような気持ちになったんだけど、なんでかしら。
ちなみに、岡田将生演じる高槻が追突事故を起こしているシーンでは、どうしてもアクサダイレクトのCMが頭をよぎりました‥
正直、つまらなかった。
いいじゃないですか!
なんのこっちゃ
脚本家夫婦のおしゃべりセッ○ス、奥さんは旦那さんいないときも若いの連れ込んでまたセッ○スそれを目撃する旦那さん、浮気みても旦那さんは盛んに奥さんとセッ○ス、空き巣はしてもオ○ニーはしないお話しながら奥さん昇天、夫婦仲は良さそうだけど娘が死んだよう、ある朝なにか話があると言い残して奥さんは死んじゃう、ここまでがプロローグ
2年後、旦那さんは公演監督で広島へ、主催者から女の子ドライバーをあてがわれる、キャスティングも決まり稽古の毎日、奥さんと浮気相手だった主役が無断で写真を撮る奴をなぐり殺して公演を中止するか旦那さんが主役を務めるか考えるためにドライバーの生まれ故郷の北海道までロングドライブ、旦那さんは自分が妻を殺したと悔やみドライバー女子は母親の多重人格と災害で見殺したことを悔んでて2人は仲良しに、公演は旦那さんが主役やって拍手喝采、ドライバーちゃんはなぜか韓国で同じ赤いサーブに乗ってて、おしまい。なんのこっちゃ
引き込まれて魅せる3時間
物語は淡々と過ぎて、派手な事件もショーアップされたシーンも無く展開するのですが、それでもグイグイと映画世界に引き込まれる3時間で、最後まで目を離せず、胸に迫る様な台詞に心が揺すぶられます。
物語の主軸とは別に、世俗的メディアやそれに共鳴する現代社会、最近の国際社会の動向へのアンチテーゼも含まれて、それがさりげなく心に問いかけるエッセンスの妙味。音楽は控えめで沈黙と対比され、自然で美しい映像が綴られ、ロードムービー的展開で観客は一緒に旅する。舞台で繰り広げられる劇と映画の物語がシンクロしながら、いつしか観客は、物語と舞台の区別が無い世界に導かれていく…これは凄い。
そして、それぞれの役者の静謐だが迫真の演技は見所だろう。西島秀俊が妻役・霧島れいかとのベッドシーンで描く官能的で内省的な演技、終盤の舞台での虚実混沌とした世界で無言での表現など胸を打たれる場面の数々。岡田将生のオーディションシーンや車の中で西島演じる家福に語る長回しの演技は彼の白眉では無いかと思う。ドライバー役・三浦透子のミステリアスな演技と、そして最後のシーン…。
虚構と現実をシニカルにどこかで捉えているクールさは村上文学のエッセンスを見事に表現していて感服。
非常に文学的で知的な作品だが、決して取り澄まさず、映画的面白さが漂う品格のある作品に仕上がっていて、鑑賞した後にこの作品と出会いに心が楽しくなりました。
今年初の残念映画
後半明かされる事実に、あれ?そうなの?と。
私の読解力不足かもしれないけれど、たまたま偶然妻の不倫現場を見てしまった夫。そのように理解して物語を追っていた。
実は複数の男と関係を持っていた妻、その事実を知りながら問い詰められなかった夫だったということ?
でも、そんな描き方してないよね?
後出しジャンケン感が半端ない。そこでガクッとズッコケた。
一歩引いてフラットに見ると、要は男漁りをやめられない妻に、それを知っていて責めることもできない夫と、その後の話。
それを勿体ぶって語られてもなぁと。
村上春樹原作らしいけど、どこまで原作に忠実なんだろう?男女のドロドロを意味ありげに描かれても。例えるなら温いカフェオレにはミルク、砂糖を大量にぶちこんだべとつく感覚.(語彙力不足)。
演劇と重ねて描いたり、個々のシーンはとても好きだったので少し残念。
村上春樹は嫌いです
彼の作品は興味深いものがあるのだが、どうも文体と台詞が鼻に付く。知性的ではあっても、不細工な男が目一杯カッコ付けている感じがして、どうにも好きになれない。全く妙な作家だと思う。彼の原作だということで全く気にも留めていなかったのだが、アカデミー賞の前哨戦にあたる賞を取ったということで、ミーハー気分に乗っかって鑑賞した。台詞は村上春樹丸出しで食傷気味ではあったが、チェーホフの戯曲が自然とまとわりつきストーリーが進み行く様は中々面白い演出だった。役者が西島秀俊と岡田将生を除いてはほぼ無名と言って良いキャスティングが功を奏したようで、3時間という上映時間も気にすることなく鑑賞出来た。脚本は間違いなく素晴らしい。さすがに、アメリカの映画界もキチンと内容を見ているようだ。
満員でした
良くも悪くも村上春樹
全795件中、501~520件目を表示