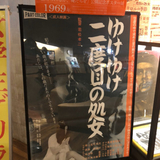ニューオーダーのレビュー・感想・評価
全82件中、21~40件目を表示
【”新しい秩序。”社会派ミシェル・フランコ監督が”格差社会を解消しないとこの映画の様になるかもしれないよ・・。”と物凄いシニカルな視点でメッセージを発信した恐ろしい作品。】
ー 冒頭は、格差社会の上位と思われる人たちが、主人公マリアンの結婚式を祝いに来ている。皆、瀟洒な衣装に身を包み談笑している。
だが、その外部では暴徒化したメキシコの軍勢が今までの社会秩序を崩壊させるが如く、非道極まりない行いをしいていた。-
◆感想・<Caution!やや内容に触れています。>
・社会派ミシェル・フランコ監督の言わんとしている事は良く分かったが、観ていて相当にキツイ映画である。
・マリアンは式を抜け出して、元召使のロランドの娘、エリサを助けに町に車で出るのだが、アッサリ暴徒化したメキシコの軍勢に捕まり、非道なる仕打ちを受ける。
ー 善が機能していない事を、示している。-
■因みに、リドリー・スコット監督の「悪の法則」では、メキシコの麻薬カルテルの異常なる残忍さが描かれている。
ペネロペ・クルス演じる美女が恋人の弁護士が麻薬カルテルと接触してしまった事から、トンデモナイ事をされるのだが、ブラッド・ピットが演じた男が”メキシコ人の一部は人間の姿をしているが、中身は別の生き物だ。”と言う台詞がある。
何故か、今作を観てその台詞を思い出してしまったよ・・。
<舞台はメキシコであるが、もしかしたらどの国でも起きてもオカシクナイ気がする映画である。
マリアンにとって、人生最良の日となる筈の日が、最悪の日になるというシニカルな展開も、鑑賞後の実に嫌ーな感じに輪を掛けて来る作品である。>
社会問題への注意喚起と、それに対する民主主義的な解決を願う監督による作品
メキシコのリアルな社会課題が描かれていると聞いて映画館へ足を運んだ。
冒頭の結婚パーティーから圧巻。貧富の差、富裕層内での癒着、お金のやり取り、コカインなど薬物との共存、子供に対する親の権力など、リアル。
その上でクーデター。
富裕層から急に身柄を拘束される側になる人々の様子や、クーデターを起こした軍も結果的に権力に癒着していく様子が生々しい。
ミシェル・フランコ監督の民主主義による解決を求める声が詰まった映画だと思う。
中々の胸糞具合
面白いとは言い切れないが特別さは感じる
これは衝撃的でなかなか興味深い作品ではあるものの、娯楽性という意味では少子物足りないものがあった。
貧困層が富裕層に対して牙を剥く対立の物語ではあるけれど、その奥には暴力による新しい秩序の構築がある。平たく言えばクーデターだ。
これら一連の展開が容赦なく描かれ、一筋の救いもないところが本作の魅力といえよう。
いうなれば、善が悪に蹂躙されるだけの作品だ。
そこに慈悲や躊躇いのような葛藤がないところがすごい。力あるものがさらなる力を手にするため、その障害となるものは全て駆逐する。人間をいとも簡単に処分する。人が人ではない、何か物かのように。
力のない者が淡々と塗りつぶされていく様を見るだけでドラマ性が薄く、すでに書いたように娯楽度は高くない。
それでも、次々に襲いくる容赦のなさに恐怖を感じ、作品に特別さを見出す人の気持は分かる。
ゾンビの出ないゾンビ映画
WOWOWでタイトルだけみて、またマンチェ関係の映画だと思って観たら違った。全然バンドとは関係なかった。ゾンビ映画がメタファーとして描いてきたものを、メタファー抜きで直接に富裕層と貧困層の対立として描いたリアルに胸糞悪いパニック映画だった。世界の現実を映し出す意図も明確だし映像も鮮烈、徐々に拡がっていく不穏さもホラー映画として面白かった。しかし統治する体制そのものが悪の根源として描かれたとしても結局のところ『匿名の群衆』が怖ェ〜という印象が1番強烈に残ってしまうのは、映画の伝わり方としてどうなん?、というところもあり、やはり〈人間怖い!〉という映画はゾンビなどのオブラートに包んでもらった方が楽しみやすいな、とは思った。群衆心理が怖いとか人間が醜いってのは重々承知なので、それをそのまま描かれると凄く滅入るというのもあるし…。
いゃ〜怖いわ
メキシコでの事件。貧富の差に激怒した貧しい人たちが富裕層を襲う。自宅で結婚のパーティーをしていたマリアン宅に暴徒と化した労働者が侵入し始める。パーティーの最中、あやしげな人が次々に塀を乗り越えて入ってくる。怖いよね〜。すぐに銃を撃ち始め、パーティーに集まった客達を部屋に押し込め、略奪、殺害し放題。貧富の差に苦しい思いをしても、ここの家庭、客達が悪いわけではないのに、そんなことはお構いなし。たまたまパーティーに来た人達は巻き込まれて気の毒。マリアンは元メイドを助けようと家を抜け出していたから難を逃れたが、こちらも地獄。
軍隊が富裕層を連れていく。助かるのかと思ったらとんでもない。監禁されて、ビデオを撮らされ、身代金を要求する。同じ国の国民同士で、ここまでするか、、、
男も女も関係なくみんなの前での集団暴行、暴力。男も女もごちゃ混ぜで裸にされてシャワー浴びて、といっても水をかけられているだけよようだが。
人権も何もない。やりたい放題。軍人がこんなことしていいのか?身代金を受け取りに行った数人は処刑されていたが、もっと大勢処罰されるべきだろう。
同じ国民なのに、なぜ軍人もここまで残酷になれるのか。暴徒と化した人々も我慢の限界だったんだろうが、怒りの矛先が違うのでは?
ただの“胸糞映画”と言うなかれ
話題になっていた様なので何気に借りて見たが、いやぁ~久々に落ち込む作品を見てしまった。
いや、映画的にダメな作品という意味ではなく、むしろ凄い作品ではあるし映画史的にも非常に重要な作品であると思います。
で、本作を一口で言い表すならば正真正銘の“胸糞映画”という事になるのでしょうかね。
最近、他者の映画の感想を知りたい時まず最初に観るのが映画サイトレビューよりもYou Tubeになっていて、本作を検索するとサムネイルに“胸糞映画”という文字が並んでていて、正にそう思わせる作品なんだと私も思いましたよ。
いや、こういう悲惨で残酷な光景や痛烈な社会批判の作品は今までにもたくさん見てきましたが、多くのそうした同系の作品とも違う嫌な肌感というか、どうしようもない嫌悪感を刺激させられる作品でもありました。
本来こういう作品は、メッセージとしてこうならない社会を目指し考えましょうというのが根底にあるのですが、本作の場合はそれがあまり感じられず、人間とは本質的にこういう生き物なんだという事を描いているようでした。
(私に)そう感じさせたことは作り手にとっては大成功なのでしょうが、見ている方は堪ったものではない。しかし、リアルから目をそらすなという方向性の作品であるのなら仕方ないですね。
まあ、世界を見渡すと映画の中で起きている様な出来事は山ほどあり、現状なんらかの方法で秩序が保たれている社会の人間からすると、この秩序はなんで保たれているのか?その方法または力とは何なのか?それはひょっとしたら非常に危ういバランスで保たれているのかも知れないし、本作を見ていると戦争(若しくは反乱、革命、暴動)が起きる必然性とか、それが起きた時の人間の本質であるとかリアルな姿を非常に冷徹に明確に端的に容赦なく描かれていて、全ての登場人物に対して、もし自分がその場に置かれても只々無力に絶望するだけという、全く救いのない作品なのです。
逆に言い換えると、様々な問題があろうとも今何らかの力で(たまたま)秩序が保たれている国の国民であることの幸運に感謝したくなるような作品でもありました。
また、本作を“胸糞映画”と言う事は、そもそも人間の存在そのものが胸糞であると言うのと同じであり、その点を考えさせる(伝える)映画だったのでしょうね。
新しい気付きを得られる=これは良い映画だ
公開時より観たかったがなかなかタイミングが合わずDVD化してから鑑賞
良い映画というのは言わずもがな面白い(興味深く、関心する)という意味である
ストーリーについては救いもなく、息を呑む容赦ないシーンが見どころ
鑑賞後は幾つかの疑問が残るが、鑑賞中は難しいことは考えずに観ることができた
やはりラストの展開
一見すると市民が暴動を起こし、富裕層が襲撃めちゃくちゃに振り回される主人公。暴動は鎮圧されつつあるが軍の力が強くなりさらに振り回される。その時警察は味方なのか…?という話だが。
"振り回される"で済んでいい展開ではなくそれは強烈なものになっている。
他の評価者のレビューから色々と分かったこともあり、「なるほどなぁ」と感心する点は多かった
反体制を描いているように観ているだけではこの作品の真意は汲み取ることができていないかも
軍も警察も、上層部は富裕層の一部や政治家と手を組み新秩序へ誘導されていたということなのか
エンタメ性が高い一方で監督の格差への批判も鋭く刺さった作品だった
個人的には一市民の自分はエンタメとして楽しめたが、国としての根幹を揺さぶられる感覚は恐怖でしかない
90分足らずと見やすいが、展開(特にラスト)はあっさりしておりこれはこれで物足りなさもある
今まで見た映画名の中で一番ひどい映画でした。 ただただひどい状況を...
三色鬼
ミシェル・フランコの作風がどんどんミハイル・ハネケに似てきている、そう感じているのは私だけでしょうか。一見、貧富格差が原因で起きた暴動を描いたディストピアムービーのような体裁をしていますが、本作には目に見えない別の伏流水が流れています。しかもそのヒントとなるキーの開示が極めて不親切でハネケっぽいのです。あの傑作スリラー『隠された記憶』のように、気づけない者を嘲笑う監督の意地悪い顔が目に浮かびそうなのです。
メキシコのとある市長宅で、娘マリアンの結婚を盛大に祝うパーティーが開かれていた。そこにヒョコヒョコと現れた屋敷に昔雇われていた使用人。かみさんの手術代の無心にやってきた男を哀れんだマリアはなんとか力になってあげようと元使用人の甥と共に、暴動が起きている中元使用人の家へと向かう。その時、市長宅に賊が押し入り拳銃を乱射、市長もその銃撃に倒れてしまうのだが.....
ここで不自然なポイントを箇条書きで整理してみましょう。
①暴動が起きているにも関わらず何故軍か動かなかったのか?
暴動が起きることが予めわかっていた、もしくは軍によって導かれた群衆がおこした計画的暴動だったのではないでしょうか。市長宅を襲った輩の中に警備の連中も混ざってましたよね。さらに、ボスと呼ばれる軍のトップが賊が侵入する前にちゃんと屋敷を脱出していました。予めこれから起きることがわかっていた証拠でしょう。
②何故、市長は殺されなかったのか。
軍と市長が予めつるんだ計画だったからです。後で怪しまれないよう、賊には急所をはずして市長を撃つよう指示があったはず。一命をとりとめた市長が後に軍によって手厚くガードされた理由もこれで説明がつきます。冒頭、市長とボスがズルズルの関係にあることをマリアンが揶揄ってましたが、後々起こることの伏線だったわけです。
③なんのための計画だったのか。
すべては『ニュー・オーダー(新秩序)』のため。市長のライバルとなる他の金持連中を潰し、暴動をおさめた軍の権力をより拡大、ロイヤリティの欠片もないパンピーへの監視を強化、体制に逆らった者や体制維持に都合の悪い者は容赦なくパージしていく『1984』のような社会を築くためといってもよいでしょう。現代社会がその過渡期にあることをミシェル・フランコは我々に鋭く警告しようとしているのです。
④マリアンは何故殺されたのか?
娘が屋敷を脱走して使用人宅へ向かうことははじめの計画にはなかったはずです。息子や娘むことともに生き残りリストに入っていたと思われます。ちなみに、前妻姉妹の命令を無視した市長の看護担当は新しい奥さん候補なのでは?マリアンは軍の一部が金に目がくらみ密かにおこした、クーデター内クーデターの餌食になってしまったのです。そして、真犯人が軍人だとバレると何かとマズいと思った制服トップが、全てを使用人たちのせいにして揉み消しをはかったのでしょう。
こういう映画を見た後だと、何もないけどとりあえず平和にだけはこれ幸い恵まれている日本に生まれて本当に良かったと思うのです。クリーンに見える輩ほど中身は真っ黒、皆さん気をつけましょうね。
予告動画だと面白そうだった。
予告動画だと、水道から出る緑の水、ゾンビ?ぽい人間。パニックホラーかな?と思って、レンタルでパッケージを見ないで借りたら・・・・内乱と言うかクーデター、貧困層に襲われた富裕層の話だった。
うーん、襲撃・惨殺、性的暴行などのシーンはリアルかなぁと思ったけど、政治的あるいは軍事的な背景が殆ど無視されていて、「だから?」って感じだった。
ハードボイルドだど!
内戦に巻き込まれる恐怖
怖い。。
鑑賞動機:何か大変なことになっているらしい10割
つい欲張って手を出して、2022年の終わりが緑で塗りつぶされてしまった。何となく暴動の中でのサバイバルみたいな話だと想像していたが…。暴動は単なるきっかけで、不条理と理不尽の嵐の始まりでしかなかった。ノブレス・オブリージュどこいった。軍隊という暴力装置の恐ろしさは、中の人も実はよくわかってない。自己保存が何をおいても優先されるってことか。
時間が短めなのがせめてもの救い。
明日かもしれない物語
結婚式が無事にとり行われ、マリアンは幸せの絶頂にいた。
そんな時、かつての使用人の男ロランドが結婚式にやってくる。
彼は病気の妻の手術費用が高額のため、マリアンたちにお金を借りたいと頼ってきたのだ。
彼女は必死に解決策を探すが、家族たち全くは取り合ってくれない。
時を同じくして、街では低所得者たちが突如反乱を起こし始めていた。
そして、その地獄は富裕層が集まるマリアンの結婚式会場にまで忍び寄っていた。
目を背けたくなるような現実の映画。
ただし、せめて映画の中だけでもしっかり直視しなければならない。
社会に根強く存在している目に見えないヒエラルキー。
その均衡の崩壊は今すぐにでも起こる可能性があるし、映画内の地獄のような惨状は今も世界のどこかで起きている真実だ。
緑の塗料が社会組織の危うさや脆さを鮮明に色付ける。
きっともう現実は水道水が緑になるレベルまで達しているはずだ。
特に印象的だったのが、敵も味方もないというところ。
はじめは貧困層の富裕層に対する反乱だったのだが、それをすぐに治めた軍隊が今度は覇権を握る。
秩序を守るものが壊れたら元には戻れない。
金のために金持ちを誘拐して拷問にかけ身代金を要求する。
そして金のない一般市民には罪をなすりつけ微塵の遠慮もなく殺す。
軍部がクーデターを起こし…という事象は日本でも起きているようにものすごく身近だ。
これは軍などに問題があるというよりは社会のシステムの問題。
平和ボケしている現代の日本人こそ観るべき作品だと思った。
圧倒的なリアリティだった。説明が全く無いので、ある程度の背景知識...
圧倒的なリアリティだった。説明が全く無いので、ある程度の背景知識がないと難しいけれど、本当にムカつく映画だった。メキシコの貧富の酷さとそれに基づく対立や憎しみは画面から伝わって来たけれど、秩序を手にする奴らの卑劣さも描かれていて、さらにはすべてをもみ消そうとする軍上層部の権力。権力というものの象徴のような映画。
Getting Worse
だから。ますます悪くなってるんじゃないですか....
打ちこわし/略奪系な訳だから革命に非ず。ジリ貧はミエミエです。人質を一か月も閉じ込めるなんて、国内のその辺に。無理でしょ。
軍の不良分子の関与がバレるとマズいんで、全部闇で処理。人質も、あの後全員、同じ様に「処理」されたんでしょうね。
新しい体制・秩序は、以前にもまして、更に悪くなったよ。
って言う、暴動が更に状況を悪化させただけに終わったと言う惨劇。
ショッキングで情け容赦無しの展開ですが、なんか一本調子で面白くなかった。と言うか、処刑シーン等々、恐怖をあおる演出が全く無いんですよ。銃声だけ、ってのが数か所。これって、どんな狙いがあるんでしょうか。また、さすがに、あの誘拐&身代金振込の組織犯罪は、ずさん過ぎて現実感が無いです。
これがショート・フィルムなら、「面白かった」って言えると思います。
全82件中、21~40件目を表示