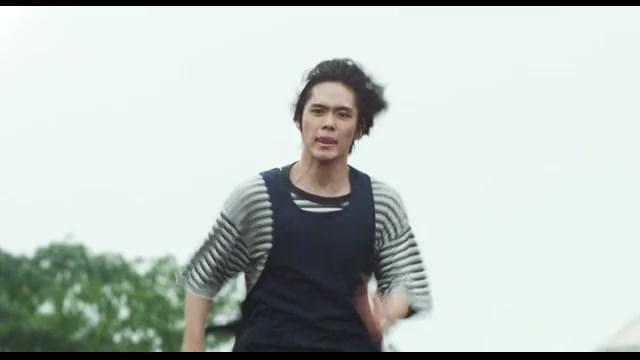子供はわかってあげないのレビュー・感想・評価
全99件中、1~20件目を表示
「水は海に向かって流れる」実写化と見比べると、良さが一層引き立つ
本作を公開当時見逃して残念に思っていたが、田島列島の人気コミックの実写映画化という点で共通する「水は海に向かって流れる」(2023年6月公開)を観るにあたり参考のため配信で鑑賞。「南極料理人」「横道世之介」など大好きな作品の多い沖田修一監督、やはり期待を裏切らず楽しませてくれる。冒頭前触れなく始まって観客を面食らわせる劇中アニメへの尋常ならざる力の入れようなどは、「おらおらでひとりいぐも」の遊び心を想起させると同時に、やはり人気コミックを原作とした石井裕也監督作「町田くんの世界」(町田くんを演じた細田佳央太が本作の主人公の一人・門司くん役)にも似た、邦画界で量産される青春漫画実写化作品の定型を作家性で打破する強い意志を感じさせもする。
上白石萌歌がちゃんと高校の水泳部員に見えるすっぴん(に見えるナチュラルメイクかもしれないが)で、しっかり日焼けしながらプールや海で演じているのも高ポイント(インタビューによると、きちんと夏に順撮りしたという)。そうしたリアルな若者像を丁寧に映像化した点も魅力になっている本作と見比べると、「水は海に向かって流れる」で描かれる世界は表面的でどうにも嘘っぽく、量産型の青春ドラマ邦画の枠を抜け出せていないと感じる。田島列島原作の映画2作品で比較するなら、この「子供はわかってあげない」に軍配を上げたい。
高校生が日焼けしている、という当たり前の素晴らしさ
なんでこんなにしあわせな映画ができるのか? 沖田修一監督のもっているリズムとユーモアや、その世界観で漂っているような俳優たちの妙演など、素晴らしいポイントはいくつもあって、何の話かよくわからないまま、しあわせに時間が過ぎていく。なんだこれ、発明か。
そして数ある青春映画の中でも特異とも言えるのが、上白石萌歌演じる主人公、朔田美波の、毎日を楽しむ力の強さ。朔田さんは、目の前にあるものをいつも思い切り楽しんでいて、屈託や悩みもあるにはあるけれど、概ね前向きな気持ちが勝ってしまう。青春映画の多くは憂鬱や行き止まりの感覚を描くものだが、本作の朔田さんにはそれがない。しかしそんなものは本作には要らないのだと、上白石萌歌の屈託のなさに教えられる。
この映画は二年前のひと夏に、順撮りで撮影されたという。気がつけば真っ黒に日焼けして、ニコニコしている上白石萌歌の無防備さに、知らず知らずのうちに救われてる。この演技を見るだけでも、割増料金を払いたいくらいである。
沖田監督ならでは独特の空気感が秀逸
いつも独特の温もりと緩急自在の笑いと、心がスッと澄みわたる特別な時間を創り出す沖田修一。彼が手がけると何もかもが沖田カラーに染まっていく。本作もまさかアニメーションで始まるとは思わなかったが、そこから時間をかけてじっくり捉えていくリビングの風景が実に素晴らしい。こんな覚悟の要るアプローチを飄々とやってのけるのが沖田監督らしいところ。上白石や細田のイメージも無理に原作に寄せるのではなく、むしろ彼らの持ち味を大切にしたキャラクターが生き生きと青春を謳歌していて、隅から隅まで好感が持てる。脇を固める名優陣も独特の沖田ワールドを力まず、泳ぐように生きている。この間合い、この呼吸。どこまでも心地よく、クスクス笑わされたかと思えば、ふと涙してる自分に気づかされたりもして、これまた新鮮。ちなみに原作漫画では別の角度からの味わい(もじくんのお兄さんの名探偵ぶりなど)が楽しめたりするので、こちらもお薦めだ。
「ややタイトルの引きが弱いかも?」と感じ、勿体ないと思う、沖田修一監督作品ではベスト級の面白さを持つ映画!
まず、この映画を見ている人は、きっと「あれ、間違って別のスクリーンに入ってしまった?」と冒頭の数分は、そんな疑問が生まれることでしょう。
でも、心配ありません。間違いなく「子供はわかってあげない」の本編です。
本作は、沖田修一監督作品ですが、これまでの作品の興行収入から考えると、まだ一般的にはそれほど広く認知されているわけでもないのかもしれません。
「南極料理人」や「横道世之介」といった作品などで着実にファンを増やし、実力のある監督の一人です。
ただ、これまでの沖田修一監督作品から考えると、本作は、割と新鮮な感じがします。
それは、これまでは「ちょっと可笑しい」という感じが持ち味でしたが、本作では、「結構、面白い」という感じになっていたからです。
理由の一つには、同名のマンガを原作としていることも関係あるのでしょう。
ただ、それを上回るくらいに上白石萌歌と細田佳央太の演技の化学反応が良く、結構、面白い感じで物語が進んでいくのです。
さらには、千葉雄大も「本領発揮」といった役どころでした。
あえて言うと、大きく前半と後半に分かれているイメージで、特に前半はテンポも良く面白いです。後半も面白いのですが、味のある面白さに変わっていきます。
とりあえず気になったら迷わずに見てみてほしい「良作」です。
青さ、爽やかさが素晴らしい
自宅で動画配信サービスを利用して視聴しました。
見終わった後は、若いハツラツとした爽やかさが残りました。夏の青空や高校生という若さがとても印象的だなと思います。
上白石萌歌さんをはじめとした俳優さん達が各人物をあっさりと、でもしっかりと演じられていますし、人物の言動からも、空気感が重々しくならず、とても爽やかに見ることができました。出てくる人物たちに基本的に悪人がいないですし、なにより主人公のとても前向き(楽天的?)な性格が、見ていてとても気分が良いですね。
間の取り方やカメラワークが独特ですが、この独特さが不思議とより身近な日常感を感じさせてくれているように思いました。
とても良い作品だと思いました。
こ~~れは…
夏はいいよね、高校生の走る姿もいいよね
沖田監督らしい「間」が描かれます。
冒頭、カメラは主人公の少女・美波(上白石萌歌)にぴったりと寄り添います。真夏 のプールで泳ぐ姿を主観映像や水中撮影で描くのです。
その元気に溢れた描写から、今は暑いだけにしか思えない夏であっても、子供の頃はあんなふうに何をするにも気持ち良かったのだという、忘れていた感覚が、少女の肉体を通してありありとよみがえってきました。学校の階段を一段飛ばしで駆け上がる姿を延々と見せること。プールの水の中の心地よさの感覚。こんな軽々とした体からはじけ出る若い力をまず見せつけてくれたのです。
田島列島の同名漫画を「横道世之介」の沖田修一監督が映画化したのが本作です。夏休みの少女の成長を描いた、輝くような青春映画でした。
美波は高校2年。アニメおたくで水泳部所属。好きなアニメを父親と見て一緒にエン ディングテーマを歌い踊るほど家族とは仲がいいが、実は幼いころ離婚して家を出た実 父(豊川悦司)がいたのです。
あるとき、部活もクラスも違う書道部の門司くん(細田佳央太)が自分と同じアニメのファンと知り意気投合。彼の家を訪ねると、幼い頃に家を出て顔も行方も分からない父の手がかりを見つけます。美波は門司くんの兄(千葉雄大)が探偵だと聞き、実父捜しを依頼します。
見つかった実父は新興宗教の教祖で今は海辺の町にいると調査の報告を受けます。実の父の居場所を突き止めた美波は、意を決して家族には内緒で、夏休みに実父に会いに行くことに。
いつまでも帰って来ない彼女を心配し、門司くんがその跡を追います。
若者たちに寄り添う前半。沖田監督は珍しく長回しの移動撮影を多用し、テンポよく物語を進めてくれました。
美波が実父に会う後半からは、沖田監督らしい「間」が描かれます。例えばテーブルを挟んで向き合う実父と美波。彼らを左右対称に真横から捉えた構図が何度も出てくるのです。人間関係の距離感が、2人の実際の距離を強調した構図で表現されました。しかし、お互いの気持ちが通じていくにつれ、距離は同じでも、2人の間にある空気はだんだんと優しく、温かくなっていくように見えてきたのです。
構図だけではありません。カットとカットの間。セリフの間。それらを積み重ねてオフビートなリズムを作ることで、微妙な感情を描き、ユーモラスな雰囲気を醸し出すこと。森田芳光監督の影響もありますが、雰囲気はより柔らかく、沖田監督独特の間になっていました。さらに「岩合光昭の世界ネコ歩き」サントラのタッチによく似た牛尾憲輔による劇伴がよく沖田監督の作品世界とマッチしていました。
放課後の喧噪。プールの匂りゆるく流れる時間。一見、普通の高校生の爽やかな夏の恋の物語に見えてしまう本作。けれでも美波の周りには、生き別れた父、怪しげな宗教、見た目は女性の門司の兄など、ややこしそうな事情が散りばめられていたのです。
美波はそんな周りの人とくだらない会話で屈託のない笑顔を見せる一方、大人たちの事情を察し、距離をはかりながら接していると見て取れました。
母(斉藤由貴)や血のつながらない父(古舘寛治)、門司の兄ら各登場人物からも、何気ない場面で、言葉にはしない心の奥やそれぞれのドラマから伝わってきました。
海辺のシーンでは、青い空や海に美波の焼けた肌の色が映えます。子供らしくはしゃぐ彼女の明るさがまぶしいかったです。そしてラスト。学校の屋上で、美波と門司くんが正座して向き合うのです。緊張すると笑い出してしまう美波は、笑いながら涙を流して門司くんに気持ちを打ち明けます。奇妙に見えて、しかし真っすぐな少女の気持ちを、上白石が実に見事に表現していました。そんな2人をカメラは向き合う真横から映す映像が印象的でした。2人の醸し出す「間」の凛とした美しさに深く胸を打たれたのでした。
人生、実はいろいろあるものです。それを知らないわけじゃない2人のラストシーンがまぶしすぎました。
追伸
水泳部の監督の語尾に強調する『なっ!』と同調を求める口調が、頭からこびりつきました。水泳部員たちも監督の口癖が病み付きになったのか、次第に部員の合い言葉に。美波が絶妙のタイミングで繰り出す『なっ!』には吹き出しました(^^)あれって茨城訛りなのでしょうか?(公開日:2021年8月20日)
会話とカメラワークが絶妙過ぎる
面白い
沖田修一の独特の「間」
沖田修一の独特の「間」。その「間」から創り出される唯一無二の空気感。
彼の作品、「おらおらでひとりいぐも」、「モリのいる場所」、「滝を見に行く」。すべてにその「間」がある。
その「間」を演じれるのが、上白石萌歌であり、豊川悦史である。
おねえ役の千葉雄大の存在も欠かせない。「ミッドナイトスワン」の中村倫也に匹敵するおねえぶり。
古本屋の店主の高橋源一郎も素人ながら存在感が光る。
上白石萌歌と古館寛治が、アニメの主題歌をデュエットするオープニングは、斬新な切り口。
パワハラのようでちっともパワハラでない、水泳部の顧問のキャラも、いかにも沖田修一らしい。
誇張がない、かっこつけない、かといってどん臭くもない、夏休みがそこにある。
タイトルが今一つ分からないが、結構な良作だった。 主人公・美波には...
大人はわかってくれない
主人公(上白石萌歌)は高校二年生の水泳部に所属する女子高生でアニメオタクでもある。
赤ん坊のときに出ていった父親の消息を、男友達の兄に頼む。
すぐに分かったがなんと、新興宗教の教祖だった。
とても面白く、上白石萌歌が最高。
共感性羞恥耐性を鍛える
さいきん共感性羞恥心という言葉をよく見かける。
ネットには、
『共感性羞恥とは、他人が恥をかいたり失敗したりする姿を見て、自分まで恥ずかしくなること。』
──と説明されている。
誰にでもある感覚だが、それを感じすぎる場合、HSP(Highly Sensitive Person)が疑われる──らしい。
HSP(Highly Sensitive Person)は「高感度な人」と訳されるが、臨床的にはプラス方向の意味はなく、言わば「ちょっとしたことが過負荷になってしまう打たれ弱い人」と俗解できる。
昔はなかったが、現代人は、さまざまな精神疾患をじぶんに当て嵌めることができるようになった。
わたしもそれにあやかって、じぶんの失敗した人生を“ビョーキ”のせいにしようと画策しているところだ。
それはさておき、かつては共感性羞恥心という言葉がなかった。
とは言うものの、はて、なんと言っていただろう。
はずかしい、いたたまれない、きもちわるい、きまずい、ぎこちない、ぞわぞわする・・・。英語だったらAwkwardかもしれない。
完全に合致する言葉はたぶんなかった。
これだけ感じる感情を言い表す言葉が昔はなかったことが驚きだ。
強いor鈍いゆえに共感性羞恥心を感じないひともいるであろう。そんな方に共感性羞恥心がどんなものか体感できる絶好のサンプルがある。「スカイピース 明日があるさ」で検索すると突起で大根をおろせるほど鳥肌立つこと請け合いだ。
言うまでもなく日本の映画/ドラマも共感性羞恥心の宝庫。
わたしたちが日本の映画/ドラマが嫌いな理由のひとつでもある。
面白くないうえに共感性羞恥心をいじられたら、たまったものではない。
とりわけ海外映画/ドラマを好む人が、たまに和製映画/ドラマを見たときに感じる共感性羞恥心は、はなはだしい。
作り手が撮影中のテイクに共感性羞恥心を感じないのが不思議でならない。
どんだけ共感性羞恥心耐性の高い人たちの集まりなんだろうか。
それとも(共感性羞恥心を)狙ってつくっているのだろうか?
日本映画/ドラマの品質というものは、われわれ素人にとって、謎のつきないミステリーである。
──
これは原作マンガを読んでいる。
原作は軽妙な夏物語になっている。
青春と夏と海なのに情熱的ではなく、積極的なコメディでもなく、ひとつ大人へちかづく少女を、ふわりとしたペーソスで描いていた。
問題は情熱的ではなくコメディでもない、少女の成長物語をふわりとしたペーソスで描くなんてことが日本映画にできるのか──という話。
映画は、作中アニメ「魔法左官少女バッファローKOTEKO」の一場面からはじまる。
原作ではそのアニメ及びアニメ内キャラクタをあっさりと扱っているのに対し、映画では冒頭から振り回してくる。しっかり作り込まれ、擬人化されたモルタルやコンクリやセメントが面白いことしてるでしょの承認欲をギラギラとみなぎらせ、アニメの熱狂的ファンらしい上白石萌歌と古舘寛治が展開に涙を流しながらダンスをする。・・・。
押してはくる。が、日本映画は引いてほしいときにぜったいに引いてくれない。
スカイピースの明日があるさに共感性羞恥心を感じるのは音痴だからでも低レベルの替え歌だからでもなく彼らがスベっていることに無頓着だからだ。
共感性羞恥心とは穴があったら入りたくなるような恥ずかしいことをしながらオフィシャルの体をしている“こと”や“モノ”のことだ。
(たとえば)商業施設で1,000人目の来場者にプライズをする場合、店はぜったいにそれに相応しい家族連れを選ぶ。凶器を隠し持ったようなチー牛を選ぶことはぜったいにない。
共感性羞恥心とは凶器を隠し持ったようなチー牛が商業施設の1,000人目の来場者としてプライズと写真撮影におさまるようなシチュエーションのことだ。
あるいは強面でまじめな一般庶民の老人が、外国人の大観衆を相手に、必死でダンディ板野の真似をする──というようなシチュエーションのことだ。
そういう、あきらかに常軌を逸する事態にたいして、共感性羞恥心を感じない人はたぶんなにかが抜け落ちている。
わたしたちはじぶんが持っている外観などの属性から、大幅に外れてしまうことをぜったいにしない。
『滑稽な外形を持った男は、まちがって自分が悲劇的に見えることを賢明に避ける術を知っている。もし悲劇的に見えたら、人はもはや自分に対して安心して接することがなくなることを知っているからだ。自分をみじめに見せないことは、何より他人の魂のために重要だ。』
(三島由紀夫作「金閣寺」より)
一般的に人は、人とのあいだを変な空気にしない。
原作にはどのキャラクタ間にもAwkwardがない。必要以上に気を遣ったり、言いよどんだり、つっかえたりして関係性に苦しさを感じることがない。
とりわけ主役のふたり朔田(上白石萌歌)は独立系(徒党を組まないタイプ)で楽天家、門司(細田佳央太)も独立系で超然型だった。
が、映画ではさいしょからずっとぎくしゃくする。映画の朔田と門司は、まるでお見合い中の処女と童貞のようだ。すなわち冒頭のアニメからずっと共感性羞恥心になやまされる。
実父(豊川悦司)と朔田が初対面できまづく押し黙るシーンも原作にはない。海パンで追いかけたり弾まない会話で食事したりむりやり三木聡風のオフビートをやったり映画はむしろ積極的に共感性羞恥心へ導いている。
しかし、なぜそんなことをするのだろう。まったくわからない。感覚のずれを飲み込むことができない。
いやわたしの主観なんぞはどうでもいいが、ふわりとしたペーソスをめざした原作者はこの映画の甲冑を着こんだようなぎくしゃくのキャラクタと空気感を見てどう思ったのだろうか。
ところで、言うまでもないが、これは重篤なHSPをわずらっているわたしの偏向評であって巷間では本作は概して好評を得ている。上白石萌歌も豊川悦司も熱演しているし、夏の気配と発色がいい。
ただじぶんはHSP(感受性過多)なので余計なこと(共感性羞恥心)を感じてしまった。見ていてずっとはずかしかった。疲れた。
PS:現代病ってとりあえず酷評の免罪符になるよね。
なんか、すごく、いい。観終わった今、爽快だ
水泳部の主人公が書道部の男子と知り合い、顔も知らない 「前のお父さん」 を訪ねてみる話。
オープニング、「お、実写なのにアニメシーンから始まるのか」 と思った。そしてこのアニメは本気だった。水泳部の主人公が書道部の男子と知り合ったきっかけは、ふたりともこのアニメのコアなファンだったから、というあくまでも材料なのだが、その力の入れ方と言ったら。オープニングでは5分超のストーリーを見せてくれるし、その後もストーリーと関連しあってしばしば現れ、主題歌だけでなく挿入歌まで作られているし、DVD5枚組パッケージも作ってあるし、なんと言ってもエンドロールで「アニメ制作」というパートで十数人のメンバーがちゃんとクレジットされているし。「魔法左官少女 バファロー コテ子」!(KOTEKO、が正しいらしいですね)
「壁は越えるものじゃなくて、塗りかえるもの。君と一緒に塗りかえていくんだ」 という歌詞がちゃんとストーリーとも重なっていて、すごいじゃん。
なんか、すごく、いい。観終わった今、爽快だ。
上白石さん(萌歌)、細田さん(佳央太)、最高。そしてそれにもまして、千葉さん(雄大)、すべての役の中でこれが最高だと思う。ほんとにはまってました。古館さん、齊藤さん、豊川さんといった頼りになる人たちを周りにおいて、若手ふたり(と千葉さん)を最大級に輝かせてくれた沖田監督、ありがとう!!
「人は教わったものは他の人に教えられるんだよ」というもじ君のセリフが最後までつながっていたり、なにかと気持ちがよい映画でした。
実父の家にもじ君がやってきてからのコメディは、秀逸。映画館中が笑い声であふれていた。「いや安心しな、読まれてないから。おんなじ苗字だから」「とりあえず入りなさい。・・いや、そっちじゃない」
おまけ
「江虫の愛」ってどんな菓子なんだろう?
あー、ホントに見逃さなくて良かったー‼️
沖田修一監督の傑作
アニメーションから入るの不思議な感覚だったけど、劇中限定とは思えないぐらいKOTEKOのクオリティがえぐい。そして声優陣が豪華。
このアニメを通して美波(上白石萌歌)ともじくん(細田佳央太)の距離が縮まっていくところも見どころ!
この作品って美波が自分が生き別れの父を探すことがストーリーで一番の核なんだろうけど、個人的にはそれ以外の部分も面白くて仕方なかった…!
お笑い要素も含んでいたし、是非映画館で見たかった…!
細田佳央太さんは「町田くんの世界」から知っていたんですが、お芝居が素敵ですね。大型新人俳優現る、と話題になっていた頃が懐かしいです。本当にこれからどんどんたくさんの作品で見たいです。
全99件中、1~20件目を表示