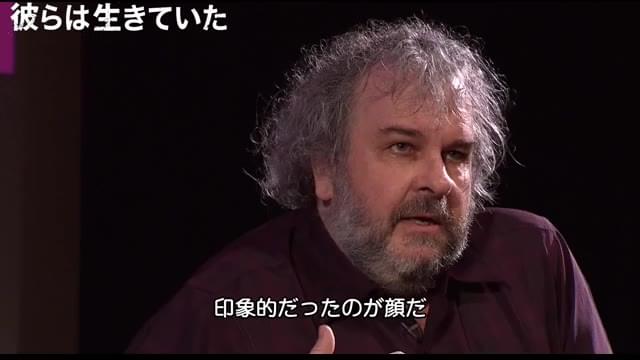彼らは生きていたのレビュー・感想・評価
全77件中、61~77件目を表示
膨大な手間をかけて再現された地獄絵図の向こうに透けて見える微かな希望が眩しい
あんまり見たことないロゴから始まる本作、英国の芸術プログラム”14-18NOW”と帝国戦争博物館の共同製作とのこと。モノクロな上に無音声で100年分の経年劣化で激しく傷んだ博物館所蔵の膨大な記録映像をデジタル修復の上着色。とても100年前の映像とは思えないほど鮮明で滑らかになった映像に被せられるのは、BBCが保存していたこれまた膨大な量の退役軍人のインタビュー、そして唇の動きから読み取った会話や地雷の炸裂、機銃掃射等の臨場感溢れる効果音。これはとにかく圧巻。
そしてまず驚かされるのは自ら志願して戦地へ赴く若者たちの素っ頓狂な明るさ。プロパガンダで鼓舞された愛国心と世界大戦に従軍する高揚感に背中を押されて、まだ徴兵制のない英国で年齢を詐称してまで従軍する若者達の満面の笑顔が眩しい。100年前なので風景もほぼ別世界。列をなす若者はほぼ全員洒落た帽子を被ってタバコをふかしている。6週間の訓練を経て送り込まれる最前線は地獄絵図。両軍の間に横たわるノーマンズランドに転がる無数の亡骸も容赦なく映し出す。束の間の休息で談笑した後もまだ殺し合いは続く。そしてさりげなく訪れる終戦。地獄から解放された若者達が苛まれるのは故郷に残った人々から浴びせられる罵声。そんなこともシレッと回顧する退役軍人達の声のトーンが明るいのが唯一の救い。人はこんな仕打ちも乗り越えて笑顔になれる、そんな希望が背後にあるから最後まで鑑賞出来ました。でなければ途中で吐くレベルです。
イギリス側の兵士から見た「西部戦線異状なし」
予告編を観て気になっていた、第一次大戦のドイツ対イギリスのフランスでの塹壕戦を描いたドキュメンタリー。
1915年から18年当時のモノクロサイレントの映像を修正着色して最新の映像に変換して当時の戦争帰還者のインタビューや談話を当てて構成されて映画。
戦争の発端には殆ど触れずに、当時のイギリスの若者達が、無邪気に志願して出兵して凄まじい戦場を経験して行く様が割と淡々と描かれる。
冒頭からは、スタンダードサイズ(昔のテレビと同じ正方形に近いもの)のモノクロだが、兵訓練が終わりフランスに出兵して最前線に到着すると、ゆっくり画面がカラーと横長になり、生々しさが加速してゆく。
そこからは、凄惨な戦場の様子の連発で、絶え間無い爆撃と塹壕での待機。
そして泥、汚水、ネズミやシラミの被害と不衛生な生活、突撃と後退の繰り返しにより仲間たちは減り、そして次々と無残な死体と凍傷や壊疽など負傷を見せつけられる。
悪夢と地獄が本当にある。
一進一退の戦いで、末端の兵士達には、次第に戦争の勝敗など、どうでも良くなり、名もない戦友や同じ境遇の捕虜のドイツ人達のつかの間の交流が唯一の慰みになる
そして停戦により国に帰ると次第にモノクロスタンダードに戻り、帰還兵達は、まるで地獄の戦場など存在しない様に振る舞う世間に戸惑う。
そこで映画は終わる。
復元着色されて映像は凄いが、本当の戦闘場面は、当時の時点で撮影出来なかった様子で、イラストや絵を使って処理されており、その部分だけは、推測による物語性が強い。
第一時大戦を描いた昔の名作映画で、「西部戦線異状なし」に描かれる内容に、とても酷似している内容だと思うが、あちらはドイツ人側が体験したフランス戦線の話だか、どちらも無邪気に志願した末端の兵士達に降りかかった戦場の地獄と祖国に、帰還してからの世間との剥離感が同じで、ここまで似てるとは。
さすがピージャク。
え、凄くない?
蘇った映像には感銘
より存在を近く感じる
語り継がれる話、「1917」にもつながる話
映画の紹介に追加すると、一部兵士の会話は、読唇術の専門家が読み取って、アフレコにしたらしい。
そう言う意味でも生々しい。
第一次世界大戦は、大量の弾薬や、映画の中にも出てくるが、世界で初めて戦車が投入され、毒ガスによる虐殺も行われた戦争だ。航空機も潜水艦も登場したが、まだ実験段階程度だったと言われている。
しかし、もっとも強調すべきは、国家が国民を総動員するような形で、兵士を募り、多くを戦場に送ったことだ。
これまでの戦争とは全く異なる様相になった。
少年もいた。
戦場に向かう時は、敵を鬼畜のように思いこまされる。
訓練時は、まだ、やる気満々だが、いざ戦場に送られると、そこは荒廃し切った西部戦線の塹壕で、人間のまともに生きていくような場所ではない。
そして、悪臭、死臭。
記録フィルムに色付けされたのを見て衝撃なのは、やはり兵士の血塗れの、身体の一部がちぎれたような遺体だ。
累々と積み重なっている。
ドイツ兵の傷を負った少年兵に水を飲ませてあげてお礼を言われたと語るところや、自分の父親によく似たドイツ兵士の身体が半分無かったと語る場面は、胸が締め付けられるようだ。
とても言葉では言い表すのが難しい。
そして、停戦。
捕虜にしたドイツ兵も何ら自分達と変わらない普通の人間。
結局、戦争とはこういうものだ。
砲撃を潜り抜けるように走る兵士を捉えてるシーンがある。
伝令かもしれない。
無線などない当時は、物事を伝えるのが命がけだったのだろう。
きっと、これから公開される「1917」に通じる場面ではないのかと思った、
第一次世界大戦の、この西部戦線の話としては、ドイツ人が実体験として書いた、「西部戦線、異常なし」がよく知られているが、映画にもなった反戦の作品だ。
この作品と通じるところがあるし、戦場の人の命のちっぽけさと、虚しさが綴られる。
結局、祖国に還っても、それ程歓迎もされず、仕事を見つけるのもままならない。
大規模な戦争の戦費は天文学的で、経済も疲弊するだけなのだ。
湯水のように使われる弾薬にも相当なコストが費やされている。
税金と国の借金で戦争を行い、それだけにとどまらず、志願して人の命も差し出せと。
第一次大戦は、冒頭で語られるようにサラエボ事件がきっかけだが、背景は複雑怪奇だ。
普仏戦争でアルザスロレーヌを取られたドイツのフランスに対する昔年の恨み。
オーストリア=ハンガリー帝国の弱体化と、東欧で起こった民族主義。
それに乗じて南進を企むロシア帝国。
南進を喰い止めようとするオスマン帝国。
イギリスとドイツの植民地政策の対立、つまり3C政策と3B政策の対立。
直接的には関係ないのに、インド、日本、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランドなど離れた国の参戦。
この中で、二つの勢力に分かれて戦ったのだが、兵士のアイデンティティは一体どこにあったのだろう。
どこも異なるところないもの同士が、誰かに言われて憎しみあって殺し合っただけなのだ。
いつも、こうした戦争は、悲劇でしかない。
実は、この対戦の後、反省のもとに、さまざまな講和や国際連盟の設立などが行われるが、ドイツを必要以上に締め付けすぎたことや、なんら植民地主義に変わりは無かったこと、国家間の富の格差などがこの残り、結局は第二次世界大戦につながってしまう。
人間はつくづく馬鹿だと思わざるを得ない。
人は、人を殺したことを、この映画にもあるようにおぞましいと感じることが出来るが、AI搭載の武器だったらどうだろうか。
限界まで殺し続けるのだろうか。
この映像の中で、彼らは老いずに生き続け、僕達に語り続けるのだ。
むごい
イギリスに残る第一次世界大戦の記録映像を修復し、BBCの退役軍人たちの証言インタビューと合わせて、ピーター・ジャクソン監督が編集したドキュメンタリー。
冒頭はモノクロのスチール写真を使っていたが、西部戦線でのドイツvsイギリスあたりからカラー着彩の動画に変わり。
塹壕に浸かって壊死した足のドアップや、撃たれて死んだ英独兵士の顔やハラワタまでカラーなのは、なかなかのインパクト。
証言の繋げ方によるものではあるが、「仲間と気軽に祖国のために」と志願したところから、地獄を見て、やっと国に戻ったら市民から差別され汚いもののように扱われ、失業して生きていけないという現実まで、克明に描かれていた。
根底にはピーター・ジャクソン監督の、祖父やその代の先祖たちへの敬意と、戦争を繰り返してはならないという思いを感じました。
私は戦争に参加した彼らと似たような感覚で映画を見てしまった。
モノクロからカラーへ、戦争の悲惨さがリアルに蘇る!
「戦争に参加しないものは臆病者だった。」
臆病者と思われたくない、友達も参加するから一緒に参加しよう。
そんな軽い気持ちから参加することにした当時のイギリス人の姿が、何故か現代の若者の姿にダブって見えてしまいました…。
やりたいことも特にない、友達がいるから参加したい。
よくあるなし崩しな感じの参加だったはずなのに、いざ始まってみるとそれは想像以上に過酷な世界でした。
戦争前のモノクロだった世界に、戦争スタート直後から、鮮やかな色彩が加わった瞬間。
まるで寓話のようにしか思えなかった世界が、突如として鮮やかに目の前に現れる感覚。
これは、なかなかの衝撃的な印象でした。
銃を片手に溝に潜り込み、敵がいつくるのか待ち続ける、ジリジリする緊迫した世界。
いつ、自分が殺されるかわからない状況の中、仲間の存在は常に自分の心のそばにあったとのこと。
でも、いざ隣にいた親友が銃弾で撃たれて死んでしまえば、突如として仲間の存在は自分から離れていく…。
自分たちが潜んでいる場所の数メートル先で、死んでいった仲間が腐ってネズミに喰われていくという…。
そんな悲惨な現状が、カラー画像によって鮮やかに蘇ります。
モノクロの漠然とした映像ばかりだった戦争が、緻密に悲惨に残酷に冷静に、映像から全てを伝えてきます。
上官の命令から始まり、鐘の音と共に静かに終わりを告げた戦争。
この戦争で彼らが得たものって、なんだったのでしょうか?
戦争が終わっても、街中の人々は戦争のことを一切語らず、帰郷してきた兵士にも冷たい態度。
更には、就職先まで見つからないという過酷さ。
命がけで戦い抜いて生き残った自分の存在価値って一体なんだろう…。
虚無感の残る、悲しく寂しいラスト。
その後、こんな悲しい出来事があったにもかかわらず、第二次世界大戦がまたまた勃発してしまうのですから切ない…。
あれだけ悲しくて辛い思いをして来たのに、また戦争が起こってしまうのですから、人間って実に愚かな生き物。
鮮やかすぎる映像故に、そのリアルな生活感と虚無感が全身を包み込むラストでした…。
貴重な映像をありがとうございました(^^)
タイトルなし
祖国の敵は自分の敵と
年齢までも偽り戦地に赴く
一緒にいた仲間が一瞬のうちに無に
それを悲しむまもなく
勝敗などどうでも良くなる
ただ戦うだけ
.
『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズの
ピーター・ジャクソン監督渾身の一作
.
彼らは生きていた
映像の中には
敵意に満ちた人々の姿ではなく
私たちと同じ普通の人々が
戦地にいました
観賞後 頭と心に穴が空いてしまったような
空白の時間が続き 戸惑いも
「戦争は無意味
避ける努力をしなけれれば」
復員兵のインタビュー音声から聞こえた
そんな言葉が心に深く残っています
.
兵士たちがみた戦争の記録として
平和に暮らせてる今だからこそ
戦争をしてはいけないとわかっている頭にも
この映像を観て
記録しておかなければならないと思う
*2021/4/17再鑑賞
さすが!本物の映像・音声
全77件中、61~77件目を表示