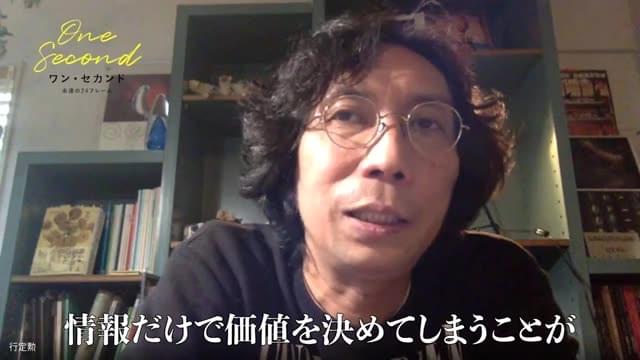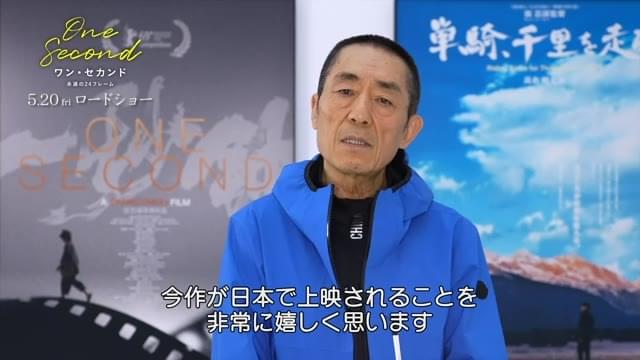ワン・セカンド 永遠の24フレームのレビュー・感想・評価
全6件を表示
表現の不自由な国で作られる映画の不幸
中国で毛沢東が主導した文化大革命の真っただ中、1969年のとある村を舞台に、映画館に関わる人々が巻き起こす「ニュー・シネマ・パラダイス」的な人情話……のように物語は展開する。
縁を切られて会えない愛娘の姿がニュースフィルムに1秒だけ収められていると知った男が、強制労働所から脱走し、村の映画館で観ようとする。だがフィルムが少女に盗まれたり、保管用の缶から飛び出して地面の泥にさらされ汚れたりと、なかなか上映される段にまでたどり着かない。当初は反目しあっていた男と少女だが、やがて奇妙な絆が生まれて……。
しかし観ていて、違和感を覚える点もあった。男はなぜ、1秒だけの娘の映像を繰り返し見せろとしつこく要求するのか。2年後に釈放されて、自分の娘ではなく少女に会いに行ったのはなぜか。
プレス資料に高原明生氏が寄せた解説(劇場パンフにも掲載されると思われる)を読んで、その理由が分かった。映画では元々、娘が事故で亡くなったことを主人公の男は知らされていたのだという。しかし、文化大革命が引き起こした悲劇という要素を、検閲当局が「あまりにも暗くて悲惨だと判断したため、編集を余儀なくされたものと思われる」としている。
確かに、死んでしまい二度と会えない娘の姿をせめて映像で見たいということなら、あの必死さも理解できるし、孤児の少女に亡き娘を重ねて釈放後に会いに行くのも納得がいく。だが、その肝心のポイントが検閲されてぼかされ、違和感のあるストーリーになってしまった。
監督は巨匠チャン・イーモウ。北京2022冬季オリ・パラで開閉会式の総監督を務めたということで、体制側に近い人物との批判があるのも無理はない。現在の習近平政権は、文化大革命そのものの歴史的意義は否定したとされるが、自らすでに「第二の文化大革命」を推進中との見方もあるようだ。いずれにせよ、文化大革命に関する話は現在の中国でも依然として取扱いが難しい、ということを本作は示唆している。
1秒のフィルム
『活きる』『初恋のきた道』『サンザシの樹の下で』『妻への家路』に続くチャン・イーモウ監督5度目の文革映画だが、同時にこれはフィルム映画という今やデジタル化で失われつつある映画への愛に満ちた“映画の映画”でもある。果てしなく続く悠久の砂漠のシーンなんかは、チャン・イーモウが撮影を務めたチェン・カイコー監督のデビュー作『黄色い大地』など第5世代の初期作品を思わせた。映画上映のシーンは日本で言えば戦前とか戦後すぐみたいな時代なので、さすがに僕が物心ついた頃の映画館はああではなかったが、子供のころにやってたスライドや8mmフィルムの上映会みたいなのを思い出したな。館主がフィルムをぐるっとつなげて無限ループ上映できるようにするところなんかは、イーモウお得意の大仕掛け嘘道具と思われ、なかなか面白かった。
これがデビュー作だったヒロインのリウ・ハオツンはすっかり売れっ子スターだそうで、これまでコン・リー、チャン・ツィイー、ドン・ジエ、チョウ・ドンユイ、ニー・ニーとニュー・ヒロインを次々発掘してきたチャン・イーモウの面目躍如といったところか。
ただ最後のエピローグは余計な蛇足に思え、なんか不自然な気がした。と思ったらパンフレットを読むとやはり当局の検閲でラストが悲劇的すぎると修正命令が出て追加撮影したらしい。また主人公の娘が実はすでに労働中の事故で死んでおり、そのために娘の姿をもう1度見たい主人公は娘がわずか1秒だけ映ったフィルムを探していたという重要な描写もやはり悲劇的すぎるとの理由でカットされてしまったとのこと。その2つの修正がないほうが絶対により胸に残る映画になっていたはず。まったく持って権力による検閲というのはろくなことをしない。
あと邦題はもう少しなんとかなんなかったのか。
フィルムを巡るエピソード
中国の田舎町では地域の公民館で映画を上映しているらしい、次の公民館にフィルムを運ぶために青年がバイクのバックにフィルムを乗せるが、夜は運ばないと言ってそのまま酒場に入ってしまう、なんとも不用心だと思ったら案の定、バイクから少年がフィルムを盗む、偶然目撃した男が追跡しフィルムを取り返すが、頭を殴られ、また奪われてしまう。しばらくは取り返したり盗られたりの繰り返し・・。
少年と思ったが実は少女だった。男は映画の冒頭、砂漠を歩いており放浪者かと思ったが訳あって、とあるニュース映画を観たがって上映先を探していたらしい・・。
タイトルの24フレームは映画フィルムの1秒間のコマ数、男が見たかったニュース映画に死んだ娘が1秒間だけ映っていたことを指しているのでしょう。男のフィルムへのこだわりは分かったが、少女がフィルムを盗むのはフィルムでランプシェードを作りたい一心、弟の為だと言っているが盗んだりナイフで襲ったりと根っからの犯罪者のような演出は甚だ疑問、おまけに2年も経ってから砂漠に捨てられた2コマのフィルムの切れ端を探す様、どう考えても無理でしょう。娯楽もなく映画館も少ない時代に町の公民館で上映される映画を多くの町人が楽しみにしているのは伝わりましたし、汚れたフィルムを皆で洗って乾かす様は熱意は感じますが、映画愛とは異質でしょう。
映画好きな町民たち、映画本編ではなく娘の映ったニュースに惹かれただけの男、単に物理的なフィルムを欲しがる少女、ドジな運び屋、生真面目な映写技師などフィルムを巡る様々な視点で描いたエピソード集、巨匠チャン・イーモウ監督作ではありますが作家性が強すぎて好みではありませんでした、ごめんなさい。
ファン電影
なんという名前。そのまま映画大好き映写技師を象徴するようなネーミング。中国で一人しかできないと自慢する連続投影のシーンは胸が熱くなった。
終盤はとても良かったし、映画ファンにとっては『ニュー・シネマ・パラダイス』を想起せずにはいられないほど映画愛に満ちているのです。ただ、序盤のドタバタ喜劇風の展開はさほど魅力を感じなかったし、逃亡者(チャン・イー)が過酷な強制労働や脱獄シーンすらなかったことに平穏すぎて感情移入も半減。
さすがにオリンピックの総監督を引き受けたほど国民的大監督のチャン・イーモウだけに検閲の目も光っていただろうし、文化大革命批判の描写はカットされたのかもと想像してしまう。逃亡者もファン電影もリウの娘もいい感じで終わり、めでたしめでたしとなってしまえば駄作となってしまう・・・と思っていたが、ファンの息子ヤンのエピソードが語られると、さすがに目が潤んでしまった。そしてラストには孤児少女と再開して、彼女を養女として育てていくのかな~などと想像させる演出もにくい。
劇中劇でもある『英雄子女』はチャン・イーモウが選んだのかどうかは知らないけど、反米作品なのだろう。そして第22号ニュース映像。たった1秒しか映っていない生き別れとなった娘の姿を何度も見たい。そんな逃亡者の気持ちもよくわかるし、心を汲み取ったファン電影の優しさも心地よい。幼い頃は映画本編前に必ずニュース映像が流れてたなぁ~などと、懐かしく感じてしまいました。いつから無くなったんだろう?
未だに検閲が続いてるのか
途中不可解に思った点もプロレビュワーの方が書いたレビューで判明した。
パンフレットに主人公の設定が書かれていたんですね。
しかも、当初はきちんとその設定の説明描写が映画の中にあったのに当局の検閲で再編集を余儀なくされたとか・・・
多少マシになったのかもしれないが、本質的には文化大革命の頃と変わってないんだなと思ってしまった。
そういうことならラストシーンも納得がいく。
冒頭の明らかな引き伸ばし描写を除けば普通に良作。
うーん
何を表現したかったのか、今一つはっきりしないですね。フィルムを探す父親の苦労と愛情劇なのか、フィルム争奪を描くドタバタ喜劇なのか…。唯一、当時の中国における娯楽としての映画のあり方がよくわかり、田舎者の自分も公民館に暗幕を張って上映されていた映画をすし詰め状態で見たのを思い出し、ある種の郷愁を得た事ですね。
全6件を表示