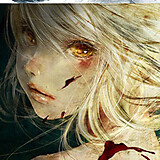ROMA ローマのレビュー・感想・評価
全141件中、1~20件目を表示
時と場所の垣根を超える、モノクロゆえの親密さ
ああ、いいもの観たー、と久々にしみじみと思った。その一方で、この素晴らしさは、言葉にするのは難しいな…とも。けれども、やっぱり自分なりに心に留めておきたいので、敢えて言葉にしてみようと思う。こぼれ落ちないように、余計なものを足さないように。
「天国の口、終わりの楽園。」に出会って以来、アルフォンソ・キュアロン監督について行こうと決めた。だから、当時距離を置いていたハリー・ポッターシリーズも「アズカバンの囚人」だけは、いそいそわくわくと足を運び、今も子らに推している。 そんなキュアロン監督の新作を、映画館で観ることができる。席に着いただけで、すでに満足感があった。
冒頭のクレジットの背景で、白地に点在する黒いものが取り除かれ、何度も洗い流される。これは何だろう…と、じーっと観ているうちに物語は幕を開ける。少しすると冒頭の種明かしになり、凝視していた分気恥ずかしくなるのだけれど、それはいっときの話だ。
家政婦として働く、あどけなさが残るヒロイン・クレオは殆どしゃべらないし、情感を盛り上げる音楽も流れない。掃除に洗濯、料理に子守を求められるままに黙々と片付ける。彼女の思わぬ妊娠から出産を横糸に、挟み込まれる暴力的な内乱を縦糸に、淡々と物語は進む。彼女が寡黙な分、働いている家の中でのいさかいや、街の喧騒が耳に刺さる。
分かりやすい事件は起きず、彼らの日常にいきなり放り込まれた感覚が強い。初めは少々面喰らう。けれども、モノクロの画面に向き合っているうちに、いつの間にか、彼らと共に過ごしているような気持ちになっていく。
物語になじみ、気を許して身を委ねていると、終盤でふたつの大きな揺らぎが現れる。人の限界を突きつける一度めと、自然が牙をむく二度め。彼らを容易く呑み込もうとする画面いっぱいの波に圧倒されながらも、まばたきを惜しんで見つめずにはいられない。モノクロゆえに、泡立つ波の白さ、砂のざらつきや体温が生々しく想起される。身を寄せ合う彼らの輪に自分も加わっているような、不思議な親密さに包まれて、胸が熱くなった。
夢から覚めるように、物語は終わりを迎えてしまう。けれども今も、私の一部は、時と場所を超えて彼らとともに生きている。同時に、彼らがひっそりと私に寄り添ってくれている。(特に、クレオのように荒れた部屋を片付けているとき、汚れものをきれいにしているとき、洗濯を干しているとき、彼女と繋がっていると思える。)そんな得難い感覚を日常に与えてくれる、かけがえのない作品だ。
追記: モノクロ、区切られた空間の中の移動という骨組みは共通しているけれど、物語は対照的な「ヴァンダの部屋」との二本立て、体力が許すならば観てみたい。
画面を支配する"グレーのグラデーション"
広い邸宅のリビングからキッチン、階段を上った先にある個々の部屋、洗濯物を干すベランダ。ゆったりと動くカメラが映し出すのは、外からの光の案配や、前後の位置関係によって微妙に変化する"グレーのグラデーション"だ。ただ色彩を排除することで色を想像させるのでもなく、モノクロの美しさを単純に探究するのでもなく、これほども豊かな映像表現というものに久しく出会ってない気すらする、撮影監督、アルフォンソ・キュアロンの戦略的カメラワークに思わず惹きつけられる。そして、一人のメキシカン・ネイティブの家政婦の体験をベースに綴られる、廃れゆくブルジョワ家族の儚さと悲しみに心が震える。メキシコの近代史を描きながら、この映画が国籍や人種を越えて人々にアピールするのは、誰の胸にもある懐かしい我が家の記憶を呼び覚ますからだ。時は移り、記憶は薄れ、国家は分断され、国境に壁が建設されても、家族という最小で最強のコミュニティは存在するはず。監督、キュアロンの祈りのメッセージは、今、ストリーミングを通して世界中に伝播中である。映画はあくまで"どう作る"であり、"どう見せる"ではない。筆者はキュアロンの意見に賛同する。
最悪ではない不幸の先の光
AMOR ~メキシコ ローマ地区での愛~
アルフォンソ・キュアロン監督は『ゼロ・グラビティ』(2013年)で、“宇宙の映像は作れる”ということを証明してくれました。まるで本当に宇宙で撮影したかのような臨場感のある映像で、もし本当に宇宙があるとすれば、そこは恐ろしい場所であるという現実を見せつけてくれました。
今作は2018年に、1970年から1971年のメキシコのローマ地区を舞台にした家政婦に焦点を当て、Netflix作品としてモノクロ映画というスタイルで登場しました。
ナレーションやBGMといった、わかりやすい演出はなく、淡々と横にスライドするカメラワークで、当時の人々の様子を冷静に見るというスタンスです。手前も奥もピントがあっているため、VRのように自由に好きなものを見ることができます。
平面な広い大地を感じます。
海のシーンの後、カメラの動きが変わります。
背景も人もリアルにCGで作れるとしても、これほど拘って当時のメキシコのローマ地区を再現したのは何故なのか、考えてしまいました。
まるでイタリアのローマにあるような建造物に注目してほしいのか、メキシコの歴史に興味を持ってもらいたいのか、家族の愛(ROMAとAMOR)について描きたいだけではなさそうです。
撮影方法等についても魅力を感じます。Netflixで配信されているメイキングドキュメンタリー『ROMA/ローマ 完成までの道』を観たいと思います。
『ROMA』で体験する映像と音が織り成す「時間」と「社会」
Netflixで視聴した映画『ROMA』は、従来のストーリー重視の映画とは一線を画す、映像詩のような作品でした。1970年代初頭のメキシコシティを舞台に、中産階級の家庭で働く家政婦クレオの日常を静かに描いています。劇的な展開は控えめですが、暴動や社会階層の描写を通して当時の歴史的背景が自然に浮かび上がり、映像と音の織り成す空気感に深く引き込まれました。
クレオの無口で表情の少ない姿がかえって彼女の存在感を強調し、物語を動かすのではなく社会の一部としての彼女の立場を感じさせます。街の騒音や鼓笛隊、犬のフンなど細かな象徴も印象的で、普段の映画とは違った時間の流れを味わえる作品です。ドラマ性を求める人には向かないかもしれませんが、映像の美しさや歴史の空気感をじっくり味わいたい方には強くおすすめします
とても澄んだ作品
「ゼロ・グラビティ」がすごく良かったので、アルフォンソ・キュアロン監督作品である本作も鑑賞。
なんときれいなモノクロだろう。生々しいほどの日常生活もきれいに撮れていて映像がとても澄んでいるため、生活音や街の喧騒すら心地好く感じる。日常的な雑多な音の拾い方が絶妙で、耳に届くちょっとした音すら澄んでいる。
そして、時代のせいか一部例外の男性もいたものの、基本的には登場人物皆の心も澄んでいるので、ストーリー全体としてもとても澄んでいる。特に、海で溺れた子供達を迷わず救った主人公の損得勘定なしの澄んだ心は、まっすぐ過ぎて思わず涙してしまったほどだ。
その他にも本作にはコメディチックなトリッキーさもあり、とても魅力に溢れた作品だ。
それにしても、時たま映り込む飛行機、なかなか良いアクセントになっていたな。
さすがはアルフォンソ・キュアロン監督、次作は必ず劇場で観るぞ。
民族間や他人との見えない壁を痛く感じさせる作品。
内容は、アルフォンソ・キュアロン監督の幼い時の回想録を映像化。監督自身の切り取った少年時代1970〜1971年を再構成した作品。主に召使い女性クレオ・グティエレスを主人公とし当時のメキシコを感じさせる繊細で臭いまで伝わって来そうな迫力ある激しくも静かな作品。印象的な言葉は『ミドルネームも歳や年齢も知らない。関係は、雇用主よ。』作品終盤に起こる破水と出血で緊急に病院に行くが受付でお婆ちゃんが話す言葉。召使い感が半端なく大切に扱ってもらってる様で、全然違うことが分かり寂しく感じました。印象的場面は、その後の病院で死産した時に対する寂しそうな主人公の顔と安堵や後悔にも似た表情が印象的でした。観てるこちらまで胸に詰まる。その後に『欲しくなかったの…』の言葉には、裏腹に元気に産まれて欲しかった様な気持ちが見え隠れして何とも言えませんでした。全体的に凄いエキストラの数と構図、シネマスコープの表現はテレビで観た事を後悔しました。監督の少年時代を違った角度で覗き見る事の出来る面白い作品だと思いますが、前半はあまりに単調なので挫折する人は多いと感じました。最後にギリシャのローマではなく、メキシコシティー郊外のコロニア・ローマが舞台だったと観終わってから合致したのが一番スッキリしたという情けない自分自身の観点です。
心を揺さぶる
水、そして羊水、波
70年代メキシコの夜ドラ
色がなくても生きている愛が鮮明に伝わってくる
全編モノクロで音楽もないので淡々と静かに進む印象だが、ドラマチックな展開をスマートに差し込んできてその世界に惹き込まれていく。情報が少ない分、役者の機微に注目できるという効果がある。演技未経験者を起用した狙いもあり、息遣いが自然な仕上がりとなっている。
流れていく日常の中にある、奇跡的でありときに残酷な命の尊さが描かれている。表裏一体である生と死を対比させることで、生きていること、生きていくことを改めて解像度を上げて考えさせられる。
彼氏や父親という男が悪のようにされている部分もあるが、それは子どもを産み育てる女性への畏敬の念の現れであると感じる。
そしてまた、決して血のつながりだけが家族ではない。
舞台はメキシコシティでタイトルの『ROMA』は何かと思っていたら、逆から読むと「AMOR」となりスペイン語で「愛すること」という意味。アルフォンソ・キュアロン監督が、故郷、家族、育ててくれた人への感謝を込めた映画だ。
Netflix製作で、ネット配信映画から初めてアカデミー賞が出たのが頷ける作品である。
メキシコについて知っていること
「ゼロ・グラビティ」以来のアルフォンソ・キュアロン。事前の知識はNetflix、東京国際映画祭、ヴェネツィア金獅子、アカデミー外国語映画賞だけ。予告編もみていなくて、3月からシアター公開されていたことにも気づかずにいた。Netflixの無料体験で見られるのだろうか、とボンヤリ考えていたほどだ。
同じシアターの同じ時刻に、ゴダールの「さらば、愛の言葉よ」がかかっていて、チケット窓口に並ぶ多くがそっちに行った。
こっちのほうが断然いい。そっちを見に行ってほとんど寝ていた私が保証する。
この作品の強度は、「牯嶺街少年殺人事件」に匹敵する。
学生のころ、モントリオールに滞在したとき、メキシコからの同世代と知り合った。みんなヒスパニックで、ネイティブ・アメリカンはいなかった。ビックリするほどのスパニッシュビューティーもいた。家にプールがあったりする、少なくとも中産階級以上だった。この作品の家庭みたいなんだろう。
それももう四半世紀以上も前だ。そのころの私のメキシコのイメージはルチャリブレ、マラドーナのW杯、そんなところだった。いまもたいして変わらない。当時のイメージも間違っていただろうし、いまはずいぶん変わっているだろうけれど。
決して救うことはできない距離感で我々は歴史を見つめている
徹底的なひきの構図、一定の距離で縦と横に移動するカメラワーク、白と黒の間のグラデーションの間で揺蕩う景色。
これを観ている我々が神の目線にいることを意識した造りである。
昨今は臨場感や主観性、共感性を観客に与えるために、そのようなことを意識させない造りが主である。
あたかも我々が映画の中にいるような作りとでも言おうか。
しかし、この映画は我々をその世界の中には入れてくれない。
あくまで外から、神や幽霊の目線から、この世界に生きる人々を眺め続けなければならない。
だからこそ、この不条理な世界の惨状に憤りを覚え、無力感に襲われる。
救いの手を差し伸べたい欲求に駆られる。
ベルリン天使の詩の天使のような気持ちにさせられるのだ。
しかしどうやったって地上に降りることのできない私たちは、この映画の結末を見守るしかない。
映画を通して我々が目撃するのは、
愛で傷つき、愛で救われる人々の普遍の在り方である。
そして終盤にかけて、この映画の徹底的な構図やカメラワークのこだわりこそが一種の伏線であったと気付かされたとき、その驚くべき映画の完成度に圧巻させられる。
そしてこれは、監督自身が「大切な誰かのために」、また「この時代だからこそ」作らなければならなかった映画だったことを知る。
バックグラウンドから構図、映像美、サブテキスト、など様々な難解さを自然と盛り込みながら、これほど愛に満たされ、人の感情を滑らかにさせる映画は稀有である。
50年前の世界を、よく再現しているとは思いました。
現代芸術の祭典、たとえば瀬戸内の直島とか、越後妻有トリエンナーレとか、金沢21世紀美術館とか、そういうところに行くと、決まってモノクロの映像が何カ所かで放映されています。
それらモノクロ映像は、制作者たち自身は独自のゲージュツを目指しているつもりだろうと思いますが、出来上がりを鑑賞する部外者の立場から見ると、典型性、類型性が観て取れます。
すなわち、
(1)あえて白黒の映像。
(2)ストーリーが皆無。
(3)BGMもないのが通例。
(4)現地のクリアな音や息吹、つまり空気感を丹念に流す。
こういう典型的・類型的な点が、現代芸術のアーティスト達の間での流行なのでしょう。
アルフォンソ・キュアロン監督のこの映画は、そういう最近流行の「感覚に訴えかける空気感の映画シリーズ」の潮流の上に乗る一本だと考えると腑に落ちます。
アカデミー賞を獲れたのも、選考する人たちがゲージュツ家の一群だからだと思います。
もちろん2時間もの間、「なんのストーリーもない感覚だけの映像」を見せられたのでは退屈で死んでしまうので、この映画には最低限のストーリーはあります。
しかし、ストーリーを楽しむ、つまり頭脳で理解することを求めるのではなく、感覚が人間内部にダイレクトに何かを賦活するのを愉しむ、そういう映画なのだと思います。
なので、THXなどの音響効果の良い映画館で観ることが絶対のお勧めです。
この点、映画とすれば面白い試みに見えたのかも知れませんが、現代芸術の潮流の中からは一歩も踏み出していない作品なので、まあ★4つかな、と。
普通の音響効果の映画館で観たなら、★3つかも。
家で貸しビデオで観たら、怒りのあまり★一つしか付けなかったかも知れませんが、それは鑑賞環境の問題で、これほど環境に左右される映画は珍しいかも知れません。
というわけで、50年前の世界を現代に再現してみせているこの映画、音響の整った映画館で、観て、聴いて、感じるなら、損はないと思います。
きめの細かいモノクロ
情緒という名の色彩
難しい
モノクロ映画とカラー映画は似て非なる物のような
印象を受ける。
絵画的に感じるし、
一つ一つの絵を大事にしてるように思えて、
それ故に時に不自然な動き?
カメラに寄って来るような動きをして、
それは舞台のような生々しさもあった。
1人の女性の激動の一年はわかるのだけど、
何が評価されてるのかが全く分からなかった。
分からない事が多過ぎた。
ぺぺの前世の話。
ゼログラビティを彷彿とさせる宇宙映画
謎の武術集団と怪しい先生。
サクッとやるなら分かるのだけど長い事回してたのは
何か意味があるのだろうか?
何故犬の糞を取らないのか?
今アメリカでの白人警察による黒人殺害事件を受けて、
奴隷制度を思い、それに比べて
メキシコの中流階級の家族と召使いさんの関係は
とても美しかった。
映画評論家に説明してもらいながら観たい映画だった。
全141件中、1~20件目を表示