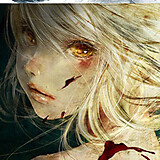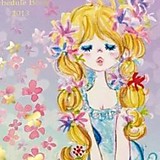ROMA ローマのレビュー・感想・評価
全172件中、21~40件目を表示
メキシコについて知っていること
「ゼロ・グラビティ」以来のアルフォンソ・キュアロン。事前の知識はNetflix、東京国際映画祭、ヴェネツィア金獅子、アカデミー外国語映画賞だけ。予告編もみていなくて、3月からシアター公開されていたことにも気づかずにいた。Netflixの無料体験で見られるのだろうか、とボンヤリ考えていたほどだ。
同じシアターの同じ時刻に、ゴダールの「さらば、愛の言葉よ」がかかっていて、チケット窓口に並ぶ多くがそっちに行った。
こっちのほうが断然いい。そっちを見に行ってほとんど寝ていた私が保証する。
この作品の強度は、「牯嶺街少年殺人事件」に匹敵する。
学生のころ、モントリオールに滞在したとき、メキシコからの同世代と知り合った。みんなヒスパニックで、ネイティブ・アメリカンはいなかった。ビックリするほどのスパニッシュビューティーもいた。家にプールがあったりする、少なくとも中産階級以上だった。この作品の家庭みたいなんだろう。
それももう四半世紀以上も前だ。そのころの私のメキシコのイメージはルチャリブレ、マラドーナのW杯、そんなところだった。いまもたいして変わらない。当時のイメージも間違っていただろうし、いまはずいぶん変わっているだろうけれど。
決して救うことはできない距離感で我々は歴史を見つめている
徹底的なひきの構図、一定の距離で縦と横に移動するカメラワーク、白と黒の間のグラデーションの間で揺蕩う景色。
これを観ている我々が神の目線にいることを意識した造りである。
昨今は臨場感や主観性、共感性を観客に与えるために、そのようなことを意識させない造りが主である。
あたかも我々が映画の中にいるような作りとでも言おうか。
しかし、この映画は我々をその世界の中には入れてくれない。
あくまで外から、神や幽霊の目線から、この世界に生きる人々を眺め続けなければならない。
だからこそ、この不条理な世界の惨状に憤りを覚え、無力感に襲われる。
救いの手を差し伸べたい欲求に駆られる。
ベルリン天使の詩の天使のような気持ちにさせられるのだ。
しかしどうやったって地上に降りることのできない私たちは、この映画の結末を見守るしかない。
映画を通して我々が目撃するのは、
愛で傷つき、愛で救われる人々の普遍の在り方である。
そして終盤にかけて、この映画の徹底的な構図やカメラワークのこだわりこそが一種の伏線であったと気付かされたとき、その驚くべき映画の完成度に圧巻させられる。
そしてこれは、監督自身が「大切な誰かのために」、また「この時代だからこそ」作らなければならなかった映画だったことを知る。
バックグラウンドから構図、映像美、サブテキスト、など様々な難解さを自然と盛り込みながら、これほど愛に満たされ、人の感情を滑らかにさせる映画は稀有である。
50年前の世界を、よく再現しているとは思いました。
現代芸術の祭典、たとえば瀬戸内の直島とか、越後妻有トリエンナーレとか、金沢21世紀美術館とか、そういうところに行くと、決まってモノクロの映像が何カ所かで放映されています。
それらモノクロ映像は、制作者たち自身は独自のゲージュツを目指しているつもりだろうと思いますが、出来上がりを鑑賞する部外者の立場から見ると、典型性、類型性が観て取れます。
すなわち、
(1)あえて白黒の映像。
(2)ストーリーが皆無。
(3)BGMもないのが通例。
(4)現地のクリアな音や息吹、つまり空気感を丹念に流す。
こういう典型的・類型的な点が、現代芸術のアーティスト達の間での流行なのでしょう。
アルフォンソ・キュアロン監督のこの映画は、そういう最近流行の「感覚に訴えかける空気感の映画シリーズ」の潮流の上に乗る一本だと考えると腑に落ちます。
アカデミー賞を獲れたのも、選考する人たちがゲージュツ家の一群だからだと思います。
もちろん2時間もの間、「なんのストーリーもない感覚だけの映像」を見せられたのでは退屈で死んでしまうので、この映画には最低限のストーリーはあります。
しかし、ストーリーを楽しむ、つまり頭脳で理解することを求めるのではなく、感覚が人間内部にダイレクトに何かを賦活するのを愉しむ、そういう映画なのだと思います。
なので、THXなどの音響効果の良い映画館で観ることが絶対のお勧めです。
この点、映画とすれば面白い試みに見えたのかも知れませんが、現代芸術の潮流の中からは一歩も踏み出していない作品なので、まあ★4つかな、と。
普通の音響効果の映画館で観たなら、★3つかも。
家で貸しビデオで観たら、怒りのあまり★一つしか付けなかったかも知れませんが、それは鑑賞環境の問題で、これほど環境に左右される映画は珍しいかも知れません。
というわけで、50年前の世界を現代に再現してみせているこの映画、音響の整った映画館で、観て、聴いて、感じるなら、損はないと思います。
きめの細かいモノクロ
情緒という名の色彩
難しい
モノクロ映画とカラー映画は似て非なる物のような
印象を受ける。
絵画的に感じるし、
一つ一つの絵を大事にしてるように思えて、
それ故に時に不自然な動き?
カメラに寄って来るような動きをして、
それは舞台のような生々しさもあった。
1人の女性の激動の一年はわかるのだけど、
何が評価されてるのかが全く分からなかった。
分からない事が多過ぎた。
ぺぺの前世の話。
ゼログラビティを彷彿とさせる宇宙映画
謎の武術集団と怪しい先生。
サクッとやるなら分かるのだけど長い事回してたのは
何か意味があるのだろうか?
何故犬の糞を取らないのか?
今アメリカでの白人警察による黒人殺害事件を受けて、
奴隷制度を思い、それに比べて
メキシコの中流階級の家族と召使いさんの関係は
とても美しかった。
映画評論家に説明してもらいながら観たい映画だった。
芸術性とモノクロの映像美
期待外れ
アカデミー賞を受賞や作品賞候補という触れ込みだったので、結構楽しみに観たのですが。
え?ホントにアカデミー賞候補だったの?? 嘘でしょ?
結構駄作でも楽しめる方だ思っていたのですが、いまいち感性が合わなかったようで。
途中まで超つまらなくても我慢して観ていて、家政婦クレオの恋人が登場した辺りからは、やっと面白くなる!?と期待したのに、火事の中オッサンが歌を歌うシーンでドン引きして鑑賞を止めようかと思いました。ゲージツ作品の映画ではあれは当たり前なんですか??あれは酔っ払いなんですかなんなんですか?おかしいでしょ。あんなことしてたら燃えて死にますよ。新年のお酒が割れるシーンも、まんますぎません?お腹の子、亡くなるフラグ立った、と、バレバレ。
出産、結局死産だった訳ですが、出産経験も、流産経験もある身としては、女優さんの感情表現に若干物足りなさが。歓迎されない子とは言え、10ヶ月近くお腹で育てていた訳で(胎動があると、生きている実感があるので)、もっとうわーっと、溢れるものがあるはず。もっとボロボログチャグチャでないと、物足りない、違和感があるのです。
よかった点は、雇用主側と雇われる側が、あくまで対等で、温かい関係であったことですね。雇用主の奥様が、一番等身大な感じでした。妊娠したクレオを病院に連れて行くなんて、懐大きい!夫の不倫の事で、ついクレオに八つ当たりしてしまう辺りも、良く分かる。最後はポジティブな終わり方で、まあよかったかと。一応最後まで観れました。
美しく悲しい
淡々としているけれど、最後まで飽きさせませんでした。
南米に住んでいたことがあるので、コロンブス上陸以来今だに続く、先住民とヨーロッパ系移民との階級差、先住民の貧しくて厳しい暮らしぶりや、男性が女性をないがしろにするマチスタぶりに、ああそうだったなと思い出し胸が痛みました。差別、暴力、貧困は当時から今も変わっていないと思います。
ラストで、クレオが「子どもを産みたくなかった」と吐露するシーンは、他のレビューの方々の解釈とは違って、「子どもを産みたくないという気持ちが死産を招いてしまった。ごめんねごめんね」という自分の赤ちゃんへの懺悔の気持ちではなかったかと私は受け止めました。
先住民であり女性であるという二重苦を生きるのは本当に過酷なことだなと同じ女性として胸を馳せました。
「ROMA/ローマ」アルフォンソ・キュアロンの少年時代の家政婦への...
浸る
ほんとに「凄い」撮影というのは、その凄さが決して先行せず、ただひたすら映像に没入出来るものなのだな。。そんなことを思いました。観るもの全てが子供達の無事のみを強く祈ったであろうクライマックス。後々考えると、どうやって撮影したんだろう??完全に溺れて(いるように見えて)いて苦しそうな子供達だったよね。。自然でありながら全てが整っている。うんこから水から何から全てに意味があるように思えてひたすら考え続けて疲れた。
どこかで味わった感覚。。これは想田和弘監督の一連の観察映画の世界だ。
決して特別でない、その時代を生きた家族の物語かも知れないが、素晴らしく豊かな映像はいとも簡単に自分の心の奥に入って来るような感覚を覚えた。
あいつ「や、今、リハーサル中だから」なんてアホな切り返しだろう!!
視覚と聴覚への文句のつけどころのない表現。 リアルな人の温かさを感じられるストーリー。
映画館にて鑑賞。
冒頭1分の素朴なシーンで視覚、聴覚、想像力をこのうえなく刺激してきた。
音が鳴ってる。
この音はなんだろうな。
カメラの水平移動に合わせて人が歩いてる。
先に何があるんだろうな。
映像を見てて自分のなかでの意識/心の根本的な動きが最初から最後まで心地よかったです。
視覚情報はグレイの映像が素晴らしい。
色が付いてたら意味が強くなりすぎてしまう。
色彩がないことで無駄な情報が省かれて画面に集中する。
向いている意識に応えるだけの美しいカット、面白い構図の数々。
音もまた素晴らしい。音楽でなく音。
人の歩く音。
水の流れる音。
草が揺れる音。
ラジオのノイズ
……現実的な音が鳴ってるだけ。
その耳への刺激がアンビエント・ドローンを聴いてるかのように心地よい。
日常の音がこうも面白いのか、と。
日々の聴覚への意識が変わりそう。
そして、ストーリーも味わい深い。
最初の方は穏やかな日々が延々と描かれて“音像/映像美による日常を眺める作品かな?”と思った。
でも後半は、あくまでも過度に盛り上げることなくじんわりと心に染みる話に。
出てくるのは基本的に良い人。そして人間味がある人。リアル。
だからこそ胸がキュっとなる。
だからこそ一人のゲスさが際立つ。
でもあの人も人間的なんだよなぁ。
ところどころ笑っていいのかわからないシュールなネタが炸裂してたのが奇妙だった;
先生;;;
視覚と聴覚への文句のつけどころのない表現。
そして、リアルな人の温かさを感じられるストーリー。
間違いなく良作でした!
P.S.
実際にROMAを見て素晴らしい作品だと実感しました。
でも自分の考えとしてはアカデミー賞は違和感があるんよなぁ。
Netflix発だから作品としての魅力が下がるとはまったく思わない。
でも映画館で上映されてる作品のレースに参加してしまうと、色んなモノが崩れていく気がする。
あらゆるディテールに隙がない。
とりあえず、忘れないうちに書いておきたかったので。
音の効果。
この映画の最大の魅力。他の要素も素晴らしいクオリティでしたが、音に関しては新次元だった。
映画館くらいの音響でないと聞こえないであろう音が、遠近大小あらゆる所から聞こえる。それによって、画面外の場所で何が起きているのか、どこに誰がいるのか、はてはモブシーンの人生や遠くの情景まで想像してしまう。
意図的に左右で違う音が聞こえ、右で激しい轟音が鳴り響いているのに左では小鳥のさえずりが聞こえたりする。世間では大変な出来事が起きていたとしても、個の家族の生活は日常規模の出来事が進む。隣同士なのに左右でお互い無関心な線引きを音を使って説明している。
劇中でBGMがなく、音をこだわり抜いた結果のような、実際この映画には不要だったと思う。とても潔い。
映像。
光、汚れ、煙草や炎の煙、砂煙、それぞれのディテールが美しく強調され、白黒映画ですがそれを忘れる程の彩りに満ちている。
決して輝度が強い訳でもないのに、暗闇でもそこにいる人が何をしているのか自然に解り、細かなこだわりを感じた。
モブシーンの服装や、動きがとても現実的で、国も時代も違うメキシコを身近に感じてしまえるほどリアルだった。音の部分との相乗効果もかなりあったと思う。
今回、映像にルベツキを起用してなかった訳なんですが、それによるマイナスが一切なく、ワンカットの長さも丁度良い。ルベツキが得意な人物を追うカメラワークも、キュアロンなりにとても自然だった。オープニングシーンなんか、ルベツキ使わなくてもできるんです!的なドヤりさえ感じた。
ストーリー。
メキシコの貧乏でも裕福という程でもない、とある一家の物語。凄く地味。それなのに全く退屈する事がないのは、ワンシーンワンシーンの中にある音や映像や隠喩などの、作り込まれた重量の賜物だと思う。「この世界の片隅に」を彷彿とさせる。
時代を言葉や文ではなく街中の雰囲気や人々で説明する巧みさは、とても自然に映されていて素晴らしい。何より個人的に好感が持てる。
派手な演出もなく、色々な出来事を凄く自然に見せているのだけど、そこに地味さはなく、ここにも他人の無関心さが漂う。それがあくまで嫌味ではなく現実味として感じれるのは、絶妙なバランスによるものだと思う。
主人公の彼氏の違和感。全体的に現実味のある登場人物が多いのだけど、彼氏とその周囲の空間だけ妙に作り物っぽく、奇妙で物凄い違和感を感じた。おそらくこれは監督の意図したものなのだろう。空っぽの正義感と陳腐な精神を持った彼は、作り物の象徴として、とても効果的だった。そこを確信できたのは、先生のポーズを周囲の人達は誰も出来なかったのに、主人公が出来たから。合気道の達人の動画みたいな感じ。ここはキュアロン自身がそういう特定の人達に対して、このような違和感を感じているという事を表している。
オマージュ。
タルコフスキーと、小津安二郎の色が濃い。
元々、キュアロンはルベツキと組むと極端な長回しをよくするので、以前からタルコフスキーの色がある印象だったが、タルコフスキーの隠喩をこれみよがしに使うイメージはなかった。今回は逆に極端な長回しを抑え、隠喩の部分をふんだんに盛り込んでいる。炎、水、風、漏れるミルク、マジックアワーなどなど、微妙なラインを入れるともっとある。事前にタルコフスキーの隠喩を知っておくと、この物語をより深く観る事ができると思う。
主にストーリーの部分で、小津安二郎の色を濃く感じる。家族、他人、関心と無関心などなど小津作品が基本的にテーマとしてきたものと酷似している。キュアロンの過去作でも日常会話の感じは以前から小津っぽかったが、ここまで色濃く感じたのは初めて。映像でも白黒やカメラワークの部分で小津安二郎から効果的に引用している。
強烈に感じた引用がこの二人というだけで、他にも沢山の監督や作品からの引用が盛込まれていると思う。
個人的な感想。とにかく良かった。本当に良かった。素晴らしく良かった。非常に異常に良かった。
関東ではもう、ほぼほぼ上映していなかったが、友人から本厚木にある「厚木の映画館」という映画館でギリギリやっていると教えられる。
音響も素晴らしく、清潔で良い映画館でした。
厚木の映画館には感謝しきれない。
広すぎる画面に拘りを感じる!!
ストーリーは家政婦が妊娠するというだけですが、自然な演出で、人々の生活や町並みを自由に観てくれと押し付けがましくないです。日本映画で70年代が舞台の映画を作るとしたら、とにかく画面を狭く狭くして現代で撮っているのを誤魔化すと思いますが、キュアロンはとにかく画面を広く広くして、これ以上ないくらい広くなっているという、凄まじい拘りを感じました。良く言えば、どのシーンもモノクロの長い絵葉書のような感じでした。日本人の時間の流れからすると退屈ですが、映画を作るならここまで拘れよ、という思いは感じました。
実は弱い女性を描いた作品。だが強くある必要もない
アルフォンソ・キュアロンの天才ぶりが発揮されてしまった作品。
演出面では、大衆を上手く利用するあたりは黒澤明を彷彿とさせ1シーン殆ど1カット長回しだが、飽きさせない。映像の中で何かしら起きている。
そもそもキュアロンは長回しを多用する監督であるが、今作はとても効果的だった。主人公が一人で何かと戦っているシーンでは孤独感が強調され、白人家族と一緒にテレビを観るシーンは対照的に家族団欒のゆっくりな時間が滲み出ている。
映像も去ることながら、録音がとても素晴らしい。洗濯物から落ちる水滴の音、遠くで聞こえる犬の鳴き声、空を飛ぶ飛行機、タイヤで踏まれる犬のフンの音、そしてあの波の轟音… 音がとにかく気持ちよく完璧。この音が作品にのめり込む大きな要素になっていたと思う。是非良いサウンド環境で観ることをお勧めします。
Me too運動などの影響で“強い女性”を描いた作品が好まれる昨今の映画業界では、今作も“強い女性の映画”として評価されるかもしれない。しかし僕はむしろ“弱い女性”を描いた作品だったと思う。その弱い女性が周りに助けられ、そして助け、人生の一幕が過ぎていく。強くある必要はない、弱くても彼女が生きている姿はそれだけで美しい。そう僕の目には写った作品だった。
命あってこそ
1970年から1971年のメキシコの一家と家政婦の激動。
家政婦のクレオが主人公なのだが、クレオが妊娠に気付き出産するまでの間、一度も家に戻らぬ一家の父親。
父親は医者、母親は元生理学者の家庭で子供4人、家政婦は2人。物にも恵まれ側から見れば何不自由なく見えるが、母親の心は家庭を顧みない夫に波打ち、取り戻そうと最初は思うが、後にあてにせず生きる事を決め、乗り越え強くなる。
一方クレオも、休みの日は同僚とダブルデートに行かれたりと、出身は貧しい村でも、仕事に就き住み込みでそこそこ恵まれた暮らしをしているが、雇用主の家のような豊かさとは産まれたときから立場が違うし、妊娠までしてしまい、お腹の子の父親フェルミンは妊娠を知るや姿を消し、晴れない1年が続く。
どんな経済的背景でも、仕事も持っていても、女性の扱われ方の地位が低い。
年が明けて1971年。飲み物の器は割れるわ、山火事は起こるわ、幸先の悪い年明けは予想的中。
スラム街出身のフェルミンのように、貧しい子供達は大きくなると怒りの矛先が政府となり、有り余ったエネルギーや若さ、不満をデモにぶつけていく。フェルミンも、武術に出会ったお陰で不良になりきらずにいたが、政治不安の渦に簡単に扇動されてしまった。
クレオは暴動する学生達が乱射する中、そこに混ざっていたフェルミンにたまたま再会するが、彼はクレオに銃を向ける。ショックもあったのか破水するも、暴動のせいで病院へ駆け込むのが遅れ、死産。
蒸発した父親の子に嬉しさを感じられぬままどんどんお腹は大きくなるが、望んでいなかった妊娠。それでも10ヶ月お腹にいた子を失った虚しさで抜け殻のようになっているが、一家の母親の計らいもあり子供達も連れみんなで海に旅行へ。
打ち寄せる波に溺れた子供達2人を泳げないのに助け、みんなで死にかけて、生きている事を実感する。
夫を失っても、父親を失っても、子供を失っても、絶望的状況でも、命は助け合って続いていく。そして、すぐそこに死はある。
淡々とした中に、大げさでない見せ方で、命あってこそなんだという事を教えてくれる作品。
家族の淀みを現すかのような、犬の糞の数。
それを掃除するのがクレオの仕事であり、家族の淀みを受け止めて清めているのもクレオ。母親の八つ当たりもその理由を黙って理解しながら、余計な事を言わず受け止める。
小さな子ほど親の気持ちに敏感で、最初から不和で何かつまんないなと抱えている節があるが、母親の気持ちを汲んだ行動をしていたりする。それでも、クレオには皆甘えんぼモード炸裂。家政婦さんって、子供にとってはちょっとした駆け込み寺、避難所だったりする。
階級社会では上から見られがちだが、家族を助け大きく影響する家政婦さんにスポットが当たっていて、彼女も1人の人間であり、家族の一員なんだと示しているところが良かった。
車庫に車が入る様子が、家族の変化をあらわしている。最初は、ぶつけるのはミラーだけで父親の目線が外を向いた暗示のようだが車体はすっぽりと収まる。父親が出ていくときは車は車庫の外。途中車を修理して気を取り直しクリスマス休暇を過ごしに行くが、その後も母親が駐車すると常にボコボコにぶつけ壊れゆく車と家族。最後は古い車を処分し、父親抜きで団結する一家のように、コンパクトな新車へ。家には、父親が本棚という枠を持ち去り、「理想の家族」という枠が取り払われても残った、中身の部分の本と母親と子供達。
家の中のカメラワークも独特で、徐々に間取りが見えてきて、最後に家全体がわかる構図。
全172件中、21~40件目を表示