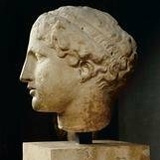教誨師のレビュー・感想・評価
全72件中、61~72件目を表示
現存する世界宗教の限界を感じた
死刑囚の改心の一助となることもなく、
ただ話を聞くことしかできない主人公。
キリスト教の牧師さんという設定なのだが、
キリストの言葉も聖書の引用も、賛美歌も
何一つ死刑囚たちの心に響いていない。
「魂のぶつかり合い」などのキーワードが広告に踊るが
まったくそうとは思えない。
単なる自己顕示欲と自我我欲。死にたくないと言う執着。
キリスト教に改宗した人には、ふさわしい言葉を伝えられたのか。
「キリスト教でよかった」と思わせる、魂に刻まれる言葉を。
そういうシーンはひとつも出てこない。
人間の悲哀を伝えるという意味だけに置いて存在価値があるかもしれない。
でもただそれだけ。
キリスト教も、仏教も、イスラム教も、
既存の宗教の形骸化が悲しく実証された映画。
全ての宗教を包括するような、新しい教えこそが必要と
強く強く感じさせてくれたことだけがよかった。
大杉漣の役者魂を感じる濃密な作品
自分の運命との向き合い方が様々な6人の死刑囚との対話劇。拘置所の一室での場面が作品の大半を占めるが、そこでの教誨師と死刑囚のやり取りは一言一言の重みをひしひしと感じる真剣勝負。来たる死を前に虚言を弄して平静を装う者もいれば、自己の正当化に懸命な者もいる。でもそれらは全て死への恐怖から逃れたい一心の身勝手な行為である事をこの作品は図らずも曝け出す。一方、教誨師の仕事は無償だと言う。では彼はなぜこの仕事を引き受けるのか?その問いから教誨師自身が負う心の蹉跌も明らかになる。人の心の深淵を炙り出すようなこの作品の主役はやはり大杉漣。いぶし銀のような彼の演技無くしてはおそらくこの作品は成り立たなかったと思う。彼がくれたこの濃密な二時間に感謝です。もっと彼の作品を観たいと思うのですが、本作が最初で最後の作品とは残念。合掌。
穴をのぞいたその先は…。
・生きるとは?死刑制度とは?裁判員制度って?等々…。非常に難しいテーマで、いくら考えても明確な答えは見つからないと思う。
・高宮とのやり取りが一番印象的だった。終盤 佐伯が本音を熱く語ったことによって、高宮も想いに答え出したシーンは感動した。
・佐伯と会話を繰り返していくうちに、囚人達それぞれに何かしら生まれているように感じた。
・世界的には死刑制度は反対という流れが主流だが、被害者遺族の方々の気持ちや様々な状況もあるので、やはり完全に死刑制度を無くすことは出来ないのではと思う。
・大杉さんの意欲作であり遺作となったこの作品は、非常にインパクトが残る作品だった。
6人に真剣に対峙すればするほど、息が苦しくなってくる
※(注意)感想を書く上でばっちりとネタバレしてますので、鑑賞前の方はご遠慮された方がよいですよ。
はじめ、「教誨師」というタイトルを聞いた時、堀川恵子の同名著作の映画化かと思ったがそうではないようで、かの本は浄土真宗の僧侶だが、こちらはキリスト教の牧師であった。それもまだ着任半年で、経験が足りないゆえの焦りや戸惑いがあった。むしろ、教誨という仕事に慣れきれず、未だどこかに新米臭さを残すには、半年と言う設定は絶妙だなあとも思った。
そんな佐伯にとって、ワンステージ、ワンステージ、どこかから何かに襲われるんじゃないかと警戒しながら身構えているような、緊張感の連続。そのせいか幻覚(と解釈していいのか)を見てしまったりなど、すでに死を約束された人間と対峙するのは半端な覚悟では務まらないのがよく伝わってきた。
そんな密室である教誨室は、三角形の間取りをしていた。僕は、佐伯の背後にある空きスペースの暗がりが気になって仕方がなかった。なぜこんな部屋なのか?と考えた。おそらく拘置所においては、所長の軽い態度に見受けられるように、「教誨」という活動が低く見られているのではないだろうか。きつい言い方をすれば、死刑になる者にたいする処遇だから空き部屋をあてがっておけばいいよと扱われているじゃないだろうか、と邪推してしまうのだ。そんな誘導さえも、この映画の演出の巧妙な罠なのだろう。
そして、ようやく佐伯が仕事を終えて所外にでると、ふだんと変らない日常がある。平和な田園風景、妻の愚痴、こちらまで伝わってくるような涼やかな風。息が詰まって仕方がなかった僕も、ようやく休息が訪れた解放感であった。そんな瞬間に、最後の「仕掛け」が待っていた。
あなたがたのうち だれがつみをせめうるのか
佐伯同様、僕もハッとして背中に冷たいものが走った。
それは、気の弱い老人進藤が覚えたての字で書いたのか?いや、そうじゃないだろう。佐伯自身が、ずっと自分自身に問いかけている悩みなのだ。それが幻覚として見えたしまったのだ。そしてこの言葉こそが監督のメッセージなのだろう。
出演者の中では特に、理路整然と佐伯に問答を挑んでくる高宮を演じた玉置玲央が存在感を出している。面談のときのふてぶてしさったらない。弱者を狙った卑劣な犯行という背景から察するに、先日の相模原で起きた障碍者殺人事件がモデルのようにも思える。高宮は殺人の動機を、イルカを引き合いに出して「知能の低いバカは殺したっていいんだよ!」(台詞は大意)とまくし立てる。でもそれは、仕返しをしてこなさそうな弱気な奴と見定めて因縁吹っ掛けるチンピラとおんなじなんだよな。だから、肝が座り切っていない彼は最後のあの時、怖気ずくんだ。そして、倒れこんだ彼は、佐伯に何か耳元で囁いたように見えた。その言葉に佐伯がたじろんだようにも見えた。それがなんて言ったのか、言ったように僕が見えただけなのか、気になって仕方がないのだが、この先、この映画を思い出すたびにその問答を僕自身にずっと問いかけてみるのも悪くないと思った。
この日、上映を終えて、初日舞台挨拶。いい映画の舞台挨拶は、鑑賞後がいい。登壇した役者の表情が生き生きとしている。
出てきたのは監督の他、6人の死刑囚。大杉連はパネルで登場してきた。思い思いに大杉との思い出を語る中、やはりドラマ「バイプレーヤーズ」で共演した光石研の言葉に注目が集まった。
去り際、烏丸せつ子がパネルの大杉の肩口あたりにそっと手を添えて優しく微笑んだのが印象的だった。
タイトルなし(ネタバレ)
死刑囚の六人の心を、すべて受け入れ、対峙しようとする佐伯が、だんだんと心を擦り減らし、見透かされ、お互いが暴かれていく様に、
「死刑囚」だけの映画ではないのだなぁ、と痛感しました。
あれはきっと、佐伯も六人それぞれも、どこにでもいるひとなのだと思う。
自分を強く見せようとしたり、寂しがりで喋り続けたり、愛されたいが暴走して錯覚したり、弱さゆえに手段がわからなかったり、お人好しで逃げ方を知らなかったり。
高宮、不愉快極まりないキャラクターで、彼の正義を実行してしまったことが大きな過ちではありますが、
不純物の一切ない考え方や、(正義ではないけど)実行力は正直魅力的に感じました。
あんな風に、素直に疑問を口にできない。
その高宮に触れて、佐伯も自分を暴かれていくから、佐伯も罪を懺悔をしているように錯覚して、
わたしには「死刑囚六人」の映画ではなくて、「人間七人」の映画だった。
劇中に出てきた、「穴を穴として見つめる」というセリフが私には救いで、あれがなかったら、もっと映画の世界に呑み込まれてしまったと思うし、六人が、死刑に相当する罪を犯したことも忘れて庇ってしまいそうになった。
それほど人間味のある内容だった。
演技力・・。
俳優の力量こそが、この映画の核にある。
こんなにも生理的嫌悪感を感じざるを得ないのか、という高宮を演じる玉置玲央
虚言癖のみすぼらしい中年女性野口。こんな烏丸せつこに吐き気を催す。
進藤・・ホームレスの役なら、この役者、五頭岳夫。しかし、邪気のなさゆえ、自らの罪に気づかない。
普通の平凡な夫・小川が、一瞬に狂気に変わる。しかし、その後枕カバーの交換を心配するという日常性と突発的な暴力性を演技した小川登。
ストーカー男性のデフォルトそのものかと思わせてしまう鈴木こと古舘寛治。
光石研は、人に対しては器量を大きく見せる、しかしながらその実は極めて器の小さい組長吉田を演じていた。
もちろん、牧師佐伯の大杉漣はそれをストーリーの中で束ねてかなければならないわけだが。
この映画は、それぞれの俳優の力量こそが命なのだとつくづく感じる。
ところで、
先日NHKの某ラジオ番組で、ネタバレしないように気をつかいながら、この映画のラストシーンこそ見ものであると言っていた。
個人的な意見では、残念ながら、その点はそうでもない。
展開からだいたい、予想がつく「言葉」である。
少年時代の回想シーンとラストの場面、確かに映画の中では重要な意味付けを与えることになるのだろうが、いささか安易な流れに走ったような気がしてならない。
言うなれば、佐伯の過去は必要なかったし、ラストの「教誨」の言葉をも必要なかった。
生きているから生きる
教誨師と死刑囚の会話劇。一室からシーンが変わることはほとんどなく、殺人犯たちとはいえ過激な描写があるわけでもない。それでも飽きさせず世界に入りこませる映画でした。それぞれの死刑囚の起こした事件や裁判についての詳しい言及はなく、ただ対話を進めていくことだけで死を前にした死刑囚の葛藤が生々しく伝わってきた。死ぬのなんて怖くない、そんな風な口ぶりだった死刑囚達も執行日を目の前にして平常でいられなくなっていた。とにかく演技が生々しくいい意味で気持ちが悪かった。高宮は最後に先生の耳元でなにを言ったんだろう。
生きる理由も死についても分からないけれど
一度観て身体の震えと涙が止まらず、そのまま劇場に居座り二連続で鑑賞。
今年急逝してしまった大杉漣、彼自身を思わずにはいられないシーンも多かった。
6人の多様な死刑囚と教誨師の佐伯との対話、対話、ひたすら対話。たまーに佐伯の回想など。
それを脇に座っている刑務官のようにじっと見て聞いているしかない自分。
しかしそれぞれの対話の様子を区切りながら交互に見せてくれるので、間延びは一切感じなかった。
なぜ死刑になったのか、その犯行の詳細はほとんど語られず、話す言葉の節々で部分的に拾えるくらい。(一人を除いて)
エピソードにはあまり焦点を当てず、各々の人間の中を少しずつあぶり出すつくりが好き。
死刑囚という特殊な状況下の人間と一対一で会話するのは相当な気を使うものだと思う。
受け答えする佐伯の一つ一つの言葉選びにスリルを感じてずっとドキドキしていた。
6人と佐伯が教誨を重ねるごとに変化していく様子が面白く、釘付けになった。
それぞれ濃くて胸打ち震わされて、やっぱり何故か涙がボロボロこぼれてくる。
死刑囚という前提があっても魅力を感じたり、どうしてもそれぞれ思い入れが強くなって、救いを求めてしまう。
・高宮、まずは何と言ってもこの人。
最初はもう本当に不快。人を小馬鹿にした言動、態度や表情に腹が立つこと立つこと。
しかし言ってることは過激だけど正論、共感できる部分もあり、どんどん彼に引き込まれていった。
弁の立つこの厄介な男に佐伯がどう対応していくのか、その段々白熱していくやり取りが非常に面白くて好き。
「どんな命でも生きる権利がある、奪われていい命など無い」という言葉の矛盾。
牛や豚は良いのにイルカは殺してはダメな理由は?どんな人間でも殺してはいけないと言うのに死刑があるのは?
分からない。佐伯は先の言葉を信条としていたのだろうけど、これを問われた時の愕然とした表情は印象的。
お手本のような「聖職者としての言葉」を与え続けるだけでは駄目だった高宮から投げつけられたものが確かに佐伯に大きな変化を与え、その佐伯から「聖職者としては失格」である言葉を受けた高宮が確かに変化した。
今まで自信満々で上から目線だった高宮が初めて弱さと虚しさを少し見せた時の表情や、執行直前のこれから死にゆく時に佐伯に縋るように抱きついた時の表情が目に焼き付いて離れない。
寂しさや恐怖や罪の意識は言葉の連発だけでは拭えないもので。
佐伯が言ったように心の底で求めていた許しを少しでも受けられたと感じられたら良い。
執行時、マスクをかけられ「あれ?」と一つだけ溢した彼は何を思ったのだろうか。
・進藤、6人の中で一番明確な救いを得た人。
字も分からない彼はお人好しでどこか子供のような所があり、かなり純粋に思える発言もチラホラ。
そんな言葉の端々でハッとさせられることも多かった。
「桜は自分のことを桜とは思っていないでしょう?」というセリフが好き。
字と祈りを教えてもらい、キリスト教の神の寛大さに感銘を受けた様子が何となく可愛い。
彼のラストシーンはかなり胸に刺さった。
おそらく脳梗塞を発症しコミュニケーションもろくに出来なさそうな状態で洗礼を受け、大切なグラビア写真を佐伯に渡す姿に大きな救いを感じる。
そして最後、写真に書かれていた聖書の一節。
「あなたがたのうち、だれがわたしをつみにとえるだろうか」(たしかこんな感じだった)「せめうるだろうか」だったかな…
家にある聖書で猛烈に探したところ、ヨハネの福音書8章46節にある、キリストが言った言葉とほぼ同じ。訳し方の差はあるかもしれないけど。
進藤は何を持ってこの言葉を書き、佐伯に渡したのだろうか。
聖書では、キリストが神の子であることを疑い悪霊に取り憑かれているんだと言う人々に投げかけた言葉だった。
もしかしたら、借金の連帯保証人を受け入れてしまった時のように殺人などの罪を被せられてしまった冤罪の人なのかもしれない。
・鈴木、蓋を開けたらめちゃくちゃヤバい奴だった。
ギュッと目をつぶり自ら話すことをしない姿には、嫌な言い方だけど、一番分かりやすい死刑囚らしさを感じた。
罪悪感と死への恐怖に苛まれているのかなと思いきや。
佐伯の兄の話をキッカケにやっと話し始めたと思ったらまさかのストーカー精神モロ出し。
自分よりも被害者達を責めて疑わない姿勢にゾッとした。
鶴野さんが謝ってくれた!とスッキリしたように笑いながら話す彼には、ある意味救いが訪れたんだと思う。
あくまでも鈴木自身だけのことを考えるならそれで安らかになれるなら良いけど、そんな安らかさなんていらないじゃないかとも思う。
嫌な言い方だけど、一番分かりやすい犯罪者らしさを感じた。
・小川、6人の中で唯一犯行について詳しく話した人。
俯き加減でたどたどしく話す気弱な彼の、家族を思う心や犯行に至るまでの経緯の話を聞くと、到底死刑になるものとは思えない。それが真実ならば。
警察の捜査における問題や司法の在り方に微かに触れて終わってしまう彼の話にとても悲しくなった。
きっと小川のように訳のわからないまま重刑を背負ったままの人が現実にもいるんだろう。
あってはならない事なのに無くならないのは結局他人が罪の重さを判断しなければいけないからで、客観的証拠や自供が重視されるからで。杜撰なものだとしても。
裁判のやり直しを、と言い始める佐伯に何もかも諦めたように制止する小川に胸が痛くなる。
最後に礼を言った彼に、佐伯の気持ちが伝わっていれば良いなと思う。
・野口、よく喋る大阪のオバチャン。
エヘヘッと笑う顔がなんともチャーミング。
繰り出されるマシンガントークが結構面白くて、野口のパートではだいぶ笑わされた。
しかしリストカットの跡や自分の話を邪魔されると途端にキレ始め激昂する彼女にはやはり不安定なものを感じる。
教誨室をドタドタ出て行く際に刑務官に「良い加減にしてください!」と言われていたことから、今までも相当色々あったのかと思われる。
実在しないハゲのおっちゃんのことをどんな気持ちで話しているんだろうか。たまに出てくる不動産王の彼もいないんじゃないか。
度々「ここを出たら美容室を開くねん」と話していることから、死刑を未だ受け入れずその逃げられない恐怖から少しでも精神を均衡に保つために話し続けているのかなと思った。
自覚があるのか無いのかは分からないけどその数々の作り話は確かに野口を救っているのかもしれない。
・吉田、気さくな酒好きヤクザ。
一番安定しているように見え、教会の子供達にプレゼントを手配するなど気の良さもしばしば見える。
しかし実はいつ来るかもわからない執行の日に一番過敏に反応して反発していたのは彼だった。
押すなよ、押すなよ…押せよ!的なやり取りが痛々しくて堪らなくなる。
そして佐伯保。
教誨を始めてまだ半年。慎重に言葉を選び決して押し付けず否定せずの姿勢は上手だけど、それが裏目に出ることも。
正直最初は彼の言葉にどこか上っ面な部分を感じることもあったが、対話を重ねるにつれて言葉に重みや深みが加わっていくのをひしひしと感じる。
そこに至るまで相当悩み苦しんだだろうな。
兄の一件、カレンダーが倒れる訳には色々と衝撃だった。
昔は「逃げよう」と言っていた佐伯が「逃げない」と強く言い放つシーンが好き。
生きる意味も死ぬ意味も分からず、虚しさを感じながらも目の前の人物に向き合い知ろうとするのは容易くないのに。その決心が高宮を突いたのかも。
最後にチラッとわかる佐伯の素の顔、酒飲むんかい!っていう。
対話の時には見えなかった彼が見られて嬉しい気持ちになった。
牧師も人間、建前と本音を使い分けるのも当たり前のことで、流石に教誨の場で「いやあ私も最近飲みすぎって妻に叱られちゃってね〜」なんて言えるわけもないだろうな。
何となく、小川と鈴木は今後はもう教誨を受けないんじゃないかと思った。
野口はあのまま変わらずお喋りをしに来ていて、吉田は自分が執行されなかったことに安心して「この間はすみませんネェ」とか言いながらまた教誨室にやって来るように思う。
そして佐伯はこれからも囚人たちの穴をじっと見つめ続けるんだと。
「なぜ生きるのか」と何回も問われる映画だった。
分かるはずもない、分かる人なんていない。
ただこの世に生を受けて、寿命を消費する中で苦しいこともありつつ、少しでも好きなものや楽しいことを感じて生きていきたいと私は思う。そう思えること自体が既に幸せなのかもしれない。
佐伯が囚人たちに向けた言葉、囚人たちが佐伯に向けた言葉の数々は自分にも大きく響き、時には私に話しかけられているような気分になることもあった。
死刑囚にとっての救いは一般社会で普通に生きている私たちにとっての救いではない。
どんな人間的魅力があろうと犯した罪は消えない。
それでもこうして一人一人見ていくと、彼らを知りたいという気持ちも湧いてくる。
死に際近い老いでも病気でもなく、不意の事故でも不条理に命を狙われている訳でもなく、悪魔に魂を奪われようとしているわけでもなく。
犯した罪の代償に、色々な制限の中でやる事の少ない日々を中途半端に生かされ、いつか必ず来る死刑執行の時を待つ生活。
死刑囚達の気持ちも教誨師の気持ちもどうしたって理解出来るものではなく、それでもあの時の彼らは何を思ってどういう感情だったのか、と考えずにいられない。
考えさせられる映画
2時間、死刑囚と教誨師とのやり取りが続き
自分がその立場に立ったような気がして
すごく疲れましたが
いろいろ考えるところのある映画でした。
親に愛されない不幸な生い立ちの人、
勉強する機会を持たなかったために
他人に騙され転落してしまった人、
不幸が重なり何とか耐え忍んで生きてきたが
ある日爆発してしまった気持ちが優しく弱い人、
いろんな死刑囚がいましたが
その人を裁くことなんか誰にできるのだろう。
死刑制度って本当は殺してはいけない人を
殺してしまう恐れがあるのではないだろうかなどと
考えさせられました。
その人なりの事情を持った他人を悔い改めさせるなんて
簡単にはできることではなく
その人を知って、側にいるということが
教誨師にできる救いなのかなと感じました。
残念。
大杉漣さんの初プロデュース&遺作ということで期待して観ましたが、期待外れに終わりました。
死刑囚を演じる6人の俳優のうち、一部の方の演技が過剰でリアリティが無さ過ぎるように感じました。唐突に挿まれる回想シーンでの浅過ぎるエピソードにも興醒め。皮肉にもほぼ素人の小川登さんの演技が死刑囚らしく真に迫っていた。
全体的として内容が散漫で、「なぜ生きるのか」という重く普遍的なテーマに迫り切れていないように思いました。購入したパンフレットによると低予算で時間の少ない中で作られたようなので、仕方なかったのかも知れませんが。
色々と批判的な事を書きましたが大杉漣さんの演技は素晴らしく、それだけでも観る価値のある作品であることは付け加えておきます。大杉さん、どうか安らかに。
黒い穴を見る役目
大杉連さん主演の遺作映画ということもあり、スバル座が意外に混雑していました。
持論ですが映画はざっくりいうと2種類のタイプに分かれると思っています。「わかりやすい娯楽映画」と、「鑑賞後に感情が引きずられる映画」と。これは勿論後者でした。
草彅剛さんが鑑賞後に寝付けなかったと言われているようですが、よく分かります。
鑑賞後は本当に色々と考え、登場人物の感情が交錯してしまって、まだ未消化です。多分数日引きずると思います。
その中で今思っている事は、登場人物の人間臭さが強すぎて、体温や匂いを感じてしまう映画だったなぁ・・・と。キャラクターの体臭を感じた映画は初めてだと思います。(苦笑)
題名につけた言葉は映画の中に出てくる言葉です。何故かこの言葉のシーンと「ライ麦畑で捕まえて」の最後のシーンとがオーバーラップしてしまっているので、それがどうしてかも、しばらく考えてみようと思います。
ゴルゴタの丘
全72件中、61~72件目を表示