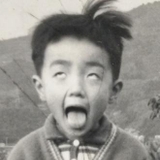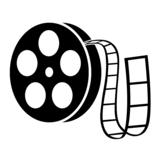幼な子われらに生まれのレビュー・感想・評価
全95件中、41~60件目を表示
現代家族の葛藤を描写
バツイチ同士の家族はもう珍しくないので、本作のような連れ子の問題はもはや十分社会性のあるテーマなのかも知れませんね。出演者皆さん良かったですが、特に父親(浅野忠信)はちょっとカッコよすぎた面はありますが、なかなか良い味出していたように感じました。ただ連れ子・薫の継父への反抗は結局上手く決着できたのか、私には最後まで良く分かりませんでした(感度が鈍くて済みません)。
現実味のある作品
現代家族事情。
まるで現代の家族事情を絵に描いたような悲喜劇である。
結婚・離婚・再婚時に連れ子は珍しくない状況で、紙面
に躍る幼児虐待やDVの記事を見るたびに、何で母親は
その子を連れ危ない男の元へ嫁いだんだろうと不思議に
思うのだが、自分の幸せを子供以上に望んでしまうほど
母親が愛に飢えていたのだろうと思う。浅野忠信演じる
父親はそんなDV夫とは程遠く地味で堅実な男なのだが、
やたら気苦労が絶えない。元妻との間にできた実娘との
面会時間が唯一の慰めのようになっている様子が切ない。
再婚した妻との間に子供ができたことによる周囲の反応
が彼を追い詰めていく。特に長女の反抗がエスカレート
し彼を罵る場面が延々と続き、彼がいつ娘に暴力を奮っ
てもおかしくない状況に陥るのだが本人は冷静に耐える。
私ならこんな悪態をつく娘にはビンタしてやればいいと
(暴力反対だが)思った。というのは却って長女がそれを
待っているように見えたからだ。父親に自分だけを見て
ほしい、実の娘以上に愛されたい願望がこの子にはある。
義父の彼を試すような申し出をしたのも、そして実際に
実父に逢わなかったのも、長女の気持ちがよく出ていた。
素直に甘えればいいものを、それができない性質なのだ。
勘のいい母親ならそんな長女の気持ちに気付いてやれる
のだがこの母親にそれはない。複雑な想いが八方塞がり
となって義父に注がれている状況。もう浅野が可哀相で
こんな思いまでして家族の為に頑張っているお父さんに
何てこと言うんだ!この娘!と思った大人も多いだろう。
追い込まれた人間の見せ方が巧く、其々の立場で各々の
孤独が伝わるが、しかしそれもこれも自分で選んだ人生
・結婚に違いない訳で、だからこそ苦悩にも共鳴できる。
あのエレベーターの様に斜めに上り下りするのが人生か。
親であることの重責
子供を持つ人であれば、親であることの重責を感じることは何度となくあるはず。
健やかに育ってくれるか、辛い目に遭ったりしないか、将来ちゃんと食っていけるか、そのために自分に何ができるか思い悩むこともあるだろう。
この作品に登場する二人の男親は、まったく違うようでどこか似ている。
よき父親であろうと責任感を持って振る舞っているがどこかぎこちなく空回りする男と、親の重責を負うことができない自分に絶望してそこから逃げ出した男。どちらも、何かちょっとしたきっかけで愛情表現をちゃんと伝えられそうなのに・・・という辺りをフラフラしている。
誰しも、自分は親として完璧だとまでは思ってはいないだろう。だからこそ、親としての在り方にもがくこの二人の男の姿を観て心が痛み、モヤモヤとしたものが残るのだと思う。
また、自分のキャリアを阻害することになるので子供を産みたくないと言う女性も登場するが、これも重い。
苦渋の選択をして、それが本当に正しかったのか悩み続けている人は多いであろうし、そもそも女性ばかりが何故その選択を迫られるのかという話にもなってくる。これを解決するにはまだまだ時間がかかるだろうが、少なくとも今できることは、夫が妻の思いをちゃんと理解してあげられるかどうかだ。本作では、これもひとつのキーとなっている。
親の在り方、夫婦の在り方、そんなことを少し立ち止まって考える機会を与えてくれた本作に感謝したい。
大人と子供が友達になる事が親子なのかも。
離婚経験者同士の再婚家庭で、妻の連れ子2人と妻と夫の生活。
そこに妻と夫の子ができる。
夫は妻の連れ子1である長女が反抗的になってきており、実子の誕生を素直に喜べないが、妻は無邪気に義母(夫の母)や連れ子たちに吹聴する。
夫は元妻の下で育つ実子(娘)に会えることが唯一の楽しみとなっている。
連れ子長女は、実父に会わせろとせがむ。
まあ、そんな話です。
連れ子次女が、終盤あたりでえらいおしゃべり達者やなーと思ったのですが、大河ドラマの直虎の子役の女の子でした。この子が6才役ってまあ・・・と思いました。そら達者なはず。実年齢10歳くらいじゃね?結構前に撮影してたのかもしれませんが。
あと、だめな大人がはまりすぎるクドカンに切なくなりました。DVとか縁遠いタイプなのにすごくそれっぽく見えて、お上手ねと思うと同時に、かっこいい大人の姿みたいよ、と思いました。まあ、脚本家・監督として大変かっこいいので役者はかっこ悪い路線でいいといえばいいのですがね。
主人公・信は、嫌いなタイプです。仕事で旧姓を使う妻を嫌がり、仕事やめて欲しい的なことをゆうたり、勝手に堕胎した事を怒り(それは分るけど)、子供できたら困るからと中だしを拒否する妻を無視して射精したりする男です。妻とは専業主婦か仕事はしてても家庭優先で、夫の世話が生きがいでなくてはならなくて、当然夫である俺様の苗字を使うことに喜びを感じて、俺様の子供を生み育てる事が何よりの喜びであるべきだという、あれです。うげー、きもい、むり、だいっきらい。なんですが、この映画では信に切なさを持ってみてしまいました。
元妻との回想部分では、元妻(寺島しのぶ)に分るよという気持ちでしたが、現妻(田中麗奈)との生活は信さん頑張ってはるよ、という気持ちでした。
現妻が自分でものを考えられない依存型の人なので、うっとうしいのです。
ななえはうっとうしいという元夫(クドカン)の意見にうなずいたらあかんけど、信は多分心の中で同意していたと思います。
うん、あれはうっとうしい。
でも、ななえこそが信が望んだ女性そのもののはずなんですね。専業主婦で、夫の世話大好きで、夫の苗字を使用し、夫の子供を産み育てたがる。望んだ女性像を得て、改めて考えると元妻の美点がよく分かってしまう。ああ、人生とは思った通りには運ばない。
家族、父親、夫。こういった役割を示す名詞にわれわれは踊らされている気がします。その名詞に色々と科せられた役割を果たす使命があるかのごとく。
そんな使命はないし、プレッシャーを与えられたならば、無用な干渉だと切り捨ててもいいはずだと思います。
信の実子さおりが、信との関係を聞かれて咄嗟に友達だといいました。私はそれが1番ふさわしいと思いました。親子の前に友達でいいじゃんって。大人と子どもがちゃんと友達であること。大人が子供に迎合するような、子供っぽさが揶揄される友達親子じゃなくて、互いに誠実でいて尊敬をしあう仲。大人の役目は、人間関係の築き方のOJT。その実践が保護者と被保護者の関係の築き方。どうだろうか。
夫婦関係は、、、、わからない。そんな関係築かないし。でもそれも友だちでいいんじゃないのかな。誠実と尊敬、だよね、多分。ただそこに性欲が絡むので私にはうまく説明できなくなるのだよね。尊敬と性欲って共存する?それが理想なんだろうけど共存するの?欲情した相手に尊敬を抱いたことないからわかんないです。だもんで結婚を欺瞞だと思っているのでワカンナイ、です。
狭い範囲の人々にとっては、響く映画かな。
もつれたときほど厄介な家族。
離婚された方。
離婚後、子持ちの方と再婚された方。
両親のどちらかが腹違いで、その親のもとに新たな兄弟姉妹が生まれたという方。
再婚の両親の間に生まれたという方。
などなど、そういう方々にとっては、ピンポイントで響く映画なのだと思います。
それぞれの立場で考えることができました。
重松清の本は全部読んでいたつもりでいたのですが、この映画が公開されることを知り、まだ読んでいない本があったということで、公開前に急いで読みました。
浅野忠信さんのダメ親ぶり、田中麗奈さんのバカ母ぶり等々、役者はいい味を出していました。
脇を固める役者の方々もよかったです。
原作既読の方にとっては物足りなさが残ると思います。
やっぱり映画は小説に勝てない。
ですが、この映画が最初の出会いという方にとっては、結構切ない映画になっていると思います。
※重松清原作の映画で、私がいちばん好きなのは『青い鳥』です。
余韻から抜け出せない映画
原作未読。
派手な事件は起こらない。
淡々と、だが丁寧に気持ちを積み重ねていく描写。
余韻からなかなか抜け出せない作品だった。
血の繋がった父娘と、繋がらない父娘。
家族という形態を取っているのは、後者。
父親として関わる子供が全て「娘」という点に、この映画の面白さがあると思う。
妻、元妻、継娘、娘、そして実母まで。
主人公を追い詰めていく存在は全て「女性」である。
「理由は聞いても気持ちは聞かない」
元妻は、そんな主人公に愛想を尽かした。
だが、それが悪い事だろうか。それこそが男女の違いであり、歩み寄らなければならない部分なのだと思う。
女性は愛する人に、「理解して欲しい」と思う。
男性は愛する人が迷っている時、解決してやろうと手を差し伸べる。
愛情の表し方に違いがあるだけで、質量は変わらない。
その事に気付かず、男女はすれ違っていく。
妻とも、娘とも。(そして恐らく、母親とも)
もし主人公に一人でも息子がいたら、どうなっていただろう。
そんな思いを抱きながら見続けた。
だからこそ、この家族の続きが見たいと思った。
妻の元夫に発せられた「どうして結婚したのか」という問いはもちろん、
主人公自身に向けられたものであり、観客にも投げかけられた言葉だろう。
結婚している人、していない人。これからする人、挫折した人。
それぞれに、様々な思いを抱きながら観ることの出来る映画だと思う。
誰もが「考え込みながら」劇場を出る
誰の言葉だったか「映画とは答えを提示するものではない。観る者に、考えさせるのが本当の名作だ」という名言があるが、まさにその意味で、この作品は「真の名作」だと言える。“家族”という普遍的なテーマに加えて、全てのシーンのリアリティが高いため、観る者がそれぞれの立場から、そこに込められた意味を考えてしまうように出来ている。私には、子どもがいないが、浅野忠信演じる父親が、娘から拒絶されるシーン他、数々の場面で「自分だったら、どんな風に応えるだろうか?」と考え込んでしまった。
演技については、即興的な手法を取り入れたことが成功していることは、すでに多くの人たちが語っている。ドキュメンタリー出身の三島監督ならではの演出として賞賛されているが、この監督は画作りもとても上手い。それは、NHKにいた時からそうだったし、これまでの映画作品全てにおいて映像のクオリティが高い。今回も、冒頭の不思議な三色から引き込まれるが、モノレールの運転席から撮ったような外廊のドーリー映像や、観覧車を空中から観たような俯瞰ショットなど、随所に「不安」を感じさせるカットが挿入されている。
また、舞台設定や状況設定も優れている。浅野忠信が働く場所は、IT技術にコントロールされていて、住んでいる団地も(実際にどうなのかは別として)斜行エレベーターにのって自宅へと運ばれる。つまり、自宅以外の場所の、ほとんどが人工的、無機的なのだ。そのため、自宅のドアを開けた瞬間、息苦しくなるような“人間臭”のようなものを感じてしまう。そこが、必ずしも「居心地の良い場所ではない」と浅野が感じている事が、こちらにも伝わってくる。
少し穿った見方かもしれないが、私は一種の「恐怖映画」のようにも感じた。そこら辺のホラー映画では感じられない、「リアルな怖さ」が、娘とのやりとりや、田中麗奈演じる妻とのケンカの場面から滲み出ていた。上記の演出による高い演技力や巧みなカット構成が、人間が心の奥に、潜在的に抱えている「家族崩壊」の不安を、刺激してくるから「怖い」のだと思う。
この作品の普遍性についてはモントリオールで、日本人ではない人々から高い評価を得たことで、客観的に証明された。純度が高いのだ。
ハッピーエンドでもなく、絶望的な悲劇でもなく、誰もが「考え込みながら」あるいは、自分の家族について、あれこれ想いを巡らせながら劇場を出る。「家族とは?」簡単に答えは出ない。人生の真理の一端に触れているこの作品は、間違いなく三島監督の、代表作の一つになるだろう。
タイトルなし(ネタバレ)
奈苗の能天気さが途中腹立たしくなった。
思春期の娘が居るのに、考えなさ過ぎだよ。
子供は自分の分身では無い。それぞれの想いや考えがあって当然。
親の都合で環境の変化を押し付けたら壊れてしまう事だってある。
自分の本当の子供では無いのに、どうにか分かり合おうと努力する信の優しさが、思春期の薫には逆に皮肉的で、嫌らしく見えたのかもしれない。
本音をキチンと表現出来ないのが思春期の難しい所。
どう頑張っても上手く行かない事が重なっていく。
そんな時、痛い目を見てしまうのは大体が弱い女性や子供なんだよ。
“また手を上げられた”時の恐怖を奈苗みたいな人には身に染みてほしい。
この人だけは大丈夫、なんて絶対にない。
沢田の待ち合わせのシーン...子供への愛情が無かった訳ではなかったんだ、と思う所。
身なりもキチンとしてきて、薫との懐かしい想い出も話したりして。
でも、きっと、離れて暮らしてるからこその愛情なんだろうな。って思う。
登場人物それぞれの心情が、非常に良く伝わってきて、終盤は涙が止まらなくなっていました。
家族の為に働くお父さん。
妻や娘に毛嫌いされても耐えてるお父さん。
本当に偉いですね。
怖かったけど…改めて、亡き父に感謝です。
舞台は東京ながら西宮名塩斜行エレベーター
府中あたりが舞台か。
重松清の原作を読んでみたくなった。
カラオケだけではなく、エンディングテーマも本家の「悲しみの果て」で締めてくれても良かったかも。
女が男に「理由は聞いても気持ちは聞かない」っていうけどそりゃそうでしょ!と思ったら父から娘を諭す伏線だった、という演出にはハッとさせられた。
子役は別にしてキャストには違和感。
ラストにタイトル出るのはまあその通りとして浅野さんの顔の静止画で終わる意味が?
とてもよかった
血縁のない父と娘二人で、長女が反発している。次女が父親になついていることにむかつくようで、意地悪を言うのだがそれは弱い者いじめであり、卑怯者のすることだとたしなめてやって欲しかった。
お父さんには、分かれて暮らしている実子の娘がいて時々面会しているのが羨ましかった。分かれた元妻も、感情より筋を優先するタイプのできた人だった。
コップを割った時に田中麗奈が「大丈夫?怪我してない?」と慌てて言う時に「見れば分るだろ、うるせえな」と切れて言い返していたのがとても心に残った。押し付けがましい感じがリアルで、女性のいい面と悪い面を見事に描いた映画であった。
クドカンのクズ男っぷりが素晴らしかった。役者としてこれまで見た中で一番よくて、見直した。長女に対してひどいことしないで欲しいと思っていたのだがきちんと正装して現れたのを見て、この人も人の子であり親だったのかと不意を突かれ、そりゃそうだよなと納得した。素晴らしく人間くさかった。
"親愛なる、よそ者"どうしの不器用な家族関係に唸る
まさに"第41回モントリオール世界映画祭"のコンペティション部門で、"審査員特別賞"を受賞したというニュースが入った。百聞は一見に如かず。この受賞の一報は十分に納得のいくものである。
直木賞作家・重松清原作といえば「恋妻家宮本」(2017)や「アゲイン 28年目の甲子園」(2015)など、ここ3年で4作品と続いている。それも監督や制作会社はすべて別で、その人気の高さがわかる。
重松作品は、いずれも現代社会における家族や人のつながりをテーマにした、"人間ドラマ"である点で共通しており、人物設定が物語の核になっているので、俳優の力量がそのまま出やすいとも言える。それを三島有紀子監督が撮るというので、それだけで楽しみになる。
本作も、夫婦役を務めた浅野忠信と田中麗奈の演技力、3人の子役キャスティングの南沙良(薫)、鎌田らい樹(沙織)、新井美羽(恵理子)の自然なカラミを存分に楽しめる。
バツイチ同士の再婚である夫婦には、妻の連れ子である2人の娘がいる。その4人家族のもとに新しい"命"が宿った。つまり夫婦初の実子である。一方で、夫には元妻のもとに娘(実子)がおり、離婚後も年に数回の対面を繰り返しているが、同居している2人の娘以上に親密な親子関係が継続している。
複雑な気持ちになった長女は、"本当のパパに会いたい"とグレ始めてしまう。さらに元妻の再婚相手が、余命わずかのガンに侵されていることがわかる。
"本当の親になれないオトナ"、"本当の子供になれないムスメ"、"形だけの親でありながら愛情を注ぐオトナ"・・・・不器用な家族関係が延々と描かれるが、飽きさせないテンションで最後まで、人間関係のシビアな課題を突きつけられる作品だ。
ちなみにモントリオールでは、外国語タイトルが「DEAR ETRANGER」(親愛なる、よそ者)と付けられたが、こちらのほうが実にタイトルらしい。しかも、"英語"+"フランス語"という実に日本的な外来語が、カナダ(モントリオール)という地においては、見事にハマったのではないかと思ったりして…(笑)。
(2017/9/5 /テアトル新宿/シネスコ)
胸にせまる
2度目の鑑賞。内容もストーリーもすでにわかっているのに、登場人物の感情がまたぐいぐい胸にせまってきた。それぞれの感情に共感してちょっと苦しくなる。すごくリアルなやりとり。役者さんたちの演技力と監督の演出力が素晴らしい。
主人公の元妻の再婚相手の病室のシーンで、悲しいシーンなのだけれど救われる。血のつながりがなくても家族になりえるのだと。。そこからは前向きなシーンが続き、ほっとする。普段はやさぐれた格好をしている元夫が着慣れないスーツを着ているシーンは切なく愛おしい。
幼子が生まれたあとの続編も見たくなった。
娘を育てる
全95件中、41~60件目を表示