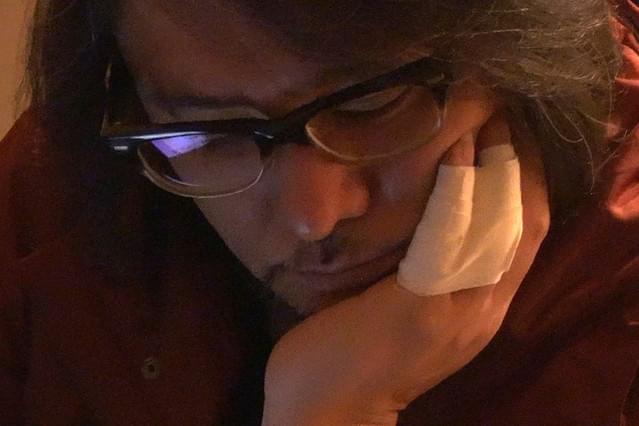FAKEのレビュー・感想・評価
全66件中、41~60件目を表示
入れ子構造のドキュメンタリー
佐村河内含めて、出てくるヤツらがみんな嘘つき。マスコミ、監督も。
ただ佐村河内って、答えにくい質問されると間をとって嘘つくんですけど、奥さんを愛してるかという質問には即答する。あと、猫がとても幸せそうできっと佐村河内自身も悪い人ではないのだろう。動物は嘘をつけないから。
この二つは少なくも真実なのではないか?
というある種の希望を台無しにして、全部作り話にしてしまう最後の12分。監督がタバコを止めることに動揺する猫すら捏造できてしまう。ベタ劇映画的な絵面で二人の愛すら陳腐化してしまう。
ドキュメンタリー映画としては反則に近いどんでん返しだと思いますが、佐村河内事件なので成立する手法だと思いました。嘘だらけの佐村河内をやらせドキュメンタリーで描くっていう。
「トルコ行進曲」をちょっとアレンジしちゃう佐村河内守
これは凄いドキュメンタリー。フェイクとは嘘とか贋作とかのことやけど佐村河内守が嘘をついているのかまたはこの作品が嘘をついているのかまたはタイトルが嘘で映るものみな真実なのかまたは…信じるか信じないかは自分次第。惹句の通りラスト12分の展開は誰にも言えないなあ
「トルコ行進曲」を思わずちょっとアレンジしちゃう佐村河内守がチャーミングだった
佐村河内守がコップに豆乳をなみなみに注ぐシーンも面白かったなあ。ご飯を食べる前に豆乳をワンパック空にするというルーティーンがあるとのこと
いや俺も完全に騒動を面白がった側の人間やし心が痛くなったよ。ただそれまでの自分の認識を揺さぶられることは文字通りの意味で「面白い」よな
関係ないけど小宮山悟も魔球「シェイク」とそれのフェイント「フェイク」で野球ファンの変化球に対する認識を揺さぶったことは記憶に新しい
損はしない1本!
前日、「貞子vs伽椰子」を見た口直しの意味もあって、鑑賞。
結論から言うと、佐村河内守を巡って、世間が大騒ぎしたその「真実」について、森監督は一定の答えを示した、と思う。
彼の奥さんが、手話通訳してないのに、うなずいているように見える場面もあったりして、彼の耳が聞こえるかどうか…という点については最後まで疑問は消えない。
しかし、現代のベートーベンと言われたとしてもおかしくないような、その「実力」は見せているのである。
いや、そのこと自体も、タイトルにあるように「FAKE」なのかもしれない。
その判断を見る者に預けている点で、「真相」を想像させる作品になっているのはすごいことだ。
映画好きを任ずるのであれば、見ておくべき作品。損はしない。
上映館が少ないのが、残念である。
結構衝撃的な内容
結局あの一連の報道は“祭り”だったのだろう。分かってはいたが、日本のメディアは真実が何か、はどうでもよくて数字がとれるかどうかが重要なのだ。絶賛もバッシングも、彼らメディアにとっては数字さえ取れれば同じことなのだ。作品中、海外のメディアも一社だけだが取材に来ていた。その取材も記者自身が納得するかどうかが焦点で、日本のメディアでは恐らくその質問は出なかったのではないかと推測する。近い将来(実はすでに現在でも?)日本人より一部の外国人の方が日本国内の事件について、より詳細に知っているなんてこと普通に起こりそうで(すでに起こっているのかも・・・)何とも実にイヤな気分にさせられた。個人的には必見の映画と思う。
真偽はわからないが・・・
黒か白かよりも大切なこと
明らかにどこかで嘘をついているのがわかっても、魅力的な嘘をつく人と、人を遠ざける嘘をつく人がいる。
例えば、
ティムバートン作品の「ビッグ・フィッシュ」に出てくるホラ吹き父さんのような人が前者。
400人いた友達をすべて失ってしまった佐村河内は後者だ。
佐村河内は、楽曲の制作において、ほぼ全てが共作であったのに単独制作だと欺いていた。そこは大衆の前でカミングアウトしているし、世間もマスコミも周知で既に過去のものになっている。
それでもなお佐村河内は、森監督や、外国人ジャーナリストの問いかけに対し、頑なに、知られたくない何かを守っている。
自分のためなのか。誰かのためなのか。
罪の意識なのか。
何か、うっすらと嘘をついている、ように見える。
それが自分を守るためだけだとしたら、うんざりするほど魅力のない嘘。
周りの近しい友人たちが離れていってしまったのは一つの事実。
佐村河内自身が白か黒かは、
そこまで大事なことだろうか。
それより、
人を惹きつけるか否か、なのではないだろうか。
どんなに嘘をついてるとしても、
魅力がありさえすれば、それでいいと思う。
なんにも過去から吹っ切れていない表情。くすぶっているオーラがハンパない。
そんな佐村河内を見ていると、息苦しくてたまらなくなる。
堂々としろよ!!(怒)
またそのフリーズ顔やめろ!!(怒)
と同時に、平然と強い態度をつき通せない、ナイーブな人柄も垣間みえるのが可愛らしいところ。豆乳好きすぎて可愛すぎ。
うーん...。
耳ってわりと聞こえてるんじゃないの?
なんでそれが聞こえて、それが聞こえないの?
新垣は接触したがってるの?何なの?
あれ?新垣が嘘をついてるのか?
楽器弾けるの弾けないの?
聞こえないのにOK出せるの?
てか本当に音楽を愛しているの?
映画全体を通して、
いーろんな曖昧なグレーが漂いまくる。
そんななか突如現れる、
テレビ局の、限りなく黒に近い黒。
そして、
バッキリ輝きを放っている、
佐村河内への愛。
グレーにまみれているからこそ、
確固たる奥さんの愛が、
くっきりと浮き彫りになって感じられる。
(それが佐村河内だけに対してじゃないのも素晴らしい。ケーキのバリエーション!)
この映画には、
間違いなく愛が記録されている。
(遠出したときの腕を組んで歩いてるカットなど、さりげないけど本当に美しい)
そこは本当に、間違いない。
信じる、信じないとかではなく、
どうであれ受け入れるのが当たり前だと。
そんな奥さんの姿勢は、ある種受け取る側のひとつの答えを提示しているのかもしれない。
疑うのも疲れるでしょ?楽になれば?
とも言われているような気がしてくるのは、大げさだろうか。
さて、
衝撃のラストシーンは、
白か黒かどころではなく、
本当にいろんな詮索や想像ができてしまう。
いずれにせよ、ラストの曲は、共作の制作スタイルがメインだった佐村河内にとって、初の100%ソロ楽曲だろうし、彼はここから始まったのだという見方もできる。
本当に彼が作ったのであれば。
監督の靴下と最後の問いかけは、
「嘘にしたくなかったらてめえで本当に塗り替えてみろ」
という監督の、愛ある怒りではないだろうか。
白と黒とが衝突して、ゼロになった今(いうても見せかけのFAKEだけど)、ここからどう舵を切るかは、彼次第だ。
共犯関係
私は佐村河内氏をほぼクロだと決めつけて、作品を鑑賞し始める。
佐村河内氏は聴覚障害者ではないのかもしれない。作曲することができないのかもしれない。もしかすると嘘をついているのかもしれない。しかし、この作品は私の期待を反して、佐村河内氏個人が起こした捏造物語ではなかった。
森監督は、撮る側も撮られる側も、作る側も作り出される側も、共犯関係であるということを暴きだした。更に、捏造を捏造と疑わずに受けとる私達をもあぶり出し、ある問いを投げかけた。
映画をニュースをテレビをどの眼で見て、どの耳で聞いて、どの頭で考えたら良いのだろうかと。
佐村河内氏が飽きられれば、メディアはネタを量産し「FAKE」を仕込み続ける。某タレントの不倫報道、某野球選手の薬物騒動、某歌舞伎俳優の、某、某、某。
しかし、私は何の根拠もない「FAKE」を目にした時、頭の中で繰り返し繰り返しこの作品のことを思いだし、そして自問し続けることになるだろう。捏造を受けとるという自問を。
全部見てきた猫がしゃべれたらなあ、と思いながら。
なんちゃない。結局、この本人も、奥さんも、ノンフィクション作家も、TVプロデューサーも、新垣も、みんなFAKE。監督自身も、その自覚があるのだろう。だから、最後の最後に、あんな幼稚な音源を自慢げに披露した本人を担ぎ上げ、奥さんをも持ち上げて、「私を信用してます?」といまさら聞き、「何か隠していることはないですか?」と踏み絵を踏ます。
どう見ても、監督自身が本人の嘘を確信しているでしょ?
こんな内容(判断を客にゆだねるような)じゃなきゃ、本人の承諾を得られないからこうしたまでだ。正直、ところどころにはっきりと悪意のある編集はされているのに、それに気づかない本人は間抜けだ。
だって、耳が聞こえない人特有のどもったしゃべりじゃないし。たまに明らかにリアクションが早い(会話を聞き取れている)ときがあるし。父親の話が、全部聞こえてる反応をしているし。
おかしいよ、観てて。いま、確実に聞こえてたでしょ!って何度も思ったもん。
それに、音楽をやっていた人間が、譜面を書けないなんて、どう考えたってあり得ない。あの、指示書見せられて、新垣がバカにしてしまうのもわかるよ。
ほんとに、マスコミがでたらめを垂れ流したって主張するのであれば、「隠してないか?」と聞かれたときに、「ない!まだ信用できないのか!」と怒るだろう?
監督は、味方のフリをして懐深く潜り込み、世間に真実の一端を公開してくれた。その労力にはご苦労さんと言いたい。
上映回数増やしても、それでも満員。いまだ、世間の関心の高さを垣間見た。
虚実皮膜の理
本当の「FAKE」は誰なのか…。
森監督のドキュメンタリーは、「A」「A2」共にリアルタイムで映画館にて観ていた為、「FAKE」も迷わずリアタイで鑑賞を選んだ。
世間で騒がれていた佐村河内のイメージが覆され、そして、如何にマスコミのやり方が汚いか知らしめさせられた。
佐村河内に有利な情報はわざと伏せ、ペテン師イメージを世間に植え付けさせる偏った報道をする日本のマスコミ…。
いや、発端となった文春の記事を書いた神山とかいうジャーナリストが一層偏った報道を煽っていたのが、本当に腹立たしかった。
一つの騒動を丁寧に描く事で、一体本当は誰が「FAKE」なのかが顕著に表現されていた。
そして、真顔で平気で嘘を吐く大人達が、これほどまで汚いやり方なのかと愕然とした。
佐村河内は、全てを失わされたけど、彼なりの出口が見えたラストを導いた森監督は、素晴らしいドキュメンタリー監督だと思う。
安っぽい。見る価値なし。
ただただ安っぽい映画。
佐村河内氏が全聾ではないことと、
ゲーム音楽くらいの簡単な(そして陳腐な)
作曲ができることは、知っている人は知っている。
騒動のあとに出されたBPOの調査レポートを
読めばよくわかる。
それなのに、それを知らんぷりして、よくぞ最後まで
「本当は聞こえるのでは?」「作曲はできないのでは?」
という「謎」で押し切ったものだ。
また、この映画で描かれる「マスコミのいい加減さ」は
さして目あたらしいものではないし、
佐村河内夫妻の愛情物語(もたれ合い?)は、
「ありそうなこと。だから一緒にいるんでしょ?」
というくらいのもの。予想を裏切るものではない。
「傑作」と評する人もいるが、
この作品は、おそらく映画史には残らないだろう。
前宣伝につられて見たが、とても残念な映画だった。
DVD化されてから見ても、十分に間に合う凡作。
これで感動したり、驚いたりすると思われたら
観客も安く見られたものだ。
悪いけど
見終わった後、ただただ圧倒され、考えさせられる。 森監督の白か黒か...
見終わった後、ただただ圧倒され、考えさせられる。
森監督の白か黒か判断したがるマスコミや世間への批評的な視線が込められているのは間違いない。
森監督は黒に白をぶつけたらどうなるか?ということを意識したと、本作のインタビューで答えている。
この映画を観る前の佐村河内守の我々のイメージは?しかし映画ではその逆のイメージをある種ドキュメンタリーという形をとって、故意的に描き出す。
ラストのある仕掛けで、佐村河内の正当性を明らかにしたいわけではないのは、森監督の最後の最後の質問をもっても明らか。
本当は何で、嘘は何なのか?そしてその間のグレーはどこにあるのか?
そのうえで我々はなにを考えるのか。
上記のテーマは陳腐だという人でも、構成が圧倒的にスリリングで、舞台はマンションの密室なのにとても映画的なのを認めるのにやぶさかではないだろう。
今年を代表するとんでもない傑作であるのは間違いない。映画が好きな人には必ず見てほしい。
悲しみを撮る
「佐村河内さんの怒りではなく、悲しみを撮りたい」と森達也監督は言った。
怒りとは即物的で、瞬時に現れる行為だろう。でも、悲しみとはもっと深い感情ともいえるだろう。
それも、渦中の出来事から少し時間が経っているから、なおさら冷静なものが必要だ。あまり、周りに右往左往されるのではなく、猫の目のように、客観的な視点が必要だと思い、自ら望んで監督を引き受けた。
はじめのうち、佐村河内氏は怒りを隠せなかった。
ゴーストライターとして告発した新垣氏にも、それを単純化して伝えたマスメデイアにも、また、それを商業化して一大見せ物としたコマーシャリズムにも。
事実よりも、面白おかしくして、見せることに佐村河内氏は不信感がいっぱいである。
そもそもゴーストライター事件として扱われることに嫌悪している。この問題は共演者事件であると言っている。
作品をつくるということはどういうことか?
僕も弟と何曲も曲を作っているが、いろんなパターンがある。
たとえば、初めに僕が詩を書き、リードとなるフレーズをつくる。そのとき、あるイメージ(それはビートルズの曲だったりするのだが)をもっている。それを弟はなるほどね、とか言ってミドルパートを作り、全体を膨らませる。僕はここはもっとこんな感じがいいな、でも、全体にはOKだといって曲ができる。レノン&マッカトニーの作品もいろんなパターンがあったろうが、こんな感じでできていったのではないかと思う。だから、佐村河内氏がイメージを伝え、新垣氏がそのイメージを膨らませていくということはひとりの作品ではなく、ふたりの共作以外のなにものでもないだろう。
耳も聞こえる音もあり、聴こえない音もあるというのは確かだろう。僕自身、長年ウォークマン生活で耳には自信がない。人には聞こえてるのに、僕には判然としない会話もあるからだ。最近、特に感じることが多くなった。佐村河内氏の場合、妻の手話がなければ困る場面がたくさんあることが、この映画でもわかる。
この映画で事実を歪曲して伝えた張本人のように描かれている新垣氏も、実はこの面白おかしくすれば視聴率があがるという組織の罠にはまっている人に思える。一個人としては気の小さな善人であるのだが、大きな体制のなかでは抗えないのだ。
個人としては悪い人はいない。しかし、それが全体として集約させる時、おかしな動き、変な結論になってしまう。それが増幅されて全く違うものとなる。いろんなディテールを切り取ってしまうとき変質が起こる。だから、表層だけでなく、「じっくり、ちゃんと考えてみようよ」と言われている気がするのだ、僕自身にも。
猫の眼にうつるもの
わりと話題になってる映画のはずなのに、渋谷の一館でしかやってないってどういうことなんだろ?
ラスト上映の3時間前に満員締め切りになってた。早めに行った方が良い。注意。
あと、手ブレがかなりキツイので、酔いにも注意。
ラストは、「ここで感動したら負け」と思いつつも感動して眼がうるうるしてしまい、この感動も含めてFAKEだなんて、なんて凝った構成なんだ、と監督の策士っぷりに驚いた。
ほんとに凝った構成。
出だし、明らかに監督の言葉に反応してうなずく様子が映り、「やっぱり聞こえないってウソなんだな」と思わせる。
観客の興味は、「ホントは聞こえてんだろ? ほら、よく言葉の反応見てると分かるよ…。聞こえないって演技も過剰すぎてバレバレだよ」というところにうつる。
佐村河内さんの「うかつさ」に逆にはらはらし、「もうちょっとうまく隠さないと…」とすら思ってしまう。
しかし、次第に「本当に聞こえてないのかも」と思わせる描写が多くなり、神山さんや新垣さんの取材拒否で、いったいウソをついてるのはどっちなのか、確信が持てなくなってくる。
ほんとのとこはどうなんだ?ともんもんとしたところで、外国雑誌の核心に迫る取材で、この事件のある程度の真相らしきものが明らかになってくる。
聞こえているか聞こえてないかもはっきりとしないし(本質的に証明することは不可能)、実質的に作曲したのがどちらなのか、ということもはっきりしない(主観の要素が大きい)が、実は「ディテール」でしか語れない部分がある。
日本のテレビの取材の不完全さがあらわになるのは、この瞬間だ。結局日本のテレビは、「わかりやすいストーリー」「わかりやすい善玉、悪玉」が欲しかっただけで、実際はどうだったのか、には関心がないことが明らかになる。皮肉にも外国人の取材によって。
そして、観客が、「やっぱり佐村河内さんて作曲能力ないのね。楽器すら使えないのね。自分で思い込んでるだけなのね。口だけヤローじゃねえか」と思ったところで、衝撃的なラストの展開。
まさか作曲なんかできない、と思い込んでしまっているところに、あの曲、そしてエンドロール。これは感動するな、という方が無理。
ここで感動したら、あの薄っぺらいテレビで佐村河内さんを短絡的にペテン師だと思ってしまうことと同じじゃね?とわかりつつも、感動せざるを得ない。
だって、無理だ、不可能だ、と思ってることをやってしまうんだから。「セッション」のラストの展開にも似ている。
そしてエンドロール後。監督の最後の問いかけに、長く沈黙して口を開く。その瞬間終わる。完璧な終わり方だ。「インセプション」を連想した。
ドキュメンタリーで、時系列で実際の出来事が展開されているだけなのに、あまりにドラマチックで、全く飽きない。
「謎」と「裏」が次々に提示されていって、観客の先入観をゆさぶり、テレビの裏にある滑稽さや残酷さを浮き彫りにする。
普段見慣れているバラエティ番組が、その企画段階や、笑われている当事者の視点から見ると、こんなにも印象が違うことに驚く。
この事件で一番の被害者は、佐村河内さんというよりはむしろ、新垣さんなのではないか、とも思った。
映画の最中、観客から何度も笑いが起こった。それは、テレビ局の担当者の振る舞いだったり、新垣さんの取り上げられ方だったりするのだけど、ドキュメンタリーの映像なのに、まるでコメディのように出来すぎた滑稽さで、滑稽すぎて残酷、ホラーにすら見える。
テレビは、僕らの頭をこんなに「馬鹿」にしてしまったんだ、と思うと、背筋が凍る。
猫の眼が印象的だった。きっと、何も考えてないんだろう。でも、人間の様子をじっと見ている。ときどき、人間の言葉に反応してるように見えるときもある。
人間の側の複雑な事情、悩みなんかは、猫は分からないし、そもそもなんの関心もない。はっ、と思ったのが、そういう、全く違う価値観をもっている存在が身近にいるって、すごい救いだなあ、と。
どんな人間にもとる行為をしても、猫だけはその人間を軽蔑することは絶対にない。だから、嘘をつく必要も全くない。
奥さんがたんたんとしてるのも良かった。だんなに寄り添いながらも、そんなに作曲に関心があるわけでもない。たぶん、誰がウソをついてるかなんていうことにも、あまり興味がない。でも一緒にいる。たぶん、ずっと一緒にいるんだろう、この夫婦は。その、ただ自然に、当たり前に、一緒にいること。なんて素敵なんだろう、すごいな、と思った。
全66件中、41~60件目を表示