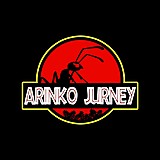帰ってきたヒトラーのレビュー・感想・評価
全213件中、161~180件目を表示
笑えるか笑えないかのギリギリ
ただのコメディだと思ってたらまさかすぎた!笑
すっごく面白かった笑
笑いと風刺とパロディと現実がごっちゃになってて
でも面白くて!
あんまりナチスの映画とか見たことなかったんだけど
これ見る前に『ヒトラー最期の12日間』だけは見て行って良かったwww
ほんとに笑えた!
この年になって日本の政党も名前すらよくわかってないけど、大学でドイツ語とってたおかげで
授業で触れたからドイツの政党はわりと分かってたから良かった〜笑
歴史は繰り返す。クスッと笑えるブラック・ユーモア。
【賛否両論チェック】
賛:ヒトラーが現代で人気を博していく様を、シュールな笑いと共に痛烈に風刺していくのが印象的。
否:笑いの感覚はやや日本のものと異なるので、笑えるかどうかは観る人次第。政治色も少しある。
設定はとても斬新です。現代へとやってきたヒトラーが、モノマネ芸人として祭り上げられていく中で、当時にはなかったメディアを駆使して、次第にその支持を拡大させていく様が、コミカルですが痛烈な風刺と共に描かれていきます。
一方で、笑いそのものはかなりシュールというか、日本人の感覚にはやや合わない感もあります。時折交えるドキュメンタリーテイストな展開も、好みが分かれそうなところでしょうか。
政治色も少しあるので賛否は必至ですが、笑うに笑えないある種の問題作を、是非チェックしてみて下さい。
民衆を扇動したのではない、民衆が私を選んだのだ
現代にタイムスリップしたヒトラーが、モノマネ芸人と間違われ、その言動などが民衆に受け容れられていく・・・という内容。
興味深いのは、タイムスリップして現代のドイツに現われて、現代が第二次世界大戦前のドイツに似ていることを理解し、ネットメディアやテレビメディアを利用して、自説を展開し、はじめは疑ったり笑ったりしていた民衆が、彼を受け容れて歓迎するようになることです。
そう、コメディはコメディでも、かなり怖い。
怖い怖い。
笑いが凍りつくとはこのこと。
後半登場する二つの台詞が印象的です。
ヒトラー曰く、「民衆を扇動したのではない、民衆が計画を提示した私を選んだのだ」「わたしは何度でも蘇る。みなの心の中にあるからだ」。
これも怖い。
世の中のバランスが少々崩れかけているのかもしれません。
グローバリズムとナショナリズム。
これは、たぶん、どちらか一色で染めることは不可能。
両方のバランスを取りつつ、生きていかなければいけない、と思う。
どちらかでなければならない、と思ってしまうと、なんだかヘンなことになってしまう・・・
と、主題の面からみた、この映画は、傑作・秀作の部類。
なんだけれど、つくりとしては少々粗っぽい。
タイムスリップしたヒトラーという荒唐無稽な題材を、ドキュメンタリーのようなタッチで現代ドイツに放り込み、そして、ヒトラーが書いたタイムスリップ後のことを書いた第二の伝記に基づいて映画化した、という二重三重のメタ構造が上手くいっているのか、上手くいっていないのかよくわからない。
あまりにも複雑な構造にしてしまった上に、映画前半からの視点が、誰のものか統一されていないのも、映画の乱れにつながっている。
特に導入部。
観客としては、登場したヒトラーは「本物」として端(はな)から認識しているはずだけれども、ヒトラーが本物かどうかにかなり尺も割かれ、彼を題材にドキュメンタリー映画を撮っているザヴァツキ青年の視点(モノマネ芸人として信じ込んでいる)がはいってきて、ややこしい。
ここいらあたり、もう少しスッキリ整理して、あくまでも虚構のコメディとして撮ってもよかったのではありますまいか。
いやいや、そうすると、後半挿入されるドイツのニュース映像も活きてこないのかも。
映画と現実の境目も判らなくするような、後半の展開も活きてこないのかも。
映画のテーマ性よりも、その複雑怪奇な構造がどうにも気になって気になって。
評価は極端に分かれる作品
つまらない
歴史は繰り返される
的確な未来予言映画
コメディーでもブラックユーモアでもない
ことしベスト1級の面白さ!
もし現代にヒトラーが現れてコメディアンになったら…というシャレにならないドイツ映画を、TOHOシネマズシャンテにて鑑賞。
レディースディ&日比谷という土地柄もあり、おばさま中心に超満席!40代以降の男性も2割ほどいて、場内はぎゅうぎゅうでした。
これは、おもしろい!
今年ベスト1にしたいくらいに喰らいました!
この映画、ただのコメディ映画ではありません。
現代の民主主義を痛烈に批判した、とても政治的な内容を含んだ作品です。
未成熟な政治に対する批判や、芯の弱い党首に対しての怒号や、低俗なテレビ番組に対する憤りなど、
世界一の極悪人のはずなのに、彼の発する言葉の数々が、至極真っ当で関心・感銘を受けてしまうことばかり。
ただ、どこか決定的な歪みがあって、ふいに違和感を感じては「はっ!いま見惚れてたこの人、ヒトラーだった!」と恐怖します。
めっちゃくちゃな題材なので、ちょっと間違えれば興ざめしてしまう危険性があるんですが、描き方が秀逸!
要所要所でドキュメント風なカットをいれたり、
何層にも入り組んだメタ構造を取り入れたり、
この映画のフィクションラインをあやふやにしていくので、
「ここにヒトラーがいる!」と思い込ませる巧みな演出で、どんどん入り込むことができます。
ただのコメディ映画を超えた、ヒトラーという人物を通して「ドイツの今」を誠実に描いた良作なので、
公開館数も少ないようですが、是非観ていただいたい一作です。
帰ってきたヒトラー
いま、全ての現代人が試されている…?
笑える。けど笑えない。けどやっぱ笑っちゃう。けど…
ヒトラーが何をしたか、どれだけ冷酷な人間か、どれだけの人を死に追いやったか、なんとなくだけど、教科書や何冊かの本、いくつかの映画なんかで私は知ってる。
だけど、あの演説。
自信と信念、カリスマ性にあふれ、何かやってくれそうな雰囲気に満ちている。
時にはユーモアを交え、話に緩急があり、引き込まれる。
何をしたのか分かっているのに、「この人いい人なんじゃない?」と一瞬思ってしまって、そんな自分に気づいてゾッとした。
そうやって、おそらく「信念がありそうだからやってくれそう」「話が分かりやすくて面白いから」といった理由で多くの人が一票を投じたことで、想像もつかない数の人たちが意味もなく殺された。
テレビやメディアの向こう側から、その人の資質や本当の信念を見極め、支持を表明するなんて、果たして可能なんだろうか。
なんかほとんど不可能に思える。
…なんて思いつつ、きっと今回の選挙も日々の生活に追われて、直前にざっと公約だけ見てなんとなく投票してしまうんだろうなぁ…。
そういえば先日、BS-1でヒトラーが書いた「我が闘争」についてのドキュメンタリーを見た。
今年の1月に本の著作権が切れて、70年ぶりに再出版されたらしい。
映画と同じように、70年ぶりに蘇った“ヒトラーの信念”だ。
「二度とあの悲劇が起きないための研究材料として出版するべきだ」
「本に感化され、共闘する人々が現れるかもしれない」
激しい議論の末、注釈付きで出版された。
70年経って、私たち現代人はヒトラーをはねのける強さを持ち得たのか。
それとも再びヒトラーに感化されてしまうのか。
世界中で軋轢が生まれている今、私たちは彼に試されているのかもしれない。
…なんてことを、ゲラゲラ笑いながら思った。
ちょび髯おじさんが、やさしく君を包む
「みんな、最初は笑っていた。」作中のセリフですが、本作を象徴してます。
ユーモアなのか、風刺なのか、判別しない作りは、ヨーロッパの今を、具現化しているようです。しかも、多数決が、正しい選択をするとは限らないと云うメッセージまで、織り込んであるあたり、時事ネタとリンク。御見物も、多かったです。
「指導者は、大きな嘘をつくべきだ。群衆は、小さな嘘しか見抜けない。」ちょび髯おじさんの、迷言だったと思います。正直、自分達にとって正しいことが、世界にとって正しいことかなんて、判別困難ですよね。それでも、選挙の結果によっては、またちょび髯おじさん、現れるよと、言われたような気がしました。
いずれにせよ、毒の効いた作品です。個人的には、本作観たら、中和剤として「サウルの息子」あたり観直したい気分です。
戦争はだれのせい
ドイツ映画
キャラクターとテーマばかり語られがちだが、演出もなかなか
指摘している人があまりいないようなので最初に書いておくが、物語自体はそれほど特異な何かがあるわけではない。
タイムスリップによるカルチャーギャップコメディのフォーマットをにおわせつつ、シドニー・ルメット『ネットワーク』('76)を本筋に、テリー・ギリアム『未来世紀ブラジル』('85)のオチをくっつけたような、そんな話ではある。
そういう意味では「よくあるタイプの問題作」には違いないのだが、この作品の突出した部分はなんといってもヒトラーという歴史的人物の持つ意味であり、それを見事に演じたオリヴァー・マスッチの演技力にある。
※ それらについては誰の目にも明らかだから、特に言及はしないが。
そして、これら作品のテーマやキャラクターを活かすかたちで効果的に使われていたのがフェイクドキュメンタリーの手法であった。
フェイクドキュメンタリーというのは幅の広い言葉というか、実際にはいろんな手法をさす言葉として便利に使われてしまっているが、本作におけるフェイクドキュメンタリーというのはサシャ・バロン・コーエンが『ボラット』などで用いた手法と同様の、
役者が現実に存在しない人物を演じることで人々のリアルな反応を引き出す
というタイプのフェイクドキュメンタリーである。
この作品ではヒトラーに扮したマスッチが街に出て「君は今のドイツをどう思うか」といったような質問を人々に投げかけるわけだが、その反応が非常に興味深いのである。
このような手法は、見ようによっては「役者は作り物だが人々の反応はリアル」といえるだろうし、「誘導尋問のように無理やり反応を引き出す卑怯な手法」ともいえるのだろうが、要は
本当の部分と本当でない部分がある
わけで、そのどこまで本当かわからない頭のクラクラする感じが、紙一重で保たれている社会のバランスを実によく表現しており、作品のテーマと見事に親和していたと思う。
もちろん、こうした手法は『ネットワーク』や『未来世紀ブラジル』の時代にはなかったわけで、作品内に登場する各種の現代らしさ(たとえば各種の IT 機器や SNS 、そして興味深いものを見るとすぐスマホで撮影しようとする大衆のリアクション等)ともあいまって、この作品が遠い世界の物語ではなく、我々の社会と薄皮一枚隔てたところに感じさせてくれるのだと思う。
そういう意味では『未来世紀ブラジル』的だと感じたオチへのくだり、急に展開が強引になったな・・・と思いながら見ていたのだが、これもやはり現実と紙一重の世界を表現していて、鑑賞後の今では一貫性があったようにも思える。
総じて、キャラクターとテーマが強烈なだけにそこばかり突出して語られがちだが、実は演出もなかなかの手腕だと感じた。
全213件中、161~180件目を表示