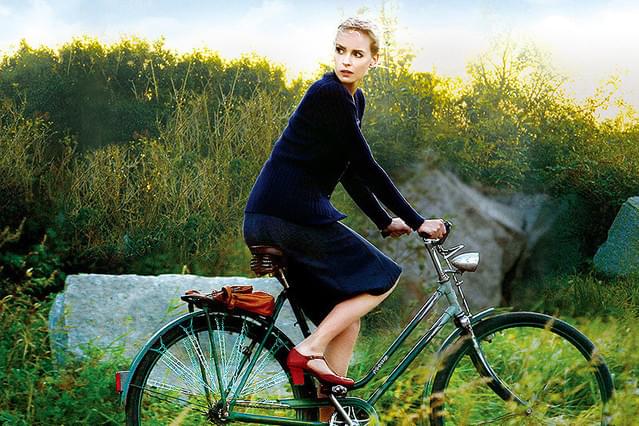「ある女の揺れる心」東ベルリンから来た女 キューブさんの映画レビュー(感想・評価)
ある女の揺れる心
ベルリンの壁が崩壊したのは1989年のこと。つまりもう20年以上も経っているのだ。完全に歴史上の一事件と化しつつあるが、この映画はそれよりもさらに前の1980年の話である。
「グッバイ、レーニン!」など、東西対立が個人に与えてきた影響を描いた映画はあったが、「東ベルリンから来た女」はそれをさらにミニマムな領域の話に落とし込んでいる。描かれるのは「東西対立により引き裂かれた男女の悲恋」ではなく、「2人の男の間を揺れ動く1人の女」の物語だ。
東ドイツの片田舎を舞台にしているため、冷戦などの影響を直接的な形として目にすることは少ない。時折登場する「外国製医療機器の話」や「外国人用ホテル」からその片鱗を窺い知ることはできるが。
それでも人々の生活には多大な影響を及ぼしている。主役のバルバラはもちろんのこと、アンドレも心の底では西ドイツ行きを望んでいるし、バルバラの恋人ヨルクは東ドイツ脱出の手配をする(この映画唯一のサスペンス要素だ)。最も顕著なのはバルバラに助けを求める、作業所から逃走したステラという少女の存在だろう。矯正という名の下に少女に過酷な労働を強いるその環境は、いかにも旧社会主義国的なものだ。このステラ役のバウアーがなかなか上手で、あどけなさを残しながらも、大人になりかけている少女を迫真の演技で見せてくれる。実際、アンドレよりも彼女の存在の方が、終盤のバルバラが出た行動の直接的な原因となっている。
だがそれらの歴史的要素よりも、この映画はバルバラの引き裂かれる感情に重きを置いている。東ドイツに未練を残さないために、誰とも深くかかわり合おうとしない彼女の硬い表情は、切実な胸の内を表している。だからこそアンドレと自然に打ち解けていく様子が微笑ましくもあり、悲しくもあるのだ。
ニーナ・ホスは、下手すると観客にも嫌われることに成り得る「嫌われ者」を繊細に演じた。彼女の心情の変化していく様をが手に取るように分かるから彼女の気持ちが痛いほど分かる。彼女が揺れ動く、2人の男がどちらも魅力的だからなおさらだ。
ツェアフェルト演じるアンドレは単純そうに見えてとても複雑な人物だ。おおらかそうに見えて卑屈でもあり、開けっぴろげでありながら繊細でもある。微妙な心の動きを完璧に捉えているから、一つ一つの会話のシーンが偽のものとは思えない。そこにはバルバラへの一途な思いがあるからこそ、全体としての彼の方向性は一切ぶれることがなく、観客も彼の肩を持ちたくなる。
対するバルバラの西ドイツの恋人ヨルクは洗練されていて、いかにも資本主義国家の人間だ。それでいて鼻につかないのが不思議である。おそらくバルバラとの愛し合う様子が、2人とも心から嬉しそうで偽りのものには到底見えないからだろう。
この複雑な人間関係が、彼女のバックグラウンドとともに重なり合って描かれる。残念なのは、ほとんどの人物はバルバラとしか係わり合うシーンがない。アンドレとヨルクは一度たりとも絡まないし(これが逆にバルバラの秘密となり、ドラマを面白くしているとも言えるが)、その他の脇役には生活感がまるで無い。それなのに「当局に監視される」バルバラを描くものだから、中途半端感が否めない。彼女が他人を避け、他人が彼女を嫌っている様子があまり見えてこないのだ。
それでもバルバラを取り巻く、悲しい恋の話には胸を打たれるだろう。幸せな場面と悲痛を感じさせる場面が程よく織り交ぜられていて、登場人物に共感できること間違いなしだ。歴史的事実を描いた作品には珍しい「個人的な」作品である。
(13年3月12日鑑賞)