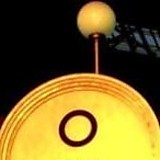汚れなき祈りのレビュー・感想・評価
全10件を表示
C教やばい
2005年に実際にルーマニアで起きた事件を元にしている映画と知ってゾッとした。21世紀にもなってこんな前時代的なことしてたのかと。
アリーナがドイツで具体的に何があったのかは明かされない。ヴォイキツァとはどうも同性愛的関係にあったようだがすでに心を神に捧げてしまったようでアガペーの愛しかくれない。すでに別の子を引き取っている里親は悪い人ではなさそうだがアリーナにとって良き理解者でもなさそうだし、あとの身よりは頼りなさそうな兄しかいない。リベラルな人間にはとても理解できない無意味に見える宗教的慣習。これは普通の人でも病みそう。
「お父様」は一応教会のトップなのだが慈悲深い人物という感じでもなく自分の教会の面子や保身しか考えてない。おまけに「C教ならロシア正教を信じないといけない」とか不寛容にもほどがある。
アリーナは突然暴れたりけいれんを起こしたりとどう見ても入院が必要に見える精神疾患なのに病院は受け入れ拒否、教会もアリーナを厄介者扱い、ヴォイキツァもアリーナを突き放すか一緒に出て行くかはっきりすればいいのに…。
あきらかに医療に繋げるべき人を、非科学的極まりない「悪魔払い」という名のもとに、真冬に拘束監禁放置するとかただの人殺しでしかないのだが、宗教が絡むとこんなに人は知能指数が下がるのか…ヴォイキツァも拘束を解くだけじゃなくてちゃんと病院か警察に連絡すりゃ良かったのに。これが信心の結果ならC教は害悪としか言い様がない。
さすが、チャウシェスクが人口増やそうと中絶避妊を禁止して、結果的に劣悪な環境かにおかれた孤児を大量に増やし破壊した国である。主人公2人が施設育ちの孤児で、教会が孤児院に寄付しているのもそのあたり関係あるのだろうか。
教会の修道女達の質素な暮らしぶりはなかなか興味深いが、明らかな病人を拘束監禁するのは信仰心のない自分にはやはり理解不能な行動だった…。同調圧力もあるのだろうか。
盲目的な黒ガラスから抜け出した白ガラス(白セーターを着たヴォイキツァ)
冒頭のシーンで、群衆の流れに逆らいながらアリーナを探すヴォイキツァ。そこで待っていてと呼び掛けるヴォイキツァに対して、レールを踏み越えてヴォイキツァを抱きしめるアリーナの姿は、はじめから二人の悲劇的な結末を予感させた。
終盤、「逃げ出して」と鎖を解いたヴォイキツァに、翌朝彼女の顔を見て微笑んだ後、アリーナは息絶える。
冒頭のシーンで二人の強い繋がりを印象付けることで、終盤の展開での切なさが活きてきた。
視覚的には、“口を開けた雛鳥”のような純真さで警察からの質問に答える黒い装束を纏ったシスターたち。それを離れたところから白いセーターを着たヴォイキツァが眺めているという色の対比のシーンが印象的。
また、邦題にて「汚れなき」と題目されてはいるものの、ラストシーンでは神父たちの乘る警察車両に泥が飛び散って終幕した。盲目的な信仰心、集団心理が倫理観を曇らせ、無関心と不寛容が悲劇を増長させるという皮肉にも感じる。
女医の演技で台無し
もったいなさ過ぎる。こんなに丁寧に作ってきたのに最終盤の女医の安い無関心演技のせいで台無しでした。最後まで見てもあのシーン丸ごとごっそりなくてもいいくらい、むしろない方が、おおそういうことなのと誘導できてよかったのではと思うくらい。ここにたどり着くまでは、まあアリーナの直情的な性格は特にこの環境ではハレーション起こすよね、とか、アリーナも悪いけどヴォイキツァも残りたいならアリーナを追い出さなきゃいけないし、一緒にいたいなら出ていくべき、それをどちらも手に入れようとするだけでなく、それを当然のように要求する、困ってるんだから助けられて当然の宗教信者精神丸出しの理論を展開していて、やっぱり宗教というのは新旧関わらず人間から責任感を奪うわよねー、なんて考えながら見てたんです。それがあの女医ったら後頭部を鈍器で殴る勢い。実話らしいから当時の世論の代弁者なのかな、にしても下手でした。それまでの修道女たちの地味な浮つくところのない演技を観ていたので、邪魔すぎて。でも話自体は面白かったですよ。ちょっとダレましたけどね
求めていたものと違ったけれど、悪くなかった。
見たかったものは悪魔祓いに必死になっていく狂気だったので、ちょっと思った感じと違った作品だった。表面的な物語については物足りなかったといえる。
しかし、違った部分でそこそこ面白く観ることはできた。
やはり気になるところは、身勝手な人々ということになるだろう。登場する人物の多くが自分の都合を押し通そうとする姿は滑稽にすら見えた。
司祭は、現実的な人なだけとも受け取れるが、お金がないために修道院や孤児院の人数を減らそうとする。
修道女たちは、自分たちの居場所を確保するためにアリーナが悪魔憑きだとしきりに騒ぐ。
ヴォイキツァは修道院の暮らしを捨てられずアリーナと出ていくことが出来ず、しかしアリーナだけを追い返すことも出来ずにいる。
教会の偉い人が、宗教画がないからと修道院を訪れないのは、面倒だからだと透けて見える。
ここまで皆、宗教関係者なのに、慈悲の心みたいなものが全然ない。表面的には当たり障りない感じに接してはいるものの、本気で助けてあげようなどとは考えていないのだ。ギリギリ修道女長だけは違ったかな。
更に驚くべきところは医療関係者どもだ。
アリーナを診察した医師は、アリーナに統合失調症の薬を出しているのだから彼女の病名は分かっている。にもかかわらず、ベッドがいっぱいだからと原因不明の病気扱いして追い出そうとする。
救急の医師などもっと酷い。死にかけのアリーナを搬送してきたことを責める。助けられず亡くなったら面倒だからと。
誰かもう何人かだけでもまともな親切心があればアリーナに降りかかった不幸は回避できたように思える。
ルーマニアは歴史の流れの中で、自分勝手な国民性になってしまったという。助け合いの気持ちがないのだ。
人間は社会性の生き物だ。そんな中で社会性を失ってしまった国はやっていけるのだろうか。本当の罪人は誰だったのだろうかと考えてしまう。
見ごたえのある映画
2005年に実際にルーマニアで起きた事件をもとに描かれた作品。
第65回カンヌ国際映画祭で女優賞と脚本賞を受賞しています。
「悪魔憑き事件」とあったので、多少、ホラーの要素があるのかと思ったら、完全なシリアスヒューマンタッチの映画でした。観た後にいろいろと考えさせられる、とても見応えのある映画でした。2時間半という長さの上、音楽やら効果音もほとんどなく、淡々と物語は進んでいきます。けれども退屈することはありませんでした。
幼少時、孤児院で共に暮らしたアリーナとヴォイキツァ。2人の少女が主人公です。ヴォイキツァは修道女として神に仕える身。アリーナはドイツからヴォイキツァと一緒に過ごしたい!という熱い思いでヴォイキツァに会いにきたのですが、アリーナの想いは伝わらず。ヴォイキツァは神の愛に包まれて暮らしており以前の彼女とは違ってしまっていたのです。(二人の関係は友達というよりも恋人に近かったような)そんなすれ違いがあり、ヴォイキツァを自分の方に向けることのできないアリーナが心を患い、激しく壊れていく。
最後まで観ると、誰が悪いのか?というはっきりした答えが出せません。修道院に身を置くことが出来なくなって、里親のところへ戻ろうにも戻れず、病院にも追い出される形になり、アリーナの身よりは頼りない兄だけ。そんな社会的な孤立もあり、アリーナは一度出た修道院に戻るけれども、そこでまた癇癪を起こしてしまい、結果、あのような不幸な結果となり。ヴォイキツァも神に仕える身といいながら、悪魔払いについては心のどこかで疑問を持っていたはず。最後に「アリーナ、逃げて」と縄をほどいたのだから。しかし、時、すでに遅し。不幸を招いた「汚れなき祈り」。世間を離れた修道院は別スポットであるかのようでした。
アリーナとヴォイキツァ、二人が出会ったとき距離感があるようで、距離が近すぎます。アリーナーは神への愛に目覚めていて、アリーナがそれを引き裂こうとするようにヴォイキツァを引き戻そうとする。ヴォイキツァはアリーナを突き放すこともなく、入院中(アリーナの)も、アリーナへの医者の質問に代わりに答えたり、何かと「世話を焼く」。二人は共依存のような関係。観ていてイライラもしますが、女優さん2人の演技は素晴らしかったです。ラスト、黒の修道服ではなく、普通のカーディガンを着て警察に向かったヴォイキツァは世俗に戻るつもりなのでしょうか。
余談ですが、神父はヴォイキツァの話から「30歳」ということでしたが、どう見ても50代位でした。何か意図があったのか? これが不思議でした。
罪深いのはどちらか?
多分に思い込みだが、厳格で狂信的な修道院が罪なき若い女性を監禁し理不尽にも悪魔祓いの儀式で死なせてしまった事件だと決めつけて観始めたので、まったく想像と違う展開に少々面食らった。
信仰の自由が認められるなら、天使や悪魔を信じることも自由、悪魔祓いの儀式もまた然り。
無神論者の人間からみれば、アリーナに必要なのは、病院での治療でありカウンセリングだが、彼女を救うために彼等が持っている方法は悪魔祓いの儀式だけだったのだ。
彼等の無知や不寛容を責めるのは簡単だ。
修道院にとってアリーナの訪問は“災い”でしかなく、彼女には出て行って欲しかった。
しかし、病院にも里親の家にも彼女の居場所はなく、混乱した彼女を受け入れたのは修道院だけだった。
社会の無関心がアリーナを追い詰めたのだ。
『4ヶ月、3週と2日』と同様、物語の根底には女(女の子)同士の共依存関係がある。
孤児院で育ったアリーナとヴォイキツァ。
二人が何故別々の道(ひとりはドイツ、ひとりは修道院)を行くことになったのか、アリーナにドイツで何があったのかは分からないが、年月の経過の中で二人の関係に変化があったことは明らかだ。
しかし、アリーナはそれを認めることが出来なかった。
二人はあまりに違う環境の中で生きてきた。
この溝を埋めることは簡単ではない。
無知や不寛容が悪いのか?
それとも無関心が悪いのか?
恐らくどちらも悪い。
しかし、両者が歩み寄り、解決の道を見出すこともまた難しい。
汚れなき祈り
異常なのは誰なのか
2005年にルーマニアで起きた「悪魔祓い」事件について、ジャーナリストが書いたノンフィクションを原案としている。題材が題材だから、異色の作品となることは間違いない。事実、この映画と似た物は思いつかない。
ほとんどのシーンにおいて、この映画は完璧に近いクオリティを保ち続けている。様々な要素、例えばヴォイキツァとアリーナの友達以上の関係性や修道院の盲目的な考え方、ずさんな病院の体制、など多くを盛り込んでいるにも関わらず、そのすべてを緻密に描くことに成功している。
ドイツで出稼ぎとして働くアリーナはヴォイキツァも一緒に来るよう誘い続ける。なぜアリーナがルーマニアをそこまで嫌うのか、1人でいるのが嫌ならどうして外国で働くのか。そういったことの明確な理由が明かされることはないが、豊かな感情表現のおかげで不思議と説得力が生まれる。また孤児院で一緒に育ったヴォイキツァに対し、過剰と言える依存を見せる点も理由は分からない。だがあえてバックグラウンドを描かないことで、サスペンスにありがちな説明過多となる語り口を避け、謎めいた雰囲気を残したままにする。これにより、元々不明瞭な点が多い事件の曖昧さを浮き彫りにし、観客の不安を煽ることにも成功している。
どんなシーンにおいても、どことなく不穏な空気が流れているのは妙にリアルで静閑な描き方が原因だろう。明らかに現代とはミスマッチな存在である“丘の上の修道院”と、そこに住む司祭と修道女。彼らが単調な活動を延々と繰り返している様は、「正教会」というれっきとした宗教であると知らなければ、その厳格さは異様な物に映る。
そんな場所に現代的な格好をしたアリーナがくれば、バランスを保っていたその狭い世界も急速に崩壊を始める。このように、視覚的にも「現代人にとって」不思議な世界が一層物語を際立たせている。
とはいえ、日本人にとって馴染みのない“ルーマニア”という国であるから、物珍しい気もするのだろう。しかし表面的にエキセントリックであっても、記憶に残る映画は生まれない。私が考えるに、最もこの映画に貢献しているのは俳優たちだ。
どの出演者も不自然な点は一つも見せない。精神に異常をきたすアリーナを演じたフルトゥルは、目で演技ができる。ヴォイキツァ以外の人間には一切心を開かず、その瞳に映るのは底なしの悲しみだ。唯一頼れる存在であったそのヴォイキツァですらも、「神」という形のない存在に奪われ、その怒りを修道院の人間にぶつけることになる。
ストラタンは自分の信念と友情との間で揺れるヴォイキツァを好演。もの静かで穏やかな人物だが、誰よりも冷静に物事を見つめることができる。アリーナをどうにかして“治療”しようとする司祭たちの行動に疑問を抱く様も非常にナチュラルで、彼女の感情の変化が手に取るように分かる。
そしてある意味で最も異常とも言える修道院の面々。彼らは盲目的に宗教的な行いを信じ込み、大きな問題に直面しても形のない存在にすがろうとする。例えば修道女たちは無知が故に自分たちの行いが、良い結果を生むと信じ込んでいる。だからこそ彼女らが暴れるアリーナを板に縛り付ける場面は目を背けたくなる。仮にアリーナが精神病だったとしたらあまりに時代錯誤で馬鹿げた行動だ。
そして修道女をまとめる司祭。全面的な信頼を置かれている彼もまた、自分が神の力を借りてアリーナを治療できると信じて疑わない。というよりは、唯一事実に気づいているが、修道女たちの手前見栄を張ることになったのだろう。そういった司祭の行動がヴォイキツァの不信感を生むことになる。
これらの要素に、精神病院での話や里親のエピソードなどが見事に噛み合わさり、事態が悪化していく様をスムーズに描いている。だが一つだけ、エンディングはあまりにも呆気ない。人間の無意識から生まれる悪意や宗教への盲目的な信仰といった問題を興味深く描いておきながら、最後はただの「異常な事件」として終わらせてしまっている。映画的な面白さを生むために過剰な演出をしろ、というのではない。しかし「汚れなき祈り」はジャーナリズムそのものではない。実際の事件をモチーフに、人間の根底にある感情をもっと掘り下げてほしかった。
そうはいっても、この映画が一級品であることは疑いようがないだろう。サスペンスとしての面白さを損なわず、芸術映画らしい洗練された演出も兼ね備えている。一度見たら忘れられない、恐るべき秀作だ。
(13年4月2日鑑賞)
タイトルなし
冒頭から複雑な展開。ファシスト神父には反吐が出る。ルーマニアではこんなものなのか。まるでカルト。世俗を捨てろと言うけど、むちゃ俗っぽく。自分たちが支配するために従属させているだけ。神父はヴォイキツァと関係を持っているふしまで。
こんなに彼女に執着してたのなら、アリーナは何でヴォイキツァを捨てて出て行ったのか。
アリーナは精神的疾患があると思われる。ちゃんと治療をすべきなのでは。
修道院にいるのは心の病を持つ人が多そう。
アリーナの仕業は気味がいい。しかし教会は悩める人の心に寄り添わず、世間体のみ。
4ヶ月、3週と2日は明るい作品だったので、びつくり。喜劇的でもあるけど。監督はジャーナリストとしてこの作品に向き合ったという。
官僚的でしかないこの神父のいうようにただ追い出せばよかった。
現実にあった事件を題材にしているというから怖い。ルーマニア怖い。悪魔祓いとか本気で信じてるのか。
実話では皆刑事犯に。当然だろう。
全10件を表示