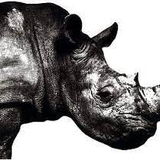ビルマの竪琴(1985)のレビュー・感想・評価
全12件を表示
反戦平和映画の代表格だがアジアへの戦争責任論の欠如により薄れる存在感
1 原作のテーマ
童話『ビルマの竪琴』のテーマにはいくつかの要素が混在する。
第一に、一高教師だった竹山が教え子を多数戦場に学徒出陣させざるを得なかった悔恨と戦死した彼らへの鎮魂。
第ニに、厭戦気分、平和主義の拡大とともに戦争指導者と日本軍への批判が高まる中、それに異議を唱え、戦死した兵士全体への鎮魂を捧げること。
第三に、敵国兵士との和解を通じて、ヒューマニズムに基づく戦後の平和を祈念すること。
こうした要素から「戦後社会の厭戦・嫌戦・反戦気分の中、平和憲法の精神と結び合い、非武装絶対平和、反戦文学の正典としての地位を占めるようになる」(馬場公彦『「ビルマの竪琴」をめぐる戦後史』)。
2 反戦平和映画の代表格
その映画化を見ると、1956年版は同時期の『ひめゆりの塔』『24の瞳』等の一連の反戦平和のメッセージを基調とした戦争映画の系譜の中に位置づけられるもの」で、こちらも反戦平和の正典としての地位を築く。
そして1985年版になると、戦争の要素は薄められ、「児童たちにも安心して薦められる、全編ヒューマニスティックな人間愛に彩られた映画に仕上げられ」、大ヒットを記録した(同)。
3 原作、映画の欠陥
ところが小説も映画も、こうした成功の陰で大きな欠陥のあることが指摘されてもきたのである。
金の星社版の伊藤始の解説は、次の3つの問題を指摘する。
①ビルマ僧の戒律は厳しく、楽器の演奏も禁じられていること。当然、僧侶姿の水島が竪琴をひくことは考えられず、1956年版の映画はビルマで上映禁止となった。
②原作だけだが、こちらでは三角山で負傷した水島を助けた少数民族が、実は人喰い人種だったというエピソード。ありえない話だという。
③ビルマ人は仏教の教えにより、欲がなく、働かないように描かれているが、豊かなコメの産地なので、働く必要がないというのが実情だった。
また、根本敬『物語 ビルマの歴史』は「『ビルマの竪琴』という幻想」と題し、①作品は上座仏教(小乗仏教)をまったく理解しておらず、竪琴をひく水島は破戒僧であること、②この宗教は遺骨に執着しないから、水島の遺骨収集、埋葬は理解できないこと、③登場するビルマ人が飾りに過ぎず、協力的だったり素朴な人間しか出て来ないが、日本人に苦しめられ、憎んでいる人間もいること――を挙げている。
4 アジアへの戦争責任論の欠如により薄れる存在感
そして決定打とも言うべきは、戦争文学、戦争映画なのに、戦場となったアジアへの戦争責任がほとんど取り上げられていないことである。
前述『戦後史』によれば、「『竪琴』に潜む戦争責任の自覚は、自国戦没者への敗戦責任を主眼に据え、敵兵への加害責任を副次的な関心とし、それらを防御・抵抗できなかった自らの不作為責任への『慙愧』の思いを中核とするものであった。(中略)だがそこには、戦場とさせられ、望みもしない犠牲を強いられた現地アジアの人びとに対する責任意識が欠落していた。そして、東京裁判においても、アジアの諸民族に対する戦争および植民地支配責任は不問に付されていた」という。
当然だろう。第二次大戦終結時、アジアはヨーロッパの植民地に舞い戻ってしまったのだから。原作小説もそれを受けた1956年版映画も、その背景にある東京裁判も、結局は先進国クラブ内の戦争責任しか問題にしていなかったのである。
この戦争責任論の欠陥は時代性に帰責して済む話ではなかろう。1985年版映画では人間愛が強調されたが、それはリアリズムを欠いた一方的自己愛の裏返しに堕してしまっているからである。つまり、戦争責任論はますます希薄化し、「自己憐憫的な慰撫のもたらす自責感の麻酔作用によって、侵略者の顔は悲劇の犠牲者の顔への塗り替わっていく」(『戦後史』)。
石坂演ずる隊長は、遺骨箱に向かって「お前の経験はわからない。しかし、お前の気持ちは分かったような気がする。つらい決心をしたもんだな。どんなにつらかったろう」と、水島に話しかける。隠れてそれを聞いていた水島は涙にくれる。そして観客も、戦友とともに帰国もできないまま、宗教的犠牲を覚悟する水島と、その後の遺骨収集の厳しい生活に同情の涙を流すのである。
ちょっと待った。これは何かが間違っているのではないか? つらかったのは日本兵に食料等を略奪され、泰緬鉄道建設等に駆り出された挙句、膨大な犠牲者をだしたビルマ人や英国軍兵士、捕虜たちだったろう。
こうした現実を無視して、単に「反戦平和だ、ヒューマニズムだ」はないだろう。日英の敵軍同士が歌を唱和するだけで和解できるのは安直すぎるだろう――そうした空疎なお花畑的平和主義が敬遠されて、現在では本作は存在感を薄めているという。当然かと思う。
ええ話なんやろけど
................................................................................................
戦争中にある小隊では、水島の奏でる竪琴が癒しになっていた。
やがて日本が降伏し、小隊も降伏するが、別の隊が降伏しない。
それを説得しに行った水島はそのまま姿を消し、時が経つ。
小隊は捕収容所近くで水島に似た兵を見かける。
しかも僧のひく曲のアレンジは、水島のものだった。
それでも水島は一切口を開かないのだった。
やがて隊は日本へ帰還できることになる。
そして水島に向かって懐かしの歌を歌うと、水島は竪琴で応える。
それでも口は閉ざしたままだった。
ビルマを去る日に水島から手紙が届き、全てが分かる。
小隊の説得に失敗し、小隊は玉砕、それからも多くの戦死者を見た。
なので鎮魂のためにビルマに留まることにしたとのこと。
................................................................................................
名前はよく知ってたけど、どんな物語か知らんかった。
感動的な話だが、水島の気持ちがよう分からんかった。
今の時代の人にはちょっと理解でけんのとちゃうんかな。
水島には日本に家族がいなかったのだろうか?
戦闘シーンは余り多くないのでむごさはなかったけれど上官が違えば部下の運命が全く変わってしまうのには切なさだけが残った。
オウムが一役買っているがちょっと弱かったか?
ただ、兵士との分かれのシーンで水島の肩に乗っているオウムは画面の中にしっかり溶け込んでいた。
その当時はどうかわからないが今観ると豪華俳優陣でその当時の姿を見れるのは一つの楽しみでもある。
中井貴一はこの頃は親の七光りであったんやろか?
川谷拓三はこんなええ役どころで出てたんや
菅原文太はぴったりの役どころやなあ 等
それはそうと疑問点もたくさんあった
戦場まっただ中にいる軍隊があんなに歌がうまい?
ハモる?!理解できません あらためて上官次第やなあと思った
中井貴一はほんとうに竪琴を弾いていたのやろか?
「通信用」てとっさに出てきたのにうまいこと言うたなあ
ビルマではそんなに簡単に僧になれるのか?等々
なんとなく美談で終った感があり戦争の悲惨さは余り伝わってこなかった 捕虜の生活も悪くなさそうだったし
セルフリメイク
市川昆監督はセルフリメイクするのが好きなのだろう。自身1956年に『ビルマの竪琴第一部、第二部』を作っていて、しかもアカデミー賞外国語映画賞にノミネートされている。
ビルマの民家に匿われていたとき、イギリス軍がやってくる。いつものように唱歌のコーラスによって敵の目をごまかそうとしたが、夜になるとイギリス軍も歌いだす。音楽によって戦争が止められる!などと感動したのも束の間、実は3日前に停戦になっていたのだった・・・そして、降伏。彼らの部隊も投降し、ムドンで捕虜収容所に入ることになるが、水島だけは三角山で抵抗を続ける日本兵へ投降を勧める役を任ぜられる。しかし玉砕。なんとか一人生き残った水島は200キロ離れたムドンへ向かうが、日本兵の無残な死骸を見ながら嘆き悲しむのだ・・・
収容所の兵士たちは水島に会いたくてしかたがない。一方の水島は慰霊のために僧になってしまっているので会わせる顔がない。一度、日本兵が作った橋の上で遭遇するが、知らないフリをしていたのだ。
ずっと「埴生の宿」がテーマのように何度も合唱され、日本へ帰ることになった兵士たちとの対面でも水島本人だと確認するため歌われる・・・その後、竪琴の独奏で「仰げば尊し」を弾き、感動の波が押し寄せた。
巨大な涅槃大仏像など美しい仏教国、日本が降伏した後だということもあり、現地の人だって日本人に優しい人ばかり。その反面、無造作に山積みされた屍たち。彼らを弔う気持ち、見てしまったために帰れなくなってしまった水島の心の奥。結果はわかっているのに、もう充分だから帰ればいいのにと願わずにいられなくなる・・・
現地のおばあさん役の北林谷榮が大阪弁まじりなので楽しい。ずっと入ってたナレーションが兵士の中でも落ち着いていた渡辺篤。石坂浩二だけが、ちょっと弱い・・・
本当に伝えたいことは撮られていないところにある
人生とは選択である。選択そのものが人生と言える。
でも、時には人に相談することも必要。
水島の生き方に全く共感できないために、途中から半ばどうでもよくなくなった感は否めない。
だって、軍人は上官の命令に従うのなら、どうして頑なに自分の行動に固執するのか。
栄養が足りずに判断が鈍ったのかとも考えたが、そうなら途中で思い返してもいい。
ということでストーリーについてはモヤモヤは残る作品です。
それでも最後まで見たのは、別の見方をすれば、ミュージカル映画とも見えるかもしれんと思ったから。
男声合唱オペラ。
そういうヒントはくれた。
【以下、ネタバレではないけどネタバレよりもある意味閲覧注意】
一度しか見ていないので、という前置きの上で進めると、これは悪夢のシーンをカットしたある種ファンタジックに描いた物語である。原作が児童文学であるということから考えて童話なのだ。
つまり水島が説得に失敗して移転先の収容所に戻る前日までは現実のことだが、そのあとは重要なシーンを大幅にカットした物語になっている。本当は見るに耐えない奴隷となり強制労働を強いられた仲間を見てしまって、自分は捕虜から逃れるために僧侶に化けて過ごしていたのだ。
会田雄次の『アーロン収容所』はビルマで英軍捕虜となった時に受けた非人道的な奴隷労働生活の記録である。推して知るべしなのである。
なのであくまでも英軍にバレぬように日本語も話せぬビルマの僧侶となり、音楽だけで想いを伝えようとしたのだ。
そう考えるとこの映画の辻褄がぴたっとハマってくる。
慰霊という行為にみる人間性
無造作に放置された死体からは、人間だったという痕跡が、まるで感じられない。
一人一人に思考があり、感情があり、唯一無二の存在だったことさえも、そして各々に人生があったことさえも、尊厳のかけらもなく放置された肉片からは、全く感じられない。
そんな無情さと、自然における人間の小ささと、大きな世界の片隅で殺し合っている行為の虚しさが、胸に迫ります。
ビルマ人にそっくりの日本兵が、ビルマの僧侶のふりをして、巡礼の旅に出る。
彼が供養したところで、何かが救われるわけではないけれど、それでも供養せざるをえない気持ちになるのが人間なのでしょう。
例え彼の名前が後世に伝わらなくても、ビルマという地で誰かが戦死者を供養した、という痕跡が残ることで、後世誰かの救いにはなるかもしれない。
日本式の納骨にその思いが込められている気がしました。
罪を贖うかのようにさすらう水島は、どこへたどり着くのでしょうか。切なさが込み上げます。
前作がよかったので見たけどさらによかった
水島、一緒に日本に帰ろう
総合65点 ( ストーリー:75点|キャスト:70点|演出:65点|ビジュアル:70点|音楽:75点 )
戦場に散っていった多くの命を目の当たりにして、いてもたってもいられなくなる。普通の兵士が体験した悲惨な出来事が彼の運命を大きく変える。別れを告げる水島の奏でる「仰げば尊し」が悲しくビルマの空に消えていく。彼の手紙が彼の過酷な決意を伝える。
いい話だと思うが、古い映画ということもあり演出は古さを感じる。日本兵たちはのんびりと生活しているし、捕虜収容所でもイギリス軍と何の問題も無くうまくやっている。三角山の司令官と兵士との交渉は短すぎるしもっとしっかりと描かないと臨場感がない。いかにも決められた台詞を喋っていますという雰囲気しかない。水島が出会う死体は腐乱して虫が湧いてもっと汚いはず。匂いの漂わない無機質な人形のような死体はこざっぱりとしていて、そんな死体を簡単に片付けられてはあっさりとした印象しか残らない。戦争の緊迫感や悲惨さを描く演出が足りなくて、水島を決意させた心の傷が直接はっきりと伝わってこないのが惜しい。
全12件を表示