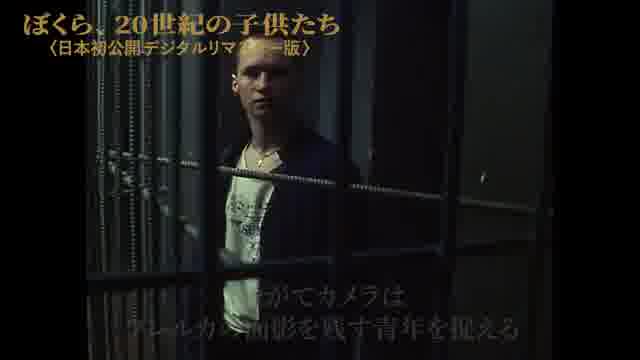ぼくら、20世紀の子供たちのレビュー・感想・評価
全2件を表示
20世紀に深く爪跡を残したカネフスキー3部作の最終章
冒頭 コッペパンを載せるトレイの上に赤ちゃんが3、4人寝ている。認識証みたいなのを付けて。まずはこの象徴的な映像。
路上でインタビューに答える子供たちの中には、屈託なく、澄んだ目の子も多い。あの日のワレルカのように。しかし語る内容はえげつない。聞いていてとても滅入ってくる。彼らが演奏するバラライカの曲が心に沁みる。
そして、ワレルカとガリーヤのまさかの再会。多少の作為はあるだろうけど、これはちょっと反則やな。対比がさすがにキツい。あの歌、胸が熱くなる。「ひとりで生きる」から2年しか経っていないのに。
本作1993年の製作なので、あのストリートチルドレンや刑務所の子供たち、「20世紀の子供たち」も今では40-50代の中年だ。彼らは新世紀をどう生きているのだろう。奇しくも隣国民の命を奪っている国家の中で。
ロシアのストリート•チルドレンとそのなれの果ての収監者たち(そのうちのひとりはなんと……) ヴィターリー•カネフスキー•トリロジーの締めはドキュメンタリー
『動くな、死ね、甦れ!』『ひとりで生きる』は第二次世界大戦終戦直後(おそらく1947〜50年あたり?)のロシア極東の町を舞台にした劇映画でした。上記2作とともにトリロジーを形成するこの作品(1993年公開)はカネフスキー監督にとって初となるドキュメンタリーです。ソ連崩壊後の混沌としたロシア社会で生きる十代、二十代の若者たち(まだまだ子供と言ってもいい人たちも含む)が監督自身によって次から次へとインタビューされてゆきます。その多くは大都市で犯罪を含む諸々の手段を使って、別の言葉で言えば、危ない橋を渡って、なんとか生き抜いています。
カネフスキー監督もかつてはそんなストリート•チルドレンのひとりだったようで、彼がインタビューで使っている言葉もきっとそういう少年たちに受けがよくて、ちゃんとコミュニケーションがとれる言語感覚でしゃべっているのかなと思いました。
監督は罪を犯した少年少女が収監されている刑務所でもインタビューを敢行します。インタビューを受けた少年少女はそれぞれがかなりの凶悪犯のようで、彼らのした殺人についてあっけらかんとした様子で語ります。そしてそこにトリロジーの第1•2作の主人公ワレルカの面影を持った少年が…… また、第1作のガリーヤ、第2作のワーリャの面影を持った少女が…… さすがにこれは「仕込み」ではないかと思ったのですが、ワレルカを演じたパーベル•ナザーロフと第1•2作のヒロインだったディナーラ•ドルカーロワが、監獄に収監されている囚人とそこに慰問にきた友人として再会を果たします。「仕込み」と書きましたが、ナザーロフは本当に収監されていたのかもしれません。彼も実際にストリート•チルドレンだったようで、カネフスキー監督自身がたくさんの子供たちと会ったすえ、「これはかつての私だ」と思って彼を自分の映画の主人公に抜擢したそうですが、彼は撮影現場でも盗みを働いて周囲を困らせていたという伝説があるそうです。
それはともかく、ナザーロフとドルカーロワの再会シーンはけっこう胸熱でした。ふたりとも1976年生まれの同い年なのでこのとき17歳ぐらいと思われますが、女性のほうが先に大人びるといった感じでドルカーロワのほうが年上に見えました。ふたりで第1作の思い出話をするのですが、ドルカーロワがいちばん好きなシーンはふたりで線路伝いに歩くシーンと言っていて、これは私の好きなシーンと一致して胸にじーんときました。
他に印象に残ったのは教会でのインタビューとそこで子供たちが聖歌を歌うシーンです。科学的社会主義を標榜し基本的に無神論だったソ連時代と違って、この時期のかの国ではこういうのも映画で表現できるようになっていたのですね。
いずれにせよ、カネフスキー監督はペレストロイカという言葉がさかんに使われたソ連の末期からソ連の崩壊までの1980年代末から90年代初頭の時期に彗星のように現れ、彗星のように消えてゆきます。今はサンクト•ペテルブルクで余生を送っているそうです。ワレルカを演じたパーベル•ナザーロフの現在はよくわかりませんが、ディナーラ•ドルカーロワは女優として成功し、監督業にも挑戦しているとのことです。
あと、ヴィターリー•カネフスキー•トリロジーとしてのパンフレットが販売されていたので入手しました。いろいろな情報があってなかなか面白かったのですが、そのうちのひとつ、第1作『動くな、死ね、甦れ!』という題名の由来について。これは日本の「だるまさんがころんだ」のような子供の遊びで鬼になった子が使うかけ声だそうです。すなわち、”Zamri!” (動くな!)と言われた瞬間、鬼以外の子供たちは今の姿勢のまま固まり、”Umri!” (死ね!)と言われたら、その固まった姿勢をずっと維持し、”Voskresni!” (甦れ!)と言われたら、また動いてもよいとの合図だそうです。カネフスキー監督はこのタイトルに不幸に打ちひしがれた人々の「再生」の意味を込めたのではないか、さらに言うとソ連末期で行き詰まった状態にあったロシアの再生の意味も込めたのではないかと考えてみたくなります。ゴルバチョフ大統領がペレストロイカを推進していた頃に映画界に登場し、短期間の活躍で去っていったヴィターリー•カネフスキーが現在のロシアにどんな思いを抱いているか、気になるところです。
全2件を表示