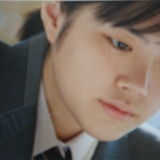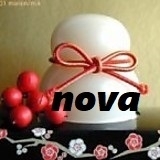日の名残りのレビュー・感想・評価
全58件中、1~20件目を表示
絶滅危惧種
昔昔、20世紀の終わり頃、この映画がきっかけで、カズオ・イシグロの名前を知った。どう見ても日本人の名前だけどカタカナ表記。なぜに、と思ってプロフィールを調べ、原作を読み、以来新刊が出るのを待ち望むようになり、ノーベル賞を受けたのは、いちファンとして喜んだ。彼の小説は、今作を始めに、「わたしを離さないで」、「遠い山なみの光」、と映画化されている。NHKで「浮世の画家」もドラマ化されていた。読んでる時は映像向きと思えないが、意外に映像と合ってるものだね。最新作の「クララとお日さま」は、すでにどこだかが映画化権を取ったとか、ニュースで読んだので、どんな映像になるかワクワクしている。
古き良き時代を体現するかのような、英国執事のスティーブンス。彼は歴史ある立派なお屋敷を差配することに、生き甲斐とプライドを持っている。しかし、かつて仕えた本物の貴族だった主と違い、今は金持ちアメリカ人の下、使用人も少ないので、四苦八苦している。思いきって、かつての同僚のメイド頭のミス・ケントンをスカウトすることを、主に上奏する。彼女は結婚を機に退職していたが、20年ぶりに手紙が来て、再び働く意欲があるとのこと。スティーブンスは西部に住む彼女を訪ねることとする。
過去と現在が交錯し、少しづつスティーブンスのことが明らかになってくる。敬愛する主のこと、父との関係、ミス・ケントンへの気持ち。ミス・ケントンにほのかな期待をして、車を走らせるスティーブンスは、道中で出会う人に職歴について嘘をつく。本当は、彼の職歴の中で一番誇らしい時代は、第二次世界大戦前の頃であり、戦後は逆転してしまうのである。
ミス・ ケントンは結局、メイド頭に復職することはなかった。スティーブンスと本当は両思いだったのに、彼らはすれ違うばかりであった。あの時こうしていたら、と後悔するのはスティーブンスに限らず、誰の人生にもある。とても大事なものだったのに、二度と戻ってこない…そんなほろ苦い気持ちを抱えて、スティーブンスは仕事を続けるのである。そう、彼は執事以外に生きる術を知らない。執事なんて、今や絶滅危惧種のようなもので、わかっていてもその道を進むしかないのである。
アンソニー・ホプキンスの姿勢の良さ、能面のような無表情が、できる執事を醸し出している。感情を抑える演技は難しいだろうが、さすがレクター博士(笑)。ほんのちょっと目線や、眉を動かすだけで、心の動きが伝わってくるのだ。職人である。
NHK BSの放送を録画で。
何を為し、何を為さなかったのか。 何を為さねばならなかったのか。何ができたのか。
厳かで華やかでありながら、静かな、静かな物語。なのに、その物語の土台には激流がふつふつと流れ…。
DVDの特典映像では、監督が、制作者が、原作者が、役者たちが、言葉を変えて、言う。
「あの時代、戦争・あのひどい出来事を止めるために、何ができたのか。
今の世界の様々な地域で起こっている紛争を止めるには何ができるのか」
第一次大戦後、第二次大戦に向かう時代と、第二次大戦後を交互に描く。
主に主人公・スティーブンスにフォーカスされて物語は進んでいくが、様々な人が出てくる。
執事として、歴史的大舞台の采配を任せられるほどの力量をもつスティーブンス。
他家からの評価も高い。職務に忠実で、職務を遂行するための努力も欠かさない。そんな自分の生き様に誇りも持っている。
職務に忠実すぎて、職務を遂行する以外のことには、見ざる聞かざる言わざるを通す。ユダヤの少女を解雇するときは、一瞬だけ反論するが、結局主の言いつけ通り。世界情勢に気を払っていれば、解雇した後、かくまうくらいはできたであろうに。女中頭のミス・ケントンがなぜ激高するかにも耳を貸さない。
高潔な主に心酔し、職務以外については自分の頭では考えない(興味を持たないように律する)。原作者は「自分の心にさえ向き合わない」と言う。新聞記者となったカーディナルからの特ダネねらいもしっかりかわすところは執事の鏡。館の中ではそれで十分ではあったが、一歩街に出れば…。でも、主の仲間貴族からは、選挙を通して政治を託すものとしては見下げられ、街の住人からも…。それでも、”ダンケルク”の状況を知るなど、戦中に起こったこと、戦後に起こったことに心を揺れ動かし、心酔していた主が何をしてしまったのか理解し、己の在りかたに、己の価値観に疑問も生じてくるが…。そして、心のよりどころとしていたミス・ケントンの選択…。
妻を愛せなかったが執事としての手本である父は、スティーブンスをどう育てたのであろうか。”男女の愛”に疎いのは養育環境によるものであろうか。
執事すべてが同じようにするとは限らない。
駆け落ちをした前執事や結婚する者もいる。
ベンのように、使える主を選ぶ者もいる。
女中頭のミスケントンは、職務を忠実にこなし、全体を見渡して気を配りながらも、自分の意見を持ち、時にスティーブンスとやりあう。
それでも、人生はままならぬ。
スティーブンスが使えていたダーリントン卿。
フェアプレイ精神の持ち主で、相手も当然そうであろうと思い、行動する。戦争を回避するための方策が…。策を講じるために、ナチスの機嫌を損ねないように、ユダヤの少女を解雇するが、それが何を意味するのかはわかっていない。後で撤回しても時すでに遅し。交渉する相手の本性を見抜けない。館を訪れたナチス将校は卿の財産を値踏みしているのに…。
ダーリントン卿と共に、ナチスと手を結ぼうとする貴族。
スティーブンスに経済や政治の質問をし、自分たちが下々を導いていかなければと確信する。
ダーリントン卿の親友の息子・カーディナルは、新聞記者になっただけあって、状況は判っており、叔父とも慕うダーリントン卿を諫められない。
アメリカ人・ルイスは、そんな卿たちを「アマチュア」と称し、「政治はプロに任せろ」と言うが、会議のばでは賛同者はなく…。
そして、街の人々。
それぞれ、しっかり意見を持ち、パブで意見を交わし、戦争にも行き、痛手を被る。
もし、政治をアマチュアに任せておかず、しっかり、情勢を見極めて、意見を出し、動いていたら、戦争は回避できたのだろうか?
でも、ヒトラーの台頭を許したのも、ヒトラーの、”強いドイツ”、他民族を排斥して、ゲルマン民族の優勢を打ち出した演説に酔った人々。
肝要なフェアプレイ精神だけでもダメ。
職務に忠実で有能でも、自分の生きる方向を人にゆだねるだけでもダメ。
世の中を見通し、それを判別する知識を身に着け、行動力があっても、自分の大切なことに対して、素直になれなければダメ。
どう生きていくのか。改めて考えてしまった。
特に、今の日本の選挙で演説される政策が、ヒトラーに似てきている。
誰が”アマチュア政治家”か、”プロ政治家”か。
そして、自分にとって大切なことは何か。成し遂げたいことは何なのか。
★ ★ ★ ★
どなたもおっしゃっているが、役者がすごい。
ホプキンス氏。
年を重ねた冒頭では、猫背で、顎を突き出して顎の存在感を強調するシーンもある。父役のボーン氏と重なる。
少し口が半開き。職務は完璧だが、世事には関心がない、魯鈍さを表現したのか。原作者も「スティーブンは大衆的なことにしか興味がない」と言う。それを表現したのか。
そして台詞の無いシーン、感情的な台詞がないシーンでも、心の揺らぎが伝わってくる。
密談、特ダネ狙いのカーディナルの来訪と、ミス・ケントンの重大発表。重ならなければ、もう少し、うまく立ち回れたのではないかと言う動揺に心が痛い。
街でのダーリントン卿への反応、ダンケルクで犠牲となった息子の部屋に接して揺らぐ様。自分の意見を持つ者と、持たざる者。自分の立ち位置。価値観の揺らぎ。
トンプソンさん。
ホプキンス氏との年齢差22歳。それでも、二人が似合いのカップルに見えてきて、結ばれることを願ってしまう。と言って、トンプソンさんが老けて見えるのではない。行き遅れとあの時代なら言われてしまう年齢の落ち着きや焦り、もどかしさ。
戦前と戦後の佇まい。
フォックス氏。
人の良い貴族が、世の中に巻き込まれていく様。己の信念が悪用されていくその様に抗うことができない無念さ。自身への回顧。
リーブ氏。
あの会議へ参加する唯一のアメリカ人。監督は出自がルイスに似ていたから抜擢したと言っていたが、あの役に”スーパーマン”を持ってくるとは(笑)。
売りに出されたダーリントン卿の館の新しい主。爽やかさを振りまき、館に新しい風を運んでくる。スティーブンスの暗さとの対比。それでも、リーブ氏に感化されて、スティーブン氏の未来まで明るい風が吹きそうな余韻で映画が終わる。
こちらも戦前と戦後の佇まいの違い。老眼をかけたままにスティーブン氏を見る様(笑)。「トースターを買えばよい」使用人への思いやり溢れる言葉なれど、合理主義が果たしてダーリントン卿屋敷の使用人に通じるのか(笑)。
グラント氏。
戦前の貴族と戦後をつなぐ予感を見せてくれる役。真面目な青年なのに、どこか(笑)をとってしまうのは天性か。
★ ★ ★ ★
意匠。
館は本物を使っているだけあって、重厚で華やか。従業員の通路はああなっているのかとか、興味深い。
それを浮ついた絵ではなく、たっぷりと見せてくれる映像。
庭や借景している自然の美。
映画のテンポもゆったりと進む。貴族の時間を味わっている気になる。
今の映画に比べると、抑揚もなく進む。
日の名残りを愛でるのに相応しい落ち着いた映画。
皆に観て、考えて欲しい映画なれど、推薦するのは人を選ぶ。
日の名残
昔鑑賞した時はじれったいだけだったが、、、
偉大な執事の条件は何より品格
いかにも英国映画
昔、原作(日本語訳)を読んだ時、執事(ホプキンス)の一人称で語られていたと記憶するけれど、この映画では全てが客観視された物語になっている。
実は彼には、かつて仕えたご主人様に関してどうしても隠したいことがあり、原作が一人称で語られるときにはそれが巧妙に隠され、わざとわかりづらくされていた。ところが三人称の映画ではあからさまとなり、原作の味わいがない・・・こともなく、この主演俳優の、切なさが抑制された重厚な演技により、むしろ魅力が増している。共演のエマ・トンプソンも見事だ。
ダウントン・アビーのような御屋敷での、静かな日常と喧騒の繰り返しがいかにも英国映画の雰囲気を醸し出す。独特の田園風景も美しい。これらは他の国の映画には望むべくもないものだ。
かつてスーパーマンを演じたクリストファー・リーブが新興の米国人財閥として出てくるが、彼の明るさと功利主義的な態度が、英国貴族の「ご主人様」と明らかな対照を見せて興味深い。
面白くないのが駄作ではない。
正直言って結構面白くはなった。主人公がやらなきゃいけない解決しなきゃいけないものがない。ただ、なんとなくこの件で不幸になっていくのかなとか。ヤバいことになっていくのかな?とかいう。仄めかしのようなものがあるだけだ。そして、その問題も、その後のヤバくなってくるところなどは描かれてない。こういうスリルもありました・・的な。さらに言うならば。主人公が誰なのかわからない。もっと言ってしまうと、99%面白くない。バスが行ってしまうところだって。なんだかなぁ・・って感じで見ていた。でも映画が終わると、この映画はいい映画だったという感慨がわいてくる。
つまり・・ジワジワ・・っとくる映画だった。
それを引き起こしたのはなんといってもラストのカメラワークだ。小城のような建物。それが大きいなぁと言った感覚からカメラが引くにつれて・・こんな小さな世界で・・に変わっていく。建物がどんなに大きくても街の中、自然の中では小さなものだ。そしてそれはとても孤立していた。ここに彼の半生があり。ここから出れなかった。執事という名の生き物のようになりきり、マシンのように生きた。ベストな仕事をするために自分の中に芽生えていたそれも・・自らシッャトアウト。人生の終わりごろを迎えてようやく気付いだが・・引いていくカメラワークと、それにのせられた音楽によって実に情緒豊かに長時間に渡って描いてきたものが伝わってきた。私は大抵の映画はエンディングロールが始まったらすぐ席をたつが。この映画はしばらく座り続けましたね。
切なすぎる
自分の感情を押し殺してきた1人のベテラン執事の切なく悲しい人生を振り返る映画。
ナチ擁護派の英国貴族だった主人を助けることができなかったことと、愛する女性を手放してしまったという2つの悔恨が痛いほど伝わってくる。
アンソニー・ホプキンスの名演技が観ている者の感情を揺さぶってくる。
決して感情を表には出さないが、何を想っているかは手に取るようにわかる演技は圧巻。個人的には羊たちの沈黙を超えるベストアクトだと思う。
一言「眼福や〜」
イギリス映画、ホプキンスが執事役なんて。もうかっこいいのなんの。
執事として主人に支える身。
どんな会議で給仕しても、聞こえない風にさりげなく佇む。
決して自分の意見は言わない、聞かれたら答える。
主人がどんな考え(ドイツとイギリスの関係等)でも、ずっとそばにいる。
徹底しているところが、素晴らしい。
それだけではなく、同僚のメイド長(エマ・トンプソン)との。
微妙な関係が入っているのも、ちょっと人情っぽいテイストも。
あとすっかり忘れていたのが、ヒュー・グラント様。
出演リストにあった、この映画。
30年以上前なので、若いのなんの。一瞬誰かわからなかった。
ホプキンスとヒュー様が一つの画面にいるって、もう眼福・・・。
ラストの鳩が飛び立つシーン。これはもしかして、執事の気持ち?。
なんてね。
⭐️今日のマーカーワード⭐️
「何なりとお申し付けを」
消えゆく光からギラギラした光へ
執事であることに自負と責任を持ち、プロ意識の高さは同業の父親から継ぎつつ自分自身を「理想的執事」にぴったり合わせることが誇りで喜びであるMr.Stevens。それは彼の話し方、語彙の選択、学習したジョーク、声の大きさ、必要最低限の体の動き。新聞一枚一枚にアイロンをかけてからLordに手渡すシーンと焦げたトーストを自分のポケットに押し込むシーン(びっくりして思わず笑えた)。個人・私人としての意見は表明しない、無駄口は一切叩かない、表情も豊かに見えない。でもずっと見ているとホプキンスの目、顔、表情のちょっとした動きに気がつく。そのために130分を超える映画の長さが少なくとも自分には必要だったとわかった。
プライベートな空間に花は邪魔だと言っていたStevensだが、いつしか彼の部屋はMiss Kenton(エマ・トンプソン、生命力に溢れている)が庭で摘んでくる花束で満たされる。
貴族は政治や世界において所詮アマチュア。うまくあしらわれ使われるだけ。そういった貴族に仕える執事はプロフェッショナル。なんだか皮肉で滑稽だ。貴族も執事もある時代からどこに向かっているのかわかるわからないに関係なく途方に暮れる存在の一つだと思った。世界情勢の中では一日の夕暮れの一瞬にやっと存在できる立場、もはや当時は。または本当はもうずっと前から。キラキラと輝く朝も昼間もない。でもその輝いていた時を忘れないこともできる。忘れないで、その思い出と共に自分も消えていく。
映像、光と影、庭園の緑、屋敷の中の静けさと豪華なテーブル、うす暗さ、俳優の立ち位置、すべてが丁寧で繊細で美しく、一コマ一コマが絵画だった。
カズオイシグロ小説の映画
原作を先に読んでから鑑賞。
原作を読んで暫く経ってから鑑賞したので小説を思いおこしながら。
主人と執事で話は絡みつつそれぞれでストーリーが静かに展開していく。
有能は執事であり続けた彼だけれども「個人」としては幸せであったのだろうか。
私を離さないでもとてもよかったがこちらもよかった。
仕事一筋に生きる事は決して美徳では無いかも〜
ノーベル賞作家カズオ・イシグロの
おそらく1番有名な原作の映画化。
もう随分以前の作品で、名前は良く知ってましたが、
午前十時の映画祭で初めてじっくり観ました。
初老の執事に旧知の女性から届いた手紙がきっかけで
その女性と一緒に働いていた日々の回想へと入って行く、
と言う感じで、ある程度の年齢の人の方が
心に響きそうな内容です。
自分の使える主人の思想や振る舞いに、
人としては納得出来ないモノを感じながらも、
執事の仕事に誇りを持つ主人公は
自分の葛藤を隠して黙々と仕事に殉じて行く。
あまりにその思いに忠実であるため、
自分の恋心さえ、悟られまいと押し隠す。
舞台はイギリスの貴族社会ではあるけど、
主人公の振る舞いは、何となく、
企業の不正を知りつつも、仕事への誇りのあまり
企業の闇に飲み込まれてゆく現在のサラリーマンにも
通じるような理不尽さが結構切ない。
で、月に8回程映画館に通う中途半端な映画好きとしては
主人公を演じるアンソニー・ホプキンスの
ストイックな演技が、流石に見ものです。
無表情の表情。
そんな合間に僅かに見せる動揺シーンが印象的。
密かに心を寄せている女性エマ・トンプソンが、
ホプキンスの読んでいた小説を
その手から奪い取ろうとした時、
絶対に見られたくなかったホプキンスの表情が、
見ようによっては恐ろしげで、
もしやドクター・レクターに豹変しやしないか(笑)
なんだ別の意味でドキドキしてしまった。
冒頭の見もの、
華やかなりし大英帝国貴族の贅沢な遊び「狐狩り」の
勇壮なシーンは、今の時代ではもしかしたら
もう撮影出来ないかも??
それから、
第二次世界大戦で一人勝ちしたアメリカの
富豪の役を故クリストファー・リーブが演じてます。
あのスーパーマンのクリストファー・リーブ!
イギリスとは違う新興勢力の勝ち誇った王者感が
よく出てました(笑)
退職後を人生で一番いい時間にしたい
原題は「the Remains of the Day(日が暮れる前のひととき、1日で最も素晴らしい時間)」です。
邦題は「日の名残り」です。
原題の方が映画の内容をよく表しています。
邦題は、意味不明です。
原作の「日の名残り」も読みましたが、映画の方が良いと感じました。
「日の名残り」は、英国人向けに書かれている小説を映画化しているので、日本人には理解しにくいです。
細かい点については考えずに、そういうものだと解釈するほうが良いです。
伏線があり、伏線が回収されるので、ストーリーは良くできています。
時間が前後するので、ストーリーを理解するには、苦労します。
以下の名言もり、心に響きます。
・覆水、盆に返らず
・人は皆、人生に悔いがあります
・夕暮れが一日で一番いい時間
時代背景を気にしすぎると、時代を超える普遍性が感じにくくなります。
時代を超える普遍性に、注目した方が面白く、得られる物があります。
時代を超える普遍性は、「人生は一度きり、皆、後悔しますが、人生を変えることはできず、人生の最後が人生で一番いい時間」ということです。
このように考えることが出来れば、老若男女のすべての人にお勧めできる映画です。
友人、カップル、夫婦、一人で鑑賞しても良い映画です。
政治家は、歴史を知り、情報に詳しく、人脈があっても「アマチュア」です。
政治家は、歴史を知り、情報に詳しく、人脈があり、将来を見通せて「プロ」と呼ばれます。
将来を見通せることが出来ない政治家は、国民に選挙で選ばれることで、将来の責任を国民に押してける結果になります。
日本の政治は、三権分立も、民主主義も機能せず、変化に対応できず、世襲議員は貴族のようで、永田町の中だけで政治を行っている「アマチュア」です。
日本人は、民主主義のために戦ったことありません。
主人公は、父親と母親の間に問題があり、結婚に前向きになれず、執事として職場恋愛による人材不足に対応してきたので、執事として恋愛はできませんが、恋愛小説は好きです。
若い人は職場恋愛をして結婚しているので、主人公もヒロインと恋愛して、結婚すれば良いと感じさせるストーリが良いです。
主人公は、生涯独身でしょうが、2020年の日本の生涯未婚率は男28.3%で、女17.8%です。
日本に主人公と同じような人は多くいます。
独身で有名人は以下の通りです。
安住紳一郎さん、長瀬智也さん、伊勢谷友介さん、平井堅さん、中村俊介さん、金城武さん、東幹久さん
森口博子さん、井森美幸さん、天海祐希さん、片平なぎささん、島崎和歌子さん、松下由樹さん、石田ゆり子さん
現状維持で変わろうともしない主人公の人生と現状を変えていくヒロインの人生を比較してみるのも楽しいです。
主人公は、やらなかったことへの後悔があります。
ヒロインは、やってしまったことへの後悔があります。
「人は皆、人生に悔いがあります」ということです。
自分で決める、他人とは比べない、失敗をおそれずに、実行することが重要に思えてきます。
アマゾンを起業したジェフ・ベゾスは、この原作を読んで、人生に悔いを残さないために、アマゾンを起業したそうです。
この原作を読んで、この映画を鑑賞して、人生に悔いを残さないために、起業する日本人はいるのでしょうか?
主人公の父親に注目すると、役職定年、高年齢者雇用安定法が改正され70歳まで働かなければならない日本社会の現実の厳しさを再認識させられます。
退職するという引き際についても考えさせられます。
ヒロインの夫に注目すると、辞職し、無職になり、ヒロインにプロポーズするのは無謀とも考えられますが違います。
ヒロインの夫は、故郷に帰り、ヒロインと二度と会うことはないので、プロポーズして、受け入れられなければ、ヒロインに対する思いを引きずることなく、故郷で心機一転、再出発ができるという、プロポーズするには絶好のチャンスだということです。
ヒロインは、結婚したい主人公ではなく、結婚してほしいという夫と結婚することを、結婚したい主人公への嫌がらせで結婚することを決めたのだから、泣きたくなる気持ちもわかるような気がします。
多くの人は、結婚したい相手と結婚するのではなく、結婚できる相手と結婚していいる現状について考えさせられます。
結婚することでしか、子供も孫も得ることはできません。
日本では、仕事をしないで人生を過ごせる人は僅かで、多くの人は仕事をしなければなりません。
仕事で成功するには、優秀であったとしても自分の考えを言わず、無能な組織や無能な上司の考えに従わなければなりません。
無能な組織や無能な上司の考えに従って、個人的には成功しても、変化には対応できず、社会的には失敗し、日本は失われた25年を過ごしています。
無能な組織や無能な上司の考えに従っていれば、いずれは「働かないおじさん、おばさん」になります。
無能な組織や無能な上司の考えに逆らえば、個人的に失敗し、社会的にも失敗します。
女性はもちろん、男性でも、仕事か、結婚かを選択しなければなりません。
どちらを選択しても、後悔しますが、後悔を受け入れるしかありません。
綺麗な夕日を、桟橋で見たくなりました。
【”夕暮れが、一日で一番良い時間・・。”第一次世界大戦後、親ナチ思想の主の元、只管に執事の品格を保った男をアンソニー・ホプキンスが抑制した演技で魅せる作品。】
■第一次世界大戦後、親ナチ思想に傾倒する主であり、英国貴族でもあるダーリントン卿が暮らす、ダーリントン・ホールを仕切るスティーブンス(アンソニー・ホプキンス)。
夜な夜な、英国貴族たちが集まり、世界情勢について語り合う中、彼はその言葉を聞きつつ、自らの意見を言う事はない。
又、自分の父が執事として働き始めるも、歳の為か転んでしまう姿を見たスティーブンスは、父を給仕から外し、掃除係を命じる。
そんな中、メイドのミス・ケントン(エマ・トンプソン)だけが、彼に意見を言う。
それは、彼の執事の仕事に身を捧げて来た人生に、ささやかな波紋を齎す。-
◆感想<Caution! 内容に触れています。>
・前年に公開された「ハワーズ・エンド」も同様なのだが、作品を覆う気品高き雰囲気が、とても良い。それは、細部に亘る時代考証を吟味し尽くした、衣装、意匠を始めとした美術陣の拘りからであろう。
・今作は、第一次世界大戦後に英国貴族たちが夜な夜な、ダーリントン・ホールに集い、今後の世界情勢を語る時代をメインに、その20年後を並行して描いている。
ー どちらのシーンも、アンソニー・ホプキンス演じるスティーブンスと、エマ・トンプソン演じるミス・ケントン(20年後はミセス・ベン)の関係性がメインで描かれる。-
・アンソニー・ホプキンスの恋もせず、主の言いつけには忠実に従う執事スティーブンスの姿を、徹底的に抑制した演技で魅せる役者としての力量が、凄い。
そして、そんな中、彼はミス・ケントンだけには、人間らしさを仄かに見せる。
例えば、親ナチ思想に傾倒する主から、ユダヤ人の娘二人の解雇を告げられるも、それに従った事に、ミス・ケントンから抗議される彼の表情。
ー どう見ても、スティーブンスはミス・ケントンに恋をしている。彼が、密かに恋愛小説を胸に抱くシーン。それでも、彼はミス・ケントンに告白をせずに、涙する彼女に対し、静に明日の仕事の指示を出す。-
<ダーリントン卿たちの会話を聞き、”アマチュアだ!”と言いきったアメリカ人のルイス議員が、第二次世界大戦後、新たなダーリントン・ホールの主になり、許しを得て、一人旅行に出かけたスティーブンスは、多分初めて外界に出て町の人達と交流し、優しさに触れ、そして、20年振りに今や、ミセス・ベンになったミス・ケントンと会う。
そして、彼女から色々とあったけれど、
”夕暮れが、一日で一番良い時間・・。”
と言われ、清々しい顔で”もう会うことはないだろうけれど・・。”と言って別れる。
今作は、執事の品格を保ちつつ、人生を過ごした一人の男をアンソニー・ホプキンスが、抑制した演技で魅せた作品であると思う。勿論、エマ・トンプソンも素晴らしい。>
彼女の気持ちを考えると切なすぎる
執事(主人公)の彼女に対する態度がもどかしい。でもいい映画です。彼女は何度か「好き」のサインを出しているのに、執事のほうは仕事にあまりにも忠実すぎて、本当に彼女のことが好きなのかも観ている我々もわからなくなってしまう。でも、好きだったんだろう。彼女から結婚退職の話をされた時、一応平静を保ったように対応してはいたが、ワインボトルを落としてしまったのはその表れだったのではないか。結局20年経過しても、彼の態度は変わらなかった。最後、バスに乗って別れた彼女は泣いていた。2度目の別れ、多分今度は2度と会うことはないと思って。
全58件中、1~20件目を表示