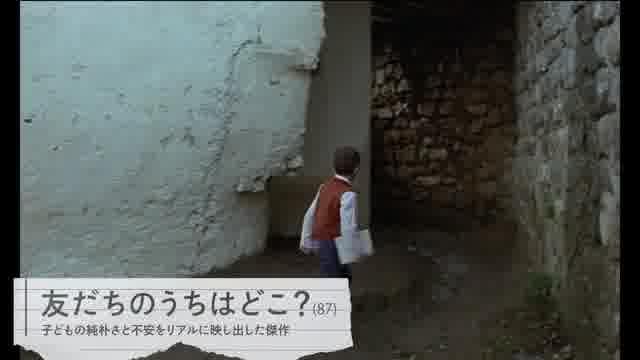友だちのうちはどこ?のレビュー・感想・評価
全52件中、1~20件目を表示
自分の中の「映画」の概念が覆される
1987年製作のイラン映画で、日本で初公開されたのは1993年。当時、全盛の都内ミニシアターで初めて見た時の衝撃が甦る。それまでハリウッドや香港などの娯楽作やアクション作品を数多く見てきて映画好きを自負していたが、「友だちのうちはどこ?」には、自分の中の「映画」というものの概念が覆された。
フィクションの物語映画でありながら、その作品世界は真実のようで、それまでの映画で味わったことのない映画表現の領域に入り込んだような感覚に陥り、特にラストシーンの感動でしばらく立ち上がれなかったのを覚えている。アッバス・キアロスタミ監督は、職業俳優を使わず、撮影地の村の住人や子どもたち、実際の家や学校を使用して撮影し、フィクションとドキュメンタリーの間の絶妙なバランスを保つスタイルを確立した作家だが、「友だちのうちはどこ?」はそんなスタイルを象徴する傑作である。
この映画は、あなたのその後の人生観や映画の見方を変えてしまうかもしれないほど、映画的な力を持っている。そして、世界には異なる文化や習慣を持った民族がいて、映画表現も国によって異なるという、未知の領域を教示してくれるに違いない。しかし、この映画で描かれているのは普遍的なもの。国や人種、文化が異なっても共感できるテーマであることが、今なお世界中で愛されている所以なのだろう。
基準点のような映画だろうか
壊れたドアと小さな花
1987年のイラン映画ですが、舞台となる田舎の風景を見ていると、まるで明治や昭和初期の日本のような素朴さを感じます。舗装された道も車もほとんどなく、ロバで移動し、土壁の家が立ち並ぶ。文明というより“時間そのものがゆっくり流れている”世界です。私はアハマッド君とほぼ同世代ということもあり、同じ時代を生きながらも、まるで異なる文明に属していたような衝撃を受けました。
主人公の少年アハマッド君は、友だちの宿題ノートを誤って持ち帰ってしまい、退学の危機にある友人を助けようと、隣町ポシュテまでノートを届けに走ります。しかし、彼が出会う大人たちは誰も話を聞いてくれず、「明日でいい」「子どもは大人の言うことを聞いていればいい」と言うばかり。アハマッド君の必死の説明は、彼らの価値観の中では“無意味な言葉”に過ぎません。
大人たちは皆、「しつけ」や「秩序」を語ります。けれどもその“しつけ”とは、実際には上からの命令に従わせるだけの服従訓練です。アハマッド君の祖父は「4日に1度は殴る」と言い、間違いを犯していなくても殴ると豪語します。本来は正しさを教えるための手段が、殴ることそのものを目的化してしまっている。つまり、倫理教育が暴力の儀礼に転化しているのです。こうした構造の中では、正義とは「力のある者に従うこと」になり、真の倫理感は育ちません。
この構造を社会的に拡張した存在が、作中に登場する「偽ネマツァデ」という男です。彼はドア職人でありながら、代金をごまかそうとし、子どもからノートを奪い、労働者から搾取します。つまり、形式的には“働き”、実質的には“奪う”人間です。祖父のしつけと同じく、「正しさの形」を保ちながら「不正」を行う。ここに、イラン社会に蔓延する強権的倫理と日常的な腐敗の縮図が見えます。
この映画で繰り返し登場する“壊れたドア”は、そのような社会の象徴だと思います。ドアとは本来「内と外」「自分と他者」をつなぐものですが、この村ではほとんどのドアが壊れていて、誰も直そうとしない。むしろ「鉄のドアなら壊れない」と語られ、壊れない=開かないドアが理想化されています。
つまり、壊れたドアは「閉ざされた社会」を、鉄のドアは「完全に閉じた心」を象徴しているのではないでしょうか。誰も他者とつながろうとせず、自分の家(自分の価値観)に閉じこもる。アハマッド君だけが、唯一ドアを開けようとする存在として描かれています。
さらに印象的なのは、祖父が「外国人は一度言われれば直すが、イラン人は二度言わなければ直さない」と語る場面です。そこには「命令に従う人間をつくることが文明だ」という倒錯した信念があります。しかしそれを突き詰めると、個人の判断力や倫理観は失われ、強者が弱者を従わせることが“秩序”になる社会が生まれます。これはまさに革命後のイランで進行していた、宗教的権威主義と社会の硬直化の影を反映しているように見えます。
キアロスタミはそうした批判を、子どもの視点という“寓話的形式”を使って巧みに隠しながら描いています。大人たちは無関心で、世界は閉じている。けれども少年は走り続ける。夜になっても、暗闇の中を、ノートを届けようとして走る。その姿は、命令ではなく良心に従う唯一の存在です。
ラストでノートに挟まれた小さな花は、おじいさんから受け取った“ささやかな優しさ”であり、閉ざされた社会の中に残された最後の希望を象徴しています。大人の世界が壊れたドアの向こう側にあるなら、アハマッド君はそのドアを自ら開けようとする存在なのです。
この映画は、1980年代のイランという厳しい検閲の時代にあって、宗教や政治を一切口にせず、「倫理とは何か」という根源的な問いを突きつけた作品です。
暴力的なしつけが倫理を歪め、従順さが腐敗を生む社会。
その中で、アハマッド君の小さな“良心”だけが、唯一、壊れたドアの外へ出ようとしている。
その姿が、心に残りました。
鑑賞方法: シネフィルWOWOWの録画
評価: 94点
あの坂道が余りに静かで美しく映る。
いつか必ず観ると決めていたアッバス・キアロスタミ監督の作品、そう思いつつも時が経ってしまい、今回初めて観ました。
主人公の男の子、アハマッドの瞳が忘れられない。
学校の先生に酷く叱られた隣の席の男の子は、次に忘れたら大変な事になるのに、宿題のノートを自分が持って来てしまった、だからその子の家を探して返そうとする。
大人達は事情も知らず、聞く耳なし、あてにならない、探しても見つからず、必死になって聞いて回り、夜になってしまう。
結末がどうと言うよりも、探している時の姿や景色など、目が離せなくて、はらはらとしてしまう。
イランの事はよく知らないが、友だちのうちを探している男の子を観ながら、村の暮しぶりを知る。
忘れられない写真を何枚も観ているような感覚にもなりました。
男の子の優しさに触れ、あたたかい気持ちになる、また観たくなる映画でした。
ジグザグ道3部作の1作目
友人の事を思い必死になる姿に心動く
主人公の小学生アハマッドを演じるのはババク・アハマッド・プールと言...
主人公の小学生アハマッドを演じるのはババク・アハマッド・プールと言う子供で、この映画はこの少年の24時間を描く。
キアロスタミ監督の「ジグザグ道3部作」
『友だちのうちはどこ?』(1987)
『そして人生はつづく』(1992)
『オリーブの林をぬけて』(1994)
と言われてる映画の1本目。
私、日本人からすると「何処か懐かしい」と言う感情なんて全く湧かない異国情緒満載の物語。
隣の席の友だちの大切なノートを間違えて持ち帰ってしまった少年が、ノートを返すため友だちの家を探し歩く姿を活写し、アッバス・キアロスタミ監督の名を世界に知らしめたイラン映画。イラン北部にあるコケル村の小学校。モハマッド・レダ・ネマツァデモハマッド(アハマッド・アハマッド・プール)は宿題をノートではなく紙に書いてきたため先生からきつく叱られ、「今度同じことをしたら退学だ」と告げられる。しかし隣の席に座る親友アハマッド(ババク・アハマッド・プール)が、間違ってモハマッドのノートを自宅に持ち帰ってしまう。ノートがないとモハマッドが退学になると焦ったアハマッドは、ノートを返すため、徒歩で遠い隣村に住む彼の家をひたすら探し回るが、なかなか見つけることができず、、、
ラストシーンは印象的で『パンと植木鉢』(1996)のモフセン・マフマルバフ監督は影響を受けているのではないだろうか?
鉄の扉
絶体絶命のアハマッド
〽 目覚まし時計は母親みたいで心が通わず
(東へ西へ 井上陽水)
どうしてこんなに母親って非情なのだろうね。溜め息。
あなたは宿題をさせたいのか、育児や洗濯の手伝いをさせたいのか。
大人って、こんなにも子供の声を聞かない。
・・・・・・・・・・・・・
先日、友人と、
ふとむかしの事を思い出して語り合ったのだ。
僕がクリスマスの「アドベント・チョコ・カレンダー」をプレゼントしたら、それに対する礼だけでなく、その友人がふと呟いたのだ
「わたし○○の子供に生まれたかったなぁ・・」と。
僕からの返信には こう書いた
「わたし○○の子供に生まれたかったなぁ」。
さらっと流して呟いた、
気(ケ)取られないように触れた何気ない言葉だけれど、
これは子供の時の「痛いコトバ」だ。
幾度、僕たちは枕を涙で濡らしたことだろう。
・なんでこんな家に生まれたんだろう、
・どうして自分はこの父親や母親のもとに自分は生まれてしまったんだろう、
・よその家に生まれたかった・・
○○ちゃんの家みたいな幸せな家の子になりたかった。
お布団をかぶって泣いた。
あのね、
むかし貧しい市営住宅に住んでいたとき、
保育園に通ううちの子の友達の「よしお君」が、中庭を通ってうちに来たんだよ。
よしお君の部屋は、玄関の土は湿っていて苔が生えている。お向かいの日陰の、すごい寒い部屋。
日の当たる掃き出し窓のところに座って、僕は よしお君を膝に抱き上げ、ギュッと抱きしめて
「かわいい かわいい」と言いながら頭をグリグリ撫でていたら
彼は言ったんだ
「オレ、おじちゃんちの子に生まれたかったな」って。
「あっ」と思って、たまらなくなって、もう一度ギュッと抱きしめた。
小さな子どもの頭は お日さまの匂いがした。
・・・・・・・・・・・・
アッバス・キアロスタミ。
プロフィール写真を見ると強面なんだが、アップの写真だとサングラスの向こうにすけて見えるその目の、なんと純粋なこと。
イランの映画は、いい。
あの頃の、子供心の焦りや嘆きの世界を、こんなにも優しくすくい上げてくれる。
子供の涙にそっと寄り添ってくれる。
子供のがんばりを認めてくれる。
その声に耳を澄ませてくれる。
この映画は、その友人が勧めてくれたので、今回僕は初めての鑑賞となったのでした。
良かった。
・・・・・・・・・・・・・
友だちのうちはどこ?
ここだよ、
レザ・マツァハデ。
·
映画というより、彼らの生活を覗いてるのかと錯覚するぐらい自然で取り...
大人は随分自分勝手だね
これくらいシンプルに
日本映画もこれくらいシンプルでいいんじゃないかな、
友達の宿題を間違えて持って帰ってきちゃって、渡さないとその子が退学させられてしまう、どうしようという話し。
子供目線で一生懸命に描かれていて、国は違うし表情や細かなしぐさとかも日本にはもちろんないところばかりなのに気づくと男の子を応援している。
がんばれ〜!!
周りの大人たちからお遣いや家事、育児とか頼まれても曲げずに友達の家を探す姿が印象的。
誰しも子供の頃って"こうしなきゃ!こうなったら怒られちゃう、ダメだ"っていう強迫観念があったと思う。
それを貫き通していく友達想いの作品でした。
ちなみにもう1つ、同じ日に見たのは日本映画のウェディングハイ。
かなり真逆の作品だったなぁ
鉄のドアの先へ…
大人は分かってくれないよね~。先生の言い付け守るのも、楽じゃない。でも、だからこそ、忘れられない。
家からの大脱出
祖父のしつけタイム
職人気質なお爺さんとの出会い
食べたくない晩ごはん
何も言わない父さん
そっと、ご飯を置く母さん
風の強い夜
そして迎える朝
総て、忘れられない大切な出来事。
子供の頃の思い出って、些細なものほど、強く印象に残ったりするものです。何だかひとり「スタンド・バイ・ミー」状態ですが、アハマッド坊やも、この日の大冒険を、きっと忘れない。そして、やがて訪れる鉄のドアを開ける…。
イランって聞くと、政治的、思想的に凄く遠い国って感じがします。実際、相容れない戒律もあるかな。ただ、この映画を観る限り、信じる神様は違えど、人として大切にしているものは、それほど変わらないのかなぁと…。
それと、私が気になるのは、町で出会った職人気質なお爺さん。おそらく、監督さんの分身ですが、誰もが慌ただしく暮らす中、未来を生きるアハマッドに、何を託そうとしたと思います?。
このクニが、土地バブルで狂騒状態の頃に創られた映画です。邦画なら「就職戦線、異状なし」の時代かな。皆様はどうお過ごしでしたか?。
アハマッド坊やは、その後、何を手に入れたと思いますか?。失われた30年で、皆様は、何を手に入れましたか?。
世界は大きく変動しています。どうせなら、今よりマシに変わってほしい。
あの日の、アハマッド坊やのように…。
大好きな作品です
採点4.3
友達のノートを返しに行く。そんなシンプルでハートフルな物語。
ポシュテという地名だけを頼りに、ほとんど当てのない旅で見ていて不安しかないんですね。
作品で特徴的なのが、全て子どもの視点で描かれています。
また俳優でなく村の住人や子どもたちをそのまま出演。
だからか、すごいリアリティなんですね。
それと子どもたちが皆可愛い。アハマッドの不安げな表情とか抱きしめてあげたくなります。
反対に、先生をはじめ出てくる大人たちが一様に面倒臭い。
全然話は聞いてくれないし、どうでも良い話ばかりダラダラとするし、全然物事が先に進まない。自分の爺さんすらもこれまた面倒臭い。
道案内してくれた親切な爺さんすらも、ドアの話ばかりで中々進まないんですね。
しかも、そんな爺さんを気遣い、そのノートを隠す優しさですよ。
結局友だちの家を見つける事ができず、家で泣きくれるアハマッドはふとある事を思い付きます。
そうして最後に開かれたノート。優しさに溢れた何とも素敵なカットでした。
爺さんもですが、帰ってきた時のお母さんもそう。優しさは優しさで繋がっているんですよね。
久しぶりに観ましたがやっぱり良い、大好きな作品です。
ジグザグ道‼️
全52件中、1~20件目を表示