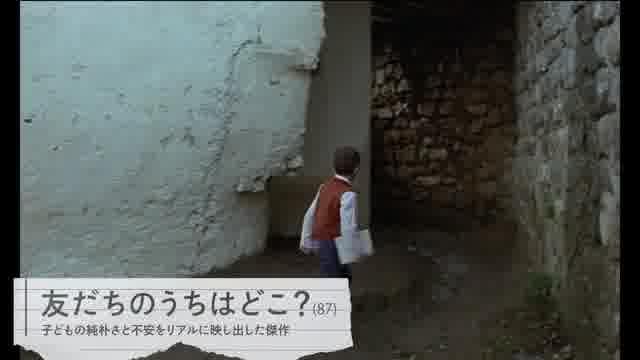友だちのうちはどこ?のレビュー・感想・評価
全62件中、41~60件目を表示
この美しさは、写真の美しさだ!
体験学習
先生っていじわる
どこの国でも先生っていじわるなんだな。子どもだっていろいろ事情あるでしょう。でもノートに宿題をやるべき理由をきちんと説明してたのはよかった。
アハマッドがまだ大人にうまく説明できないし、大人はちゃんと話を聞かないしでもどかしい!
おじいさんの勘違いにみせる優しさとモハマッド=レザへの優しさ、押し花に泣ける。漏れる光を計算した窓枠がきれいだ。
子どもの頃はあんな風にに走れたことを思い出す。ロバとの追いかけっこ、見えそうで見えないあの子、おじいさんの窓。印象に残るシーンがいくつもあった。
イランってけっこう教育熱心で躾にも厳しいんだなあとちょっと意外だった。おじいさんたちは日がなあそこでおしゃべりしてるんだろうか。
それにしてもお母さん洗濯大変…。
【”走れメロス!イランバージョン。”友だちが退学にならないように、少年がくねくね道を只管に、必死に走る無垢なる姿が沁みます。当時のイランの子供達がイロイロな仕事を親から言われて大変だった事も・・。】
ー 冒頭、質素な教室でネマツァデ君は、先生からこっ酷く叱れている。宿題をノートではなく紙に書いて来たからだ。
そして、先生からは”次に同じことをしたら、退学だ!”と言われてしまう。
隣席の、アハマッド君は心配そうに見ていたが・・。ー
◆感想
<Caution ‼内容に触れています。>
・冒頭のシーンでポシェテという地域から通学してきた少年が遅れて教室に入ってきた際に、怖い先生から、”何処から来た?””ポシェテです・・。”
仕方ないなあ、という表情で先生が”ポシェテからくる子は10分早く起きなさい、30分早く寝なさい!”と言う。
ー ポシェテってところは、遠いんだね・・。ー
・アハマッド君が家に帰ってきたら、ナント、ネマツァデ君のノートが出てくる。焦る、アハマッド君。
”このままじゃ、ネマツァデ君が、退学になってしまうよ!”
ー けれど、親からは宿題代しろ!と言われ、必死に宿題をするアハマッド君。。そして、脱兎の如く、ネマツァデ君のノートを片手に、くねくね坂道を駆け上がっていく。
ポシェテに住むネマツァデ君にノートを届けるために・・。ー
■焦る、アハマッド君を遮る数々の障害。
・突然落ちてくる洗濯物。
ー 人の良いアハマッド君は、洗濯物を投げて戻してあげようとするが・・。時間はドンドン過ぎていく・・。ー
・ポシェテには、色んな地区があって、ネマツァデ君がどの地区に住んでいるか、分からない・・。
・アハマッド君のお爺さん。
ー 孫はキビシク躾けなきゃならん!と言って、煙草を持っているのに、煙草を買いに行かせる・・。で、自分の昔話を友達のお爺さんにし始める・・。
躾じゃないでしょ!時代が違うんだよ!ー
・”儂は、何でも知っている”お爺さん。
ー アハマッド君を、ネマツァデ君の家に案内するというも、自分が作った木製の扉の話ばっかりして、到頭息切れしちゃって、到着できない・・・、というか、知らないんじゃない!ー
・意気消沈して、家に帰ったアハマッド君。食欲無し・・。
<翌日、学校にアハマッド君は来ない。ノートがないネマツァデ君は、涙顔。
ドンドン迫って来る怖い先生。
そこに、現れたアハマッド君。
最初、ノートを間違っちゃうけれど、キチンと、ネマツァデ君のノートにも宿題の答えが書いてある・・。
当時のイラン情勢を、コミカルに揶揄しながらも、溢れる山道を駆けずり回るアハマッド君の善性溢れる姿が、沁みてしまった作品。
佳き作品であると思います。>
ハマる(笑)
押し花
シンプルでリアルな眼差しが生むもの
タイトルなし
無題
似てると思ったら兄弟だったのか!赤と緑で区別したよ・・・
小学校の小さな教室。三人掛けの机に2年生のアハマッドとネマツァデが並んで座っていた。ネマツァデは宿題をよく忘れる上に、今回はノートではなく紙切れに宿題を書いてきたので先生にこっぴどく叱られる。「3回目だな!次に忘れてきたり、ノートに書いて来なかったら退学だ!」と脅され、隣にいたアハマッドまでビビッてしまった。そんな恐怖の宿題だったのに、彼はネマツァデのノートまで間違えて持って帰ってしまった。何とかしてノートを彼に届けなければ退学になってしまう!
しかし、のんびりスローライフのイランの片田舎。家の手伝い、畑の仕事、おつかいまでしなければならないけど、宿題が先。焦るアハマッドはとにかく友だちにノートを届けなければと先を急ごうとする。何とか手伝いを避けて家を探そうとするが、遠い地域なだけに全くわからない。地域だけはわかっているので大人たちに尋ねまわるのだが、要領を得ない。おじいさんたちにつかまり、与太話を聞かされたり、間違った情報を聞かされたり、町内はネマツァデ姓だらけだったりと散々な結果に・・・親切なおじいさんは歩くのが遅く、結局は先ほど行った間違いの家だったりするのだ。ここでおじいさんに気を遣ってノートを隠すのが絶妙!
夜遅く、まだ夕飯の時間には間に合いそうだったけど、諦めて自宅に帰ったアハマッド。要は明日学校でノートを渡せばいいのだから、彼の分も宿題してあげなよ!と、ずるいやり方だけど、祈る気持ちでいっぱいになった。だってそれしか方法はないんだもん(笑)。結末はあっさり、祈り通りだったけど、とにかく走れメロスの少年版のような展開は素人が演じてるとは思えないほどの演技力。目だけで訴える少年の純粋さはとても感動的。やっぱり泣きの演技は素人にしかできないリアルさが感じられた。
小津安二郎が好きだというキアロスタミ監督。思い出したのは戦前作品『生まれてはみたけれど』の子役中心の映画でした。
押し花が光った
アバスキアロスタミの初期の作品らしい。一般論だが、イランの映画を見ていると最初の20−30分は何がおきているかわからなく、そのうち何かがわかってくるという映画が多い。キアロスタミの作品もまさにその通りだ。しかし、『ともだちのうちはどこ』はかなり早い時間に作品の内容の検討がつく。
そして、忍耐強く大人に話しかけていくシーンは一般論だが、イラン映画の代表的シーンだ。子供の食いついていく力強さがはっきり出ている。子供だけじゃないんだなあ、先生、お母さん、おじいさんのもこの何度も繰り返す執拗な性格がうかがえる。好きだなあこういうシーン。それに、イラン映画は子供を使った映画が多い。なぜなら、芸術に対する政治的な検閲が厳しいからだそうだ。友達にノートを返そうとしてポシュテにという村まで、返しにいくシーンは善後策を顧みない子供の行動だが、これが友達を助けようとする一心不乱の行動なのを、この映画でなんとも良くとらえている。キアロスタミの画策が良さを出している。
最後のシーンの先生の言葉、『よくできた。』これだけしか云わない。『宿題をノートにかかなかったら退学だ」とか言ってたんなら、生徒の筆跡ぐらい注意してみろよと言いたいが、アハマッドの心の優しさの方がずうっと価値があるので、不正(カンニングの一種)であっても、許してしまう。かえって、先生に見つからなくてよかったと思う。宿題をノートにすることが大切か?それともどんな紙にでも宿題をやることの方が大切か? こういう文化は日本の文化と似ている。『先生の板書は美だ』と言っていた日本の某有名大学の教授と同じで、何が本当に大切なのか本質がわかっていない。
アハマッドが教室に遅れてきて、友達のノートを差し出した時、友達はなにがおきたのかも、どんなに苦労しても友達の家を探せなかったかも何もしらない。その時の友達の顔は愉快だった。人生において、取り越し苦労をしても相手に理解されない時のようだ。
それにまして、押し花が宿題の間にあったのに、まるで、関心も示さない先生(教育の狭さ、情操教育の無さ)にも偏見承知だが、イランの1987年の教育を垣間見た感じがする。
いつの作品かを気にしてみていなかったが、これは田舎の人里離れたところに(散村)に違いない。Kokerというところにこの少年アハマッドの家族は住んでいるが、私は地図で探すことができなかった。以前地震のあったカスピ海の内陸部らしいが。
アバスキアロスタミは個人的に好きな監督で、彼は小津安二郎のファンだったと聞いたが、小津安二郎感覚を共有している。
少年の頭をもしゃもしゃっとして抱きしめたくなる!!
少年が友人のノートを届けに行くと言うそれだけの映画
なのですが、そこには色々な日本では理解できないような
様々な家庭の事情や大人の事情が入っていて
考えさせられます
少年は小学2年生。まだまだ自分の気持ちがうまく
伝えられない世代
それでも、友だちがノートがないと大変なことになると
家を飛び出すさまは、観ていて心が洗われる
泥まみれの汚い大人心にはたまらない作品だ
見知らぬおじいさんと友人の所へノートを
届けに行くクライマックスはまさに
心がキュンキュン、子を持つ親はわーっと
叫びたくなりそうです
そのシーンを思い出すとまた涙が・・・
これで撮ろうって思わない
これで撮ろうって思わないもの。そこに驚かされるし惹かれる。
子供の頃にこんな危機感て、誰もが味わったことがあると思う。大人になって思い返してみるとなんて馬鹿馬鹿しいことで追い詰められていたんだと、アホらしくなるが当時は真剣そのもの。
程度を下げるようで申し訳ない例えだが、はじめてのおつかい、てこれと惹かれるポイントが近いような。あれ、なんか見てしまうでしょ笑
しかし。もうちょっと声でんか?とイライラしながら見た。終始遠慮がちで、でもまあ、教育がこういう感じの文化圏なんだろうな。今日本で「しつけ」て死語みたいなもん。宿題ノートに書かなかっただけで退学て、虐待とかなんとか言われて、先生が吊し上げだろう。ニュースとかなって。いや、関係ないか。。
子供の目線という共通の鍵を使って 国や民族を超えた人間の普遍性を見事に謳いあげています
素晴らしい映画に出逢えました
子供の世界は国が違えど民族が違えど同じです
宿題をやってきたかと先生に問われてドキドキしている表情を通してイランの知らない町の出来事でも共感できるものです
そしてわかってくれない大人たちの世界も同じ
自分たちの子供のころの感情をみずみずしく甦らせてくれます
そして彼の両親や様々な大人、おじいさん、おばあさん、イランの田舎の寒村の暮らし
監督は彼ら彼女らの人生がどうでであったのか、どのように育って来たのか、そしてどのように老いていくのかを様々な登場人物に語らせたり、暮らしぶりを見せて推察させたりしていくのです
そうしているうちに私達は全く知らない国でそこで生まれ死んでいく様々な人生を知り、本作を見ているうちにまるでそこに子供の頃からそこで育ってきて、そこで老いていくかのような錯覚を覚える程にその世界に吸い込まれてしまうのです
そうして、そこには国や民族の違いを超えて、普遍的な人間の暮らしがあり、私達と何も変わるところはない人間の営みがあることを知るのです
世界中のどこの村でも、街でも成立する物語のなです
つまり人間皆同じ、変わりはしません
大きく言えば人種、民族の平等を歌い上げた人類讃歌といえるでしょう
子供の目線という共通の鍵でその扉を開いて見せているのです
カメラの見つめる視線の暖かみ、その場の空気感を伝える間のあるカット回し、そして色彩
光と影
素晴らしい技量の監督だとおもいます
ラストシーンの押し花のハッとする効果的な一撃は長く記憶に刻まれるだろう見事なものでした
名作であると思います
子供の気持ち
小学生のアハマッドが帰宅して気がついたら友達のノートを間違えて持ってきてしまっていた。実は、その友達は今日学校で宿題をノートに書いてこなかったことで先生から厳しく叱責されていた。『今度同じことをやったら退学だぞ」と。彼は遠い隣村まで何とか返しに行こうとするが…。
とにかく子供達の演技が真に迫りすぎています(どうやら演出に仕掛けがあるらしく完全に演技というわけではないらしいですが)。悲しみ、不安、焦り、真剣さが画面からビンビン伝わってきて苦しくなるほどです。
見ていて自分も幼い頃の気持ちを思い出しましたね。大人にとってはどうということもないことかもしれないけれど、何気ない言葉かもしれないけれども、子供にとっては一大事。
出てくる大人たちが、これまた彼の話を聞いてくれないんですよ(苦笑)。それは、電化製品や輸送機械などが殆ど普及していない中で壮年達は日々の生活に精一杯だったり、また「子供は年長者の言うことを黙って聞くのが当たり前」という伝統的な価値観が根強かったりするためで、日本でもひと昔前はこんなだったんでしょうね。
一人だけアハマッドの話を親身に聞いてくれて案内を申し出てくれた老人がいました。でも散々歩き回った挙句たどり着けませんでした。後から考えるとその老人も行き先を本当に知っていたのかいささか怪しい。元々はドア作り職人だったらしいその老人は、歩きながら「あそこのドアは昔ワシが作った」だの「今は鉄製のドアばかり売れるようになってしまった」だの問わず語りに話します。それどころではないアハマッドとの噛み合わないやりとりが笑えるのですが、どうもその老人は話し相手が欲しかったのではないかな?「若い者は皆街に出て行ってしまう。ワシは街は嫌いだ」みたいなことを言っていたし、孤独に暮らしているらしい描写もある。
伝統的な共同体の中で人々が生きる様子と、一方でそれが少しづつ崩れつつある姿。そうした社会背景も伺うことができます。
ともかく主人公と一緒にハラハラドキドキしながらの85分。粋なラストでほっこり。
追悼キアロスタミ
全62件中、41~60件目を表示