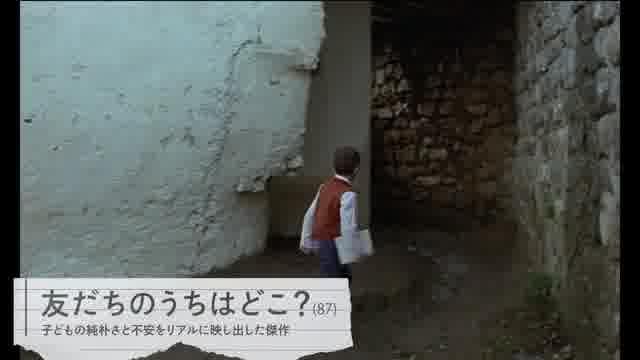「大人と子供、ドアの演出。」友だちのうちはどこ? すっかんさんの映画レビュー(感想・評価)
大人と子供、ドアの演出。
◯作品全体
物語は非常にシンプルだ。学校にノートを持ってこなければ退学だと友だちが怒られた矢先に、その友だちのノートを持って帰ってきてしまう。ノートを友だちへ届けなければ…物語は終始、ただそれだけだ。
しかし返しに行く過程の中で、8歳の主人公・アハマッドとまわりの大人とのディスコミュニケーションによって、いろいろな感情を抱かせてくれる作品だった。
アハマッドが苦悩するとき、必ず大人の存在がある。知らない大人だけでなく、学校の先生、親や祖父。ノートを返さなければならないことそれ自体ではなく、大人たちにアハマッドの心情が伝わっていないことに苦悩する。その苦悩の表現が多彩だった。
一つは大人へ伝えること自体の苦悩。アハマッドがノートを返しに行きたいことを母に話すシーンは特にその苦悩が表現されていて、忙しそうにする母へ視線を向けつつ、弟をあやすアハマッドの目線や仕草が、子供ながらの「真に迫る」表現をしていて素晴らしかった。一方で母は真に受けず、遊びに行きたい言い訳だと思っている。そのディスコミュニケーションがもどかしくもあり、二人にとっての日常の風景として説得力あるシーンでもあった。他の場面でもどの人に話しかけようか、なにを伝えようかと逡巡するような仕草や話し方がアハマッドにはあり、アハマッドの少し内気だけれど真っ直ぐな心を感じられた。単に「話を聞いてもらえないシーン」ではなく、アハマッドたちの生活や心の内側を描いているところに、この作品の表現の豊かさを感じた。
二つ目は大人に伝わらないことの苦悩。アハマッドが伝えたいことをうまく言語化できていないこともそうだし、大人もアハマッドの話していることを話半分で聞いているもどかしさがある。祖父が話す一方的な教育論がそのことを強調していて、子供が正しいことを言っていようがいまいが大人はあまり関係なく、大人自身の立ち振る舞いばかり気にしている。もしかしたら実際、普段は子供の話していることは他愛のないことばかりかもしれないが、作中では子供であるアハマッドの方に道理があり、それを聞く大人は不義理な存在だった。こうした関係性が、真っ直ぐに目的へ進むアハマッドの物語に起伏を生んでいた。
アハマッドの伝わらない苦悩を描くのに強く印象に残った演出として、動物の鳴き声があった。アハマッドが向かうところや大人と話す場面では、いろいろなところにいろいろな動物がいて鳴き声をあげている。これが大人に気持ちが伝わらないアハマッドの言葉のように、聞き流されてしまうものとして重なった。アハマッドも声が通らず(または他の会話に無視されて)、鳴き声のように何度も同じ言葉を口にする場面が多々ある。大人から同じ「鳴き声」として扱われている状況を、環境音から巧く演出しているように感じた。
大人と子供のディスコミュニケーションは特別なことではなくて、どこの世界にもあることなのだと思う。そのディスコミュニケーションを子供の視点で描いていることがまず面白かったし、その苦悩が日常の中にある演出も見事だった。
映像演出の中でカギになっていたのは扉の演出だった。
扉は要所の場面で登場する。ファーストカットの教室や、青い扉を探す場面、宿題をするアハマッドの近くで勢いよく扉が開く終盤。扉は風の通りを防ぐもの・通すものとして存在するが、本作では物語としての、そして人としての「風通しの良さ」を表現するものでもあった。
教室の壊れた扉は子供が往来するたびに開いたままになるが、一方で教師は何度も閉じようとする、という場面があった。この冒頭の扉は物語と具体的に関連付けるのではなく、子供の風通しの良さと、大人の風通しの悪さを概要的に表現していた。アハマッドが先生の言った言葉を飲み込み、いろんな人に声をかける風通しの良さがある一方で、大人のアハマッドの感情に対する理解のなさを風通しの悪さとして重ねていたのだと思う。
作中でも大人たちが鉄の扉に買い替える話をしている。鉄の扉は隙間風を通さず、どんどんと木製のものから置き換わっているという。歳を重ね、錆付いたように自分の考えに固執する祖父のように、大人たちの考えが凝り固まっていることと重なって見えた。一方で道案内をしてくれたお爺さんは鉄の扉に置き換わることを寂しそうに話していて、すべての大人がそうではないことも語っていた。
アハマッドが探す友だちやその親戚の扉は閉まっている。外出していたり、見当違いの家であったりする。物語としてなかなか上手くはいかない「風通しの悪さ」の表現だ。終盤のアハマッドの家の扉が勢いよく開くのは物語の解決を示したものだろう。二人分の宿題を解けば良いと閃いたアハマッドの心象風景と重ねっているように感じた。
物語がシンプルな分、映像の中で語られる大人と子供の関係性やディスコミュニケーションは非常に饒舌。扉というモチーフの扱い方も見事で、見ごたえある作品だった。
◯カメラワークとか
・手前と奥を意識したレイアウトが多い。集落の間にある道は遮るものがほとんどなくて拓けてるのに、集落は狭い道が多いから画面の情報量に緩急がある。手前と奥の空間のまわりにある建物がシンプルなのも良い。こちらも白い壁や木の色味が縦に複雑な集落のメリハリになってた。
キアロスタミ監督が小津安二郎ファンだとか。最近『バッファロー'66』を見たけど、あっちも小津調を意識したとか書いてあった。こっちのほうが小津らしさがある気がする。屋内を映すときのカメラの低さ、奥行きの使い方、あとは親と子の独特な雰囲気。アハマッドがセリフを用いず表情で語るようなカットがあるのも小津作品の笠智衆っぽさがあった。
◯その他
・この作品って幼い子が遠くまで一人旅をするっていうところが『はじめてのおつかい』っぽい。目的は一つなんだけど回り道してしまうところとか、大人に助けを求めるところとか。でも明らかに違うところがあって、誰が主役の心情を語るかという部分。『はじめてのおつかい』はナレーションがそれを語るんだけど、本作は主人公の表情がすべてを語る。だからアハマッドの今回の旅が切り取られた特別なものではなくて、アハマッドという一人の人間があるときふと思い出すような日常の一ページに見えてくる。映画だから創作物であることは間違いないんだけど、日常の一ページというスタンスによって、見ている自分のノスタルジックを刺激する作品になっていた。