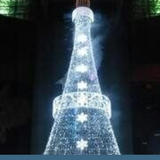テオレマのレビュー・感想・評価
全22件中、1~20件目を表示
流石パゾリーニ!彼の創造した乾いた世界が凄すぎる
もちろん難解である。
主な登場人物は裕福な一家と謎の青年。
ジャズとクラシック、それと家政婦。
顔のアップに人間の内面を見せる。
人の本性とは
乾きとは何か
目覚めとは
潤とは何か
謎の青年の魅力
彼は何者なのか
明かさない。
受け取り方で沁み入るものの姿が違う。
それは何なのかは創造主しかわからない。
※
「回心」の定理
パゾリーニという監督は、映像という手段を使って哲学を行おうとした稀有な作家だと思います。『テオレマ』というタイトルはイタリア語で「定理」を意味しますが、本作はまさに「人間が神的なものに触れたとき、どう反応するか」という“定理”を映画という形で証明しようとした作品だと感じました。
ある日、平凡なブルジョワ家庭にひとりの青年が現れ、家族全員と関係を持ち、やがて去っていく。この青年は明らかに“聖なるもの”のメタファーであり、神・奇跡・超越的な存在の象徴です。
しかし彼に触れた人々の反応は、各々の生きる「体系」によってまったく異なります。父親は所有と合理の世界を放棄して荒野へと彷徨い、母親は欲望の再現に溺れ、息子は芸術に逃避し、娘は沈黙の中に閉じこもる。彼らはみな、唯物論的な価値観の枠の中でしか“聖なるもの”を理解できず、その結果として精神の崩壊や虚無に至ってしまいます。
一方、家政婦だけが奇跡を起こし、神に近づく存在として描かれます。それは、彼女が信仰という内的な“聖性”をすでに持っていたからだと感じました。
この構造を見ていると、パゾリーニが描こうとしたのは「回心への道」そのものではないかと思います。
人は“奇跡”や“聖なるもの”に触れたときに、必ずしもすぐに救われるわけではありません。むしろ、それまでの自分の価値体系が崩壊し、虚無を経由してしか回心には至れない。
『テオレマ』の登場人物たちは、それぞれの立場や欲望に応じてこの“聖なる衝突”に晒され、その結果として「回心する者」と「虚無に沈む者」とに分かれていく。
まるでパゾリーニ自身が、神の存在を前提としない現代社会において、「人間がどうすれば再び聖なるものと出会えるのか」という問いを、実験的に描いたように思えます。
個人的には、私自身も長い時間をかけて唯物論的な世界観から少しずつ離れていった経験があるため、この映画の主題には深い共鳴を覚えました。
“回心”とは、突発的な奇跡ではなく、存在の構造そのものがゆっくりと変わっていく過程なのかもしれません。
そう考えると、『テオレマ』は単なる宗教映画でも社会批評でもなく、**「人間はどのようにして神なき時代に回心しうるのか」**という、非常に現代的な問いを突きつける哲学映画だと思います。
映像自体は静謐で、構図や空間の使い方にも宗教画のような厳粛さがあり、まるで全体がひとつの祈りのようです。終盤、荒野を裸で歩く父親の姿は、理性と所有を脱ぎ捨てた“現代人の最後の祈り”に見えました。
美と虚無、聖性と欲望、そして回心と崩壊。そのすべてが同時に存在している――そんな奇妙で荘厳な映画でした。
(イタリア芸術の伝統としての『テオレマ』)
イタリアの芸術には、常に「神」と「肉体」のあいだを往復する緊張が流れています。
ジョットの宗教画、ミケランジェロの彫刻、カラヴァッジョの光――それらはいずれも聖なるものがこの地上に“現前する”瞬間を描こうとしたものでした。
パゾリーニは、そうしたルネサンス以来の伝統を20世紀の映像表現へと継承し、
「聖性がもはや信じられない時代に、それでもなお聖性を描く」という最も困難な挑戦を引き受けた監督だと思います。
『テオレマ』における青年のまなざし、家族の崩壊、沈黙、光の使い方――そのすべてが、イタリア美術の精神的遺産を現代的に再構築している。
つまりこの映画は、宗教画の終焉ではなく、**「神を失ったあともなお神を描こうとするイタリア芸術の延長線上」**に位置しているのです。
鑑賞方法: Amazon Prime (4Kスキャン版)
評価: 92点
レトロぶっ飛び過ぎでワケわからん…
突然来た男に魅了される
突然ミラノ郊外のブルジョワ家庭に見知らぬ美形の男が訪問し、家族全員を魅了して去っていく。残された家族は彼の不在に耐えかね家庭崩壊する。そんなあらすじを聞き、大変興味を持ちましたがレンタルにもないしなかなか見られる機会がありませんでした。
映画「モリコーネ」で音楽をエンリオ・モリコーネが担当してると知りますますみたいと思っていたら運良く配信していて、タイトル知ってから20年越しに見られました。
皆が誰かの客と思ってて、接してるうちに徐々に魅了していくのかと思いきや、メイドさんには即!だったので笑えました…このメイドさん関係はキリスト教への皮肉めいたものなのでしょうか。キリスト教に詳しくないから笑わそうと思ってるように見えてしまい。目に砂が入ってただろう撮影は気の毒でした。
テンポが早かったのに、彼が去ったあとは妙に時間を取って話がすぐに進まない。天衣無縫だった息子は彼が去った心を埋めるため突然アートに目覚めるけど、アーティストへの苦言三昧でこれは監督が日々思ってることを言わせたとしか思えない。
娘は気の毒。見てて少々退屈するような無意味な行動を長々と繰り返すものの、心の空白を埋められずおかしくなる。
元々男性恐怖症ぎみだったが一番酷い状況になるのは何の罰なのか。しかも心配してるの新メイドさんぐらいで、搬送時に家族の見送りもなく寂しい限り。
妻は予想に近い変わり様だったけれど、イタリアは普通に街に男娼がいたのでしょうか。そして妻は庶民の街をみて何を思ったか。
街並みが絵画のように美しく感じます。キリコの絵みたい。
資本家だった父親は、心の空洞を埋められなく奇行に走った挙げ句、工場を労働者に譲る決意をする。
労働争議にも心動かないのに1人の男前により人生を転換させる。
これは不足なく生きて貧乏人の暮らしなど想いもよせない富裕層達に行動を変えさせるには、今の生活が非常に虚しいものだと気づかせるだけパンチのあるものを投入しないといけないってこととか…?
時代背景や宗教に詳しければもっと深く観られるのでしょうか。
仏映画「ブルジョワジーの密かな愉しみ」も思い出しました。あちらはシュールかつ皮肉めいてクスリと笑えるところもあるけど、こちらは笑っていいのかどうか。
テオレマ
【”謎の美青年の訪問により、瓦解していく裕福な民主主義家族の顛末を描く。謎の美青年の正体は何か・・。】
■イタリアの異才・パゾリーニが共産主義者であったことは有名である。
してみると、謎の美青年の訪問者の正体が分かる気がするが、パゾリーニは彼はキリストではないと否定している。
<物語>
・ミラノ郊外の大邸宅に暮らす裕福な一家の前に、ある日突然見知らぬ美しい青年(テレンス・スタンプ)が現れる。
何の前触れもなく同居を始めたその青年は大工場を持つ父親、美しい母親、無邪気な息子と娘、そして女中を魅了し、関係を持つことで一家の穏やかな日々をかき乱していく。
◆感想<Caution!内容に触れています。>
・ご存じの通り、パゾリーニは共産主義者でありつつ、ホモセクシュアルであった。特に若い青年を求めて居た。
結果として、遺作となった「ソドムの市」は余りに衝撃的な描写の数々で、今や普通には見れない。
その後、パゾリーニは悲惨なる轢死体で発見される。
犯人は、「ソドムの市」に出演した青年であるとか、パゾリーニの思想に反感を持った者たちの仕業ではないかとなっているが、今だに真相は闇である。
・今作のテレンス・スタンプ演じる見知らぬ美しい青年は、私の勝手な解釈であるがパゾリーニが自身を投影したモノではないかと思う。
退廃的で、その行動に道義はなく、裕福な一家を破滅に追い込んでいく姿。
ー 因みに、パゾリーニは極端なナルシストでもあった。-
<パゾリーニ監督作はどれも難解であるが、見る側が自由に解釈すればよいと思う。
何故ならば、映画には正解はないからだ 。
そこから自由な発想が目覚めると思うのである。
但し、パゾリーニは晩年、人道主義を踏み外してしまった。
その代償は大きいのである。
狂ったのは、今作の裕福な家族なのか、パゾリーニなのか・・。>
パゾリーニ自身の悲劇をも予感させる不穏な傑作
う〜ん“Tears for Dolphy”よ!
パゾリーニは、映画館で集中して観ないとダメだろうと思ってたが、やっと観ることが出来た。
まさに現代(と言っても60年代だけど)の寓話。
なので寓話として観ないと難解な映画と思われるかもしれない。
テレンス・スタンプの存在自体、まさに寓話の体現なので、ここで乗り損ねると最後まで???となってしまうだろう。
ブルジョワの家族全員(&女中)が心の奥深い欲望を炙り出され、既存の倫理観や固定観念から解放されるが、訪問者のテレンス・スタンプが去ってしまった後、その喪失感から崩壊や機能不全へと陥っていく。
奇跡を起こして、聖なる復活を願うかのような女中(労働者階級)以外は。
カトリックのマルクス主義者と自称してたらしいパゾリーニという男の風変わりな寓話として観ていけば、割とシンプルな話だ。
そして寓話なので、いくらでも深読みも出来る。このあたりが映画マニアに魅了され続けている所以かもしれない。
それにしても、60年代なのに古臭さが全くない。全く退屈にもならない。
俳優陣が、とにかく魅力的だ。
特にシルヴァーナ・マンガーノの妖艶な色気は、下手するとステレオタイプ的なお笑いコントネタにもなりかねないが、やはり、この人の退廃的な官能美は本物だ。
テレンス・スタンプに関しては、もっと色々と出来たとは思うけど…
役柄としては旧約聖書の預言者だったらしいが。
『世にも怪奇な物語』のような悪魔的な魅力全開で発散して欲しかったかなあ。ここはやや残念。
むしろ、全くマークしてなかった女中役のラウラ・ベッティが本当に素晴らしかった。彼女なしでは、この映画は成立しなかったと思う。
そして音楽も良かった。
まずオープニングのタイトルバックでテッド・カーソンの「Tears for Dolphy」が流れて来て予想外の選曲にグッと来てしまった(ラウラ・ベッティが涙を流しながら土に埋められる際にも流れていた)
それにモーツァルトのレクイエム。
そのレクイエムが引用されたモリコーネの不協和音。これがまた良かった。永遠の安息と程遠いブルジョワ家族たちへの皮肉なテーマ曲か。
しかし、ラストはちょっと唐突すぎて、思わず「マジか?」と呟いてしまった。
出来れば、心象風景のようにインサートされていた砂丘の砂風をラストでも流して、カメラの望遠の向こう側で、砂漠の預言者の如くテレンス・スタンプを登場させて、最後にもう一度「Tears for Dolphy」流して欲しかったなあ。
本当にこの時期のイタリア映画は面白い作品が多いが、どういうわけかビデオで観ると全然ピンと来なかったりする。
『王女メディア』がまさにそうだったが、これも映画館で見直せば面白いかもしれない。本当に今回のリバイバル上映は感謝感謝である。
尚、あの頃のフェリーニの『甘い生活』やアントニオーニ『情事』など、戦後の物質的な豊かさとは裏腹に荒涼とした心を描いたイタリア映画が苦手な人には、この作品は殆どお勧め出来ない。
テレンス・スタンプや、シルヴァーナ・マンガーノの熱烈なファン以外は。
強烈フェロモン怪人Vs.ブルジョワジーww 突然走る! 叫ぶ! 浮く! 難解さを切り裂く素っ頓狂!
パゾリーニは、なぜかこれまで観る機会がなかった。
『ソドムの市』と『豚小屋』くらいはさすがに観ておかないとまずいかなとは長年思いつつ、難解だとか共産主義者だとか聞くたびに恐れをなして、つい後回しにしていた。
今回、武蔵野館で『テオレマ』と『王女メディア』がかかるということで、こいつは良い機会だと参戦。
チラシに書かれたあらすじくらいしか知らない状態で観たので、(その政治的含意や宗教的隠喩の深遠さはさておき)こんなウルトラアホな話だとは思っても見ず、何度も爆笑してしまった。
出だしの左翼記者の演説とか、そのあとのBGMだけで延々展開されるセピア色の状況説明シーケンスの辺りは、意味が分からなさ過ぎて、「ああこれムダに難しいヤツや」とゲンナリしてたのだが……本編は、意想外なまでにおバカな艶笑譚でした。
てか、これ今だと難解な思想的映画に振り分けされてるけど、当時の感覚でいえば、ピエトロ・ジェルミとか初期のマルコ・フェレーリみたいな、イタリア艶笑映画や桃色リアリズモの伝統を引き継いだ(もしくは引き継いだうえで、異様な改変を施した)映画として観られてたんじゃないのかな?
要するに、ブルジョワ一家のところに電報が来て、若者をひとり滞在させることになるのだが、こいつが「いるだけで相手の性欲を猛烈に亢進させる」とんでもない超常能力者で、次々と家族4人と初老のメイドをコマしていくのだ。いや、ホントにそんな話なんですよ!
それも、もう横にいるだけで頭が煮えて、すべてをかなぐり捨てて襲い掛かるくらいの、猫まっしぐらな性欲増進マタタビ作用。最近エロ界隈で大はやりの催眠アプリものも真っ青の効果覿面ぶりだ。
少女がそういう体質という漫画はお恥ずかしながら何冊か持っているが、男性がってパターンもあるんだな。
正直言って、そこまでテレンス・スタンプがカリスマ的にセクシーだったり、フェロモン出しまくりだったり全然しないのがまた奇妙で、なんというか、こちらが試されている気がしてくる。
たしかに顔立ちは整っているし、瞳のブルーはきれいだけど、小男だし、威厳ないし、草食系だし、しょせん『コレクター』の変質者だし……。毎回、わざわざ大股開きで股間を強調して座らされてるところ見ると(これ、パゾリーニじきじきの演出らしい)、むしろこれ、パゾリーニに内心馬鹿にされてネタでキャスティングされてんのかな?とか、いや、同性愛者だったパゾリーニ(本人も小男だった)にとってはこのタイプがマジで琴線に触れるタイプだったのかな?とか、いろいろ考えてしまう。あるいは、そうは見えないのにモテまくるという部分にこそ、神の定理(テオレマ)とか、宗教的な神秘を読み解かないといけないのかな? こんなバカな話なのに? とか。
なんか彼が庭に現れただけで、いきなりメイドのババアが急に血相変えて走り出したりするわけですよ(笑)。どうしたのかと思ったら、部屋に戻ってメイク直したりして、またハアハア駆け戻ってきて、お願いしますから入れてくださいみたいな。
奥さんとか、もうとろとろになって、お外で全裸待機しちゃってるし。さすがは原爆女優!
ほぼ、ノリはモンティパイソン。小説でいえば、全盛期の筒井康隆とか。
彼の性的魅力の有効範囲は、女性にとどまらない。
なんと、男性まで見境なしで発情させてしまう。
最初の晩にいきなり、長男がまず辛抱たまらんようになって、ベッドで裸を覗き見とかしてて「ごめんなさい、ごめんなさい」とか言ってるうちに、慰めてくれた青年に優しく掘られてしまう。
お父さんなんて、突然訪れた強制的な「目覚め」に苦悩しすぎて、病に倒れちゃうくらい。でも、結局ボクシングごっことかしてじゃれてるうちに、お外でこちらも無事ヤラれてしまう。
お堅いファザコンの娘(『バルタザールどこへ行く』や『中国女』に出てたアンヌ・ヴィアゼムスキー)も、魔の吸引力には抗えず、自ら望んであたら花を散らす。
で、全員がお手付きになって、新たなる性癖に目覚め、新たなる自分を解放する決意を胸に、その自覚的な宣言を高らかに謳い上げた直後……また電報が来て、青年は家から去ってしまうことに。
いきなりの新展開。さあ大変だ。
数日過ごす間に、彼に肉体的にも精神的にも依存し、いざ新たな人生を始めんと興奮状態にあった5人から、いきなりハシゴがはずされてしまったわけで、皆さん訳も分からず惑乱するばかり。
「サれ家族」が玄関先に全員殺到して、仲良しプチブルの「家族の肖像」みたいにワンフレームに収まって青年を見送っているショットは、本作最高の笑わせポイントだ。
で、このあと、五人五様に「しゃぶ抜き」の如き壮絶な禁断症状が訪れる。
即効性と依存性の強い「ヤク」ほど、いざ打てなくなったときの離脱症状は強烈だ。
一番、適性を見せていたメイドのぶっとんだ覚醒ぶりが最強過ぎて度肝を抜かれるが(とくに浮いてるとこww)、どのエピソードも「突飛さ」と「唐突さ」と「キテレツさ」がずぬけていて、基本は観客を「笑わせにかかっている」としか思えない。小難しい話はそのあと、という感じだ。
もちろん、こうやって前半だけでもあらすじをまとめてみると、すげえ面白そうな映画に思えるが、実際には語り口は晦渋かつ難解で、理解の及ばないところも多い。
パンフレットの町山さんと四方田さんの素晴らしい解説を読んで初めて得心のいったところが、何カ所もある。まあ、日本人がこれを観て、このマタタビ青年が「旧約聖書」由来の奇跡をもたらす存在であり、家族は使徒とパラレルであり、父親の奇行は聖フランチェスコのエピソードに由来してるなんて、なかなか思いつかないよね(笑)。
ただ、「新たな性癖に強制的に目覚めさせられた人々のひとときの昂揚と、その後の苦難」をシニカルに描いたネタ映画として、見た目どおりに捉えて鑑賞しても、十分面白い映画だと僕は虚心に思う。
深遠な宗教的なテーマ性や社会的な風刺は読み解けなくても、たとえば、電車の終着駅(すべての線路が目の前で終わってる)ってのは、まさに精神的に行き詰まった父親の心象風景なんだろうな、とか、もともと路電が敷設されていた跡地のような道路の情景が挿入されるのも、自分を導いてくれる中心的存在の不在と欠落の象徴なのかなあ、とか、何度も出てくるスモークのおりてくる高山(ラストで父親が全裸で登ってる)ってやっぱりシナイ山なのかな、とか、いろいろ想像することはできる。
もともと自認していた性癖から、「解放」後の性癖への飛躍が大きかったキャラクターほど、青年の不在によって引き起こされる反作用が大きいのも、一応よく考えられてるなあと。いちばん悲惨なうえに滑稽な扱いになってるのが、ほとんど何も悪くない長女で、そこは観てて可哀想だけど……まあ面白いけど(笑)。
他にも、部屋で青年と長男が一生懸命一緒に観ているのがフランシス・ベーコンの画集で、顔が性器の聖職者の絵が大写しになったり(「性なる神」である青年の存在とシンクロする。もちろんベーコンもゲイ)、トルストイの『イアン・イリイチの死』がゲイネタに転用されてたり、とにかく小ネタは満載。
エンニオ・モリコーネにわざわざ十二音音楽のテーマ曲を書かせつつ、同じくらいの頻度でモーツァルトのレクイエムかけてくるのも、クラオタとしてはとても馴染みやすい。そういや、モツレクも灰色の服を着た「謎の訪問者」にせかされて死の床で書いたって話になってたよな。
あと、晦渋な映画だとはいっても、唐突に走りだしたり、唐突に脱ぎだしたり、唐突に叫びだしたり、唐突に浮いちゃったりするのは、やはり本能的に身体言語の一発ギャグとして、ふつうに面白いものだ。まして、下ネタメインなので、こういった「ヘンな映画」が好きな人は、先入観抜きでご覧になっても、十分楽しめるのではないか。
最期に、鑑賞後はこの映画(と『王女メディア』)に関しては、パンフ購入はマストだと思う。
この映画を理解するために、知っておいていい情報がきわめて平易にまとめられていて、さすがの町山さん&四方田さんのご両名といった感じ。あと、テレンス・スタンプのインタビューがめちゃくそ面白い。
なぜかパゾリーニからは一言も声をかけられなかったとか、かわりにパゾリーニとツーカーのラウラ・ベッティ(メイド役)が高圧的に指示を伝えてきてセクハラされたとか、完成して吹き替えられた映画は撮影時から全く新しい脚本にすり替わっていたとか。
「パゾリーニは理論的には左翼で共産主義者かもしれませんが、実際は自分の利益を追求していました。すっかり騙された私は、本当に一銭たりともこの作品から払われていないんです」
……ま、そういうもんだよね!!(笑)
三上博史の憧れのテレンス・スタンプ
テレンス・スタンプ目当てで観ました。武蔵野館のポスターには三上博史のサインが!憧れの俳優で有名。若い頃に初めての寺山修司の映画で主演を努めた美少年の三上博史。なるほどね。
1967年のケン・ローチ監督の夜空に星があるように(原題 Poor Cow)をみて、素敵だなぁと思いましたが、1968年のこの映画では実はあんまり感じませんでした。ピエル・パオロ・パゾリーニ監督作は苦手。コメディなんですかねぇ?
ブルジョアという言葉は懐かしい。死語?
テレンス・スタンプがブルジョア一家の全員を魅了してゆき、そして突然いなくなると、家族やお手伝いさんに異変が起こる。
お手伝いさんの変化はカルトがかっていた。
お母さんの変化はわかるけど、一番俗っぽい。ブルジョア夫人のよろめき。ブルーアイの男を探して、血眼になっていました。
息子はただただ痛々しい。才能ないし、自虐的だし。
お父さんは男色に目覚めて、価値観がガラッと変わって、駅でまっぱになって砂漠をさ迷う。オヨヨ。会社を労働組合にあげちゃう。あっ、それで冒頭の場面に繋がるわけね。
娘はどうだったっけ?
当時は何もかも目新しかったのでしょうけど、とにかくテンポが遅くて眠かったです。
ピエル・パオロ・パゾリーニ監督の映画はそのあとのエロチックコメディ3作品(デカメロン、アラビアンナイト、ソドムの市)の再上映を武蔵野館さんには是非ともお願いします。観に行きますよ~ 今年の10月~12月あたりでお願いします。シネマカリテでもいいです。
タイトルなし(ネタバレ)
パゾリーニ監督は1922年生まれなので、ことし生誕100年。『王女メディア』とともにリバイバル上映されています。
現代(つまり、60年代後半)のイタリア・ミラノ。
大工場主のパオロ(マッシモ・ジロッティ)は工場の経営を労働者に譲ると発表。
マスコミは騒ぎ立てている。
そんなある日、パオロの邸宅に「明日、着く」とだけ書かれた発信人のない電報が届く。
現れたのは、見知らぬ美貌の青年(テレンス・スタンプ)。
家政婦をはじめ、パオロの妻ルチア(シルヴァーナ・マンガーノ)、息子ピエトロ(アンドレ・ホセ・クルース)、娘オデッタ(アンヌ・ヴィアゼムスキー)は青年の魅力に虜となってしまう。
あたかも「神は、原野で民を導く」かのように。
そして、青年はいずことなく姿を消してしまい、残された者たちは、それぞれが影響を受ける・・・
といった物語で、テレンス・スタンプ扮する青年が姿を消すまでが前半、以降が後半。後半にはスタンプは登場しない。
何度となく挿入される原野の風景や「神は、原野で民を導く」というモノローグから、神と人間についての物語であることはわかり、後半描かれる顛末から「神の不在」と「神の導く先」が主題であることは容易に察しが付く。
で、察しが付いてしまうと、意外なことに、つまらない。
(製作後50年も経っているので、その間にこの手の作品もかなり観ていますからね)
家政婦は自死途中で青年に助けられ、故郷へ戻って、不動の聖女となる。
娘オデッタは、処女のまま青年に抱かれ、手に何かを握りしめたまま硬直状態となり、これも一種の聖女と化す。
息子ピエトロは、青年の肖像を描こうとするものの技術が足りず、技術がたりないことを隠すための絵画技法を編み出す(これはパゾリーニ自身ではないか)。
妻ルチアは、青年の寵愛が忘れられず、街で青年に似た男性を漁るが満たされず、助けを求める先は教会だった、となる。
主人パオロは、ミラノ終着駅テルミナで突然すべてをかなぐり捨てて(文字どおり全裸になる)、ブルジョアの立場を棄てようとするのだが、時空を超えた原野を素っ裸で彷徨する羽目となる。
誰も神に救われていない。
これはこれで救われているのかもしれないが、救われていない。
という話なのだけれど、どうにも映画としての語り口がギクシャクしすぎていて、面白さに欠けている。
語り口という点でいえば、「明日、着く」の電報の時点だけがモノクロームで、このモノクロームが何を意味するのかがわからない。
電報が来て、青年が去るまでがモノクロームならば、わかりやすいのだけれど、そんなことはしていない。
というか、テレンス・スタンプは絶対カラーで撮りたかったんでしょうね。
青い眼と、悩ましい股間・・・
恐ろしいぐらいの頻度で股間のアップが写されます。
庭でランボー詩集を読む、大股開きのスタンプ青年。それを視る家政婦の視線。
青年に魅惑され、戸外で自慰に走るルチア。駆け付けたスタンプ青年の股間を見上げるルチアの視線。
同室隣同士のベッドで寝ることになったピエトロ。隣のベッドで、素っ裸になるスタンプ青年の股間はピエトロの目の前に。
娘オデッタは、ベッドに腰かけたスタンプ青年の股の間に座り込む・・・
って、パゾリーニ、テレンス・スタンプに魅了されていますな、こりゃ絶対。
というわけで(ってどういうわけだか)、パゾリーニの趣味や嗜好や志向が満載。
パゾリーニ映画は、このほかは先に観た『王女メディア』と、30年以上前に観た『デカメロン』他の艶笑三部作、『華やかな魔女たち』の1エピソードぐらいしか観ていないのですが、この作品がパゾリーニの極めつけではありますまいか。
寸分の隙もない完璧な画に魅了される、パゾリーニ監督の傑作。
名作と聞いていたが。。
自分には難解です💦
全22件中、1~20件目を表示