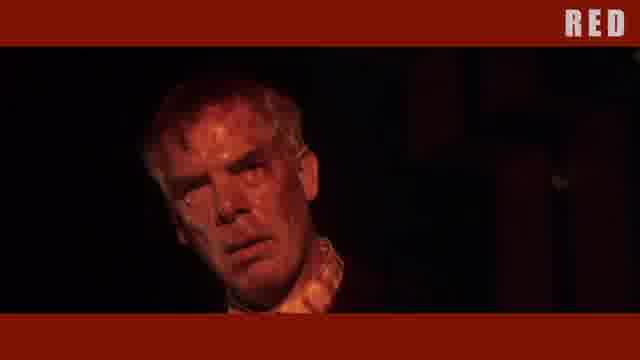殺しの分け前 ポイント・ブランクのレビュー・感想・評価
全19件を表示
ザ・ロック‼️
原作はリチャード・スタークという作家のハードボイルド小説「悪党パーカー/人狩り」‼️映画の原題は「POINT BLANK」なんですけど、そこに「殺しの分け前」という憎たらしいサブタイトルが付くんですから、当時の配給会社の方々のセンスは素晴らしいですね‼️親友マルに勧められて大金を強奪したウォーカーは、マルに撃たれ、金と妻を奪われてしまった。一年後、ウォーカーはマルを探すが、ウォーカーの前に現れた妻は自殺し、妻の妹クリスもマルに狙われていた。そしてついにマルを追いつめたウォーカーは背後にある組織へ闘いを挑む・・・‼️まずはスゴ味たっぷりに、ハードボイルドな魅力を爆発させるリー・マーヴィンがホントにカッコいい‼️ダークスーツとダークタイでビシッとキメたリー・マーヴィンが、アルカトラズ刑務所の高い金網を越えて跨ぐ途中の、「明日に向かって撃て!」な哲学的な顔‼️妻と出会い、デートを重ねる中での哀愁に満ちた顔‼️まさにリー・マーヴィンの最高傑作‼️そんなリー・マーヴィンを盛り立てるジョン・ブアマン監督の、シャープでスタイリッシュで沈んだトーンの映像世界もホントにゾクゾクさせられます‼️マーヴィンがマルに裏切られて弾丸を喰らうフラッシュバックがなりふり構わず挿入される編集のテクニックもかなり印象的‼️オープニングのタイトルバックに描かれる前述のアルカトラズ刑務所からの脱出シークエンス‼️シーツを巻いただけの裸のマルがウォーカーに屋上で追いつめられ、シーツだけはウォーカーの手に残り、中身のマルは落ちてしまうシーンもショボくて、合成感丸出しなんだけど忘れられない‼️クライマックスのアルカトラズ刑務所での対決シーンもシビれる‼️迫力十分なんですが、どこかシュールで冷たく切れ味のいいジョン・ブアマン監督の演出に、初見時、たちまちファンになってしまった事が鮮やかに思い出されます‼️もちろんウォーカーに協力するクリスをセクシーに艶演してくださってるアンジー・ディキンソン姉貴の魅力も絶大でした‼️
リー・マーヴィン、無駄に拳銃撃ちすぎ
やっぱり、リー・マーヴィン!
ストーリーの設計はヘンテコなのだが、ナゼか画面の中へ最後まで引き込まれる。
やっぱりリー・マーヴィンの魅力は特大級。
あの迫力ある最高のアクションはスクリーンでないとダメだろう。
ジョニー・マンデルの作った音楽も雰囲気とバッチリ。ハードボイルドも得意だったとはチョット以外。サントラあるかな?
そして、やはり60年代のフィルム撮影というのは、今更ながらやっぱりイイ。あの時代にしか出せない色味は勿論のこと、場面ごとのシーンの空気感まで見事に捉えていた。
フラッシュバックの唐突なインサートもこの頃の流行であるが、あそこまで多用されると一歩間違えばダメダメな外連味が出てきそうだが、
これもナゼか?この作品の必然に見えてしまうから不思議だ。たぶんノーランの『メメント』は影響を受けているのだろう。
その一方…
ラスボスの正体は途中でなんとなく分かるし、予告編で匂わせていたような現実と妄想が錯綜するような混沌とした展開も予想を下回る。
あの至近距離(Point-Blank)から数発も撃たれて助かる訳もないので、全ては主人公の死の間際の妄想と捉えるのが現実的とは思うが…
闇の中へとウォーカーがフェイドアウトしていった後、ズームインされるアルカトラズ島のラストショットは、そんなオチを示唆してるのだろうか?
と、いうことは…
『Point Blank』の”Point”とはアルカトラズの廃墟でもあり… “Blank“は、そこで亡霊のように消えゆくウォーカーでもあるという…
ダブルミーニング?
だとしたら、もうちょい、それを匂わせる伏線など、もう一工夫は欲しかった。
一応、女のセリフで「亡霊を追っかけて… その金で何するの?」なんてのはあったりするが…
というか、Point-Blankには、そもそも単刀直入や頭ごなし、といったような意味も含まれてるから、トリプルミーニング?
あと、思ってたほどの目眩くサイケ感もない。
色彩設定の拘りにゴダールの影響はありそうだが…
犯罪組織は徹底してグリーン。
ウォーカーは銀髪ヘアーでスーツもシルバー・グレー。
妻リンの服もアパートの室内もシルバー、その銀色が増幅する鏡面使いを多用。
妹クリスの方は金髪にハニートラップな予感の黄色い服。それに合わせて望遠鏡のカラーリングまで真っ黄色!などなど。
しかし、ヌーヴェル・ヴァーグ感は殆ど無い。たぶん即興的な会話が無い所為だろう。
というか、会話以前に、主人公のウォーカーは殆ど喋らず、説明的なセリフなど殆ど無い。
そのハードボイルドな抑制的な設定をベースとしつつ、ヌーヴェル・ヴァーグからの断片的な影響(他にも『突然炎のごとく』など)が本作の特徴とも言えるが…
正直、もっと上手く出来たのでは?トライした方向は面白かったが、ちょっと消化不良だったのでは?と少し欲求不満には思ってしまう。
これは同じように元ネタが好きすぎて、偏愛的にパクってしまう自由なタランティーノなんかを、もう随分前から観てしまっている所為なのかもしれないが。
とはいえ、しかし、なんだかんだで、全てのショットが抜群に本当に素晴らしい。
なんとも言いようのない独特の味わいがある。
不思議といえば不思議な映画である。
それにしても60sのファッションは、やっぱりイイ。
またミニのワンピースとかが流行ってもイイと思うんだけど。
暫くはないかな〜
25-093
異色な色彩ノワール
この映画はミニシアターで、たまに上映していたりします。リー・マービン主演だから刑事物と勘違いしておりました。ノワール(犯罪物)ですがサイケデリック・ノワールとも呼ばれてます。まぁミケランジェロ・アントニオーニ監督の「欲望(Blow Up)」に似ていなくもない。劇中に出てくるムービーパブでのレイパーカーJrもどきの音楽ライブがヤードバーズ(「欲望」に出演)のと重なるなぁ。この映画(ポイント)を意識したのは映画秘宝の雑誌連載に町山智浩さんが取り上げておりました。内容は忘れてしまいましたが、ウォーカー(リー)が幽霊説で裏切った妻リンを射殺したら猫に変身(?)と結構面白かったです。
この映画を観た感想はフラッシュバックを多用してる割には、あまり上手くいっていないような気がします。やっぱり脚本に問題があるのではないのでしょうか?
ラーメン屋さんで言えば麺が美味しいのにスープが追いついていない。
ただ「ダーティーハリー」で市長役をやっていたジョン・バーノンがウォーカーを裏切るリース役で出ていたのは良かったです。
オープニングの音楽も暗いですが、この映画の雰囲気に合ってますね。
映像はシャープで色彩が綺麗でした。ウォーカーが化粧品を溢した液体がドロドロとサイケデリックに輝くのは、この映画を象徴していますね。ウォーカーが海岸で覗く黄色い望遠鏡やクリス(リンの妹)のオレンジを基調とした部屋や組織の幹部カーターの緑色のオフィスなど、色彩心理を意識したのか意味が隠されていそうです。
色彩映画としてはゴダール「軽蔑」、ベルとルッチ「暗殺のオペラ」、小津安二郎「秋刀魚の味」に並びうるのではないでしょうか。
プアマン監督の「未来惑星ザルドス」と同じく傑作ではないけれど愛すべき作品ですね。
リー・マービンを愛で観る作品
全編クールなハードボイルド! 金と復讐に執着する男・寡黙なリー・マービンがめっちゃカッコイイ。
全編クールなハードボイルド!
金と復讐に執着する男。寡黙なリー・マービンがめっちゃカッコイイ。
いきなりぶっぱらす拳銃の迫力。
ひたすら男の胸を借りて殴り続けるシーンなど、アンジー・ディキンソンが魅力的。
(アンジーといえば「女刑事ペパー」!海外TVドラマブーム下、毎週家族で観ていた。)
閉鎖後初の映画撮影となったアルカトラズ刑務所や、巨大用水路など、ロケも殺伐とした風景、冷たいコンクリート基調で統一されている。
時代を反映した美術、テーマカラーで統一された女優の服装と、近代的で洗練された冷たい室内デザイン、挿入されるサイケなイメージもクール。
ラスト、あれだけこだわっていた金を取り戻さず消えてしまう男。
最後まで寡黙でイケてる。
実験的ハードボイルドは標的を大きく外れて
今時なぜリバイバルされたのか、よく分からない犯罪もので、当時としてはニューウェーブな作品を狙っていたのかもしれないけど、空振り感が強いです。組織の金の強奪に成功したものの、仲間と女房に裏切られ撃たれてしまう男の復讐劇で、主演はリー・マービンと来たら期待は高まるけど、脚本が穴だらけのご都合主義満載でつまらない出来でした。主人公が単身、組織の幹部を次々とやっつけるのに、敵もあんまり警戒していなくてあっさりやられ過ぎです。所々、過去のフラッシュバックやサイケな画像が挿入されたりするけど、それで主人公が苦しむわけでもなく、あまり意味が感じられませんでした。ファッションやカメラの構図もただ気取った演出のような気がします。役者では、若い頃のリー・マービンが見られたのはよかったけど、もったいない使われ方でした。
1967年の映画ですが、なぜか退屈するシーンは一瞬もありません。音も映像も色彩もファッションも、すべてがスタイリッシュ!
以下はyoutube「Point Blank (1967) | The Documentary/The Tapes Archive」から得た情報です。
海兵隊の兵士だった若きリー・マービンは1944/6/18に南太平洋で日本軍の待ち伏せ攻撃に遭い、マシンガン掃射による瀕死の重傷を負った。247人中生存者はたった6名という激戦だった。その後PTSDに苦しみアルコールに溺れた。生き残った罪悪感と内なる葛藤が演技に影響を与えている。
MGMとの契約により、監督のジョン・ボーマンと主演リー・マービンは本作をほぼ完全なコントロール下におくことができた。
ストーリーは断片的で、非線形で、意図的に夢のようなシーンが挿入される。主人公のキャラクターは疎外され孤立無援の男であり、企業や組織のエリートと対立する一般人に設定されている。ヘイズ・コードによる脚本の検閲により、使用禁止ワードや暴力シーンを削除されたが、「成人向け推奨」でやっと製作の許可が出た。本作はヘイズ・コード廃止のきっかけの一つとなった。
当初ロケ地はサンフランシスコを予定していたが、荒涼とした冷たい映画である本作にふさわしくないという監督の意見でロスアンゼルスへ変更となった。1963年に閉鎖されたサンフランシスコのアルカトラズ刑務所で撮影された最初の映画でもある。
前の日にエラ・フィッツジェラルドと飲みすぎたため、リー・マービンが撮影初日をドタキャンした。ボーマンは激怒してホテルの部屋を破壊した。
スタントマンが海の水が冷たいと文句をいったため、リー・マービンは自分でスタントシーンも演技した。そのためリー・マービンはスタントマンのボーナス報酬をもらっている。
監督のボーマンは当初モノクロで撮ろうとしていたが考えを改め、初めてカラー映画を撮影した。色を使用して物語を語り、感情を呼び起こす革新的なアプローチを採用し、シーンごとにテーマカラーを決めた。
カーターのオフィス:緑(金を持っている)
姉リン:シルバーグレーとメタリックブルー(冷たく無菌的な死のイメージ)
妹クリス:黄色とオレンジ(暖かさ)
監督のボーマンは色彩へのこだわりについて「アンジーの髪の色をドレスと同じ色にしたいという狂気じみた考えを持っており、それを実現するために髪を3回染めさせた」と語っている。
撮影監督ラスラップはそれまでメインだった大型据え置きのミッチェルカメラではなく、小型で機動力のあるエアフレックス(Arriflex)カメラを使用した。レンズはシネマスコープと呼ばれる横長の映像を撮影するためにPanavision C シリーズanamorphic 40mmを採用した。
すべてのキャストに隠しマイクを装着した初のメジャー映画である。125個の特注ワイヤレスマイクを使用し俳優は自由に動き回れるようになった。不要な背景ノイズが大幅に減少し、自然で臨場感あふれるサウンドスケープが実現した。
ウォーカーとリースの関係は隠に同性愛を示唆している。ウォーカーは本作の中で直接殺人を犯していない。撃たれる前は黒髪、その後白髪に変わっている。金を奪わずに影の中に消えていくラストシーンからウォーカー幽霊説、ウォーカー冒頭で死亡説などの解釈がある。本作は6人の観客がいたら6通りのストーリーを語ると評された。
編集段階でMGMの上層部が介入してきたが、スーパーバイジングエディターであるマーガレット・ブースの鶴の一声で介入が阻止され監督の編集権が守られた。
ジョニー・マンデルはアルカトラズ刑務所の地下室で、何十年も放置され調子の狂ったピアノを見つけ、それに触発されてシュールで断片的なスコアを書いた。
リー・マービンの実生活上のパートナーだったミッシェル・トリオラもかつて服毒自殺を図っており、その経験がリー・マービンの演技に影響を与えた。
公開後の批評家の評判は芳しくなかった。興行収入は1967年のトップ100中32位であり、同年公開、リー・マービン主演のThe Dirty Dozenに負けた。
ブルースターのプール付きの豪邸は1966年にビートルズが滞在している。2002年にドリュー・バリモアが300万ドルで購入し、2018年に1600万ドルで売却している。
リー・マービンとジョン・ボーマンは終生友人関係にあった。リー・マービンの死後、未亡人がボーマンに形見分けをする際、ボーマンはマービンが本作で履いていた13サイズの革靴を選び、現在インディアナ大学のボーマンアーカイブに保管されている。
はっきり言って見づらく面白くありません。
1967年の作品。50年近く前のものである。今回、初見なのだが多分、当時観たとしてもあまり面白くなかったであろう。
まずタイトル。原題は「Point Brank」で直訳だと「至近距離」となるのだろうが意味不明。クレジットされている通りベースになっている小説は「悪党パーカー 人狩り」である。ただし原作者との間で何があったのか、そもそも主人公の名前さえ「ウォーカー」に差し替えられている。
1999年のメル・ギブソン主演の「Payback」も同じく「人狩り」を原作にしているが、Paybackは自分の取り分を支払ってもらう、という意味合いなのでストーリーをなぞっているとはいえる。
因みに、パーカーものの映画化最新作はジェイソン・ステイサム主演の2013年「PARKER/パーカー」なのだがこれは「人狩り」ではなくウエストレイクのずっと後の小説「悪党パーカー地獄の分け前」を原作としている。「分け前」がたまたまタイトルで重なるのは悪党パーカーシリーズは、悪事の収益を仲間内で奪い合う話が多いからだろう。
さて本作だが、カットバッグを多用してネオ・ノワールの作品群の中で差別化しようとしているものの、ごちゃごちゃしていて見づらいだけで何ら効果は上がっていない。そして音楽がやたら喧しい。また主役のリー・マービン始め、登場人物が陰気臭く全然魅力的に描けていないこともあり、はっきり言って面白くありません。パーカーものだと先に述べたジェイソン・ステイサムのものが一番、スッキリした出来上がりですね。
フラッシュバックを多用した実験的犯罪映画。アンジー・ディキンソンのタコ殴りに震えよ!
最初に言っておくと、シネマート新宿で売っているパンフレットが、異様なボリュームと内容の異常な濃さで異彩を放っていて、どう考えてもお買い得すぎる(笑)。
ちょうどアメリカン・ニューシネマの時期に、ヌーヴェルヴァーグやイタリア芸術映画の強烈な影響のもとに製作された「遅れてきたフィルム・ノワール」としての本作の特異な立ち位置を、あらゆる観点から精査し、語り尽くす、かゆいところに手の届くパンフレットだ。
執筆陣も、押井守に滝沢誠、江戸木純、渡辺幻と豪華で、公開時のパンフにあった川喜多和子の貴重なルポも再掲している(リー・マーヴィン&ジョン・ブアマン監督の来日時のルポ。この映画のあと両者は、三船敏郎と組んで戦争映画『太平洋の地獄』を撮る。その打ち合わせに日本に来たときのエピソード。リー・マーヴィンがいかに自分の出ている映画をきちんと理解して語ることの出来るインテリかがひしひしと伝わってくる)。
たとえこの映画を動画配信で観たとしても、60年代~70年代の犯罪映画がお好きな方なら、パンフだけでも買いに行って損はない出来だと思う。
― ― ― ―
僕個人はジョン・ブアマン監督にはそこまでの思い入れはないが、リー・マーヴィン(『北国の帝王』のホーボー・キング!)もアンジー・ディキンソン(『殺しのドレス』の姥桜!)も大好きな俳優さんなので、全編を通じて楽しんで観ることが出来た。
映画の紹介としては、パンフで引用されているマーティン・スコセッシの評価が簡にして要を得ている。いわく「ヌーヴェルヴァーグのストーリーテリングの革新――衝撃的な編集、フラッシュフォワード、表現の抽象化――を初めてクライム・フィクションに応用し、ジャンルを再定義した作品」。まさにそういう映画だ。
個人的には、ひとつだけどうしても強調しておきたいことがある。
とにかくアンジー・ディキンソンが、リー・マーヴィンに侮辱されたと感じて、彼の胸を叩きまくる中盤のシーンが、最高に素晴らしい!!
このシーンの映像的な完成度とリズム取りの完璧さについては、もっと取りざたされてもいいくらいではないか? これぞ計算され尽くした、美しき暴力のコレオグラフィ。
私的には、『裸のキッス』(64)の冒頭シーンと同じくらいのインパクトがあった。
このシーンを観るためだけでも、『ポイント・ブランク』はじゅうぶん視聴に値する映画だと思う。
― ― ― ―
アヴァンに出てくるウォーカーとマルの最初のシーンから、この映画が一筋縄ではいかない作品である空気はビンビンに漂っている。
親友に犯罪ほう助を依頼するにしては、あまりに過激で顔の近い暑苦しい説得ぶりからは、容易にホモセクシュアルな関係性を想起させられるからだ。
このあと、一人の女を二人の親友が取り合うトリュフォーの『突然炎のごとく』(62)、ゴダールの『はなればなれに』(64)、ロベール・アンリコの『冒険者たち』(67)あたりと酷似した、ウォーカーとマルのリンをめぐるさや当てが展開するが、これはヘテロの皮をかぶった男と男の駆け引きであって、マルが「本当に気を惹きたい(&マウントを取って滅ぼしたい)愛憎半ばする相手」は、ウォーカーなのだろう。実際、ウォーカーからリンを奪ったあと、マルはリンの元を去っている。気が済んだからだ。
そう考えれば、冒頭のウォーカーをいきなり裏切るシーンも、マルからすると必然だったのだろうと思う。最初から「仲間に引き入れて」「相手が骨なしだと断じて」「その場で射殺して」「リンを奪い去る」というのが、マルの最初からの計画だったのではないか。
そうして、ウォーカーを滅ぼしたい。ウォーカーに勝ちたい。
それくらい、マルはウォーカーを愛し、ウォーカーに執着している。
この関係性が逆転するのが復讐パートに入ってからの展開で、ウォーカーが「マルのいないリンのベッドをいきなりマグナムで撃ちまくる」シーンは、アヴァンのマルからいきなり2発撃たれるシーンと対になっているし、ペントハウスに侵入したウォーカーと裸のマルの絡みなどは、そのままホモセクシュアルな隠喩に満ち溢れている。
ウォーカーのマルに対する執着と憎悪と破壊衝動もまた、もともと根っこのところにあった愛情の裏返しといっていいだろう。
パンフによれば、マルを演じたジョン・ヴァーノンは、リー・マーヴィンに触れられることを極度に嫌がり、撮影の進行が滞った。業を煮やしたリーがヴァーノンのパンツをはぎ取り、尻の穴に足を一発みまった。ヴァーノンは泣きながら監督に「リーが、リーが……」と訴えたという。
ウォーカーがマルを葬った時点で、ホモセクシャルな潰し合いの物語としての『ポイント・ブランク』の核心は、すでに終わっているといっていい。
そこから続く「9万3千ドル」に執着する終わりなき悪夢の如き復讐劇は、あたかもウォーカーの心にぽっかり空いた穴を埋めるための長いコーダのように思える。
― ― ― ―
『ポイント・ブランク』で描かれる復讐劇全体が、冒頭のシーンで友に撃たれて死んだウォーカーが死に際に観た「夢」であるという解釈も、作品の夢幻的な構造上、十分に成立すると思う。実際、ジョン・ブアマン監督自身が初期にはその解釈について肯定的な反応を示していたらしいし、当のウォーカー本人がアヴァンで「これは夢、夢だ……」とつぶやいている。さらにはアンジー・ディキンソン演じるクリスも、ウォーカーと別れ際に「あなたはアルカトラズで死んだのよ、間違いなく」と言う。
本作のウォーカーが、裏切られ傷ついた男の怨念の化身だとすれば、その魂を復讐の荒野へと駆り立てるヨストは、さしずめメフィストフェレスのような存在だ。彼の魂は、夢のなかで裏切った妻を(自分の責任ではない形で)死なせ、裏切った友を(自ら手を下す形で)殺し、失った金を追って組織の上層部を次々と屠ることでプライドと暴力的衝動を充足する。ラストで、あれだけ執着していた9万3千ドルを手にしないまま、闇のなかに溶けるように姿を消すウォーカー。あれは(現実だとすれば)危機に際して発揮するウォーカーの嗅覚の鋭さを示すシーンであると同時に、(夢だとすれば)復讐を果たして幹部連中を次々に抹殺することで、いつしかウォーカーの魂がすでに「成仏」しかけていたのだともとれる。
彼の魂は、悪夢のような「地獄めぐり」を経て、いつしか充足したのだ。だから、成仏した。そういう映画だととらえることは、じゅうぶんに可能だろう。
その意味では、本作もまた『ベン・ハー』『時計じかけのオレンジ』『ジェイコブズ・ラダー』『神々のたそがれ』『異端の鳥』といった作品群と通底する「地獄めぐり映画」(自らの悪行や恐怖を追体験することで魂が浄化され転生するまでの過程を描く、ダンテ『神曲』の伝統をベースとする映画)だといっていい気がする。
それと、他にも似たような定型にのっとった復讐劇は腐るほどあるのだろうが、最近初めて観たということもあってか、僕はこの映画の組み立てが、サミュエル・フラーの『殺人地帯U・S・A』(61)にとてもよく似ていると思った。
復讐のためにマフィアの上層部を追い詰めていく過程で、小物っぽい男や、大企業の社長風の男や、得体の知れない殺し屋を順に相手にして、最後はプールのある大邸宅に押し入ることになるあたり、両作のストーリー展開はほぼ同一のラインを辿っている。
いかしているが少し病んだ女が出てきて、復讐劇と恋愛模様がいっとき交錯するところや、マフィア内部の抗争を巧みに利用して『用心棒』のように相手どうしで殺し合いをさせるところも、両作に共通する要素だ。
あとは、アルカトラズに始まり、フォート・ポイントで終わる「男2人と女1人」のノワールという意味では、刹那的なエンディングも含めて、先に名前を出したロベール・アンリコの『冒険者たち』とラストのロケーションがやたら似ているのが気になる。
『ポイント・ブランク』と『冒険者たち』は同じ1967年の公開だから、直接の影響関係はないだろうとは思うが、ヌーヴェルヴァーグの流儀に強く影響を受けた英仏の新進監督が、恋のさや当てに始まり要塞での銃撃で幕を閉じる、似たような映画を撮っているのはじつに興味深い。
― ― ― ―
『ポイント・ブランク』には、一見して忘れがたいシーンが多い。
以下、羅列する。
●冒頭のアルカトラズのシーン、最初のうち「なんでわざわざ監獄で犯罪組織の金の受け渡しとかやるのかな?」「リー・マーヴィン以外誰もいないけどなんで?」とか思って観ていたのだが、だいぶ経ってから「ああ、もうここはとっくに監獄としての使命を終えた、ただの観光名所として出てきているんだ」ということに気づいた。
●アヴァンのあとのタイトルロールで、鉄条網のうえにまたがるリー・マーヴィンが出てくるのだが、静止画かと思いきや、後ろのトンビのような鳥はふつうにぐるぐる飛んでいる。ささいなシーンだが、不思議な感興を与えるショット。
●奥さんの家に押し入るやいなやベッドに向かって銃を乱射するシーンは、まさに本作を象徴する名シーンといえるが、彼が洗面所の棚から払い落とした薬品や化粧品やモンダミンの原色の中身が、ぐちゃぐちゃのマーブル状のたらしこみのようになって排水溝に流れていくカットも、かなり強烈な印象を残す(パンフレットの裏表紙に使われていて、さすがのセレクトだと感心)。
●「ムーヴィーハウス」における「乱痴気騒ぎ」と「乱闘」の合わせ技も、いかにも『ポイント・ブランク』らしい素晴らしいシーンだ。黒人歌手が奇声をあげている背景のスクリーンには泰西名画が映し出され、気づいた範囲ではルーブルにあるルーベンスの『ユノに欺かれるイクシオン』やレンブラントの『ダビデ王の手紙を手にしたバテシバの水浴』、ボッティチェリの『男の肖像』などが映っていた。女優の写真と交互に映っていたのもボッティチェリか?
●黄色で統一されたクリス(リンの妹=アンジー・ディキンソン)の部屋をウォーカーが訪れるシーンから、緑色で統一されたカーターの部屋をマルが訪れるシーンへと移る対比の妙。黄色い望遠鏡。クリスが黄色いコートを脱いだら黄色のボーダーの服。でガウンに着替えたら真っ赤っ赤(笑)。アンジー・ディキンソンの衣装は、このあとの登場シーンではオレンジで、最後まで華やかだ。
●アンジー・ディキンソンが必死でリー・マーヴィンの胸を叩きまくるシーンの素晴らしさは先述したとおりだが、そのあとの一連の「嫌がらせ」シリーズからベッドインまでのテンポ感や呼吸も練り上げられている。
「私の姓は?」「俺の名前は?」のやりとりは、たとえ肉体関係を持っても、お互いに対する理解や共感とは程遠い男女の殺伐とした距離感をうまく表した名シーンだ。
●フォート・ポイントでのラストシーンから、カメラはぐっと上昇して、海を隔てたアルカトラズをアップで映して終わる。こうしてウォーカーの魂は、もといたアルカトラズの独房へと帰ったのだ。
●原作はドナルド・E・ウェストレイクが「リチャード・スターク」名義で執筆した小説「悪党パーカー/人狩り」(原題は『The Hunter』、1962年)。もともとはニューヨークが舞台の小説で、それをサンフランシスコ(冒頭とラスト)とロサンジェルスに舞台を移し替えている。大筋はだいたい一緒だが、細かい設定や展開はかなり大胆に変更されている印象。
ちなみに、同じ原作をもつメル・ギブソンの『ペイバック』(99)は未見である。
●パンフによれば、2017年に英国映画協会が『ポイント・ブランク』50周年を記念して、「時間を歪め、断片化する5作品」を掲載した。いわく、
ニコラス・ローグ他『パフォーマンス/青春の罠』(70)
アラン・パーカー『エンゼル・ハート』(87)
スティーヴン・ソダーバーグ『イギリスから来た男』(99)
クリストファー・ノーラン『メメント』(00)
デイヴィッド・リンチ『マルホランド・ドライブ』(01)
なるほど、いずれも語り口に共通性がある本作の「後継映画」揃いだよね。
独特の編集と美意識に中毒性があるハードボイルド
「1967年の作品アメリカ映画が変わる時」
"黒幕"
謎
全19件を表示