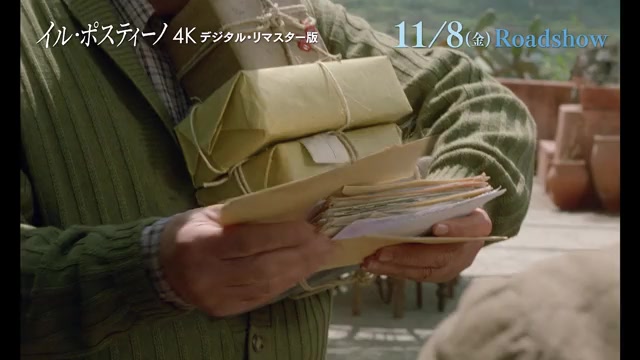イル・ポスティーノのレビュー・感想・評価
全54件中、21~40件目を表示
歴史的名作! 4K修復のこの機会に見て良かった!!
見終わったあとも余韻が消えず、心に深く刻み込まれる作品でした。舞台のイタリアの小さな島、純朴な主人公マリオの成長、世界的詩人パブロ・ネルーダとの交流を通じて、言葉が人に与える力を鮮やかに描き出しています。
1. 郵便配達人──「言葉」の架け橋
主人公マリオが郵便配達人としてパブロ・ネルーダに手紙を届ける役割は、時代や場所の象徴そのものです。ラジオもテレビもましてやインターネットもない島では、手紙が唯一の世界とつながるメディアです。
マリオが手紙を届ける行為は、詩人ネルーダにとっても外界との接点を保つ重要な仕事です。マリオはネルーダとの交流を通じて、表現を学んでいくことになります。
2. 主人公の成長と「詩」の力
物語の核は、主人公マリオの成長です。無口で未熟なアラ30未婚男性だった彼が、ネルーダとの交流を通じて詩の技法「隠喩」を学び、表現を得ていく過程がとても感動的でした。詩人としてのネルーダがただ一方的に教えるだけでなく、マリオ自身の純朴な感性がネルーダの心をも動かしていく対等な関係もまた見どころです。
主人公は表現の獲得によって恋を実らせるだけでなく、それは同時に自分の島の美しさや人生の意味に気づくことにもつながっていきます。言葉とは表現の手段であるとともに、自分の内面に感動を生み出すものでもあるということを教えられた思いです。
3. 主演脚本のマッシモ・トロイージのその後
この映画を語るうえで、主演・脚本のマッシモ・トロイージの存在を欠かすことはできません。彼は心臓病を抱えながらも、手術を延期してまで撮影に挑み、撮影終了直後にその命を落としたことを、見終わってから知りました。
彼の命懸けの挑戦が、映画に込められたテーマ「表現を獲得すること」と深くリンクし、この作品が、彼の遺言でもあり、生きた証でもあり、世界に残した貢献でもあることに衝撃を感じています。
映画を観た後に彼の背景を知ったことで、作品の余韻はさらに深くなり、感動と切なさが入り混じった特別な一本になりました。
4. 人に何かを「伝え残すこと」の意味
『イル・ポスティーノ』は、単なる物語以上のものを観客に届けてくれる作品です。「何かを誰かに伝え残すことの意味と価値」とは何か。それが受け取った人に与える勇気や人生への気づき、人とのつながりへの感謝。
マッシモ・トロイージの人生そのものが映画に重なっており、この作品は観た人それぞれの心に「言葉」として残り続けるものだと思います。
ポエジア 詠まれなかった詩
人が思わず詩を口ずさんでしまうのはどんな時だろう。愛しい人を想うとき、故郷の海の香りをかいだとき、さざ波の音を聞いたとき、まぶしいばかりの日の光に照らされたイタリアの故郷の大地を想うとき、そしていとおしい映画を見たとき、そんなときに人は心に詩が浮かんでくるのかもしれない。万物を感じ取る心があるのなら誰もが詩人となれるはず。
実在のチリの詩人パブロ・ネルーダが母国を逃れ、青の洞窟で有名なイタリアのカプリ島で暮らしていた事実をもとにした物語。
ネルーダは常に素朴な人たちのために詩を詠んだという。外交官でもあり共産主義者でもある彼は資本主義が生みだした貧困に苦しむ祖国の人民のために戦った。その波乱万丈の人生においてひと時の安らかな時間を彼はイタリアの小島で過ごし、そこで一人の郵便配達員と交流を重ねた。時が止まったかのようなのどかな島でネルーダは心豊かにその時を過ごせたことだろう。
漁業以外産業のない貧しく小さな島で数少ない読み書きができたマリオはネルーダ専属の配達員となる。日々の配達の中でネルーダと交流を深め次第にマリオは詩に魅了されていく。そして彼はネルーダの思想を受け継いでいく。
共産党の集会でマリオはネルーダから学んだ成果として詩を読み上げるはずだった。しかし弾圧により彼は帰らぬ人となってしまう。それを知ったネルーダはイタリアの弟子を想いただ彼を悼む。
マリオの遺したテープには島のあらゆる自然の営みの音が残されていた。それはそのまま詩に書き替えられるために残された島の記録。それを聞かされたネルーダはマリオとの想い出、そしてこの島でのひと時の暮らしを想い詩を詠んだことであろう。
そんなネルーダもチリで起きたクーデターにより命を落としてしまう。世界初、無血で民主的に社会主義国となったチリではあったがアメリカの謀略によるクーデターにより人民の希望は打ち砕かれてしまう。その後チリは独裁政権により多くの人民が虐殺され、暗黒の時代を迎える。世界初の新自由主義の実験場とされたチリはさらに貧富の差が激しくなりネルーダが目指した人民のための国の建設の夢は打ち砕かれる。
近年、バイデン政権下で当時の機密事項が公開されこの時のアメリカの詳細な関与が明るみになり、病死と言われていたネルーダの死も毒殺だったという事実が明らかとなった。
西欧諸国の植民地支配による搾取に苦しめられてきた人民のために戦ってきたネルーダの詩は同じく人民のために戦う革命家たちにも愛されてきた。キューバ革命のチェ・ゲバラも彼の詩を好んで読んでいたという。
資本主義的帝国主義に抗い続けたネルーダの精神は今も多くの人々に受け継がれている。
本作に入れ込みマリオ役を演じたマッシモ・トロイージの執念が本作を名作たらしめた。劇中でマリオが命を落としたように彼も撮影終了後の12時間後に帰らぬ人となる。心臓病を患いながら撮影に挑んでいたのであった。
革命に命を懸けたパブロ・ネルーダ、そして彼の物語を命を懸けて紡いだマッシモ。そんな映画にかかわった人々の魂が本作を名作たらしめたのだった。
私にイタリア映画は向かないことがよくわかった
世間的に大絶賛されてる「ニュー・シネマ・パラダイス」しっくりこなくて脱落してる私
他の映画のために立ち寄った映画館で、著名人の方々が絶賛していた本作のポップを見て、これは見ておかないと!と足を運んだ
でも……何だか、しっくり来ない
ヤマザキマリさんがイラスト描いて褒めちぎっていた中年ニートのどこか足りない主人公に魅力を感じないし、詩人もいけ好かなくて、佇まいも何だかなぁ…どこか生々しい。詩人の奥さんが脇で無駄に色っぽくて、片田舎の閉鎖的な生活なのに、バカンスで遊びに来たようにしか描かれないのはイタリア映画だからか?
主人公が唐突に一目惚れする居酒屋の女性も無駄に色っぽくて美しすぎる。主人公のような朴訥な中年ニートに言い寄られて喜ぶタイプにはとても見えない。あれだけ美しいなら、さっさと都会へ行っている。居酒屋の女将があんな男は駄目!と怒ってたけど、私も深く深く同意する、私だって嫌だ
でも本作の筋立ては好きなので、日本の役者に置き換えてみると、もうちょっとシックリする気がする
詩人は火野正平さんのようなちょっと茶目っ気があって、先の見えない亡命生活に愚痴も言わず、酸いも甘いも噛み分けた男性
詩人の妻は…風吹ジュンさんのような可愛げがあるけど、夫の政治的亡命に従うこともいとわない、どこか芯がある女性
主人公は若いピュアな青年に…例えば「海に眠るダイヤモンド」の神木隆之介さん、居酒屋の女性は杉咲花ちゃんとか!(笑)
(話が逸れました)
他の方のレビューにも同じような意見があり、ちょっと安心しました
「ライフ・イズ・ビューティフル」はとても好きだったんだけどなぁ〜。多分イタリア映画は私には合わないんでしょう
お好きな方、申し訳ありません
美人!
「いんゆ活動」に笑って泣いた2時間です
谷川俊太郎さんが亡くなった。
「芝生」って好きだ。沁みる。
詩人って、どうやって暮らしているんだろう。
郵便配達のマリオも、きっと素朴にそう思ったんだろう。
むかし、新宿の地下道で、
「私の詩集」と書いた札を胸元に持って、動かず語らず、まっすぐ円柱の前に立っている女性を見た。
周りを大勢の人間が川のように流れているのだが、そこに一人だけ動かずに立っている人の影は、目を引く。
一瞬立ち止まり、雑踏の中、その人に近付いて、彼女は何も言わないから僕も言葉無しで「指を1本」差し出して、お金を渡した。
粗末な わら半紙の手製のしおりを彼女の手から受け取ったし、僕はそれを読んだはずなのだが、その中身については何も覚えていない。
ただ、詩人に会ったその夜のことだけが残った。
・・・・・・・・・・・・・
「詩」を書いてみたいと思ったマリオは、
詩人パブロ・ネルーダへ配達する「ファンレターの大きな束」と、それを受け取っている「詩人」という人種に興味を持ったわけだ。
近付いて、もじもじと声を掛けるところから、人と人には心の関係が出来るし、交わす言葉は手紙となり、そしていつしか、人は詩になる。
プータローの困ったちゃん、=モラトリアムの息子が、
とにもかくにも無職から脱するために、自転車を押して叩いたのが郵便局のドアだった。
恋を囁くために学ぶ「隠喩」とは?
外国語を習得するためにはラブレターを書くのが最適と云うではないか。
その“必要”を見つけて向学心に燃えたマリオが、誠に可愛らしいのだ。
教えを請うて詩人を訪ねるうちに、彼の人生の扉とコトバのドアも開いてゆくのだ。
・嫌々の就職
・詩人との邂逅
・マニュアル購入
・下心だけでの詩作スタート
・ベアトリーチェへの求愛
・島を出る
マリオと師匠パブロのやり取りの変化が、目を見張らせる。
夢中になって郵便配達人に極意を伝え始めるパブロの背中が踊っている。
弟子マリオの語彙発見のセンスに一瞬驚き、そのマリオから言霊を授けられるシーンに、我々も惹きつけられる。
二人はついに同志の関係になっていた。
そうして
とうとう海辺で、初めて吟ずるマリオの愛の詩をあなたも聞いてくれただろうか・・
あの海の泡から生まれる「詩人の誕生」に、僕はベアトリーチェならずとも、応援していただけに、なんだか感激してしまって、押さえようもなく 涙がこみ上げてくる。
溢れ出すコトバは、その人、そのものなのだ。
映画は冒頭
小さい入江に入ってくるバルケッタ(小舟) の姿、
鳴り出だすアコーディオンとギター。
風の中を走る自転車のシーンから物語は始まった。
主演のマリオはクランクアップのその日に、本当に急死してしまったそうだ。
共演者・スタッフたちが、どんだけ大泣きしただろうかと思う。
イスキアだろうか、カプリだろうか、島の陽光と海がただ眩しい。
桃色の邸宅で、そして波打ち寄せる浜辺で、
僕らも人生を謳って、詩人にならずにいられようか。
・・・・・・・・・・・
メモ
あの「シネマ・パラディーソ座」のアルフレートに再会できたこと。飛び上がって喜んだ映画ファンは、世界中に大勢いたはずだ。
飲み屋のマンマたちが、またとっても良い!
そして、人間のすべてがしみじみと切なくて温かい。
ビバ・イタリアーナ!
チンザノ買って帰りますね。
ミ・アモーレ、東座の合木社長
いい映画をありがとう♪ 大好き。
・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・
付記、2024.12.2.
感想が止まりません ―
「中央から隔絶された離れ島」という設定は、チリやモスクワやローマでのあの厳しい政治的闘争からは、地理的にも精神的にも遠くに置かれた島の住民たちの「ローカルなストーリー」を成立させるための手法であるかも知れません。
外界からのニュースは、新聞やニュース映画でしか入ってこない彼ら。その彼らにとっては、政治のスローガンは遠い世界でのおはなし。(島民は水道が欲しいだけなのですから)。
しかしラストで一瞬だけ映る残酷な光景・・
「純朴な詩人が大都会ローマ?に出て行って、そこでまさかの死に巻き込まれる」シーンは本当に胸が痛かった。
「詩作」を教えてしまったがために、結果、あろうことかマリオを死なせてしまったチリの政治犯=パブロの、海岸での悔悟と哀惜の表情が、本当に辛い結末でした。
木訥な郵便屋さんの話
初見で、この作品
5つ星以外考えられない、魂のこもった名作に再会できた喜び
28年前に劇場で観て好きすぎた『イル・ポスティーノ』
4Kで今また劇場で再会できるなんて、最低二回は観ないと、と先週は恵比寿と今日は有楽町で鑑賞。
書きたいことがありすぎるから、ただ一言だけ書きたいです。
この映画を、どうか見逃さないでくださいね。若い人にも観てほしいな、と思いましたが、結構若い人がいたので嬉しかったです。
人生を豊かにするものを観てほしいです。
「何でこいつが俺より先に…」 by E・モリコーネ(うそ)
実在したチリの詩人のイタリア亡命時代を元に描かれたヒューマンドラマ。
反体制の知識人が政治的迫害によって移り住んだ僻地で地元住民と交流するという物語の骨格は、F・ロージ監督の『エボリ』(1979)と似ているが、神すら降臨を躊躇する荒涼たる寒村に流刑されるドン・カルロと違い、本作のドン・パブロは妻を伴って亡命してきたナポリの小島でワインを嗜みながらタンゴのレコードに合わせてダンスに興じるなど、何だかバカンス気分。
一方で、観終わったあとに宗教的感動にも似た不思議な余韻を味わえる『エボリ』に対し、本作では予想外の結末が用意されている。
チリ出身の実在した詩人パブロ・ネルーダに扮するのはフランスのベテラン俳優フィリップ・ノワレ。『ニュー・シネマ・パラダイス』(1989)の映写係アルフレードとは異なる役柄の知識階級を優雅かつインテリジェンスに演じている。
家業の漁師を継ぐことを嫌っていた地元の男性マリオは文字が読めるおかげで、亡命中のネルーダ宛てに世界各国から集まる膨大な郵便物を届けるための彼専属の配達夫として雇われることに。
当初は相手にしていなかったマリオの感性に気付いたネルーダは彼に詩作の手ほどきをし、マリオは次第に詩藻を開花させるが、彼のなかで目覚めたのは詩のセンスだけでなく…。
マリオとネルーダの心の交流や、島の美しい娘ベアトリーチェとのロマンス、許されて帰国が叶うネルーダとの別れなどの人間模様が南イタリアの眩しい陽光の下、穏やかに紡がれるので、ラストのマリオの悲劇は唐突な印象。
ネルーダの影響で共産思想に傾倒していったマリオが共産党の集会で詩の朗読を試み治安部隊の暴行を受け死亡する結末は、チリに帰国後ピノチェト政権によって虐殺同然に命を奪われるネルーダの暗喩なのだろう。
作中のネルーダはマリオの詩の才能に着目するあまり、自身に感化されて彼が左翼思想に芽生えたことに気を払っていない。
妻に捧げた詩をベアトリーチェとの逢瀬で使ったマリオを咎めた際に、「詩は創った人のものではなく、詩を必要とする人のためにある」と反論されたネルーダは一本取られたぐらいの反応しか示していないが、マリオのこのセリフは彼が共産主義に目覚めたことの証左でもある(詩の箇所を物質的な価値の言葉に置き換えれば分かりやすい)。
素朴な演技でマリオの純朴さや一途な人柄を体現したマッシモ・トロイージが本作の撮了12時間後に他界した逸話は有名。結果的に本作は実在のネルーダだけでなく、トロイージへのレクイエムにも。
ラストシーンで後悔に苛まれて海辺をさまようネルーダの姿は、トロイージを作品に殉じさせたことへのM・ラドフォード監督自身の自責の表明にもみえる。
作品に抱く感慨は人それぞれだろうが、自分はこの映画のラストがS・レオーネ監督の『夕陽のギャングたち』(1971)と、どうしても重なってしまう。
亡くなったトロイージの主演男優賞を含め、本作は複数の部門でオスカーにノミネートされたが、最終的には作曲賞のみ受賞。
音楽を担当したのはルイス・エンリケ・バカロフ(媒体によって名前の表記がさまざまだが、作品のオープニング・クレジットに従えば上記どおり)。
アルゼンチン出身ながら人生の大半をイタリアで過ごした彼はマカロニ・ウエスタンのサントラで多くの傑作を残し、共作もあるエンニオ・モリコーネとは師弟関係(だったと思うんだけど、今SNSで調べても詳しい話出てこなくて…。でも、使い回しのマエストロぶりはモリコーネ譲り?!)。
本作以前のバカロフの実績を知る人に「ほかの代表作は?」と訊けば、おそらく多くの人が択ぶのが「続・荒野の用心棒」(1966 原題 Django)。
短期間に低予算で製作され本来ならB級映画扱いの筈が、タランティーノをはじめとする多くの映像作家に愛され、ついにはリブートのTVシリーズまで登場した作品の魅力の一つは間違いなくバカロフが作曲したサントラにある。
同作に提供した哀愁漂う主題歌や情念まみれの曲と異なり、本作ではバンドネオンなどのタンゴの要素を採り入れた軽快で抒情豊かなサウンドを、波の音やウミネコの鳴き声などの効果音と調和するよう過剰にならない範囲で使用している。
悲劇的な結末で作品が暗い印象になるところを美しい音楽で和らげている点も、『夕陽のギャングたち』(モリコーネが作曲を担当)に通ずる。
本作でバカロフがオスカーを受賞したことを知って「モリコーネより先に?」と思ったのは、自分の率直な感想。
2017年没。
五歳年下のバカロフの訃報に接して、「何でこいつが俺より先に…」とモリコーネが思ったかは不明。
4Kデジタルリマスター版で久しぶりに観賞。
作品の性格上、セリフ過多なので、字幕が顔のアップに重ならないよう、もう少し工夫して欲しかった。
24-133
「詩は必要としている人のもの」なのか?
マリオがパブロの詩を使ってベアトリーチェを口説いたのが最後まで引っかかってしまった。「詩は必要としている人のもの」というのがマリオの考えだ。なるほど、そういう考えもあるかもしれない。共産主義的な言い方をするなら、詩という財産を共有する、ということかな。
それでもやっぱりマリオの考えには賛成できない。創作物というのは作り手の個人性が宿るもので、それを自分のものかのように使うのは作り手に対して敬意が無さすぎる。どれだけ稚拙な表現になっても、マリオは自分の感性を懸命に働かせ、必死に言葉を生み出してベアトリーチェを口説くべきだった。人の言葉を借りて思いを寄せる人を口説いても、嬉しいとは思えない。
ただ、最後の最後でマリオは詩人になったと思う。島の海や風、息子の心音を録音するという発想に感動した。彼の感じる島の美しさを、自分の声とともに残すという姿勢は正真正銘詩人。実際に島の風景や音、島民たちは様々な美しさを備えていたと思う。
悲しいラストだったが、海岸を歩くパブロの姿に深い余韻を感じる。
見終わった後に、良い映画だったなと思える映画!
見終わった後に、良い映画だったなと思える映画でした!
特に、最後の脚本と映像が素晴らしく、こういう終わり方をするのか!?という感じです
郵便配達人と高名な詩人のふれあいが、どうして映画になるのか?と不思議に思っていましたが、最後に納得できました
言葉の持つ魅力が恋を成就させ、その言葉に憧れ、自らも言葉の魔術師になろうとした主人公の気持ちもよく判るし、二人の間に生まれた友情以上の心の通い合いが、人間の魅力だと思えるし、背景に当時のチリ・南部イタリアの政治的混乱、選挙・議員への皮肉も描かれており、帰国後、恐らく軍部に殺されたであろうネルーダ氏への鎮魂映画ともいえる作品です
主人公の郵便配達人が、言葉の魔術師ネルーダに再訪して欲しくて、自分の住む故郷の美しさを言葉ではなく、録音して送ろうとした気持ちも素敵だし、故郷チリのクラブ・街角で踊っていただろうと思わせる、ネルーダ役のフィリップ・ノワレの上手なダンスも素敵でした
BGMも映画に合った音楽で、バンドネオンの音色が何故か心に沁み込み、印象的だなと思っていたら、アカデミー賞作曲賞だったと知り納得!
また郵便配達人を演じたマッシモ・トロイージが、『イル・ポスティーノ』制作時には即時手術が必要な状態にも係わらず撮影を優先し、撮影終了から12時間後に41歳で死去したと知り、大きな驚きでした!
地中海の強い日差しと抜けるような青い空と海はもう一つの主役
『イル・ポスティーノ 4Kデジタル・リマスター版』
製作30周年を記念して4Kデジタル映像になって11月8日(金)からリバイバル上映。
早速、角川シネマ有楽町さんにて鑑賞。
日本での公開は1996年の春。劇場での鑑賞は実に28年ぶり。
『ニュー・シネマ・パラダイス』(1988)のアルフレード役で知られるフィリップ・ノワレの最新作と知って劇場に足を運んだ記憶がありますね。
高名な詩人パプロ・ネルーダ(演:フィリップ・ノワレ)と内気で実直な配達人マリオ・ルオッポロ(演:マッシモ・トロイージ)の日々の交流から徐々に縮まる二人の距離感、パプロに感化され詩作に目覚め、才能を開花させていく過程が丁寧に描かれていますね。
フィリップ・ノワレの愛嬌と包容力ある演技は素晴らしいのですが、脚本兼主演のマッシモ・トロイージは撮了後わずか12時間後に41歳で逝去、精細な演技の方だっただけにもっと出演作を観たかったですね。
マリオの恋人役ベアトリーチェ・ルッソを演じたマリア・グラツィア・クチノッタは、ソフィア・ローレン、モニカ・ベルッチのような典型的なイタリア美人。その後『007 ワールド・イズ・ノット・イナフ』(1999)にも敵役で出演していましたが、もっと活躍して欲しかったですね。
そして、地中海の強い日差しと抜けるような青い空と海はもう一つの主役、同作品のビジュアル面に大きく寄与していましたね。
改めて見直すとイタリア映画で大戦後盛んになった「ネオレアリズモ(=イタリアのネオリアリズム)」を踏襲、労働者の要求、市民の暴動といった側面も描いているのは再発見でしたね。そういう部分でも本作が永くイタリアで愛される所以かもしれないですね。
これは実話なのか、それとも創作なのか。
世界一幸せなアラフォーのシンデレラボーイの恩返し
1948年に 国外退去処分 となり、イタリアに亡命し、ナポリ沖の小島の別荘にやってきたチリの政治家、外交官で世界的に有名な詩人でもあるパブロ·ネルーダ (フィリップ・ノワレ) 。のちにノーベル文学賞受賞。カプリ島で出会った郵便局員の男との実話に基づく1994の映画。今回、4Kデシタルリマスター版で劇場鑑賞。
郵便局員のマリオ(マッシモ・トロイージ)は生来体が弱く、内気で普通の仕事につけないでいる不思議なおじちゃん。年取った漁師の父親と二人暮らし。お父さん役に顔がそっくり。体が弱いというよりも、多少オツムが弱い美青年(アドニス)のマリオ。鼻にかかってこもりがちなトーンの声も魅力的。映画館のニュースで世界的詩人が自分の島にやってくることを知る。配達員募集の張り紙を見て、小さな郵便局を訪れる。世界中からファンレターや贈り物が届くパブロ専任の配達夫として臨時採用となる。郵便所長(共産党員)が親切でいい人。彼とマリオのやりとりにまずはニヤニヤほっこり。美人の奥さんを連れて、芸術家が作ったアトリエ風の高台の別荘。自転車で登ってくるのはとても大変そう。その分周りを海に囲まれた絶景は格別でした。
大戦後のチリの政治混乱についてはよくわかりませんが、1948年から1958年まで国外退去処分だったようです。映画の色彩がほんとに古い感じで、1960年前後の映画のようで役者さんのメイクなんかも雰囲気があります。主演のマッシモ・トロイージは撮影終了後ほどなくしてなくなったそうですね。脚本にもかかわった彼は、実際に心臓が悪く、撮影も休み休みだったそうです。自転車漕ぐだけで大変だったでしょうに。命と引き換えに撮った映画です。泣けますね。
居酒屋兼食堂の娘、ベアトリーチェ·ロッソに一目惚れし、オクテの彼はパブロに相談します。パブロの詩は
エッチな比喩や隠喩に優れ、官能的でややお下品ながら、とても情熱的なので、世界中の年頃の娘さんにはとても刺激的だったに違いありません。コーチが良かったせいで、マリオは島一番のグラマー美女(決して乙女には見えませんが)といい仲になり、結婚することに。
アラフォーのシンデレラボーイ。
夢のようです。
ワタシもあやかりたい。
カプリ島は古くからレモンの名産地で有名らしいです。
詩がとても力を持っていた時代。
あの録音機(再生機能つき)。送られてきたカセットを押し込むのは昔のカラオケみたい。当時、実在したものなのかは大変疑問ですが、マリオとパブロにとって、とても大事で重要な役割を担う仕掛けでした。郵便局長が野外の録音をサポートするのもとてもいいです。当時の集音マイクで胎児の心音が録音出来るのかは横に置いといて、
「この島で一番美しいのは······ベアトリーチェ ロッソ」
パブロとマリオの噛み合わないようで、ちゃんと噛み合っている会話は、時折とても可笑しい。
大学の部室でひとりでカセットテープに弾き語りを録音してたら、マツイ君がいきなり入ってきて、サビをハモった声が入っているテープは何度聴いても可笑しいので、上書きして消すことなく大事にとってあります。
金沢出身の映画好きの松井君。元気にしてますか?
のどかで美しい南イタリアの島を舞台に…
翼を持って羽ばたく言葉
この映画があまりに好きになってしまった。「グラディエーターⅡ」見てからまた見に行った。再発見が沢山あった(2024.11.15.)
.................................................
しどろもどろにボソボソ話すマリオ、頼りなくて大丈夫?職なしの彼が一時的に郵便配達の仕事を得た。食事中も郵便配達人の帽子被ってるのを、頭の形に帽子を合わせないと頭が痛くなるからと漁師である父親に言い訳するところが妙に可笑しくて可愛いくて笑えた。マリオによれば父親も無口、全く話さない。それがマリオの結婚パーティーで父親は幸せいっぱいの言葉で流暢にスピーチをした。驚きいっぱい!
最初はパブロも自分の為だけの郵便配達人マリオに素っ気なく、マリオは相変わらずもじもじしている。でもパブロの詩集を買って読むようになってマリオの顔が変わってくる!思索する顔、隠喩って何?これ?あれ?語彙が増えていく。ベアトリーチェに恋をしてからは頭の中はベアトリーチェでいっぱい!どんくさかったマリオが見る見るうちにかっこいいハンサムな男に変わっていく!奇跡のようだった。ぼそぼそ話すマリオはもう居ない。かなり親しくなっていたパブロに、恋におちたこと、メタファーなんかを自分に教えたあなたにも責任があるのだから力を借してくれと言い出す。恋の力はすごい。
パブロが詩を書きながら、どんな形容詞がいいかマリオに尋ねマリオが答えるシーンが好きだ。「魚を採る網は?」にマリオは言う「悲しい」。パブロの詩をマリオがベアトリーチェへのラブレターに使ったことをパブロに言われて「詩はその詩を書いた人のものでなくて、その詩を必要としている人のものだ」と言い返すところは見事、その通りだ!マリオはパブロから言葉やメタファーだけでなく考え方も吸収した。
たとえ落胆したとしてもパブロのことを忘れない、感謝しかしないマリオがあまりに健気で真面目で涙がこぼれた。郵便局長の助けを借りて、パブロへの音のプレゼントを作る:海のさざ波、大きな波、父親の悲しい魚の網、茂みに吹く風の音、教会の鐘の音、ベアトリーチェのお腹をパブロが置いていった機器で録音する。自分の言葉でナンバリングとタイトル付けをして、優しい感謝のメッセージと共に美しい島とこれから生まれる我が子の心音を残した。
誰にでもお勧めできる名作です
全54件中、21~40件目を表示