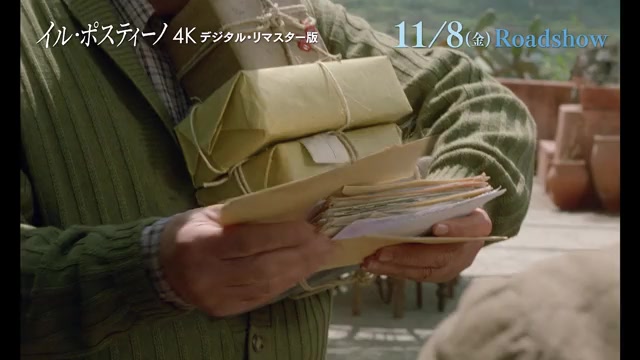「言葉を紡げる幸せ、言葉を受け取れる幸せ。」イル・ポスティーノ すっかんさんの映画レビュー(感想・評価)
言葉を紡げる幸せ、言葉を受け取れる幸せ。
⚪︎作品全体
『イル・ポスティーノ』を観て心に残るのは、単なる詩や恋の物語ではなく、「言葉」というものが持つ双方向の喜びだ。詩人ネールダと郵便配達夫マリオの交流を描いたこの映画には、派手な展開も、劇的な転換もない。ただ、島の静けさと波の音、そして二人が交わす言葉の積み重ねが、ゆっくりと人の心を動かしていく。そこにこそ、この映画の魔法がある。
マリオは最初、詩や言葉の力を知らない。ネールダに近づいたのも女性に伝える言葉を持たないから、彼のサインを求めただけだ。しかし、ネールダの語る言葉に触れ、彼が紡ぐ詩の断片を聞くうちに、マリオの中の世界が言葉によって広がっていく。海の音や風景、日常の中で見過ごしていたものが、ネールダの視線を通して詩となり、マリオの中で意味を持ちはじめる。
言葉を「受け取る」ことで、彼は世界を新しく知る。長年共にあった単なる海や山々が、言葉をもって別の景色になっていく。
だが、この映画が美しいのは、マリオがただ受け取るだけで終わらないことだ。マリオは次第に、自分自身の言葉を持ち始める。恋人ビアトリーチェへの思いを伝えるため、詩を真似るように始めた言葉は、やがて彼自身の切実な感情を伴うものへと変わっていく。ネールダから学んだ比喩や響きは、模倣のようでいて、少しずつマリオの実感を帯びたものになっていく。世界を新しく知る喜びから、自分の世界を表現する喜びへ。この変化の過程が、『イル・ポスティーノ』の最もあたたかい部分だ。
マリオにとっての言葉は、ただ恋を叶えるための道具ではなくなる。ネールダとの別れのあと、彼が自ら詩を録音し、海辺で音を拾う姿は、「世界を受け取った人間が、それを誰かに手渡そうとしている」ように見える。詩人から受け取った言葉を糧にして、今度は自分が世界を見つめ直し、言葉を紡ぐ。その過程で、彼は初めて島の風景や音を自分のものとして記録し、語り、愛する人や未来の誰かに伝えようとする。そこには、言葉を「受け取る」側から「紡ぐ」側への静かなバトンの受け渡しがある。
だからこそ、この映画は「詩の力を描いた映画」ではなく、「言葉が生きていく力を与える映画」なのだと思う。詩は特別な芸術家のものではなく、日々を生きる誰かの中に芽生えるものだと示している。マリオが感じた幸せは、ただネールダの言葉に酔いしれるだけのものではなく、自分の世界を自分の言葉で見つめ直せたことにある。それは、言葉を紡ぐ幸せであり、同時に誰かから受け取れる幸せでもある。
ラストに待ち受ける結末は、言葉の温もりとは裏腹に、社会の現実と暴力を突きつける。しかし、その余韻の中で響くのは、マリオが録音した島の音や詩の声だ。彼が受け取り、そして残した言葉や音が、時を越えて伝わっていくことで、観る者の心にも静かな灯がともる。誰かの生きた証が、言葉として、音として残る。その事実が、この映画の本当の「救い」になっているのだと思う。
『イル・ポスティーノ』は、言葉を贈ることと受け取ること、どちらの喜びも教えてくれる。人と人が出会い、互いの世界を言葉で開き合うことの尊さを、これほど穏やかで鮮やかに描いた映画はそう多くないだろう。観終わったあと、誰かに手紙を書きたくなるような、あるいは波の音に耳を澄ませて自分の中の言葉を探したくなるような、不思議な温度を持った作品だ。
⚪︎カメラワークとか
・海や空を映すときの明るさ、広さに対して屋内の狭さ、猥雑さ。マリオが世界の美しさと同居していながら、目の前のことにだけ目を向けているような、そんな序盤の物語とシンクロしているようだった。
・終盤、ネールダが再び島へやってきた時の時間経過がなにもなくて、思い切った演出だった。マリオの死を唐突に話した後、ラストでその瞬間を映すという構成も面白い。
・家の窓から父の仕事風景を見つめるマリオのカットが良かった。いつもの家からいつもと同じ風景だけれど、そこから感じる感情の表現は少し変化がある。
⚪︎その他
・劇伴が良い。素朴なマリオと美しい景色を包み込むような感覚。
・マリオが死んでしまったのは、一瞬そこまでやるか、と思ったけど、それによって言葉の力を強調させるラストになっていた。