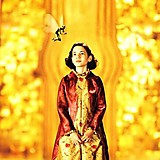イタリア旅行のレビュー・感想・評価
全6件を表示
イタリアという土地が生む奇跡
映画館で久々に再見(三百人劇場以来?)。亡くなった伯父の遺産を処分するため、イギリスからナポリ近郊の地に訪れた夫婦が、旅先での夫婦喧嘩(嫌味と皮肉による揚げ足取り)により一時は離婚の決定にまで至った関係を、イタリアという地ならではの「奇跡」によって修復する、というお話。批評家時代のJ=L・ゴダールが称賛したことでも有名な作品で、一組のカップル(男と女でなくてもよい)、自動車と道を横切る牛や人々、遠くに見える鉄道や船、歴史の記憶を宿す街や遺跡、そして海と光さえあれば、映画が成立すること、傑作さえ生み出すことができるということを、見事に証明してくれる
ナポリの観光地を巡る愛の彷徨
互いに心が離れてしまった夫婦がイタリアを旅するだけの話なのだが、なぜか引き込まれてしまう。
イタリアのモノクロ映画独特の硬い画質。アントニオーニ作品でも感じた突き放すような冷たい空気感。
ナポリの観光案内さながらにバーグマン扮するキャサリンが名所を回る。博物館の古代彫刻に圧倒され、洞窟観光ではガイドに隠れて悪態をついたりする。カタコンベでは頭蓋骨の山に気分を乱され、夫への冷めた愛情や嫉妬、かつて好きだった亡き詩人の友人への思慕など複雑な心模様を絡めて描いていく。
夫の方はいけすかない人物で、カプリ島で浮気や買春を試みるが不発に終わる。「友達が死んだの」と言う娼婦のいきなりの台詞には、さすがにドン引きしてしまう。
そんな冷め切った夫婦がポンペイ観光の後、お祭りの列に巻き込まれて愛を取り戻すことになるのだが、これがあまりに唐突過ぎる。それともロッセリーニのこの力業を「奇跡」と呼ぶべきなのだろうか。やっぱり最後まで引き込まれてしまった。
旅行は苦々し
「男と女と車があれば映画はできる」というゴダールの有名な言葉の由来は本作。そのせいで過度に神格化されている向きがあることは確か。
煙を吹きかけると「イオン化(マジ?)」によって勢いよく烟る硫黄泉や、圧倒的な群衆が押し寄せる村祭りなど、ロケーション的要素に助けられている部分は大きい。しかし男女の間に渦巻く引力と斥力、そしてそれらの心理的運動を物理化する変換ツールとしての車があったからこそ、それらのロケーションに辿り着くことができたともいえる。
それにしても終盤の畳み掛けるような離婚キャンセルには笑ってしまう。明らかに雰囲気が悪い夫婦に対して「ポンペイで生き埋めにされた遺体の石膏を見に行こう!」と笑顔で誘いかける案内人は一周回って一番心がない。しかも土の中から姿を現した石膏が夫婦の遺体。「ワオ!夫婦だね!」じゃねえんだよな。
村祭りの群衆に揉まれるという描写を通じて夫婦間に蟠っていた悪感情が次第に絆されていく一連のシーンは見事なもの。そのあまりのご都合主義ぶりを、群衆の誰かが隊列の中の聖者に向かって放った「奇跡だ!」の一言が強引に説明づける。手癖程度の力加減でこういうことができるロッセリーニはやはりすごい。
ただ、物語的なところでいうとイングリッド・バーグマンがあまりにも不憫だ。彼女のいじらしさに対して夫の無味恬淡ぶりは何なんだ。お前カッコつけてんじゃねえぞ、と思ってしまった。最後も「愛してると言って」と言われて「それを利用しないと誓うか?」とわざわざ確認を取る冷酷さ。バーグマンさん、やっぱ離婚したほうがいいっすよ。
日常あるあるの、心の機微を丹念に描いた映画。
自分の居場所は、心安げる場所であるはずなのに…。
だのに、どうして、なぜ、こうなる…。
そんな二人の様子が淡々と描かれる。
観光や現地の人とのやりとりを織り交ぜているものの、二人の関係性・直球勝負。他のエピソードは無い。
辛いですね。
お互いの心の持ちようが原因だから、逃げようがない。
釣った魚には餌はやらない典型夫。
”くれない”族の妻。でも、子どものいない専業主婦って世界が狭くなっちゃうから、夫しかいない、自分の相手をしてくれるはずの人は。TVもネットもない時代。井戸端会議もすぐ飽きるし、へたすると怖いし。あとは社会奉仕活動にのめり込むしかない…。
そんな自分のいたらなさは半分わかっている。でも私だけのせい?あなただって…。
自分の態度や心を変えればいいだけなのに、変えられない。
いじめられてとか事件とか周りのせいにできない。ひたすら自分に戻ってくるだけ。
恋し、結婚した当初は、どんなことがあってもこの愛は続き、添い遂げると思って誓ったのに、今この現実。
病気とか、経済事情とか”事件”のない”凪”の時。ただ、ひたすら自分との会話。
愛の残像?夫が自分に関心がないことがひたひたと突き付けられ…。
夫は自分の邪魔ばかりしてくる妻にイライラし…。
夫婦関係に限らず、こんなぎすぎすした関係に、少しでも身に覚えがある人にはとても痛い映画です。
よく撮ったな、この映画。
その場で台本渡されてというほとんど即興劇とな。俳優お二人の才能に乾杯。
サンダース氏はそのやり方にイライラしていたとか。夫のイライラ感を出すためにあえてそうしたのかな。
そんなお二人の才能を引き出した監督としての才能にも驚嘆するけど、離婚しそうな自分の妻・バーグマンさんにこんな役やらせて映画にしちゃうなんて。バーグマンさんもやりたいと望んだのかな?現状を客観視したかったのかしら?
この数年後、監督とバーグマンさんは離婚するけれど、納得。
監督としてはすごいと思うが、人としてどうよと思ってしまう。
「男と女と車があれば…」という名言を捧げられた映画とか。
低予算でもいい映画はできるという見本。
役者の表情と、心象風景の切り取りが見事。アンサンブルで効いてくる。
へたなドキュメンタリーよりも、「我が家覘きましたぁ?」と言いたくなるほど、ドキュメンタリーっぽい。主役の二人の美貌と経済状況を除いては。
人生のある断面、男と女の普遍的なある断面を見事に切り取った映画。
だから、名作なんだけど、あまりに身につまされるので、評価が低くなる。
「亭主元気で留守がいい」なんて言っていられるうちが安泰なのか。
松田聖子さんの「なんで私達結婚している(離婚しない)んだろう」という有名な言葉もあるし。
もっと、達観できる年齢になったら、高評価つけられるんだろうな。
★ ★ ★
バーグマンさんは、まだこの映画と『カサブランカ』しか観ていない。繊細な表情に引き込まれる。
サンダース氏は、この映画と『レベッカ』・『イヴの総て』だけ。それぞれ、微妙に違う役で、印象に残る。
映画の印象に「イタイ」が欲しい。
ちょちょいのちょい。監督の手なぐさみ
モノクロ。
古き佳き時代のバーグマンに会える。
短い映画で、その作りの単純さとプロットの明解さには驚きます。
後々の映画監督たちにお手本として大きな影響を与えているとのこと。
なるほど、「起承転結」の推移の分かりやすいきっかけやら、人間の心情の変化を単元ごとに見せる手法やら、これは確かに映画人への“指導パンフレット”かも。
ポンペイ~カプリ島は昔ひとり旅しましたが、確かにあの人形(ひとがた)を前にすると平常心ではいられませんよ。
カプリ島にはヌーディストビーチもあります。これも平常心ではいられませんよ。
DVDでは映画コラムニストの横田彦治郞氏の解説が読めます。これが噴飯もので一見の価値あり。
氏は活動弁士かはたまた講談師なのか?
「ハリウッドを捨ててロッセリーニ監督の元に走ったバーグマン。二人は映画ばかりか子供も四人作ったのであります!」
映画よりも、この「解説」が面白かったかなーw
で、女のバーグマンだけが改心して良妻賢母になろうとする結末も、時代だなぁと思います。
映画史の資料として◎
観光ガイドとして〇
車中会話が途切れる倦怠期夫婦の処方箋として△
さりげないようで洗礼されたセリフの巧みさ
全6件を表示