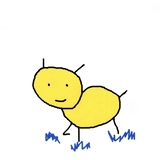宗方姉妹のレビュー・感想・評価
全21件中、1~20件目を表示
対照的な姉妹
宗方姉妹は当時人気を博した大佛次郎の新聞小説を映画化したもので古風な姉節子(田中絹代)とモダンな妹満里子(高峰秀子)を取り巻く話です。
節子は無職で酒癖のわるい夫三村(山村聰)の献身的な妻です。働かない夫のかわりに自らバーを運営しながら甲斐甲斐しく夫の面倒をみています。その様子は封建的、大時代的で隷属している感じがあります。ここでの山村聰は痩せこけて、なんというか太宰治風です。デカダンスな感じの屁理屈をこねながら、良妻をないがしろにして、猫をなでているような男です。それでも節子は夫を信じて、彼を養っています。
一方満里子は奔放で現代的な未婚女性で、奴隷のように三村に仕える節子を不憫に思いながら、姉の古風な考え方に反駁しています。姉をいじめる義兄三村を憎んでおり再三姉に別れるよう薦めています。かつて姉と懇意があった優しく理知的な田代(上原謙)がフランスから帰ってきて、密かに姉と田代が結ばれたらいいと考えています。
いよいよ退廃的になっていく三村は節子を中傷するだけにとどまらず張り手をくらわすシーンもありました。ホラーやサスペンスとして、男が女を加虐したりもっと酷いことをしたりはありますが、ドラマ映画で男が女を殴るということは今の映画ではないので山村聰が田中絹代を三発ひっぱたくシーンは衝撃的でした。
節子が貞淑であればあるほど三村は堕落の度合いを強めていきます。これは世の物語にでてくる与太男のひな形を踏襲しています。自堕落な人間は真面目で正しい人間に対峙したときに、内懐に卑下祭をひきおこし、罪もない対象によけい辛くあたります。この衝動的性向は日本映画で頻繁に描かれるちんぴらそのものです。
これらの山村聰と田中絹代の暗さ・重苦しさに対して高峰秀子は明るさ・快活さとして存在しています。この映画の高峰秀子はとてもかわいいのです。
映画レビューブログを始めるときじぶんは「かわいい」という日本文化に偏在する陳套語を使わないでレビューを書こうと決意したのですが高峰秀子だけはかわいいを使ってみました。この映画をご覧になればそれをお解りいただけると思いますが、そう思ったとき、小津安二郎監督はかわいさが映画に不要だと考えているのではないか──と思い至りました。
高峰秀子が出ている小津映画は彼女の子役時代の「東京の合唱」(1931)を除くと宗方姉妹だけだそうです。おそらく小津安二郎は高峰秀子のかわいさを引き出しながら、高峰秀子のかわいさに観衆の感興が根こそぎもっていかれてしまうことを危惧したにちがいないのです。リマスターされていない粗い画像のなかにいる高峰秀子さえわたしたちの魂をもっていってしまうのですから、小津監督が彼女を小津調にそぐわないと判断したのは有り得る話です。
結果的に高峰秀子が魅力をもっていってしまうという点において宗方姉妹は小津映画のなかで異質だと思います。
また、この映画は、松竹の小津安二郎が新東宝に招聘され、人気小説を当時最高の予算を与えてつくらせた肝いりの映画だったそうです。そのため、撮影時の緊迫した雰囲気が今に伝わっていて、ネットで以下の文献を見つけました。
ひとつ目は誰がやっているのか知りませんが高峰秀子を冠したXです。引退後はエッセイストだった彼女の著作からの引用が投稿されているXです。
『『宗方姉妹』の撮影現場は、聞きしにまさる厳しさで、スタッフや俳優の肝っ玉は終始硬直状態、シンと静まりかえったステージの中で、セリフにダメが出、動作にダメが出、十回、二十回とテストがくりかえされ、息づまるような緊張感の中で、撮影はワンカット、またワンカットと進行した。』
ふたつ目は誰かのブログにあったものです。緊張から酒盃を持った笠智衆の指が震えているのを小津監督が笠さんあんたの役は中気じゃないよとからかって緊張をほぐした──という様子が三者の著作(撮影の目撃者・撮影スタッフ・高峰秀子の「わたしの渡世日記」)から引用されていました。
この宗方姉妹のただならぬ緊張をひきおこした理由の一つはおそらくこのトリビアによるものだと思います。
『この映画は、スター女優の田中絹代が、数ヶ月にわたるアメリカ凱旋後に初めて製作した映画である。最新のハリウッドの俳優たちと接した田中は、演技に関する新しいアイデアを持ち帰ってきており、それを監督の小津に恥ずかしげもなく話したと言われている。監督である小津は、自分の演技に対する非常に強い(そしてハリウッド的でない)考えを持っていたため、これを快く思わず、撮影中の2人の関係はいささか緊迫していたと伝えられている。』
(IMDBにあったトリビアより)
このトリビアを見たとき、山村聰がやった田中絹代への痛烈な張り手が、小津監督の特別な演出に思えてきました。田中絹代にしたって小津安二郎に進言するなんてあまりにも無邪気ではありませんか。でも小津安二郎は田中絹代の監督第二作目「月は上りぬ」(1955)の制作を全面的にバックアップしたため東京物語から三年間自分の映画をつくりませんでした。これは戦後、年一本でつくってきた小津安二郎にとって長い間隔だったようです。
『『東京物語』公開後、小津は友人で女優の田中絹代の監督2作目『月が上りぬ』の完成を手伝うよう依頼された。 『早春』の製作が始まるころには、小津は監督を3年も離れていた。第二次世界大戦後、平均して1年に1本のペースで映画を撮ってきた小津にとっては、かなりのブランクだった。』
(wikipedia、Early Spring (1956 film)より)
高峰秀子は子役時代から人気絶頂期にいたるまで養母から虐待・搾取された苦労人でした。松山善三と結婚後は安寧を得ましたがスクリーン上のかわいい様子とは裏腹に仕事に厳しい人でヘビースモーカーでもあり最期は肺癌だったそうです。ひるがえって、われわれ観衆がスクリーンやモニターに映る誰かを見て「かわいい」とか「いい人そう」とか「やさしそう」とか思ってしまうことの無責任さとばかっぽさを知ることも重要なリテラシーだと思うのです。もちろん何をどう見るかは各人の勝手ですが個人的には「かわいい」が溢れる日本文化に忌々しさを感じます。
英題The Munekata Sisters、IMDB7.3、RottenTomatoesトマトメーターなし、オーディエンスメーター89%。
紀子三部作の合間に
1950年。小津安二郎監督。大佛次郎原作を読み返したのを機に12年ぶりに再見。働かない夫の代わりにバーを開いて家計を支えるけなげな妻とアプレな妹が、妻のかつての恋人との関係めぐってやりとりする。結末は原作と同じだが、そこにいたる因果関係が大胆に変更されており、夫の背景が描かれないことによって、より夫の暴虐性が際立っている。さらに後期の小津作品ほどには形式化は進んでいないものの、向かい合う人物の取り方や振り向き方、場面展開の音楽と風景は形式的に処理されていてモダン。
田中絹代と高峰秀子という、人気と実力を兼ね備えていると言われているのに個人的にどうにも合わない2人が共演しているので、初見から気乗りしないまま見ていたが、やはり小津作品の田中絹代は痛々しい。
この前が「晩秋」で直後が「麦秋」であることを考えると不思議な気持ちになる。じめじめと暗い情念が少しずつからからと明るく処理されていく過程とも見える。そういう意味ではこの映画の高峰秀子の「小芝居」ははずみになったのかもしれない。
新しいって事はいつまで経っても古くならない事
小津安二郎監督が松竹を離れて初めて撮った大佛次郎原作小説の映画化作品です。
昔の邦画メロドラマの苦手なパターンが「優柔不断なインテリ風の男がグズグズ拗ねているだけ」という人物像です。優柔不断の僕にそんな事言われたくないと言われるかも知れませんが、同じ場所で足踏みしているだけに見えるこんな男と向き合っていると僕はただただイライラして来るのです。でも、そんな作風からは距離を置いていると思っていた小津監督がこんな作品を撮っていたとは思いませんでした。愛する人を胸に秘めたまま、失職したままグダグダしている夫と暮らす姉、奔放に自由に生きる妹の物語です。
でも、本作中の山村聡さんが「戦争で傷ついた懊悩を背負った男」とも思えないし、田中絹代さんの決断も高峰秀子さんの振る舞いも「新しい女性像の表象」には見えませんでした。本作中で述べられる「新しいって事はいつまで経っても古くならない事」の言葉を借りれば、この映画は古いんじゃないのかな。
ただ、映像の切れ味は流石で、ペロッと舌を出す高峰秀子さんの可愛さは別格でした。彼女はいつまでたっても古くならない女優さんです。
唇よ、熱く君を語り、舞い上がれ
田中絹代
溝口健二作品、雨月物語、西鶴一代女での
従順、忍耐、建前、自己犠牲のイメージ
高峰秀子
成瀬巳喜男作品、あらくれ、放浪記にみる、
本音、自己主張、自己実現、つよい自我
このふたりが、
小津安二郎監督下で、ホームグラウンド松竹ではない新東宝でタッグマッチ
面白くないわけがない
松竹の社風でできなかったはず、
グラスを投げて割る、顔を打つ、
などなど激しい描写
あの土砂降り、そういえば、小津安二郎は大映で
浮草、京マチ子が強烈であった
小津安二郎は和の作家イメージがあったりするが
和洋折衷のモダニストである
わたしがはじめてみた作品は
生まれてはみたけれど、
あの自動車のエンジン音のすさまじい迫力、
大人の欺瞞を暴くような子どもという立ち位置
今作では高峰秀子のキャラクターになっている
唯一演技指導をしなかったらしい
これで最初で最後だったからか
山村聰、言葉が出てこないうつ状態は、暴力にでてしまう、不甲斐なき、哀れ。
上原謙、よるべなき自己愛、だれかに寄りかかっていなければ生きていけない。困っているおんなを狙うといういわゆる後家ごろし、色悪。
ラスト、雨上がり、土固まる。
清々しい旅立ちは、姉妹ともに
あたらしい明日へ。
東京ラブストーリーで、
鈴木保奈美が、あっちふらふらの織田裕二を好きでいながら、別れを決断したあのラストを思い出しました。
じぶんの心に支配されない生き方が爽やかでした。
古くならないことが新しいこと
「午前十時の映画祭」で鑑賞。
面白かった。
途中までは「名作やなぁ、ほんまに」と思って観ていたけれど、終盤に少し冗長さを感じました。でも面白かったです、うん。
いつもいっているように、主人公に明確な目的(「勝つ」「捕まえる」「逃げる」「何かをつくりあげる」など)のないストーリーを、退屈させずに観せるのはなかなか難しいことだと思います。それをここまで魅力的なものに仕上げているのは、やはりさすがというほかありません。
じつに74年前の作品ということで、それだけでびっくりですが、ここに描かれている人々のこころの動きは現代のわたしたちにも深く響くものでしょう。
けっきょくのところ、技術や様式は変化しても、人間の本質はまったく変わらないのだということがこの映画を観てわかりました。
そして、「古くならないことが新しいこと」という、節子の言葉。
それは、自らの作品が時を超えて生き続けるという、小津監督の、自信に支えられた予言のようにも聞こえました。
それにしても、いまの映画で74年後に再映される作品がどれくらいあるのだろう?
――と、今回もそんなことを思ったのでした(まあその頃には映画館もなくなってるかもしれないけどね)。
で、最後にひとこと。
高峰秀子、サイコー!!
家庭にも戦後社会にも居場所がない多くの「亮助」たちへ
終戦から5年、1950年(昭和25年)に公開された本作。
映画の序盤は美人姉妹宗像シスターズの父、宗方忠親(笠智衆47)が住む京都が舞台です。
ここには戦争の影は見えません。
気持ちのよい風の吹き抜ける日本家屋に一人住まいの父。父の古い友人である京大医学部の教授が、胃がんに侵された父の病状を姉、三村節子(田中絹代42)に告げます。父は病を得て余命短いことを薄っすらと自覚している様子ですが、恬淡としています。苔寺の庭、苔の上に落ちた一輪の椿の花、それを最後に見ることができたと、しきりに喜びながらうまそうに酒を口に運ぶ父と、それを黙って見つめる節子。
父の元を客として訪れる古い知り合いでフランス帰りの家具会社経営、田代宏(上原謙42)。気安い田代と父の前で幼い少女のように振る舞って見せる妹、宗方満里子(高峰秀子27)。この父と娘たち親子の間には断絶は見えません。
ある一日、姉妹で仲良く寺見物に出かけ、姉に連れ回されて退屈を口にする妹。この姉妹の間には小さな断絶が見て取れます。
病の影と命の儚さは感じられるものの、京都は姉妹にとってのびのびと明るく、安心して過ごすことのできる場所のようです。出てくる人物も、みな二人の味方ばかり。
次の舞台は神戸です。満里子は一人で田代の経営する家具会社に遊びに来ています。しゃれた明るい社長室に飾られたフランス製の人形。田代はルックスも生き方も、ちょっと日本人離れして見えます。本作の欠点と言えるのが、彼の人物設定にあると思います。こんなストイックな完璧超人、いる?いやいない。
満里子の自由奔放な一人芝居(cute&funny!)で、かつて節子と田代が恋人同士であったこと、田代の洋行でその恋が終わったこと、田代はいまでも節子のことを慕っているらしいこと、などが明かされます。
ここで、敵その1、カフェを経営する裕福な美人未亡人、真下頼子(高杉早苗33)が登場します。満里子は女の直感で頼子が田代を狙っていることを察知し、敵意をあらわにします。
次の舞台は連合国軍占領下の東京です。父の持ち家である一軒家に、姉妹と姉の夫である三村亮助(山村聡41)の3人が暮らしています。この夫の登場で、本作の雰囲気が一気に暗く苦い味に変わります。
・戦争帰りの中年男
・最初はなぜか眼帯をしている
・机に向かってドイツ語を勉強するのが趣味
・外国語はできても、自分の胸中、葛藤を言語化できない、しない
・妻に対しては単語しか発しない
・猫にしか心を開かない
・夫婦には子供がいない
・着物に下駄履きで太宰治みたい
・仕事の口がない(エリートのプライドが邪魔するのか?)
・妻の日記を盗み見て、田代にめらめらと嫉妬心を燃やす
・うらぶれた居酒屋「三銀」が唯一の心安らぐ場所(女中のキヨちゃん、千石規子がso cute!)
・「三銀」では「先生、先生」と呼ばれており、どうやらエリートだったらしい
・家庭にも戦後社会にも居場所がない
・生活能力を持たず、満里子からは邪魔者扱いされてしまう
・いきなり妻の職場に現れたり、不可解な行動を取ることがある
亮助はまるで救いのない設定の男ですが、本作の登場人物たちの中では、もっとも実在感のあるキャラだと思います。きっと当時の日本には多くの「亮助」たちがいたことでしょう。
いつも和装で古風な節子は実は東京でバーの共同経営者であり、満里子はそこでバイトしているという、なんとも奇妙な設定です。
バーが経営難に陥り困った節子は、田代に資金援助を頼みます。その件が夫にばれ、夫婦の間の断絶が深刻化します。
ここで節子はどうするか?
選択肢1:夫と別れ、田代の力を借りてバーの経営を続ける
選択肢2:バーの経営を諦め、夫とともに慎ましく生きていく
なんと節子は2を選びます。
ここで亮助はどうするか?
「夫を支える貞淑な妻」という生き方を選んだ節子の頬を何度も何度も張り飛ばします。
このシーンが悲痛なのは、妻の頬の痛みと夫の心の痛みと、その両方を同時に感じるからだと思います。この暴力をきっかけに、妻は夫を捨てて田代の元へ走る決意を固めます。亮助は妻に自分を見限らせるために、わざと暴力を振るったのではないでしょうか。
出張で東京へ出てきた田代の元を訪ねた節子。なんとそこに突然亮助が現れます。やっと仕事が見つかったことを嬉しそうに話し、また姿を消します。彼の真意はなんだったのか。田代に「妻を頼む」と言いたかったのか。それとも節子に「すまなかった、戻ってこい」と言いたかったのか。
なんとも不器用であわれな男亮助はいつものように居酒屋でクダを巻き、深酒して帰った夜に頓死してしまいます。私は亮助を「クズ男」と安易に切り捨てることはできませんでした。多くの「亮助」たちは、本作を観て自分の姿を省み、中には生き方を変えた者もいたのではないでしょうか。亮助の死は病死だったのか、あるいは自殺だったのか、詳細は語られません。夫の真意を悟ったのか、あるいは夫の死になんらかの責任を感じたのか、節子は思いを寄せてくれている田代に別れを告げ、映画は終わります。
いまだ古い価値観にこだわり、自分を殺して生きているように見える節子。でもそれを「自分の選択」だと、清々しい顔で語ります。昭和25年にはまだ多くの「節子」たちも残っていたのかも知れません。
田代の胸に飛び込んで戦後社会、高度成長期の日本を謳歌することを、小津監督は節子に許しませんでした。先立たれた夫の菩提を弔って生きる古風な女性の生き方、それが監督の節子に託した生き方でした。この映画を原節子も観たのでしょうか。
古い考えに縛られず、新しい生き方を模索しようとする妹満里子を「ほんとうに新しいものはいつまでたっても古びないもの」と節子は諭します。姉妹の間の価値観は戦前と戦後に引き裂かれているようです。節子の言葉は小津監督の映画哲学なのでしょう。たしかに、本作は令和の時代にも十分鑑賞に耐えうる映画なのではないでしょうか。
主人公姉妹が最高に魅力的で見ごたえたっぷりの名作
午前十時の映画祭14で本作初鑑賞
小津安二郎監督が松竹でなく新東宝で撮った1950年の作品、かの大傑作「東京物語」が生まれる3年前になります
主役の姉妹、田中絹代さん演じる姉の節子と高峰秀子さん演じる妹の満里子がとても魅力的で素晴らしい演技をされており、見ごたえ満点の作品です
姉の節子は失業してクサっているクズ旦那を見限らず尽くしているが、当の本人はそれに対し全く誠意もなく酷い仕打ちを重ねる日々
節子を演じる田中さん、清楚で凛とした佇まいがとても色っぽくて素敵な役者さんですね、そんな彼女が演じる節子のひたむき加減に心打たれました
逆に節子の夫を演じる山村聡さんの最高のクズっぷりもみごと、素晴らしかったです
そして妹の満里子は節子とは真逆のキャラクター、自分の意見を持ち、それをしっかり口にして他人に伝える事のできる女性、目に余る節子の夫の人でなし具合に常にフラストレーションを抱えるモダンでエネルギッシュな女性を高峰さんが伸び伸びと見事に演じきっていて本当に魅力的でした
上原謙さん演じる田代宏の前でふざける寸劇のくだりや何か言っちゃベロを出す仕草、そして義理の兄に感じるイライラをぶつけるのに物をてきとうに放り投げたりするちょっとした演技が何ともチャーミングで本当に観ていて楽しかったです
作品自体はずっと浸っていたくなる、いつもの小津調で落ち着いて観ていられる作風ですが、稀に節子が歩くのと並行し移動する非定点ショットや節子がクズ夫から何度もビンタされる衝撃のDVシーンもあり、これまで観てきた作品では無かった表現が新鮮で、これももまたいい意味で見ごたえのある作品でありました
男支配の夫婦観から脱却できていない
戦後5年が過ぎた昭和25年の作品である。焼け跡は残っていたはずだがフィルムに表れない。東京、京都、神戸の美しい風景が映る。
原作は大佛次郎の朝日新聞掲載小説。原作にはあたっていないのだが映画化で大きくは改編されていないと思われる。英仏文学に造詣の深かった大佛が、女性の解放とまではいかないものの、戦後の女性の意識の変化を描こうとしたものだろうし、新しい家庭映画を創ろうとしていた小津安二郎と野田高梧が共鳴して脚本化したのだろうから恐らくは大きくは変えないと思うからである。
さて、映画では節子と、まり子の宗方姉妹の選択が描かれる。このニ人は年が離れており、戦争を挟んで、戦前の人間と戦後の人間を代表させているのだと思う。(節子は常に和服、まり子は洋服でありこれは徹底している)
映画が言いたかったことは、戦後派のまり子はもちろん、戦前派の節子も、女性が自主的に人生の選択をするようになりましたよ、新しい時代ですよ、ということなのだろうが、そこには異議がある。
まず、まり子は何も選択をしていない。人間関係のなかをふわふわと流されながらその時々に迎合した言動をしているだけである。姉の節子に指摘されているように服や爪の色と同じでモードを追い求めているだけ。
節子はというと、一度は三村と別れて、田代と一緒になることを決意する。だが三村が憤死することにより、「暗い影に囚われ」田代の元には行けないと言い出す。三村は死んでも、いや死んだからこそ、妻を支配し続け、節子は「自主的に」支配され続けるのである。
この構造は、小津映画に頻出する「家に残った未亡人」の位置づけと実は同じである。死んだ夫は死んでもなお、いや死んでいるからこそ永遠に妻をイエに縛り付けるのである。
これが当時、新しい女性像として華々しく打ち出されたであろう小説と映画の実態であることは覚えておく必要があると思う。そして、その精神的構造は多分に現代まで継承されている。
最後に、節子の経営するバー「アカシア」(だっけ?)のカウンターの後ろの壁の英文だけど、「わたしは機会があれば飲む、時には機会がなくても飲む」。ドンキホーテの原作者セルバンテスの警句です。多分、英文学者である三村がアイデアを出した設定なのでしょう。三村は大佛次郎が自身を投影した登場人物なんでしょうね。
小津作品にしては
戦後5年、変わると変わらないの混淆
田代(上原謙)は家具屋で成功しているからか、余裕があって優しくて戦争を引きずっていない。一方、節子(田中絹代)の夫の三村(山村聡、適役!)は職がなく飲んだくれで最後は妻の頬を何度も叩いて離婚への道を自ら招いてしまった。三村は机に向かってドイツ語の本を読んでいた。文学か哲学か法律か医学か。いつの時代もインテリはそう簡単には職につけない。そして戦争での体験から抜けられない。
全く自分に合わない仕事、バーの経営をしている節子は昔のタイプの女だが、変わったのは世間だけでなく自分も変わった、と言わざるを得なくなった。でもその言葉はとても強くて「夫婦」という仕組みにはもう依存しないという、自分と田代への宣言のように聞こえた。節子の顔は晴れ晴れして暗さはもうなかった。
高峰秀子はベロを出したり口を尖らせたり本当に可愛らしい。時代の変化についていきたい好奇心と生命力がまぶしい。姉を慕い大切に思う気持ちは本心からで心優しい妹だ。姉も妹も、古さと新しさの両方を抱えながら前を向いている。
小津安二郎の映画にしては、俳優の個性がとても生かされていて、台詞のメッセージ性が強く、原作者・大佛次郎の魂がこもっていたように思った。
序盤うとうと
節子の信念の「新しさ」
<映画のことば>
新しいものって、いつまでたっても古くならないもののことをいうのよ。
本当は田代への思いを胸に秘めながらも、節子はどういう成り行きで三村に嫁ぐことになったのかは、本作の描くところではなかったと思いますけれども。
たぶん、話の成り行きからすると、父親・忠親の押しがあったのかとも思います。
(三村を見込んで節子を嫁がせたものの、今となっては彼の言動に、病を得て死期が見えている忠親の自分自身も胸を痛めているように見受けられますけれども。)
そんな節子を見ているためか、妹の満里子は、姉の生き様に対する、いわば「反発」として、あえて自由な生き方を模索しているかのようにも見受けられました。
評論子には。
そう高級そうにも見えなかった「ふだん通い」のようなショットバーのような店に出ている時を含めて、常にいつも和服をきっちりと着こなしている節子と、いつも(自由な)洋装の満里子。
死期か予告されていた忠親よりも先に三村が不慮の病死というのも運命の悪戯(いたずら)というほかないのかとも思いますけれども。
それでも、三村が亡くなっても、安直に(?)田代に走らなかった節子の信念の固さには、感銘も受けました。
「三村亡くなったから、今度は、もともと思いを寄せていた田代の下へ」というのでは、自分で自分が許せもしないし、本当に気持ちを許している田代に対しても失礼な話ー。
節子の心中は、たぶんそんなところだったのではないでしょうか。
田代に別れを告げたときの節子の表情からは、そんな彼女の思い…いつまで経っても古くならない彼女の信念の常の「新しさ」が、ありありと読み取れたように思われます。
評論子には。
そういう点では、佳作の部類に入る作品だったとも思います。
#午前十時の映画祭14 今週は #小津安二郎 監督『#宗方姉妹 』...
#午前十時の映画祭14 今週は #小津安二郎 監督『#宗方姉妹 』(1950)。
#田中絹代 さんと今年生誕100週年を迎える#高峰秀子 さんが姉妹を、#笠智衆 さんが二人の父を演じるが、絹代さんと智衆さんの歳の差はわずか5歳…恐るべき老け役です。そして恰幅の良い指揮官役や大物役を演じる前のスマートな #山村聡 さんも貴重でした。
本日は監督独特のローアングルのカメラポジションをぜひ劇場の大スクリーンで検証してみようと試みましたが、なるほどなるほど、欧米のテーブルと椅子文化と違って日本は和室。床に座った時に確かに綺麗に撮れますね。
そして、部屋と部屋を「襖」「障子」の開き加減や、箪笥などの調度品をうまく活用して「奥行き」を出して、ちょうど画面中央の演者にフォーカスさせていましたね。まさにモノクロ版『アバター』。
カメラはしっかり固定されてますが、上手く「襖」や「障子」で部屋と部屋を区切り、演者を横切らせて横移動の動きを生み出すことには感心しましたね。
屋外のシーンも、どれも丁寧に構図が練られていて驚きました。
ヴィム・ヴェンダース監督が敬愛するのも納得、私もしばらく写真を撮るときは、屈んでローアングルを狙ってみようと思います。
「新しい、ってことは古くならないもののことなの」
姉(田中絹代)は結婚しているが、夫(山村聡)が失業し実家で暮らしている。
妹(高峰秀子)は未婚、義兄を毛嫌いしている。
父(笠智衆)はガンで余命半年、別荘でひとり暮らしだ。
姉妹はバーをやっているが、姉の元カレ(上原謙)がやってくる。
妹は元カレを応援するが、姉は・・・。
小津安二郎が東宝で撮った作品で、姉の台詞、「新しい、ってことは古くならないもののことなの」がすべて。
なかなか味のある良作
小さな波のある家庭映画、 当然だが姉妹の会話が多い
名作なのだろうが、
感動する場面や、楽しい場面が少ないので、少し退屈だった
白黒なのも退屈の一因かも
なお、驚く場面はあったが、嫌な場面はなかった
面白かった所は
1.満里子が、舌を出す所
2.満里子が、声色を使う所
3.満里子が、猫の首を掴み落とす所:27分頃
4.満里子が、亮助と口論する所:78分頃
高峰秀子も若い時は、活発な娘役をやったと判明
今まで、温順な役の映画しか見たことしかなかったので、新鮮な驚き
本当の名作を観た満足感の余韻にしばし呆けてしまった
素晴らしい傑作です
流れる疎水の如く淀みなく進行する筋書き
そこに田中絹代と高橋秀子の二人の名女優の頂上決戦
丁々発止と火花のでるような名演合戦が見ものです
何から何まで、何もかも本当に見事で溜め息がでます
大好きな作品です
三村が職を得たという話
あれは嘘なのか、実は前から来ていたが気乗りせず断っていたものなのか
いずれにしても節子を失いたくなかった気持ちは熱く伝わった
それが節子に取って幸せにはならないとわかっていてもなおそうせざるを得なかった
本作の配役はどれも見事につきるが、この三村役に山村聡を配したことが最大の成功だと思う
もし森雅之ならどうだろう
そんな死に方はしない、お話しが全て嘘になってしまったろう
田中絹代と高橋秀子の対比は、本人の持つ性質が役柄と渾然一体となっており本当に見事だった
節子の選んだ結論の余韻はまた深い
田代宏もまた深い傷を負った
彼はこれからも彼女以外の女性を愛せはしないとハッキリしてしまったのだ
けれども二人の姉妹の愛情はより深く固くなったのだ
父もまたそう長くはなく姉妹二人で生きていくのだ
本当の名作を観た満足感の余韻にしばし呆けてしまった
・ペロッと舌出した後のンン〜がかわいいぞ ・姉の言う「古い、新しい...
全21件中、1~20件目を表示