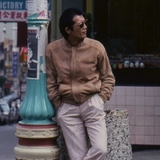激動の昭和史 沖縄決戦のレビュー・感想・評価
全35件中、1~20件目を表示
仲代達矢さんの訃報を機に、改めて振り返る1971年の映画「激動の昭和史 沖縄決戦」。
牛島満中将を小林桂樹さん、長勇参謀長を丹波哲郎さん、そして八原博通高級参謀を仲代達矢さんが演じ、これら主要な出演者が全員鬼籍に入られた今、作品の重みがより一層胸に迫ります。
沖縄戦を知りたいと思い立ち、最初に観たのがこの一本でした。
この映画は、単なる戦闘描写ではなく、インテリ層の将校たちの最期の日々を描き、欧米文化に親しみ、人生を楽しむはずの彼らが、軍国主義の渦中で「神国日本」「鬼畜米英」のスローガンに縛られていく姿が意外で衝撃的でした。
牛島中将と長参謀長のやり取りに、沖縄戦が決して遠い昔の話ではない実感が湧き、戦争の「分断」がもたらす恐怖を強く感じました。当時の日本には、洋風の言葉さえ禁止されるほどの狂気が渦巻いていた日本
特に印象深いのは、仲代さんが体現した八原高級参謀でした。
第32軍の参謀で唯一の生き残りとして、戦後『沖縄決戦』という赤い本を出版し、真実を後世に伝えた人物です。沖縄の我が家にもその本があり、戦後、生活が落ち着いたウチナーンチュ(沖縄の人々)がこれを読み、自分たちの体験した沖縄戦の、実際の戦況を初めて正確に知ったんだそうです。
この作品を観て、戦争を生き延び、復興を担った父と一緒に語り合いました。
父は無口で仏頂面の近寄りがたい人でしたが、心に大きな悲しみを抱え、「生き恥をさらした生き残り」として悔しさを胸に、日本復興の使命を背負って生きてきた人でした。八原参謀は、そんな「生き残る者の象徴」で、自暴自棄にならず、覚悟を持って前を向く姿に、父世代の矜持を見ました。仲代達矢さんは、そんな希望の光を演じきった「希望の人」だったと思います。この映画は、単なる歴史劇ではなく、失われた命と未来への責務を問いかける永遠の教訓だと思います。
【”沖縄は本土の為にある、と愚かしき大本営参謀総長は言った。”今作は壮絶な沖縄戦を様々なショットで描いた作品であり、この鑑賞するにはキツイ映画を製作した岡本喜八監督の功績は大きいと思います。】
ー 岡本喜八監督と言えば、私にとっては「日本のいちばん長い日」が記憶に残るが、今作の様なドキュメンタリータッチの苛烈な沖縄戦を描いた作品を遺していたとは知らなかった。
今作では、大本営総長たちの本土決戦を避けるための判断が、淡々と描かれる一方、沖縄を守る第三十二軍司令部の、牛島中将(小林桂樹)、長参謀長(丹波哲郎)、八原高級参謀
(仲代達矢)等の姿が対照的に描かれている。
牛島中将は、戦後名将と言われているが、沖縄の民15万人の命を犠牲にした事で評価が別れる人である。が、今作では冷静沈着、温和な人物として描かれている。
直情型の長参謀長を演じた丹波哲郎、冷徹な八原高級参謀を演じた仲代達矢も存在感がある。実際には牛島中将は二人を御せなかったという話もあるが、今作ではそれは描かれない。
印象的なのは、死地に赴くのが分かっているのに、とっとと逃げ出した前県知事の後釜として赴任した島田叡知事(神山繁)が、県民を懸命に助けようとする姿であろう。この方を描いた映画を観てから感銘を受け本も2冊読んだが、何とも立派な方である。
だが、それでも沖縄の民を救えずに、自身も沖縄のジャングルに消えた方である。
沖縄の民の、次々に砲弾に倒れ、自決していく様は、観ていてキツイが、これが事実なのであろう。
数年前に”ひめゆりの塔”に対し、不適切発言をした愚かな与党議員が居たが、政治家であるならば正しい歴史観を持つべきである。与党にはほかにも似たような輩がかなりいる。
<この映画で描かれる苛烈な戦闘シーンは観ていてキツイが、後世に悲惨な沖縄戦を伝える作品として、その制作意義は大きいと思うのである。
名匠、岡本喜八監督による強烈な反戦映画であろう。当時の邦画の有名俳優が多数出演しているのも、意義深いと思った作品である。>
丹波だ
今こそ観るべき作品ではないかと思います
尊敬する岡本喜八監督と日本映画界の巨人、新藤兼人さん脚本の豪華タッグで撮り上げ、大阪万博の翌年に全国公開された
今ではすっかり埋もれたこの傑作がAmazonプライム・ビデオで今なら400円でレンタル可能だ
敗色濃厚な日本政府は米軍の侵攻を遅らせるため、沖縄を防波堤に変えるべく沖縄住民を強制的に巻き込む軍民一体体制を構築
軍隊が民間人を護るどころか真逆のことを強いた
軍は住民を様々な方法で行動を共にすることを強要。そのため米軍も民間人の区別が付かず無差別に殺戮。そのおぞましく忌むべき事実が今、日本人の中でさえ風化しつつある
岡本喜八節全開でスピーディーかつユーモアまで交える手法を選び、敢えて悲劇を悲劇らしくウェットに描くことなく、心の奥底へリーチすることを勇気を持って選択している
戦後80年の今こそ観るべき作品ではないかと思います
ジブリを大金かけて何度も放送するのも決して悪くはないが、地上波でたった一度でもいいから、放映する勇気のあるTV局はないものか?
「人間の條件」も放送されないネ
冒頭部に軍民一体を加速させる契機として淡々と描かれる対馬丸事件
こちらの周知度も気になる
生存者には箝口令が引かれたため
戦後長きに渡り語られることがほぼ無かった
戦後80年 清算されない歴史がまだまだ多くあり、子孫へ課題として積み残したままだ
沖縄決戦の犠牲者
米国側は1万2520人。日本側はその15倍、18万8136人が亡くなったとみられている。このうち沖縄県出身以外の日本兵は6万5908人。沖縄県出身の軍人・軍属(正規の軍人、防衛隊や学徒隊など)は2万8228人。一般住民は9万4千人。沖縄県民全体では12万2千人以上、県民の4人に1人が亡くなったといわれている。
戸籍が消失し、家族全員死亡などで証言なく、いずれも推計した数字だ
現代日本映画界では作り得ない岡本喜八作品!
よりドキュメンタリータッチで描いた方が良かったようにも感じ…
日本人として知るべき沖縄戦を描いた作品
として、また、岡本喜八監督+新藤兼人脚本
への期待もあり、TV放映を機に初鑑賞。
更には、日本軍兵士と沖縄住民との関係が
どう描かれているのか、との関心もあり
観てみたが、全編、
沖縄戦での地獄絵図を見せられたような
印象で、その点においては
リアリティー溢れる作品のように感じた。
しかし、映画そのものの出来としては、
岡本喜八も新藤兼人も不在であったかの
ような、そんな地獄の羅列にしか見えない
作品のようにも感じられた。
多分に、エピソードの盛り過ぎと、
戦いの時系列にこだわった結果なのか、
作品全体としては芯の細い各エピソードの
バラバラ感があるばかりで、注目していた、
日本軍兵士と沖縄住民との問題についても、
幾つかの描写はあったものの、
特に、ガマでの悲劇を中心とした
兵士と住民の確執への踏み込みが
不充分なばかりか、
米軍の非情性の強調ばかりだったのは
残念な脚本と演出に感じた。
また、戦闘シーンにも注力する必要が
あったためかも知れないが、
3人の将校を初め、
各登場人物の心理描写が中途半端な印象。
だとしたら、そんな演出要素も切り捨てて、
同じ岡本喜八監督の傑作
「日本のいちばん長い日」のように、
より徹底したドキュメンタリータッチで
描いた方が良かったようにも感じたのだが。
人間の本質
文民保護、民間人を加害しないという国際法上のルールは1949年のジュネーヴ条約で規定されたらしいので、太平洋戦争時においては明確に違反ではなかったといえるのだろうか。そこら辺の解釈はよく分からないが、銃後もへったくれもなく、民間人が多大な犠牲を被ったという点で特筆すべきなのが沖縄だし、日本軍のどうしようもなさが極まったのもここ沖縄。そのどうしようもなさは、実のところ人間の負の側面そのもので、我々現代に生きる者も同じような行動をとる素地があり。戦時のみならず、平時において同様な行動をとっているのではないか、という内省に至る。
沖縄、自決したりさせられたり、戦うこと守ることを強いられたり。老若男女、誰にとっても生き地獄だっただろう。10代で爆弾抱えて突撃とか、青酸カリを口に含むとか。今の時代の若者には今の時代の苦悩があるとは思うが、戦時の若者の背負っていた十字架に比べ、私も含めなんと荷の軽いことか。
彼らの荷を代わりに背負う必要はないが、人生を選べなかった彼らに思いを馳せ、自分自身の人生を胸を張って生きられるように。そんなことを思う。
そして、摩文仁は時間をかけて訪れておきたいな。
「県民に対し、後世特別のご配慮を賜らんことを」
昭和19年、大本営は米軍の侵攻を沖縄で食い止めることを決断。人格者の牛島中将が着任し、豪胆な参謀長の長少将、優秀な高級参謀八原大佐らと作戦を協議する。しかし大本営は航空決戦の意向にも関わらず、十分な部隊は送られてこない。沖縄司令部は、陣地を構築して戦いに挑むものの、圧倒的な兵力差で市民も犠牲になっていく。
昭和の俳優が大挙して出演、それにまず圧倒されます。そして物語は凄まじいテンポで展開し、そして内容の濃さに驚かされます。よくこの尺に収めたものだと、監督の手腕にただただ感服しました。小禄の海軍陸戦隊太田中将が残した「県民に対し、後世特別のご配慮を賜らんことを」という言葉が深く印象に残ります。県民のうち、三分の一、15万人が犠牲に。
多くの人に観てほしい
山岡荘八の『小説 太平洋戦争』や、吉村昭の『殉国』で、
沖縄戦の概要は知っていた。
初めて映像として観た。エアコンの効いた部屋で、ビール飲みながら。
50後半の自分が生まれる僅か20年ほど前にこんな出来事があったのかと思うと、
なんとも言えない気持ちになる。
当時の状況からすると如何ともし難い米国の攻撃への防衛、
玉砕したり、逃げまどったり、命を散らした民間人その数およそ12万人
(軍人はおよそ8万人、あわせて20万人)、
死んでも何にもならないんだが、死ぬしかない儚さ。
この沖縄戦で、日本の敗北はほぼ100パーセントとなった。
しかし、政府上層部は降伏の決心がつかず、この後、東京始め各地の空襲、
広島長崎の原爆と、戦争は、さらに数十万人の命を召し上げることになる。
開戦は避けられなかったかもしれないが、終戦へのアプローチを
もう少し強力にできなかったものか、と感じてしまう。
映画観て、画面に合掌したのは、初めてだ。
厳しい現実を突きつけられた様な展開
沖縄県民斯ク戦ヘリ
単なる英雄譚ではない反戦への強いメッセージ
新文芸坐さんにて「映画監督・岡本喜八 生誕100周年記念プロジェクト in 新文芸坐 vol. 3 「戦中派」岡本喜八」にて『激動の昭和史 沖縄決戦』(1971)を8月15日に鑑賞。
『激動の昭和史 沖縄決戦』(1971)東宝8.15シリーズの第5作。
岡本喜八監督、脚本は新藤兼人さん。
実際に戦火を越えてきた岡本喜八監督らしく太平洋戦争末期の沖縄戦を客観的な視点で捉え、敵兵の演出もできるだけ排除、日本軍と市井の人々のみフォーカスを当てることで凄惨な沖縄の事実を描ききり、単なる英雄譚ではない反戦を訴えかけておりました。
軍司令部の小林桂樹さん、丹波哲郎さん、仲代達矢さんをはじめ、中谷一郎さん、高橋悦史さん、岸田森さん、天本英世さんの喜八組の面々、川津祐介さん、池部良さん、
鈴木瑞穂さん、神山繁さん、浜村純さん、東野英治郎さん、東野英心さん、井川比佐志さん、田中邦衛さん。そしてナレーターは小林清志さん。
当時としてもオールキャストだったでしょうが、とにかくキャスト、ナレーションが多彩で重厚。
2025年終戦80周年になりますが、本作品のような個性的で重厚なキャスティングはなかなか想像がつきませんね。
毎年この時期はこのような映画ときちんと向き合いたいですね。
罪を贖えるのか?〜沖縄を知るキッカケに
映画の中盤、
宅嶋徳光海軍中尉が遺した有名な詩が印象的に読み上げられる。
(映画では触れられないが、実は、宅嶋中尉が戦死したのは東北地方で、直接的には沖縄戦とは無関係な存在と言える。作中、菊水作戦で散りゆく特攻隊の実写映像を背景に、彼の詩がインサートされる)
『俺の言葉に泣いた奴が一人
俺を恨んでいる奴がひとり
それでも本当に俺を忘れないでいてくれる奴がひとり
おれが死んだらくちなしの花を飾ってくれる奴が一人
みんな併せてたった一人』
これだけにとどまらず、
敗色濃厚な中、命じられるまま死地に赴く若者たちにヒロイズムをくすぐられる演出が随所に顔を出すが、
それらのみに気をとられてはならない気がする。
対馬丸事件、
伊江島の戦い、
菊水作戦(陸海軍航空隊による大規模特攻)
沖縄水上特攻(戦艦大和の最期)、
義烈空挺隊、
ひめゆりはじめ多数の学徒隊・・・
邦画でありながら、
日本軍が完膚なきまで負け続ける姿、登場人物の大半が次々と亡くなるのを、これでもか、これでもか、というくらい見ることになる訳だが、
これを製作した皆さんは(私の勝手な想像だが)、
・戦争の悲惨さや無益さを訴えるだけでなく、
・強引に日本国に編入した「琉球処分」から、わずか70年足らずで、15万人以上の犠牲を出した沖縄県民への贖罪の意味の記録を残したかった、
のだと信じたい。
陸軍中枢が『本土決戦のための時間稼ぎ』と沖縄戦を位置付けた瞬間から、
残念ながら、沖縄は本土として扱われていない。
島国・日本が、本土と離島を区別している事自体が歪んでいるし、悪い冗談としか言いようがない。
ラストシーン、老婆がアメリカの戦車に向かい、踊りながら近づいていく。
『唐船ドーイ』の歌声が胸に突き刺さる。
琉球処分から沖縄戦まで、日本が沖縄にしてきたことを知れば、「基地が沖縄に集中するのは、地理的に仕方ないよ」なんて簡単に言えなくなるはずだ。
沖縄を舞台にした戦争映画
東宝の作った8・15シリーズ、岡本喜八監督作。
タイトル通り、第二次世界大戦末期の沖縄を舞台にした戦争映画。
記録フィルムを使用したりしながら、本編は基本的にカラー作品として作られている。
戦争の惨さを描いており、力作ではあり、「戦争は起こしてはいけない」と痛感する映画である。
しかし、沖縄で起きたことを万遍なく捉えようとしたためか、それとも主役級俳優が多数(小林桂樹、丹波哲郎、仲代達矢)いるためか、全体的に散漫な印象を受ける映画になってしまっているのが惜しい。
尺も約2時間30分とそれなりにあるが、細切れ感は否めない。
東宝作品なので、酒井和歌子も大勢の中の一人として出演しており、みすぼらしい戦時中の格好をしているが、やっぱり好きな女優の一人。
毎年、お盆近くになると、上映されたり放映されたりするが、今回は日本映画専門チャンネルにて鑑賞。
<映倫No.16757>
日本人なら観るべきかと。
沖縄県民は帝国陸軍 第32軍に殺されたようなものと解釈できるが、本当にそうなのか?
この映画を見る限り、沖縄県民は帝国陸軍 第32軍に殺されたようなものと解釈できるが、それで良いのだろうか?ここまでひどかったのか?
この前見た 『ひめゆり』 もそうだったが、なんで似たような話になるのだろうか?
3分の1が死んだのだから、3分の2は生き残ったと思う。生き残った術を描いてもらいたかった。戦争に負けた歴史だから仕方ないのだが。
また、何故、沖縄県民は大日本帝国陸軍に忠義を立てようとしたのか?その理由がハッキリしていない。もとを正せば琉球王国。琉球処分(併合)が1874年だから、その時から、100年も経っていない。
沖縄返還の年に公開された映画だと思うが、僕が沖縄県民で、この映画が事実だったら、沖縄返還を素直には喜べない。
僕のルーツは新潟県だが、沖縄県民の忍耐強さや純粋な所に、頭が下がる。
僕なら絶対に生き残りたい。逃げる。帝国陸軍でも逃げる!沖縄県民だったら、真っ先に逃げる。何と言われようが逃げる!真っ先に白旗少女!
仲代達矢さん演じる主人公は降伏して、生き延びている。そこをきちっと評価できないのだろうか。僕が評価できる所はそこかなぁ。
県民の違いはロシアとウクライナの違いくらいあるのでは?
もはやこれまで
50年で日本人は変わった
史実を元に悲惨さを伝える。
50年前の岡本喜八作品。
濃い。凄みがとんでもない。
今後、延々もう出せないのではないかとさえ感じた。
内容ではなく、作り手側に対して、
日本は変わったし、日本人もたった50年で変わり切ったとつくづく感じた。
今の人が見たらどういう感想を持つだろうと想像して、なんだか萎えた。
物語は史実なのだから今さら言うまい。
どうしても言及しておきたいのは作品を組み上げた人間側であろう。
監督、脚本家はもちろんのこと、
どうしても目につく出演者など、外国人にさえ見えた。
顔、体格に始まって、体の使い方に声を含む演技も、
名優揃いとはいえ存在感がとんでもない。
この間見てきたNo Time To Dieに放り込んでも違和感ないだろうとさえ感じた。
(そうえいが丹波哲郎さんが「007は二度死ぬ」に出てたのもうなずける。仲代達矢さんは仏俳優のようだったし、東野英治郎のような俳優さんは今いるのか)
現代はさらさら、繊細な素麵なら、こちらは少々煮ても歯ごたえしっかりの讃岐うどんか。
どちらもいいが、好みはやはり食べ応えあるうどんだ、
としみじみ感じた作品となる。
しかしこれ以上、細くなったら今の日本人、消えてなくなるのでは。
全35件中、1~20件目を表示