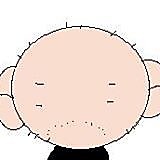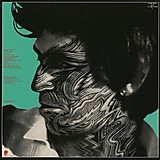許されざる者(1992)のレビュー・感想・評価
全84件中、41~60件目を表示
完全にイーストウッド西部劇のファン向け
今まで観た映画の中で1、2を争うほど好きです。
しかし本作の肝は、昔ながらの西部劇の根底を覆しているところにあるので、”そもそも西部劇の伝統やお約束を知らない”という人にはおすすめしにくいです。
できれば、ハワードホークス的な伝統的な西部劇、イーストウッドがブレイクさせたマカロニウエスタン、さらにイーストウッド監督西部劇を一通り観たあとに集大成として観るのが断然おすすめです!まさに終着点なので。
監督の功績を歴史に残すという意味でも、本作のアカデミー賞受賞はとても意義のあるものだと思います。
ちなみに、最近の映画でいうとスリービルボードが近いテーマを扱ってると思うので、同作のファンなら西部劇好きじゃなくても楽しめるかもしれません。(あれも現代舞台の擬似西部劇的ではありますが)
何に怒るのか
西部劇は、私はマカロニウェスタンが好きでそういうものを一昔前に結構見ていた。一方で荒野の七人とかそういうのはあまり記憶にない。
そういう自身の経歴というかフィルターで見ていて新鮮だったことがある。これまで悪党が暴れるというのは普通に見受けらたが、同時に無秩序な世界というのが、なんとなくではあるが前提に合ったような印象を持っている。
対してこの作品では、保安官という存在を通して秩序というものが強く印象付けられている。しかしその保安官こそ悪党だと、主人公は言い放つ。
通常であれば正義の味方として描かれるはずの保安官が殺されることにどんな意味があるのかと見ていて感じたのは、正義とか悪党とかという立場よりも、平気で人の尊厳を踏みにじるような真似をするやつに対する怒りがこの映画を下支えしているということだ。
だれにだってプライドがある。娼婦にだって、主人公の相棒にだって、どんな人間にもある。そこをないがしろにしたからこそ、ライフルが火を噴いたとみていて感じる。
複数回鑑賞して見えてくることがある、さすがの名作
Best of イーストウッド作品として必ず名前のあがる、アカデミー受賞作。運び屋含め、直近のイーストウッド作品を先に観てから遡り、満を持しての鑑賞だと、一度観ただけでは、このシンプルなストーリーのどの部分が名作と呼ばれるポイントなのか、見えなかったのが正直なところ。
グラントリノやアメリカンスナイパーで受けた衝撃のせいで、マニーは自ら殺されに酒場に行くんじゃないか?と勝手に予測した結末。予測は全くお門違い。この作品以前の一般的な西部劇のセオリーや、イーストウッド出演作のパターンを知っていれば、異色の西部劇であるということがすぐわかったのでしょうが。
あれ?悪い奴殺しちゃうんだ?あれ?しかも、宿の主人から殺っちゃうんだ?と、別の衝撃を受けたラスト。
見終わって、しばらくしてから理解したのは、これが、以降に氏が生み出す名作のスタンダードを示唆しているということ。
人を殺すとはどんなことか、のリアル。
過去の過ち、または、昔取った杵柄に捉われる主人公。
正義と罪の境界線。
二度観て、やっと、名作と言われる所以、シンプルなストーリーの中に散りばめられた細かな演出の伝える意義が少しわかった気がします。
一つ気になっているのは、モーガンフリーマンを起用した意義。南北戦争直後に、あの立ち位置での黒人のガンマンの存在がどれだけ一般的だったのか、知りませんが、ネッド役は意図的に、黒人起用したように思えてなりません。見せしめの暴力の後に生きて返されたイングリッシュボブに対して、あっけなく殺されたネッド。1880年代を描きながら現代社会の闇に対する批判やメッセージが、そこには込められているのかも。作品が公開されたのは、LA警察によるアフリカ系アメリカ人への暴行事件の直後。ジーンハックマン演じる保安官のモデルは、その問題の警察官だとか。
などなど考えると、何度か鑑賞を重ねてこそ見えてくるものがある、深い作品なのだと納得させられます。
昔懐かしい感じの西部劇。ラストの撃ち合いの迫力はさすがだった。保安...
昔懐かしい感じの西部劇。ラストの撃ち合いの迫力はさすがだった。保安官も賞金稼ぎも見方によってどちらも許されざる者となっていく。善悪ははっきりつかないが人殺しが罪なのは間違いなく、結局両方とも悪なのだろう。
名作バランス映画
正義とはなにか・・・。
腰抜けました、凄すぎ
最高にして、最後の西部劇
最後の保安官との対決はこれ以上の西部劇はない
雷鳴轟く中、雨が叩く路面をカメラがなめて遠目にサロンを写すシーンから続く展開は神レベル
イーストウッド、ジーンハックマン、モーガンフリードマン役達者ばかり
相棒の死を知り10年来飲んでない酒をあおってからの、歯止めが吹き飛び冷酷な男に戻ったことを象徴してからの演技の凄み
特にカウンターでまた飲んだあとのシーン
一瞬のためらいをみせるも、結局、許す事をせず止めをさすシーン
彼こそが許すことができなかった男だ
静まりかえり拍車の音だけを響かせサロンを去るシーンに続き、全てが終わり呆然と見送る娼婦たちの表情!
それは本作を観た私達観客の鏡だ
もうまともな西部劇を撮れるのは自分しかいない
その自負をもって、主人公の設定も、時代設定もまた西部劇の最後の時代を描いてみせる
つまり自らハリウッドの西部劇を締めくくってみせたのが本作だ
西部に帰ってきたイーストウッド
真面目に撮った西部劇
見たことのない西部劇
悪名高い悪党と対峙し、決闘の末物語が終焉する今までの西部劇をひっくり返すほどの衝撃でした。
主人公をはじめとした人物が丸腰の相手に躊躇なく引き金を引く。西部劇でそんな光景を見たことがあったでしょうか。
登場人物全てが欲にまみれ暴力を行う。人間は誰しも正義と悪の二面性を持った生き物だと訴えかけられたようでした。
映画ではよく主人公が際立って美化されがちですが世界はそう単純ではなく容赦ないのだと実感させられました。
リチャードハリスはフルボッコにされ、モーガンフリーマンはなぶり殺しに。とにかく容赦の無さはすごい。
マカロニウエスタンの色がとても濃い。
酒乱
「アッ、こいつ呑んでしまってる!」重要な瞬間なのにさりげない、自然と瓶に手が伸びる。イーストウッドらしい演出。
酒場に戻ってきた時のたたずまいの凄み、他を圧する。最初に店の主人を無造作にヤルのもいい。プライオリティに意味がある。人を殺めることの精神的負担について、滑稽なまでの銃撃シーンを見せておきながら、ここでは躊躇いがない。人の心を失ったのだろう。いやはや、酒の力は恐ろしい。
様々な変化球がさりげなく投げ込まれてくる。先の銃撃シーンもそうだ。「パスっ」といって最後にヒットする。仕留めた感がうっすら表情に滲む。「エッ?効いてるの?」と聞いてしまう。本人はまだ動いているし。しかし、じわじわと弱る。「ああ、効いたんだ」と気付かされる。
ジーンハックマンの牢屋での緊張感も良い。非情な覚悟で秩序を護る者。漢の中の漢。しかし、本人が少しドヤ顔しているのは、イケテナイ。下手くそ大工のことに触れられると、マジ切れされる。そのイケテナイ感の方が最後まで延伸される。
ダーティーハリーのおっさんが監督業に手を出して成功したというのが当時の印象。今や巨匠。同じような転身の成功事例の先駆けにもなった。イーストウッドらしさ溢れる名作である。
銃と暴力が支配する世界。許されざる者とは?
ネットで視聴(英語字幕)
舞台の背景は1881年のアメリカ西部。
アメリカではまだ西部劇の真っ最中だが、ヨーロッパに目を転じると、イギリスはヴィクトリア女王治下の最盛期の時代。
「デビッド・コッパーフィールド」が発表されたのが1850-51年。
作者のチャールズ・ディケンズが亡くなったのが1879年。
ジェーン・オースティンの「高慢と偏見」は、70年あまり遡って1813年。
フランスは第3共和制の時代で、パリ・コンミューンが10年前の1871年の5月。
「ボヴァリー夫人」(1856年)の作者フロベールが1880年に亡くなっている。
ドイツは鉄血宰相ビスマルクの時代。
「資本論」(1867年)のカール・マルクスが亡くなったのが1883年。
ロシアはアレクサンドル2世の時代。
ちょうどこの年、1881年にドストエフスキーが亡くなっている。
代表作の「罪と罰」は1866年、「カラマーゾフの兄弟」は1880年。
日本は1868年の明治維新を経て、立憲運動が盛んになっていた時代。
1881年は国会開設の勅諭が出され、板垣退助が自由党を結成した年。
こういうふうに、1881年は、ヨーロッパでは資本主義・帝国主義の爛熟と国家間の衝突が眼前に現れつつあり、後発国である日本も、列強に追いつこうと国家体制の整備を急ピッチで進めていた時代。
一方、アメリカでは、住民が拳銃を振り回しながらマン・ハントをやっていた。
オースティンやディケンズが描いたイギリス中流社会や、フロベールの田舎風景、ドストエフスキーによるペテルブルグの地下生活に比べると、いかにも野蛮で、文明の遅れが目立つ(今も?)。
映画ではイギリスから来たガンマンが登場するが、アメリカはこの時代、はぐれ者や冒険家たちが、一攫千金を夢見て数多くやってきたのだろう。
かれをはじめ、主人公のマニー(クリント・イーストウッド)も、友人ネッド(モーガン・フリーマン)も、保安官リトル・ビル(ジーン・ハックマン)も、みな荒々しい無法者で、暴力や殺人を意に介さない。
町の人間たちもその点は同じだ。
人を雇って殺そうとする娼婦たちも。(実際にカウボーイが殺されている)
唯一まともそうなのが、ネッドのインディアンの妻とマニーの子供たちだけという世界。
銃と暴力が支配するこの世界で、許されざる者というのは、はたして誰を指すのだろうか。
映画は傑作。
何度見ても見飽きない。
ヒーローか、はたまた
全84件中、41~60件目を表示