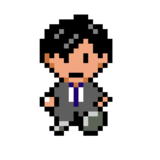「報われなくても善きことをする——戦後日本を癒し支えた「敗者の倫理」」七人の侍 nontaさんの映画レビュー(感想・評価)
報われなくても善きことをする——戦後日本を癒し支えた「敗者の倫理」
3週間限定の4Kリバイバル版上映。ずいぶん以前、ビデオで2回ほど観ているはずだから、もう観なくてもいいかなと思いつつ、映画館で観たことがないしので、錦糸町TOHOに行ってみた。20代と思われる若い人がかなり多かったのが意外だった。
初見に感じる場面が多かった。この映画を元に作られたたくさんの映画、特に「荒野の七人」や「マグニフィセントセブン」などとごっちゃになって記憶がずいぶん改変されてしまったようだ。
冒頭の盗賊集団が馬で駆け抜ける場面から記憶になかった。ここだけで、騎馬のスピード感と重量感に圧倒され、そして、最後まで圧倒され続けた。これまで70本の感想を書いたけれど、完璧な映画が現れた時のために5点満点はどんなに感動してもつけなかった。しかし、新作ではない、この70数年前の映画に満点をつけざるを得ない。
エンドロールもなくスパッと迎える終演後、拍手が起こった(僕はぼうっとしちゃって拍手できなかった)。とにかく圧倒的な映画であることを確認できてよかった。世界的にそういう評価が定着しているから、言うまでもないのだけれど、それを実際にスクリーンで観て確認するかしないかは大違いだ。
今回、気づいたことをいくつかまとめておきたい。
まず、この映画が作られた時代背景との関連について。
本作は1954年で71年前に公開された白黒映画だ。
戦後9年。GHQ占領が1952年に終わり、やっと検閲なしで映画を作れるようになった時代。リミッターなしで全力で最高の作品を作るーー。そういう黒澤監督と、日本の映画人たちのチームの想いが伝わってくるし、その想いで団結した一流のプロたちの最高の仕事の凄みを感じさせられる。
「スター・ウォーズ」の生みの親ジョージ・ルーカスが黒澤からの影響を公言しているのは知っていた。僕はキャラクター造形のことだと思っていて、それは確かに観て取れた。
同時にストーリーの流れ(映画の構造)も酷似している。主人公が決意し、個性豊かな仲間を得て、世界のために戦い、達成する。これは、ハリウッド映画のテンプレでもある「英雄の旅」の構造そのものだ。
この構造は1949年に刊行されたジョーゼフ・キャンベル「千の顔をもつ英雄」で提示され、近年のハリウッド脚本術の本を読むと、さらに細部に渡ってマニュアル化されている。黒澤はキャンベルの本は読んでいないようだ。映画史研究にはちゃんと書いてあるのだろうけれど、知らないので推測すると、この「七人の侍」が「英雄の旅」の構造の強さの実証例となって、ルーカス始めテンプレとなるほどハリウッドに強い影響を与えたということなのではないだろうか。
ただ、大きな違いもあると感じた。典型的な「英雄の旅」は主人公の成長と自己実現の物語。成長した主人公は、困難だけれど世界にとって素晴らしいことを成し遂げて、人々から賞賛される。つまり、世界に貢献し、貢献した人々から強く承認されることでさらに報われる。
しかし、「七人の侍」では、主人公たちは貢献した相手から承認される場面はなく、自己実現した!という分かりやすいカタルシスは描かれない。最後の場面では、ファンファーレがなって、人々から賞賛されるかと思いきや、人々は以前の生活に戻り、田植え唄などを歌って、以前の生活に戻れたことを喜んでいるだけである。そして、主人公も「また負けた」と言っている。
人々からの承認はないし、主人公も多くの人を死なせた罪悪感や、もっと上手くやれたのではというような後悔を感じているようだ。
つまり、英雄には報酬も勝利の喜びもないのだが、ただ一つ「私は私にやれる善きことを精一杯やった」という倫理的な満足感は感じていると思いたい。「負けてもいい、自分にやれる善きことをやればそれでいい」というこの物語は、終戦からまだ10年経たない日本人の大きな癒しになったのではないだろうか。
それに、新自由主義、個人主義が進んだ70年後の今こそ、こうした職業観や倫理観は改めて見直し、自分の中に実装したいものでもあると思う。
主人公の勘兵衛を演じる志村喬は、この作品の2年前の黒澤作品「生きる」でも主演を務めている。こちらはお役所仕事を長年続けてきて定年間際の市役所のさえない市民課長が、ガンになってしまい、最後の仕事として公園作りに奔走する物語だ。誰もその仕事ぶりを承認しないのだけれど、主人公は「私にできる善きことがある」と、その小さな仕事のために残りの日々を使う。
報酬も承認もいらない。生きてきた証として自分のできることをやる。
自分が自分を承認できればそれでいいーーこの姿勢は、「七人の侍」の勘兵衛と完全に重なるし、公開当時の観客も志村喬演じる二人を重ねて見たはずだ。
勘兵衛と共に戦う侍と農民も、それぞれ違った動機と価値観を持っていて、一人一人が印象深い。特に印象に残るのはやはり三船敏郎演じる自由奔放な暴れん坊の菊千代だ。
英雄性のかけらも感じさせない破天荒で未熟でバカにも見える菊千代がトリックスターとしてこの物語では重要な役割を果たす。ここもしびれるところだ。
菊千代の侍姿はコスプレで、実は農民だ。農民らしい控えめさ、周囲と同調してコツコツ働く姿勢とは無縁の菊千代は、おそらく農村で浮き上がっていたのではないだろうか。そして、農村を離れ、戦国のどさくさに紛れて、浪人侍のコスプレをしたのだけれど、侍からも仲間にしてもらえない。どこにも居場所がない孤独な人物であり、アイデンティティも持てない根無草なのだ。
そして、どこに行っても浮いてしまう人物だからこそ、価値観も考え方も生き方も違う異質な人間=侍と農民を精神的に結びつけることができるというストーリーには引き込まれてしまった。三船演じる菊千代がいなかったら、この映画は随分地味な映画になっただろう。本作を元に作られたアメリカ映画では菊千代的なキャラは見当たらないように感じる。ハリウッドも、三船演じるこのキャラクターは再現不可能と諦めたのかもしれない。
若い人たちが大勢見にきていたのは、スターウォーズやアベンジャーズの原型がここにあるということが知られているからだろうか。いや、それら以上に面白い凄い日本映画があるという評価まで広がっているのだろうか。
有名な作品だけれど、劇場で見た人はもう80代、90代の先輩方以外には相当少ないだろう。大きなスクリーンで見なければ、真価はわからないし、何よりこの迫力も味わえない。この機会に観ておいてよかった。
TOHOシネマズさん、ありがとう。
ヒーローズジャーニー構文にのっとった映画は数あれど、その中で自己的か利他的かという視点で分析するとおもしろそうですね。歴史を通した民族性が映画の見方に影響するということをおっしゃってるように受け止め腹落ちしました。ありがとうございます😊