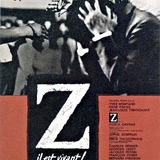エデン 楽園の果てのレビュー・感想・評価
全21件中、1~20件目を表示
北の国から、蠅の王、シャイニング、藪の中。多様な物語要素を含むが、ほぼ実話ベースという驚き
知らなかったが、1930年代にガラパゴス諸島のフロレアナ島に移住を試みた人々の間で起きた未解決事件にほぼ基づく。「ほぼ」というのは、この事件の当事者による回顧録がベースになっているからで、真相はまさに「藪の中」なのだろう。
2番目に島に来た夫婦(ダニエル・ブリュールとシドニー・スウィーニー)と息子が竹材で水路を作るあたりは「北の国から」を思い出させ、ジュード・ロウ演じるリッター博士が執筆に行き詰って狂っていくさまは「シャイニング」。孤島で権力争いが起きるのは「蠅の王」、当事者たちの間で言い分が食い違うのはもちろん芥川龍之介の小説「藪の中」とその映画化である「羅生門」。
ロン・ハワード監督が本作に着手した当初のタイトルは「Origin of Species」(種の起源)だったとか。ダーウィンの著作の題を検討したのは、ガラパゴス諸島という場所とのつながりはもちろん、生存競争、適者生存といった進化論における概念が、入植者らが島で適応とサバイバルを繰り広げるさまに重なると考えたからではないか。
アナ・デ・アルマス、バネッサ・カービーを含むメインの5人はいずれも熱演だが、とりわけシドニー・スウィーニーの変化(あるいは“進化”)が見応えあり。エンドロールで映るフッテージは、劇中でも描かれた裕福な冒険家が率いる撮影班が記録したものだろうか、映った彼らのにこやかな様子が逆に物悲しい。
なお、この事件を扱ったドキュメンタリー「ガラパゴス・アフェア 悪魔に侵された楽園」が2014年のラテンビート映画祭で公開されており、評価も高いようだ。これを機にドキュメンタリーも配信などで視聴できるようになるといいのだが。
1930年代、ガラパゴス諸島フロレアナ島で実際に起きた未解決事件に...
1930年代、ガラパゴス諸島フロレアナ島で実際に起きた未解決事件にインスパイアされた実話ベースの作品。
理想郷を求めて島に移住した人々が、次第に疑念・嫉妬・支配欲に侵され、やがて凄惨な事件へと転落していく過程を、生存者たちの証言を基に“二つの視点”から描く構成が特徴。
閉ざされた島という舞台が生む村社会的な空気、外界から隔絶されたコミュニティ特有の不穏さがじわじわ効いてくる。
そして何より強烈なのが、男爵夫人を自称するアナ・デ・アルマス(役:エロイーズ・ベアボン・ド・ワグナー・ブスケ)。存在そのものが島の均衡を狂わせる“カオスの触媒”として圧倒的で、彼女が登場するだけで物語の温度が変わる。
実話ベースのミステリーとしての面白さと、人間の欲望・虚栄・理想と現実の乖離を描くドラマがしっかり噛み合った1本。
事実は小説よりも奇なり
第二次世界大戦前、ファシズムを嫌って、ガラパゴス諸島の無人島に住み始めた哲学者夫妻(ジュード・ロウ、バネッサ・カービー)。
そこへ同じような理由と、息子の結核療養のため家族三人がやってくる。
そして悪魔のような女(アナ・デ・アルマス)がホテル建設のため、手下を引き連れてやってくる。
事実は小説よりも奇なり。
「民主主義→ファシズム→戦争の繰り返し」
楽園ぽさは全く感じないが
バネッサを見つけた映画
シドニー・スウィーニーの素晴らしさ
とても面白い
マインクラフト好きの息子と観れば良かった。
「ザ・ビーチ」といい楽園を求めたグループが壊れて行く様を観るのが好きなのかもしれない。
アナ・デ・アルマスがなんでこの役を引き受けたんだろうと言うくらいの混沌と混乱を生み出すクソビ○チで
素晴らしかった。
展開は楽園でのんびり幸せライフとは真逆で、
閉鎖された島と言う空間で、人間の汚い部分がどんどん
浮き彫りになって陰鬱な展開と、嫌なキャラクターが
次から次に出て来てストレスが溜まるが、
それが癖になる面白かった。
出産シーンのストレス度はマックスで、
誰も手伝わず、自分勝手な男たちに、
全然帰って来ない旦那にめちゃくちゃ腹が立ちました。
何が恐ろしいってこの面白い物語が
本当にあったという事。
結局領地争いに権力争い、食品の強奪と
小さい戦争が起こってしまうのが
人間と言うことなんでしょうか?
すごい実話だ
【実話ではなく、生存者の証言】
ロン・ハワード監督による重厚なサスペンス。設定や展開にはやや無理があるが、俳優陣の演技力と映像の力で最後まで引っ張る吸引力はさすが。
なかでもアナ・デ・アルマスが圧巻。単なる色気担当かと思いきや、物語の軸は彼女にあった。女性としての嫌な部分、人間の醜さまでも背負いながら、冒頭から少しずつ朽ちていくような演技に凄みを感じた。
本作はR18指定。性的な描写があるのが惜しい。18禁に頼らずとも、サスペンスとして十分成立したはずだ。監督が「人間の性」をどうしても描きたかったのだろうが、やや過剰に感じた。
25年前まで登場人物が実在したという触れ込みだが、実話なのか脚色なのか、その線引きが曖昧で惜しい。もし本当に実在する島での出来事を基にしているなら、もう少し多くの観客に届く描き方があったはずだ。
俳優たちの力強い演技と、他作品では見られない役どころが魅力的なだけに、「あと一歩で名作になり得た」という印象。完成度の高さと同時に、もったいなさが残る作品だった。
名匠に豪華キャストではあるが…
全く知らない作品だったが、ロン・ハワード監督作品ということと、何といっても超豪華キャストに魅せられて鑑賞。
島が舞台とのことで、特にアナ・デ・アルマスちゃんとシドニー・スウィーニーちゃんの海岸で戯れるお姿を勝手に妄想し期待は膨らむばかり…だが、観てみるとそんな楽園ベイビーは微塵も感じられず、のっけから不穏な空気が漂いまくる。それだけならまだ観方を変えるだけで良かったのだが、中盤からはほとんど昼メロの如く怒涛の泥沼劇へ…。これはいくらなんでもベタベタ過ぎるでしょ…とは思うものの実在の事件に基づいてというんだからしょうがないのか(汗)
自分的今をときめく二大女優の白熱の演技も虚しく、とても後味の悪いものになった。ロン・ハワード監督って、たまにこの手の安っぽい系を手掛けるのは何か狙いがあるのか、それとも単に好みの問題なのか…。
静かに暮らしたいのに、こっちに来ないで!
ビリングではジュード・ロウが最初で文句ないが、主人公は5番目のシド...
ビリングではジュード・ロウが最初で文句ないが、主人公は5番目のシドニー・スウィーニーだと思う。
3人の女性が三者三様ではまっている。
バネッサ・カービーは意見が揺るがない強気な女性を演じて眼力で納得させる、シドニー・スウィーニーはどんな女性も演じられるので今回は微妙な立ち位置の女性を演じている。
そしてアナ・デ・アルマスが場違いで派手な女性を饒舌に演じる。
その3人の一人が今までのキャリアで最上級の "悪女" を演じている。
「どうして そんな所で?」「何がしたいんだ?」と思うキャラが多くいるが実話なんだとか。
正しさという幻想
エデン 楽園の果て —— 正しさという幻想の果てに
誰が正しかったのか?この問いが、映画『エデン 楽園の果て』を観る者の胸に、終始重くのしかかる。
実話をもとにしたこの作品は、ガラパゴス諸島の孤島に集まった人々の、理想と現実、信念と欺瞞、そして「正しさ」をめぐる静かな戦争を描いている。最後に語られるナレーションは、島を出たドーラの手記と、それに反論するマーグレットの手記の存在を明かす。そして、マーグレットはその後も島に残り、ホテルオーナーとして生きたという。
果たして、正しいのは誰だったのか?この問いに対し、映画は明確な答えを出さない。だが、殺人事件の真相、論理の整合性、そして何よりも「その後の生き様」が、監督の視線がマーグレットに向いていることを静かに示している。
人はいつも、「正しいことをした者だけが救われる」という幻想を抱いている。それは、リッター博士が信じた「哲学で人々を救える」という妄想と、どこか似ている。
博士の思想に惹かれて島を訪れた人々。ハインツ一家も、バルメス一行も、皆が「逃避」という共通項を抱えていた。そして、島にやってきたばかりのマーグレットが感じた不安と孤独は、誰もが共感できるものだろう。特に、リッター博士からの冷遇は、彼女にとって「誰にも頼れない」という現実を突きつけた。
博士は「人を救う」と言いながら、隣人を冷たくあしらう。その矛盾に気づかない彼の姿は、まさに多くの白人知識人が陥るダブルスタンダードの縮図だ。彼らはもっともらしい理屈を語るとき、常に自分自身を蚊帳の外に置く。
バルメス一行は、支配欲と独占欲にまみれながら、それを自覚することなく行動する。一方、ハインツ一家は「誰とも争わない」だがそれは、争わないのではなく、争えないほどに弱かったのかもしれない。
マーグレットは、そんな一家の中で最も無知で、最も弱く、そして最も成長した人物だった。彼女は観察し、気づき、行動した。リッター博士の策略を見抜き、ドーラの不信感を察知し、腐った鶏肉をめぐるやりとりで博士を論破するような言葉を差し出す。それは、ハインツ一家が逮捕されないための、静かな保険だったのかもしれない。
ドーラは島を出たが、逮捕されなかった。証拠がなかったからだ。だが、彼女は後になって復讐に打って出る。なぜハインツが罰せられなかったのか?なぜ自分が信じたものが崩れたのか?その怒りと混乱が、手記という形で噴き出したのだろう。
だが、マーグレットの反論手記によって、ドーラは初めて自分が彼女の「掌の上で転がされていた」ことに気づく。そして、信じていたビーガンや呼吸法が「嘘だった」と思った瞬間、彼女の病は再発し、命を落とす。それは、信仰の崩壊がもたらした心因性の死だったのかもしれない。
リッター博士もまた、自らの哲学に酔いしれ、そのドーパミンに満たされていた。ドーラという信奉者の存在が、彼の「正しさ」を証明してくれる限り、彼は自分の思想に疑いを持たなかった。だがそれは、自己満足のための「正しさ」にすぎなかった。
マーグレットは、そんな人々の中で、唯一「進化」した存在だった。彼女は、リッター博士やドーラ、バルメス一行という反面教師たちから、注意深さと深い思慮、そして「したたかさ」を学び取った。それは、ガラパゴスで進化したトカゲのように、環境に適応し、生き抜くための変化だった。
そして、そこには「正しさ」などなかった。あったのは、ただ「生きようとする覚悟」だけだった。
グローバリズムのなれの果て
主演のジュード・ロウを筆頭に結構なメジャー俳優が顔を揃えているにも関わらず、なぜか日本公開が見送られた作品だ。ガラパゴス諸島のフロリアナ島で起きた実在の殺人事件を元に撮られた心理スリラーなのだが、その実態は、人類共同体の誕生から崩壊までを寓意に満ちた文体で描いた映画なのである。アメリカの凋落と共に資本主義の限界が叫ばれている昨今、現代グローバル社会の縮図としてご覧になっても十分通用する中味のつまった1本だ。
2度の世界大戦の狭間、ドイツ人哲学者フリードリク・リッター博士(ジュード・ロウ)は、文明を捨て、弟子であり恋人でもあるドーラ・シュトラウヒ(ヴァネッサ・カービー)を伴ってガラパゴスのフロレアナ島へ移住し、話題を集める。より良い人生と新たな社会モデルを追求する彼らの姿に刺激を受け、退役軍人のハインツ・ウィットマー(ダニエル・ブリュール)も妻(シドニー・スウィーニー)子を伴い島へやってくる。しかし、隣人の存在を望まないリッターとドーラに歓迎されず、両者の間には緊張が走る。その後、島にやってきたのは「男爵」を自称する大胆で謎めいた女性、エロイーズ・ベアボン・ド・ワグナー・ブスケ(アナ・デ・アルマス)。彼女は島に高級リゾートを建設する野望を抱き、ほかの住人たちを追い出そうとするが……。
映画.COMより
リッターとドーラしかいない原始的な共同体では、日本の縄文時代のように精神的なつながりが重視されている。そこへ、勤勉なウィットマー家が合流し、弥生時代の稲作のように本格的な野菜栽培と牧畜を開始、土地やロバの“所有”という概念がそこに生まれるのだ。さらに武器と兵士?を携えた植民地開拓者エロイーズが現れ、リッターやウィットマーが貯蓄している缶詰を隙をみて略奪し取引に流用、両家の分断&統治を常に画策しながら放蕩三昧生活はDSそのものといってもよいだろう。移民労働者や腹心の部下も容赦なくリストラする冷酷さを見せるのだが、しまいには両家のクーデターにあいあえなく殺されてしまうのだ。
その殺人の濡れ衣をリッターになすりられることを予測したウィットマーの夫人マーガレットは、難病を患っているドーラにフェミ的連帯で接しリッターの殺人教唆に見事成功する。(立膝片腕で)子供を産んだ女房ほど恐ろしいものはないというが、赤ちゃんに母乳をあげるため片乳をもろだしにしながら警察の取り調べに平然と応じるスウィーニーちゃんのたくまししさは、アナ・デ・アルマスのそれを軽く凌いでいた。日本のような人口減少国家とインドのような人口増加国家の勢いの差をまざまざと見せつけられた瞬間だ。
自分たちで作った農作物なんかの物々交換をしている間はそれなりに上手くバランスがとれていたものの、そこに貨幣が媒介して使われ出すと、なぜか共同体は心身ともに腐敗していく。ドーラの重症化する多発硬化病や歯の化膿、腐った鶏肉等の効果的メタファーにも注意したい。歯をすべて抜いてまで“腐敗”に気をつけていたはずのリッターが、なぜあんなことになってしまったのだろう。本作では唯一描かれていない“信仰心”や“モラル”が、この共同体に欠如していたからではないだろうか。
マックス・ウェーバーが唱えた勤勉さの喪失、不正を呼びやすい多数決という民主主義の根幹をなす制度、そして忘れてはならない信仰心や道徳心の欠如。物理的に言うならば、(グローバリズムの影響で?)曖昧になった国境、水利権をきちん定めておかなかったことも大きな問題だろう。今までお金、軍事力、科学にばかり頼りすぎていた私たちが見失っていたもの、“風の時代”といわれる今後200年の世界で最も重視される価値観を、故意か偶然かこの映画は映し出しているのかもしれない。
事実を基にした物語。1930年代のガラパゴス諸島の無人島にまず歯科...
事実を基にした物語。1930年代のガラパゴス諸島の無人島にまず歯科医で哲学者の男女二人組が住み始めてそれを見聞きしたとある家族も住み始め、ついにはその無人島にホテルを建てるために男女数人のグループが居座る。やがて事態はまるで三つどもえの様相を見せはじめて各々が敵意とずる賢さと生き残りを賭けて事件が発生していくサバイバルスリラー作品。夫婦の妻マーグレット役のシドニースウィーニーが一番気丈でしっかりとした女性を好演していた。アナデアルマスも身体を張って男を従わせるイやな女を見事に演じていた。人間の極限になった時の醜さや野生的なところなどをロン・ハワード監督は丁寧に描いていたと思う。ただ何故に今の時代にこの作品を世に出したかったのかはよく分からなかったが…。
こんな島には行きたくない
全21件中、1~20件目を表示