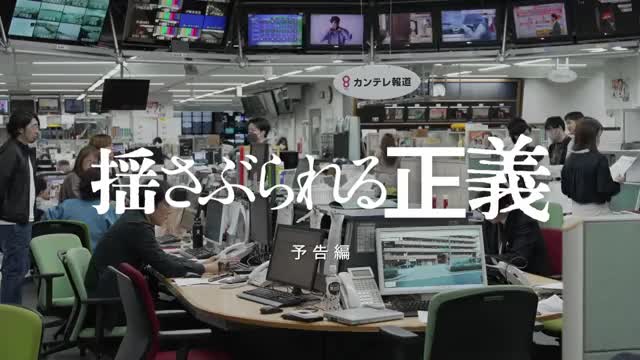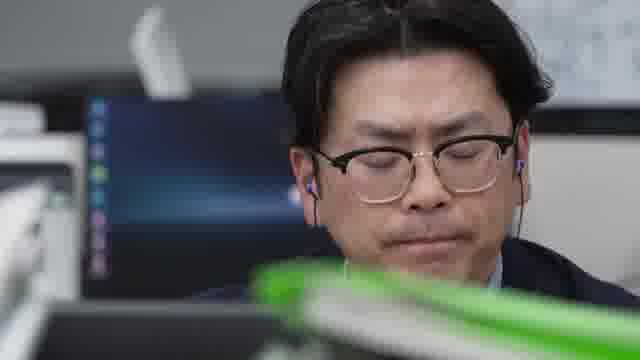揺さぶられる正義のレビュー・感想・評価
全18件を表示
「振り出しにもどる」を繰り返す
赤ちゃんを激しく揺さぶった為に脳に障害を負わせたとされた事件、2010年代当時「揺さぶられっ子症候群」と呼ばれた事案で、多くの親御さんが刑事訴追を受け、マスコミでも虐待親として連日の指弾を受け続けました。しかし、後の裁判で多くの案件が「赤ん坊の体質上の問題」や「揺さぶりとは無関係の不慮の事故」として無罪判決が相次ぎました。
親御さんにとっては二重三重の悲劇と苦難です。愛する我が子を失った上に、虐待親の烙印を押され世間から冷たい目で見られるのです。無罪・冤罪の判決が出て、それが報じられたとて一度広まった評価は二度と覆す事は出来ません。本作は、事件勃発時には世間を煽るかの如き報道をした関西テレビの記者が自身も手を染めた誤報の背景を検証したドキュメンタリーです。
本作が突き付ける問題は複雑です。冤罪はあってはなりません。「疑わしきは被告人の利益に」「推定無罪」の原則は守られるべきでしょう。しかしだからと言ってジャーナリストが尻込みしていてはあらゆる事件の報道が生ぬるく成り、場合によっては犯罪を見逃しかねません。では、どこでどんな基準で線引きされるべきなのでしょう。本作でも結論は示されず、結局は報道の振り出しに戻ってしまうのでした。進んでは振り出しに戻るを繰り返すしかないのでしょうね。辛いお仕事です。
上田さん、応援してます!
子どもが突然死ぬ。
報道のされ方と冤罪
虐待か冤罪かをめぐり、二つの異なる「正義」を深く考えるきっかけにな...
虐待か冤罪かをめぐり、二つの異なる「正義」を深く考えるきっかけになった。マスコミの安易な演出が、冤罪による差別を招き、家族を更に不幸にすることも胸に刺さった。誰のために理不尽な冤罪が面白おかしく報道されるのだろう。クロにされた容疑者たちが奪われるものに、私たちの想像力は及ばず、正義感は全く当てにならない。それぞれの正義や、それぞれの役割や都合を、根本から疑い続けることが、理不尽な世の中を少しでも改善し、信じる人を守る事につながると受け止めた。
終始、胸が痛むほど切ない
上田監督の誠実な姿勢
起訴こそされませんでしたが、ごく身近で類似の体験をした(今年です)ものとして、親子が引き離された辛さが痛いほどわかります。
映画には登場してこないもう一つの機関として児童相談所があり、その職員から当初から犯罪者のごとく扱われ子供を隔離(拉致)されたのです。起訴、逮捕、拘留などに至らない類似案件はかなり多いと思います。児童相談所の職員はマニュアル通りの対応なのでしょうが、本人との面接や自宅の育児環境確認などを通じて、明らかに虐待でないと常識では判断できる場合でも、たいへん心無い言葉を浴びせられ、改善や再発防止と称する対応を指示されました。理不尽な対応に怒りを覚えました。
虐待または不注意や過失での傷害を認めない限り子供を返してくれない事例が横行していた(いる)と思われます。
この映画では、冤罪被害者の方々も医師もカメラの前で勇気と覚悟を持って語ってくれていると思います。これは上田大輔監督が人と向き合う誠実な姿勢があってこそであり、素晴らしいドキュメンタリーです。警察発表、メディア報道を疑うことなく受け入れてしまう、SNSでの根拠ない攻撃など、私たちのあり方への問題提起として、多くの方に観てもらいたい作品です。
人が人を裁くということ。正義とは?
小児虐待から、子供をいかに守るか、誰が監視する?
何も言えない子供を大人が守るか?
誰から守る?生んだ親であり、育ての祖父母から?
子供を守る時に、家族、親が犯罪者となる事。
家族のなかから、犯罪者がでるということ。
人が生きていく上での、基本単位である、家族がやられてしまう。正義はどこですか?
冤罪がテーマであるので、明らかな、誰からみても、犯罪者はいない、そのなかで、人を裁く。
正義は存在しない。自然に起きた現象であれば、正義はあくまで自然の中にのみ、存在する。
一般の判断で正義側に立つ、警察、医師、弁護士、なども、自然のなかでは、むしろ、邪魔であり、驕りの存在である事が浮きでてくる。自然ではない、人為の介入においては、正義の判断が必要となる事がある。
人は、全てを理解、判断できると思い裁いてしまう、
そんな力は何もないのに、人の驕りが、人を裁く事になる。
自然に起きる可能性は、人為ではないと、弁護士が指摘、修正をする。悲劇からの救済としての、弁護士の活動、家族の悲劇は、心を震わせる。
ただ、監督作成者が、司法に携わったものとして、
小児虐待に携わってきた、医師が、自然な現象を、人為的であるとした事、それにともない、家族の悲劇、冤罪が生み出された背景を出すことはいいが、作り手から、映画からは、医師は、世間の名誉を優先したともとれる撮影であった。
人が人を裁くということ。
人為を超えた、自然の中では、人による正義は存在しないという事。
人為がある出来事でさえ、人が人を裁くのは、驕りではないかと考えさせられる。
そんな映画を見ることが、出来て良かったです。
個人の権利、ソーシャルメディア事態のあり方をも問える
映画でもあり、こっそりと、ひっそりと、個人で楽しむ映画です。事実より衝撃は強いです。
そして、口コミでこっそりと広げていってほしい映画である事を、期待します。
正義を観る観点
このような「調査報道」番組や映画が観たい。
とてもスリリングでしっかりした構成、見事な作品でした。若干、情緒的な家族の抱擁シーンなどが長く感じましたが、許容範囲でしょう。反対派の医師などもキチンと判決後もインタビューに答えていて立派でした。無理は承知で言うと、検察側の役人の意見も聞いてみたかったですね。昨年の「正義の行方」も力作だったが、最近は眉唾のドキュメンタリー映画も多い。自分たちの原罪に無自覚な東海テレビの「さよならテレビ」や扱うテーマとSEほかで茶化しまくりの演出が鼻につくチューリップテレビの「はりぼて」、テレビマンユニオンの「ヒポクラテスの盲点」はこれを見て勉強して欲しい。「WHO?」の監督は、ドキュメンタリー風は断念してそれまでのエンタメ路線で啓発して欲しい。
たくさんの人に観てもらいたい
今日の味方は、明日の敵
前半は一連の「揺さぶられっ子症候群(SBS)」裁判、後半は養父...
前半は一連の「揺さぶられっ子症候群(SBS)」裁判、後半は養父による児童虐待死裁判を追う。衝撃的なのは前者で弁護士側についていた脳外科医が、後半では検察側の証人となっていることだ。事故(あるいは病死)か虐待か、専門家であっても、家庭という密室で起こる事件立証の困難さ。「10人の真犯人を逃しても1人の冤罪をつくってはいけない」という原則は、児童虐待死という悲惨の前にはどこまで固持できるのか。本作では、冤罪によって引き裂かれた家族の苦悩も描き、それを見ればまた天秤は逆方向に揺れる。科学的証拠(とされるもの)に頼り過ぎることの危険性も感じさせられる。素人目には、むしろ健全な「常識」(2子以上をそれまで平常に育ててきた家庭で、なんの前触れもなく凄惨な虐待死が起こるものだろうか?など)にもっと依拠することができないものか、とさえ思える。後半の虐待死事件についても、個人的にも記憶している事件でもあり(報道から受ける印象は完全にクロだった)、「科学的証拠」をチェリーピッキングするような検察のやり口に衝撃を覚えた。大きく観れば、日本の司法が昔ほど硬直的ではなく、批判を受ければきちんとアップデートされていく、という改善の記録ではあるのだが…その過程で苦しんだ人たち、戦った人たちのことを忘れるべきではない。
全18件を表示