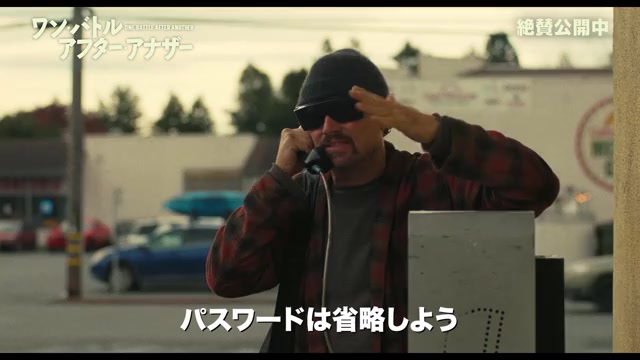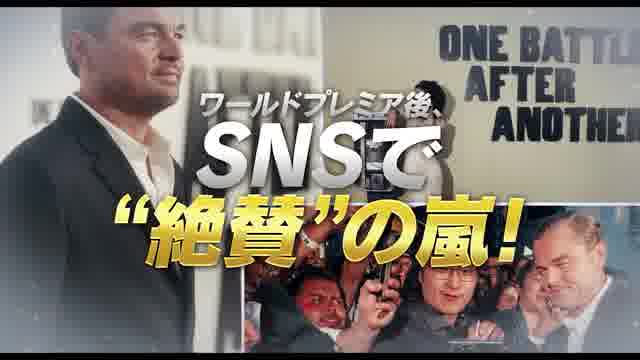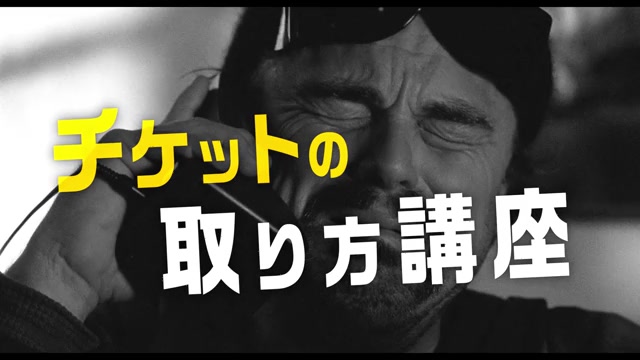「革命と前衛音楽」ワン・バトル・アフター・アナザー あんのういもさんの映画レビュー(感想・評価)
革命と前衛音楽
映画全体のクオリティが非常に高く、重厚感があり、広大である。何より最近の映画では感じられないリアリティを映像から深く感じられた。古き良きアメリカ映画のようだった。しかし、テーマとなっている移民や革命は昨今の国際的な問題が反映されており、現代へ問いを投げかける社会派映画だった。映画が始まってすぐにその世界観に引き込まれる。いつの間にかどんどんと飲み込まれていき、そしてあっという間に終わってしまう。しかし、頭の中にいくつかのシーンが鮮明に残っている。映画のどこで一時停止をしても画になる。意図的に静止させている箇所はなおさらである。理想的な映画であることは間違いない。
実はこの映画を観に行く動機となったのは、映画館で見た予告編だった。どの画も特徴的で記憶に残るものだった。しかし私がそそられたのは音楽だった。音楽を目当てに観に行ったと言っても過言ではない。
今までも予告編の音楽に興味を持って映画を観に行ったことは何度かあったが、映画本編で予告編の音楽を超える映画にはなかなか出会ったことがない。しかし、この映画は違った。予告編の音楽のハードルを平気で超えてきた。この映画の音楽の特徴に、クラシック音楽、特に前衛音楽の技法が数多く使われていることが挙げられる。具体例を挙げると、ミニマルミュージック、微分音、アコースティック楽器の特殊奏法、電子音楽等、サウンドだけをみても実に多種多様。それにとどまらず、これらの技法を組み合わせることで、表情をつけ、微妙な心理描写を音楽で描いている。昨今の映画音楽ではほとんどなくなってしまった、特徴的で耳に残るテーマ曲。また、そのテーマ曲を情景描写や心理描写に合わせて編曲して用いる方法がこの映画では取られている。なんと、前述した前衛音楽の技法を用いた音楽で。確かに前衛音楽は美しいメロディやハーモニーが無い分、心理描写や情景描写に長けているとされるが、これほどまでの成功例は今まで目にも耳にもしたことがない。これは映画と音楽が組み合わさることによってこそ起きた現象だろう。この作曲家の卓越した音楽性や芸術性が垣間見える。また、前衛音楽のサウンドを用いたのは、単なる音響上の実験にとどまらない。前衛音楽とは、アドルフ・ヒトラーが愛したドイツ・クラシック音楽の象徴する秩序や権威への否定という側面も持ち合わせている。秩序から逸脱した響きによって「革命」というテーマを音で体現しているようにも感じられた。
実はこの映画には前衛音楽だけではなく、聴き馴染みのある美しいメロディやハーモニーが使われている音楽もある。映画冒頭にも流れるこの映画のテーマ曲であり、ストーリーが大きく変化する重要な場面でも用いられるため、とても記憶に残る。前衛音楽だけにこだわらず、聴きやすい音楽も用いている点から、あくまでも映画音楽の体裁を保ち、大衆を置いていかない心意気が伝わってきて、評価できる。
昨今の映画音楽はどれもこれも風景のような脇役になっているものばかりである。その風潮に一石を投じる映画であり、映画音楽であることは間違いないだろう。この映画が提示した音楽の可能性は、映像と音響の新たな融合の始まりを告げているように思う。
映画チケットがいつでも1,500円!
詳細は遷移先をご確認ください。