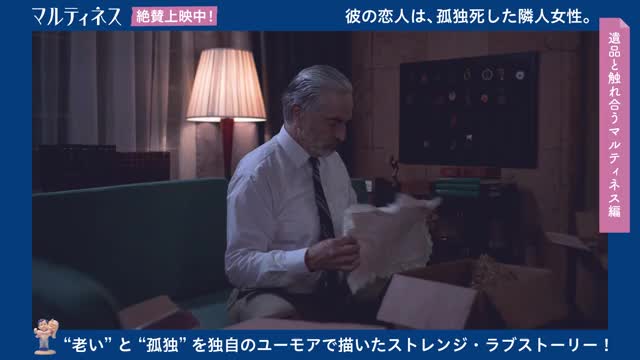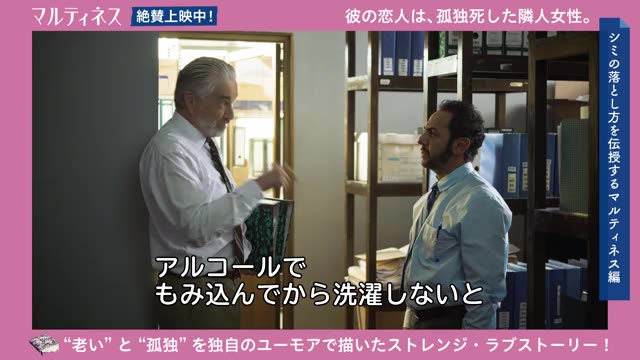「これは拾いものだった。」マルティネス 詠み人知らずさんの映画レビュー(感想・評価)
これは拾いものだった。
主人公マルティネスは、初老のチリ出身の移民男性、メキシコの古都グアダラハラの役所で働いていて、定年退職を控えていた。内面的で、極めて狷介だが、本当に最初からそうだったかどうか、少なくとも20年前は、かなり魅力的な男性だったのではと思う。大柄で美丈夫、服装もしっかり、何より、部屋がきれいに片付いている。
おそらく老獪になったのは、仕事の影響もあるのでは。役所の書類の系統的な整理と言う、誰にもできないことをしたようだ。同僚と付き合いもせず、毎日、家と職場の往復のみ。休日は、プールで水泳をするくらいか。誰一人、信頼し、心を許せる人はいない。
そんな彼だったが、アパートの階下の夫人アマリアが亡くなったことをきっかけに、変わって行く。いわばアマリアは仮想の恋人。彼女が遺したスケジュール帳を見ては、彼女が行きたかった場所を訪ねてみる。鼻歌を歌ったりするようになった彼を見て、驚いたのは彼の同僚のパブロと、秘書役のコンチタ。マルティネスに恋人ができたのではないかと思う。彼らも、本当は孤独な魂を抱えているのだが、表面上は外向的に見える。マルティネスは、かつて付き合いのあったらしいコンチタの誕生パーティに出かけて、カラオケでカミロ・セストを熱唱したりする。私は黒澤明の「生きる」に出てきた定年間際の市役所の課長を思い出していた。マルティネスが、アマリアをきっかけに、同僚との交流を通じて、改めて気づく「生きる悦び」。
頂点は、アマリアと二人だけの食事会。めかしこんで、テーブルをセットし、赤ワインが用意される。アキ・カウリスマキを思い出すが、北欧フィンランドより、ずっと美味しそうだった。
そんな彼だけど、やはり決断の時は来る。パブロは彼の後任だったから。それが、とても心配だった。でもマルティネスらしい生き方を見つける。どうやら、彼のモデルは、ロレーナ・パディージャ監督のお父さんだったみたい。
舞台を回してゆくのは、やはり音楽。これもアキ・カウリスマキと同じ。スペインの往年のアイドル、カミロ・セストのラテン・バラードもよかったけれど、私には、太陽が沈んでゆく時、一瞬輝いて見えるような、ストラヴィンスキーの「火の鳥」の終曲が、一番良かった!
孤独を抱えている、現在と将来の高齢者の方に、ぜひ!