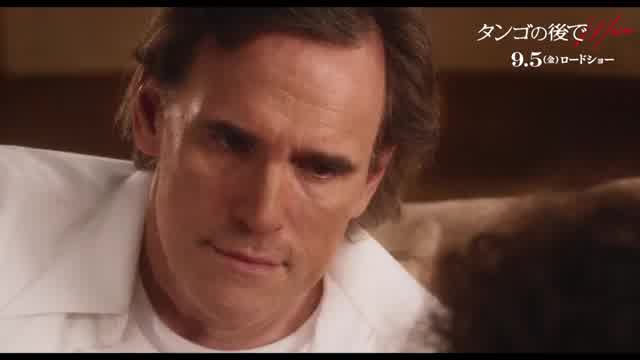タンゴの後でのレビュー・感想・評価
全24件中、1~20件目を表示
不都合な過去に向き合う劇映画が、社会の想像力と共感性をはぐくむ
映画業界をはじめとする華やかなエンタメやメディアの世界で絶大な権力と影響力を手にした男性の成功者が、社会的な経験や知識が少なく立場も弱い若い女性(や未成年男性)に性的な行為を強要したり、直接的な加害でなくとも精神的なダメージを及ぼす不適切な働きかけをしたりといったことが、洋の東西を問わず半世紀以上にわたり繰り返され、それを知る関係者がいる場合でもたいてい黙認されてきた。そうした悪弊の流れを変えたのが、2017年10月にニューヨーク・タイムズが映画プロデューサーのハーヴェイ・ワインスタインによる性的虐待を告発した記事と、それをきっかけにSNSを中心に広がった#MeToo運動だった。
運動の盛り上がりを受け、欧米の映画業界では不都合な過去に向き合い、実話をベースにして事件の真相や被害者の内面に迫ろうとする劇映画を作るようになってきた。先述のワインスタインの事件を題材にしたものでは「アシスタント」(米2020)と「SHE SAID シー・セッド その名を暴け」(米2022)。ほかに、米FOXニュースの女性キャスターがCEOをセクハラで提訴した騒動を扱った「スキャンダル」(カナダ・米2019)、フランスの50過ぎの著名作家と14歳の時に性的関係を持った文学少女が後年発表した告発本に基づく「コンセント 同意」(仏・ベルギー2023)など。本作「タンゴの後で」もそうした流れに沿う一本だ。
ドキュメンタリーに比べて劇映画は、登場人物に感情移入して出来事を疑似体験するのにより適したフォーマットであることから、観客が被害者の心身のダメージを想像するのを促す効果が認められる。本作について挙げるなら、「ラストタンゴ・イン・パリ」のあるシーンの撮影で、ベルナルド・ベルトルッチ監督が主演のマーロン・ブランド(マット・ディロン)にもともと脚本になかった過激な性行為の演技を指示し、19歳の新人女優マリア・シュナイダーには具体的な変更内容を伏せたまま本番に臨んだ場面で、アナマリア・バルトロメイが演じるマリアの屈辱的な思いや、大勢の男女スタッフが見ているのに誰も何も言わないときの孤立感などが、まさに今自分が体験しているかのような痛ましさで迫ってくる。
過去の不祥事や不適切な出来事に向き合う劇映画が観客の想像力や共感性をはぐくみ、ひいては社会の想像力と共感性をはぐくむことにつながると信じたい。
性加害を受けたことがある女性は直視できないでしょう。かつて性加害者...
性加害を受けたことがある女性は直視できないでしょう。かつて性加害者であった
男性が、この映画を観ても、大多数は過去の自分を悔いることができないのでは
ないか……。そんなことを考えながら鑑賞しました。
性加害のワンシーンの問題だけではなくて、これでもか、これでもかと押し寄せる
セカンドレイプ。そこから逃げるために陥った麻薬の罠。それでも立ち直って
マリア・シュナイダー自身は58歳で亡くなるまで生き抜いたのです。
誰よりも早く1970年代から声をあげていたのに誰もその声を聞こうとしなかった
ばかりでなく罵声さえ浴びせた「善良な人々」こそ、この映画を観るべきなの
ですが、おそらく、直接の加害者以上に反省しないであろうということが容易に
想像されて、そのことが、もっとも口惜しく感じるところなのです。
マリアを演じたアナマリア・バルトロメイはミッキー17 で何とも魅力的な女性を
演じて私は注目していましたが、本作品での鬼気迫る演技には、すっかり、
魅了させられました。
ベルナルド・ベルトルッチ監督は、2003年にドリーマーズという、しょうもない
映画を撮っています。女優マルレーヌ・ジョベールの娘のエヴァ・グリーンの
全裸だけではなくワレメもアップで映しています。女優の娘という気負いも
あったでしょう。初出演の映画の中で右も左もわからないまま巨匠の指示に
従ってしまったのではないかと気がかりです。
でも、悔しいけれど「ラストエンペラー」だけはスゴイ作品だったと記憶して
いるんですね。
見たかった「ベルトリッチの視点」
1972年、ベルナルド・ベルトリッチ監督の『ラスト・タンゴ・イン・パリ』は嘗てない大胆な性描写で世界を揺るがしました。主演女優を務めたマリア・シュナイダーは本作で名声を得たのですが、この映画では、脚本にない性暴力場面を彼女に前もって何ら知らせる事もなくぶっつけ本番で撮られた事を彼女は後になって告発しました。急な撮影変更を事前に知っていたのは監督と相手役のマーロン・ブランドだけだったのです。その出来事を中心に描いた物語です。
日本の映画界でも嘗ては、女優さんは「脱ぐ」ことで「女優魂」とか「熱演」「一皮むけた」などと称揚されました。僕も以前は確かにそう思っていました。ただそれは単なるスケベ心の裏返しに過ぎないんですけどね。でも、男性俳優がスッポンポンになったって「男優魂」「熱演」と言われる事は確かにありません。そこには明らかに映画界の性差別があったのです。性的な場面の撮影に当たってはインティマシー・コーディネーターが関わる様になって来た近年は、緩やかにではあるけれど確かに進歩したのでしょう。
ただ、当時のそうした歪んだ価値観を物語にするのならば、ベルトリッチ自身の視線を作中でもっと描くべきだったと思います。だまし討ちの様なその撮影を当時のそして後の彼はどう考えていたのかが映像化してあれば、表現活動が持ついかがわしさという一面と矛盾をもっと強く打ち出せたのではなかったでしょうか。
途中寝落ち
恐い映画でした。アリア・シュナイダーの恐怖を追体験します。
カメラが回るとサディストに?
MeTooのだいぶ前のお話ですが、究極のリアリティ、衝撃、話題性を追求した結果かと感じた
主演男優配役難航、無名の新人に大役がってところでもう危険な香りプンプン...女性の気持ちや人権など以前は無いに等しかったのでしょうね 名が売れることには繋がったようだけどその後が酷くて最初の役って大切なんだなぁ それにしてもオカン厳しい、こういう時こそ側についてほしかっただろうのに家族にも恵まれてない、父の家族は離れていったのかいな
マットディロンの喋りがマーロンブランドそっくりだった アナマリアさん不幸な役どころだったけど美しい。そしてヌールさんの登場謎だったが何故今この話なのか分かったような気が
望みと違う
こないだ鑑賞してきました🎬
マリアにはアナマリア・ヴァルトロメイ🙂
「ミッキー17」
にも出てましたね😀
私は件の映画は見てませんが、ネットで記事を読んだことはあります。
普通に考えれば、脚本にないシーンを演者の同意を得ずに強行撮影するのはあってはならないことだと思います。
しかしこの頃は、時代が違うのもあってまかり通ってしまったのでしょう😔
これ以降のマリアは、退廃的になってしまい、いたたまれません。
その辺りのヴァルトロメイの演技もまた、心情を大胆かつリアルに表現していました。
ちょっとそれますが、ずっと彼女を見ていると、アナに似た美しさを感じますね😀
マーロン・ブランドにはマット・ディロン🙂
ブランドも最初はマリアの頭を浴槽に沈めるシーンを心配したりますが、なぜか問題のシーンでは強行。
とても悲しい場面です。
それ以外では、普通に彼女に接しているので残念でなりません。
ディロンのブランド感は、それなりでしょうか🤔
この件は今でもタブー視されているらしく、映画化まで苦労されたという記事をネットで読みました。
マリア・シュナイダー当人が声をあげた以上は、埋もれさせてはならないはずですが。
しかしこうして日本でも公開されたので、その点は良かったと思います。
ハーヴェイ・ワインスタインの件もありますし、いくら権力があろうと越えてはならない一線はあるわけで、それを越えるのは許されないことでしょう。
映画制作の現場で、同様のことが再び起こらないよう切に願います。
2011年に亡くなったマリア・シュナイダーのご冥福をお祈りします。
美しさの裏側に
監督や相手役に詳細を知らされないまま過激なシーンを演じさせられたことにより心が壊れていく女優を描いた作品。
主演女優の切符を手にし、年齢差あるとは言え良い感じの相手役にも恵まれ、スターへの階段を登っていくかと思いきや…。
世代的にもワタクシ、元ネタ作品やそれが良くない意味で話題になっていたことは知らず。
それでも、ザッとラストタンゴ・イン・パリのことを調べただけでも、これは中々に感じるものがありますね。
私の映画に役者はいない…。確かに気持ちは分かるし、リアルを追求するならなおさら。そしてそれこそが芸術だという考えもね。
ただそれにより1人の女性の精神が壊れてしまってはな…しかしそれが皮肉にも出世作になるとは。本当に、観ていて狂おしくなった。
俳優という仕事の難しさや、作品を作り上げることの大変さ、残酷さをこれでもかと感じさせてくれた作品だった。
それにしても…主演のバルトロメイさん、可愛すぎやしませんか!?彼女の作品を観るのは恐らく初めてなのですが、初っ端からそのご尊顔の強さに、しょっちゅう一目惚れのワタクシ、またしても推しが増えてしまいました(笑)
今後にも期待ですね!
女優になるには純粋すぎた
野心的な新人女優なら「えー、その程度で?」と思うかもしれない。
松田暎子さんなら「何言ってんの、このヒト?」と怒り出すかもしれない。
中森明菜は波乱の半生を「少女A」を歌わされたせいにするかもしれない。
和泉雅子のような、監督にどつき回されて本気で怒った目をした女優にはもう会えないのかもしれない。
あのシーンが問題なのではなく、あの瞬間に限界に達したのだろう。
あの役が19歳の女の子の許容範囲をゆうに超えていたことは想像に難くない。
彼女は心も裸にされた。
しかしドミニク・サンダが演じていたらそうはならなかったはず。
彼女の中で燻り続けたのは、あの日、あの時、女優としての自分を受胎出来なかったことへの怒りではなかったか。
もちろん彼女はあの作品で女優になった。
マリア・シュナイダーという悲劇の女優を演じ続ける女優に。
どんな運命に翻弄されようと、ヘロインに依存する理由にはならない。
それでも彼女は、自分に負けることで永遠に勝利した。
あの作品は彼女の物語になり、彼女のものになった。
ディスコミュージックが似合う、本当は陽気で素敵な女の子のものに。
生まれた時が悪いのか……
「ラストタンゴインパリ」が物議をかもしたのかどうか、認識していませんが、日本で言うと「愛のコリーダ」みたいな感じなのでしょうか。
藤竜也さんはその後も様々な作品で活躍を続けますが、松田瑛子さんという方は存じ上げなくて、その後の出演作を見ると、どうもコリーダの「色」がついてしまったように思えます。
そんなレッテルが貼られてしまうと払しょくするのは難しいですよね、本人の意欲や努力とは無縁に大人の世界は動いてしまうから。
現代だったら異なる評価をされて、活動の幅が広がっていたのかもしれませんね。
薬物にはまり、その離脱症状に苛まれるシーンは【ボブ猫】の主人公の依存から脱却しようとする際の苦しむ様を思い出してしまいました。クスリは恐ろしい……
それにしても主演のアナマリアさん、「あのこと」でも難しい役どころを演じていましたが、これからも楽しみですね。
作品的にはもの悲しさばかりが募ってしまい、今ひとつ感情移入できませんでした。
タンゴの後で(映画の記憶2025/9/6)
観るのに体力いる映画だった
主人公の苦悩を長時間見続けるのは正直しんどかったです。
ラスト近くで女性スタッフが放った質問には驚きました。あんな目に遭わせた監督とのコラボを尋ねるなんて、同姓として理解できませんでした。たとえ事件を知らなかったとしても、主人公の深い傷を示す象徴的な場面だったと思いました。
救いの光が差す瞬間を期待しましたが、最後まで訪れませんでした。それこそがこの映画の凄みであり、事実の重さを映し出していました。
単なる「重たい映画」ではなく、観る側にも覚悟と体力を求める作品だと感じました。
この映画は、トラウマや苦悩に共感しすぎてしまう人にはとても辛いかもしれません。
けれど、現実の重さを直視したい人には強く訴えかけてくる作品だと思いました。
映画は結局、誰のためのものか。
マリア・シュナイダーは2011年に亡くなっている。この作品「Maria」は本人の死後に従姉妹が出版した評伝を映画化したもの。ベルトリッチへの暴露ものといった評価もあるが、マリアの女優スタートであり結果として彼女の名前を後世に残すこととなった「ラスト・タンゴ・イン・パリ」でのエピソードはマリアのキャリアにおいて取り上げざるを得ないし、撮影時のトラブルと、マリア対マーロン・ブランド、ベルトリッチのその後の不和はとてもよく知られたものでありいまさら暴露云々という話ではない。
この映画は、「タンゴ」のあと、いわば女優として最初からつまずいてしまったマリアが、以降も表現者としてなんとか生き延びていこうともがき苦しむ話である。その中にはヘロイン中毒という負の側面もあったが、映画の中でも触れられているように、例えば、アントニオーニの「さすらいの二人」のような良作への出演もあるので沈み放しというわけでもない。女優人生をアナマリア・バルトメイが好演、見応えのある作品となった。
ところで、本作を#Me tooトレンドへの追随と捉える向きもある。そもそも#Me tooをトレンドとして仕分けることに問題があるのだが、それはさておき、「タンゴ」はハーヴェイ・ワインスタインの件とは異なり、撮影現場で起こっているところに問題の本質がある。つまり、男性が女性を性的に支配することをテーマにした作品が、監督と主演男優が圧倒的に力を持っている現場で撮影される、二重の抑圧である。
これは結局は「映画は誰のものか」というところに帰結する。いまさら撮影現場の民主化みたいなことは言いたくないが、少なくともベルトリッチのように自分の映画には出演者はいない、登場人物しかいない(そして登場人物が何を語りどんな行動をするかは自分だけが決める)と嘯くようなマネジメントはもうあり得ないとは思うけど。
ちなみに私は自分自分が若かった頃はともかく、今となってはベルトリッチは全然良いとは思わない。「暗殺の森」も「シェルタリング・スカイ」もね。何、オッサン格好つけてんねん、っていうところですかね。
ところで、バターの件ですが、日本映画だけど「花腐し」にもバターが登場します。あれは意図的にやったのかな?荒井晴彦に尋ねてみたいところです。
ベルトルッチが生きている時にやってほしかった…
この映画のもとになっている『ラストタンゴ・イン・パリ』はずっと昔に見ていて“例の場面”だけが今も印象に残っている。その女優のこと、またその後の女優のことは全く気にかけていなかったが、この映画はそのことを扱っている。
“me too運動”後のトレンドに追随したものだろう。日本でもタレントのおっさんたちが過去の女性問題を掘り起こされ謹慎させられているがその種の系統の話だ。監督も原作も女性だが、ベルトルッチの死後に暴露本や映画を発表するのはやや公平さに欠ける気もする(ベルトルッチは「当該場面は脚本に含まれていた」と主張しているらしい)。
“#Me too運動”をトレンドと捉えることに問題があると捉える向きもあるが、Twitter・スマートフォンの普及以前には考えられない情報の拡散が見られたわけだから、その在り方は紛うことなき「trend」である。また、マリアの親族が著した原作をベルトリッチの下でインターンとして働いていた監督が映画化するという中途半端な構図も潔くなく、当事者が生きている間に当事者間で解決すべき問題なのではないか…。
芸術という名の罪、男という名の罪びと
「ラストタンゴ・イン・パリ」は1972年公開ですが、私が観たのは2000年のリバイバル。
映画的には、スキャンダラスな話題性の割に描写はそこまで過激ではなく、コメディ的な部分やガトー・バリビエリの素晴らしい音楽も相まって、お気に入りの作品でした。
しかし、制作過程でこのような事実があったのなら、もはや同じ感覚では観られないでしょう。
マリア・シュナイダーは薬物中毒とは聞いていましたが、アントニオー二の「さすらいの二人」やリヴェットの「メリー・ゴー・ラウンド」に主役級キャストで出演されていましたので、2011年に58歳でガンで亡くなられた時は驚きました。
芸術と性加害の問題に対し、今ようやく世の中の意識の変化が見られますが、当時は圧倒的な従属関係があったわけで、マリアは声を上げられず、世界的名声を得つつある気鋭の監督が望むんだからしょうがない、みたいな空気が周囲にもあったと思います。
薬物依存が社会的には問題があるとは言え、マリアの苦悩とその後の境遇には同情を禁じえません。
映画制作も人を相手にする以上、やはり人権尊重は大前提で、ベルトリッチのような才能溢れる人物なら尚更説明を尽くすべきでした。もしそれが出来ないということであれば、これはもはや「男であることの罪」と言うしかなく、昨今のキャンセルカルチャーも致し方ないと思います(純粋に映画好きには、お気に入りだった名作が観られなくなるは残念ですが)。
さて「タンゴの後で」ですが、マリア役のアナマリアの熱演もあり、監督の主張は伝わってきたのですが、映画的にはやや平板に感じてしまいました。ここはベルトリッチの芸術的な映画技法を逆手に取って駆使し、完膚なきまでにやり返すという方法もあったかもしれません。
インフォームド・コンセント
舞台となった1970年代初頭、人々が愛と平和と自由に至上の価値を置いていた時代の空気とは裏腹に、映画制作現場(だけではないだろうが)がパワハラ横行の男社会だったことが描かれていて、男女問わず「マリア・シュナイダー」が続出した事は容易に想像がつく。インティマシー・コーディネートに代表される、本人の自由意思を尊重する手続きの普及を願うばかりだ。
一方、芸術表現上の情熱とわがまま、あるいはハラスメントの境界線は余りにも曖昧で、特に映画・演劇・オペラ等パーフォーミング・アーツの監督や演出家は、芸術家として優れていても出演者への配慮が足りないばかりに只のセクハラ糞野郎として葬られる危険があるという点で、画家や小説家のような個人営業主とは別種の才能が求められる。同意を得るのも才能のひとつ、という事になるわけだが、ベルトリッチにはこれが欠けていた。しかし例のシーンに関して「胸は痛むが後悔はしていない」とうそぶいているので、自覚はなさそうだな。
マット・ディロンのそっくりさん振りはお見事です。
75点。アナマリア・バルトロメイ
この映画を観るために、本作で裏話が描かれる『ラストタンゴ・イン・パリ』を観ました。
『ラストタンゴ・イン・パリ』は良くなかったし胸クソでキライだけど、この映画は良かった、面白かった!
『ラストタンゴ・イン・パリ』の話が大部分かと思いきや、その部分は半分もなく、出演時に性加害を受けたマリア・シュナイダーの半生を描いてます。
そのマリア・シュナイダー役を『あのこと』のアナマリア・バルトロメイが演じていて、キャスティングがピッタリだと思う。
『あのこと』も女性の権利を訴えるような作品で、その役を体当たりで見事に演じていたので、これ以上ないぐらいのキャスティング。
この映画を観た1番の決め手は『あのこと』のアナマリア・バルトロメイが出てたことです。
次はマーロン・ブランド役でマット・ディロンが出てたこと、このキャスティングもピッタリですね。
とにかくアナマリア・バルトロメイが素晴らしく、脚本も良かった。
もう1回観たい♪
戦わない女
マリア・シュナイダーが「ラストタンゴ・イン・パリ」の撮影で受けたトラウマで変貌して行く話。
監督名も俳優名もあまり覚えない自分には、マーロン・ブランドぐらいしかわからないけれど、顔が似ているのもさることながら、表情や仕草までそっくりでビックリ。
導入部分の主人公の背景は少々わかりにくいけれど、「ラストタンゴ・イン・パリ」を多分みたことない自分にも、この作品のストーリー自体は良くわかる。
擬似とはいえども、確かにこの監督とマーロン・ブランドのやらかしたことは、マリアの演技力に不満を抱えていたからなのか、作中で語っていた通りなのか…。
ただ、そこからの堕ち方は自分の選択な訳で、それはそれと思ってしまうし、そこについては響かず。
しかも終盤ちょっと抵抗はみせたけれど、というぐらいで残念だった。
全24件中、1~20件目を表示