実は、観始める前から予感はあった。
だが、実際に観てみて、確信した。
「これ、アンドレ・ブルトンのコレクションの様子をおさめたドキュメンタリー映画とそっくりじゃん!!」
1920年代のヨーロッパを席捲したシュルレアリスム運動。
その中心にいた思想的支柱がアンドレ・ブルトンだ。
彼は、1924年にシュルレアリスム宣言を発表して以降、「帝王」として運動体の頂点に君臨することになるが、一方、その生涯を通して数多の文物を蒐集しつづけ、自宅を埋め尽くさんばかりのコレクションを形成した。
それらの5300点に及ぶ厖大な蒐集品は、結局のところブルトンの死後、オークションにかけられて散逸することになったが、ごく一部がポンピドゥーセンターなどで保存されている。
これらのコレクションの内容を記録したフィルムが、ファブリス・マゼ監督の「野性の目」である。手持ちカメラがブルトンのアトリエに入っていき、内部を埋め尽くす圧倒的な蒐集品と呪物の数々を一人称視点で舐めまわすように撮っていく。
音声やテロップによる解説のないまま、ひたすらコレクションの内容を映し出していく手法は、きわめて不親切で非商業的ではありながらも、ブルトンが生涯をかけて集めた呪物の「圧」とコレクターの「妄念」をひしひしと感じさせる。
で、このドキュメンタリーを去年の秋に観ていたので、今回の「クンストカメラ」にはちょっとびっくりしたわけだ。
撮影の対象(コレクション)も、撮り方(一人称カメラ)も、説明を一切しない作りも、両作はまるで一緒だったからだ。
さすがにこれ、シュヴァンクマイエルは
「野性の目」の存在を絶対知っていたでしょう。
そもそもシュヴァンクマイエルのコレクションの傾向は、アンドレ・ブルトンのそれとよく似ている。大量のアフリカ製彫刻やオセアニア原住民の工芸。中世から近世にかけての妖しげな版画やシュルレアリストによる創作物。生物標本から雑多な生活具まで、ありとあらゆる事物がごちゃまぜに蒐集されるカオスな「博物学的」テイストは、まさに両者に共通するものだ。
一方で、「だまし絵」への傾倒や、自作および妻の作品をコレクションに「混ぜる」やり方などが、シュヴァンクマイエルのコレクションに独特に味わいを付与しているが、彼がさまざまな芸術品や民芸品を蒐集するにあたって、アンドレ・ブルトンを意識していなかったとは、さすがに思いづらい。
おそらくならシュヴァンクマイエルは、アンドレ・ブルトンの「ひそみに倣って」、自分の「驚異の部屋(ヴンダー・カンマー)を持つ」という野望を実現させたのだ。
殊更に彼が、みずからを「シュルレアリスト」と呼称するのも、夢日記を長く付け続けているのも、すべてブルトンへの敬慕と憧れのなせるわざではないのか? とも思ったりするくらいだ。
そして、そのコレクションの全容を紹介するフィルムを製作するにあたっても、ブルトンのそれを紹介するフィルムの作りに寄せたのではないか、というのが僕の推測だ。
― ― ― ―
Kunstkameraという語は、一般的にはサンクトペテルブルグにあるピョートル1世が創設した大博物館のことを指すが、もともとこの言葉は、ドイツ語のKunstkammer(美術陳列室)の訳語であり、 Wunderkammer(ヴンダーカンマー、驚異の部屋)と同義の言葉ととらえて問題ない。
シュヴァンクマイエルは、 ホルニー・スタニコフにある城と穀物倉庫からなる、自作の工房兼保管庫であるこの場所に、まさに「驚異の部屋」という意味合いで、その名を当てているということなのだろう。
映画の冒頭から、ありとあらゆる「綺想に富んだ」文物が入り乱れて、観ていてときめきがとまらない。
建物の中庭のようなところにある、日本の石庭のパロディ的インスタレーション。
アルチンボルドの「ウェルトゥムヌスとしての皇帝ルドルフ2世像」のコピー。
奥さんのエヴァ・シュヴァンクマイエロヴァーが描いた、性的な壁画や扉絵。
水晶の原石(錬金術のアタノール加熱において重要な役割を果たす物質である)。
大量のアフリカの呪術的彫刻。東南アジアやオセアニアの祖霊信仰の仮面や彫像。
骨や陶器を用いたオブジェの大半は、シュヴァンクマイエル自身の手になる作品だ。
浮世絵の春画。
仏像、ヒンドゥー神。
性的玩具、バリの影絵。
センザンコウやアルマジロ、
亀、蛇、ヒトデなどのはく製。
蝶・蛾・その他の昆虫の標本群。
ブリキの車のおもちゃ、中世の拷問画。
ブリューゲル、デューラー、ダリ、マッタ。
まさに、「驚異の部屋(ヴンター・カンマー)」
としかいいようがないコレクションだ。
「驚異の部屋」に関しては、すでにブルトンのドキュメンタリーの感想を書いた際、詳細に記したので、ここでは繰り返さない。とはいえ、まさに本作冒頭で野菜を組み合わせた肖像画として登場するルドルフ2世によって、1605年に開かれたコレクション展示室こそがその源流のひとつであり、彼を画業のパトロンとして活動していたのが他ならぬジュゼッペ・アルチンボルドであることは強調しておく必要がある。
ブルトンとシュヴァンクマイエルの充実した「綺想コレクション」の概要を見ていると、好事家の王侯貴族たちを虜にした博物学的関心と、彼ら金満家の承認欲求が結びついた個人コレクションとしての「驚異の部屋」の伝統は、20世紀になって、コノワッサール(目利き)でもあるシュルレアリストたちに、正しく引き継がれたともいえそうな気がする。
その系譜にはもちろんながら、碩学バルトルシャイテスや、日本の種村季弘や澁澤龍彦、荒俣宏、高山宏といった「紹介者」たちも、やがて加わることになるだろう。
ただシュヴァンクマイエルの場合は、これに「自分と妻の創作物」が加わるという部分に、コレクションの最大の特徴がある。
要するに、「世界各地からかき集めた珍奇で奇怪なアート」に、「自分の作ったアート」を混ぜ込むことで、彼のコレクションは成立している。
純粋なコレクションではなく、コレクションを「自らの芸術的営為によって上書き」「魔改造」している状態だ。
だから、一見して「アフリカから買ってきた土着の人形」に思えたとしても、もしかしたらそこにはシュヴァンクマイエルの「手」が加わっているかもしれない。
オセアニアの仮面のように見えても、実はシュヴァンクマイエル自身が作り出した「偽」の民俗工芸品かもしれない。
そういった、「偽装性」「仮想性」「加工性」の可能性と余地が、シュヴァンクマイエルのコレクションには常につきまとう。
そもそも、シュヴァンクマイエルは、自作オブジェに経年劣化を生じさせるために、わざわざトウモロコシ粥のペーストを塗り付け、虫や微生物によって腐蝕させるという。
彼のオブジェは総じて、「年を経た」作品として「偽装」されている。
すなわち彼の創作物は、自身の雑多な綺想コレクションにもとより「馴染む」ように仕組まれているのだ。
この作業は、架空の海底遺跡とサルベージされた財宝を「すべていちから偽装し」、偽のお披露目展覧会をヴェネチア・ビエンナーレで開催したダミアン・ハーストの試みを想起させる。
シュヴァンクマイエルは、自らの芸術的営為によって、時間に干渉し、歴史に干渉し、蒐集品に干渉する。コレクションと自らの創造物のあいだに境界はなく、すべてがいっしょくたにとりまとめられて、私的な「小宇宙」を形成している。
シュヴァンクマイエルの綺想コレクションは、ただの純粋なコレクションではない。
コレクションを模した(騙った)『驚異の部屋』風のインスタレーション。
自らの創造性によって肉付けされた、「理想化された」コレクション。
蒐集家自身の手によって「魔改造」された、コレクションもどきのフェイク・アートなのだ。
― ― ― ―
●シュヴァンクマイエルのアートの傾向としては、ある種の破壊性を帯びた幼児性と、グロテスクに対するまっすぐな羨望を挙げることができるだろう。
その延長として、シュヴァンクマイエルの作るオブジェには、むき出しの「メメント・モリ(死を想え)」(骨、死体、腐敗、虫、種子)と、むき出しの性的な要素(棒状の突起=男性 貝=女性)が露悪的に付与されている。
ある意味やっていることはえげつないが、どこかあっけらかんとしていて、いたずらっ子然とした居直りが感じ取れる。作り手が本気で面白がり、本気で楽しんでいるのが伝わってくるから、観ていてあまり嫌な気分にならない。
●標本のパーツを組み合わせた合成生物の生成や、陶磁製の造形物に観られる「頭から手足が生えている怪物」の形状は、まさにヒエロニムス・ボスの「グリロス」(多頭・多足/胴体の欠損し「組み合わせの怪物」)と同質のものだ。
●それと、コレクションにおいて、「だまし絵」系の作品が突出して多いのも印象的。
たぶん、ホントに大好きだったんだろうなあ、この系統の作品が。
まずは、アルチンボルド、もしくはその追随者の作品群。
それから、サルバドール・ダリがよくやっていたような「ダブルイメージ(二重像。背景の自然景が男の顔に見えたりするやつ)」もたくさん出てきた。上下を反転させても別の男性に見えるような、日本でもおなじみのネタも混じっていて実に楽しい。
●アルチンボルドによる肖像画が冒頭に出てきて、そのあと博物学的な文物が音楽に合わせてひたすら羅列される展開といえば、シュヴァンクマイエルのファンなら誰しもが、初期の短篇「自然の歴史(博物誌)」を想起することだろう。
考えてみると、両作品がやっていることはほぼ同じであり、『クンストカメラ』は「自然の歴史」の発展形ということもできそうだ。
逆に言うと、「自然の歴史」のなかで登場する、昆虫・魚類・鳥類・爬虫類・ほ乳類のおびただしい剥製や骨格標本が、すべて「自分の手持ちのコレクション」を用いて撮影されていたということがわかって、さすがに衝撃を覚えざるを得ない。
●このコレクションのベースになっているのは間違いなく、アルチンボルドとルドルフ2世の「驚異の部屋」に代表される、17世紀初頭「マニエリスム~バロック」の時代に花開いた博物学愛好カルチャーだ。だが、邸の屋根回りや破風にしつらえられた「魔改造された」ガーゴイル群にはゴチック(12~15世紀)の気配もあるし、ごてごてとした装飾性とグロッタ的な胎内感にはロココ(18世紀)の雰囲気もある。何よりこのコレクションは、アンドレ・ブルトンの蒐集癖を参照して、20世紀シュルレアリスムの美意識や価値基準を通して蒐集されたものだ。さらには「フェイク・コレクション」としての現代的なインスタレーション性も備えている。
シュヴァンクマイエルは、その独特な鑑識眼と、自らの手でアイテムを魔改造する技術によって、時空を超え、時代様式を超えた、唯一無二のコレクションを形成したというわけだ。
●音楽に関しては、のべつ幕なし、最初から最後までひたすらヴィヴァルディの「四季」が流れている。この選曲は、アルチンボルドの代表作として「四季」の連作があることに由来するのではないかと個人的には想像する(時代的にはヴィヴァルディはルドルフ2世の時代からは1世紀遅れる)。
ただ注意深く聴くと、原曲のままエンドレスにリフレインをかけて流しているわけではなく、あちこちで電子的に音を加工して、わざわざチープなつくりもののような音響で流していることがわかる。これってもしかして、このコレクションがオーセンティックな「蒐集品」ではなく、芸術家の手の加わった「フェイク」であることを示唆する仕掛けだったりするのではないかな?
●最後の最後に、シュヴァンクマイエルの自室とベッドが一瞬映って、実際にここで彼が過ごしていることが明らかにされて、ドキュメンタリーは終わる。
乱雑に散らかったベッド回りの生活臭は、芸術家のリアルと当時87歳と思われる巨匠の老境を想起させる。さんざん「モノ」を見せたうえで、最後にその蒐集家であるところの「ヒト」に観客の関心の矛先を向ける作りは、なかなかに狡猾だ。


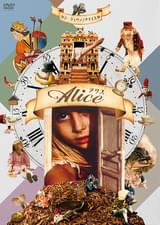 アリス
アリス オテサーネク
オテサーネク 行き止まりの世界に生まれて
行き止まりの世界に生まれて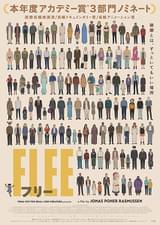 FLEE フリー
FLEE フリー ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方
ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方 ナワリヌイ
ナワリヌイ シチズンフォー スノーデンの暴露
シチズンフォー スノーデンの暴露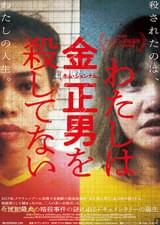 わたしは金正男を殺してない
わたしは金正男を殺してない ドキュメンタリー オブ ベイビーわるきゅーれ
ドキュメンタリー オブ ベイビーわるきゅーれ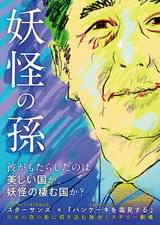 妖怪の孫
妖怪の孫












