映画レビュー
私はどこにいて、これからどこに向かおうか
身分が分からない男女が突然現れる。彼らは作品において何者かであり、それは隠されることもなく、時間を掛けず作品上の役割が(視覚的に)開示される。そうしたいくつかの組がひょんなことで交わってはまた異なる組み合わせに移行する。
山という閉ざされつつも開放的な(恐らくショットの全部(?)が自然光)映像の86分で車を軸にした脱中心的な物語は、笑って良いところか否か、面白いのか否かの間で持続する(これはムレ作品に通底する私自身の感覚)。
出会い、生起される関係性において、少なからず互いが互いへと影響を与え与えられる。秘密の小屋に誘われる女性と、その中で生活する男。そんな小屋を山を上から見下ろすもう一人の女性。その女性と小屋の男の関係を疑うアマルリック…というように。
しかし、そんな彼らに混ざって一向に与えることのない存在が一組異物化されている。それは、湾岸戦争の兵士たちである。彼らは常に誤解する存在として滑稽に描かれているが、誤解した先に何が起こるかはこの作品では描かれない。つまり、誤解された側との真意のすり合わせが全くないのだ。相手を殺して国のヒーローになることが求められる彼らは殺戮の対象ではない人らとのコミュニケーションが図ることが出来ない。言葉の銃弾は相手を打ち抜くことはなく、持つのは闇雲に発砲するしか役割を持たない銃だけである。丁寧に数回「湾岸戦争が始まって〇日目」と数日間の物語であると書き言葉によって語られてしまう兵士たち。一貫してポケットのような存在として描かれていたのは、ブラックユーモアを眼差しの一つとして所持するムレの作家性たるものなのだろうか。
場所があれば物語れるムレは、今回も「山」を選択し、何でもない描写を"斜線"という視覚化でショットを成立させる。また、それぞれの立ち位値(天文学者たちの研究所/小屋/立ち往生する車/レッカー車/映画撮影隊)を牛と歩く男性と服ドライバーの女性がそれぞれの場所を目指す歩行とその高低差(上るのか下るのか)によって位置関係を分からせる手腕は見事である。
そういった映像的一貫性からも兵士たちは逸脱していたように思える。つまり、どこにいてどこに向かっているのか分からない。
これは戦争そのものに対するムレの批判性から来るものなのだろうか……いや、ひとまず今はクスっと口角を上げるだけにしておこう。


 カメラを止めるな!
カメラを止めるな! ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド
ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド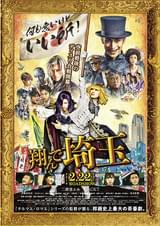 翔んで埼玉
翔んで埼玉 SING/シング
SING/シング 記憶
記憶 コンフィデンスマンJP ロマンス編
コンフィデンスマンJP ロマンス編 ザ・ファブル
ザ・ファブル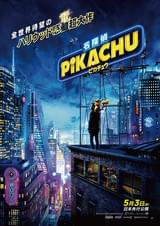 名探偵ピカチュウ
名探偵ピカチュウ エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス
エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス コンフィデンスマンJP プリンセス編
コンフィデンスマンJP プリンセス編

