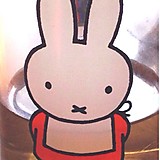黒川の女たちのレビュー・感想・評価
全43件中、21~40件目を表示
哀れ棄民政策の果ての陵辱
冒頭、「満蒙開拓」の実態がいかなるものであったかが明かされる。傀儡国家・満州を実質支配する関東軍が入植者を配置したのはソ満国境沿いであり、ひとたび急あれば入植者を徴用する意図があったこと。日本各地から貧農を集め、甘言を弄してあてがった土地は、現地農民の家屋田畑を接収したものであったこと。未開の地を開拓するのではない、武力をもって収奪した農地を居抜きであてがったのだ。さらに、入植した日本人部落の人員構成など詳細な情報がソ連側に知られていたこと。
黒川開拓団の悲劇がそのあと語られるのだが、まずもって杜撰ででたらめな植民地である満州に、多くの日本人を送り込んだ政府・軍部の棄民政策にこそ原罪がある、と制作者はこの序章を忘れなかった。
戦時中の性被害というと慰安婦問題が想起されるが、これも当事者からの告発がきっかけであった。なかったことにされては2度死ぬことになる。悲痛な声に我々は耳を傾けなければならない。
男性の愚かな弱さと女性のしなやかな強さに眩暈がしました。
昭和40年代生まれの私にとって、第二次世界大戦は、過去であり、歴史の授業で学ぶものでした。
満州という言葉は知っていましたが、それが何か、明確に理解はしていませんでした。
そして、そこに希望を抱いて赴いた日本人が、どんな末路を辿ったのかも。
「性接待」がどういう意味かは、知っています。
けれど、満州撤退時、村民が無事に日本に帰るために、共に暮らしてきた村の若い女性たちを護衛するソ連兵に差し出すなんてことが行われていたことに衝撃を受けました。
選ばれたのは、数えで18歳以上の女性15名。
彼女たちは、その場に行くまで、お酒を注いだりするような接待だと思っていたのです。
この時代なら、皆さんきっと男性経験もないでしょう。
このむごさを、段取りした男性たちは、想像できないのでしょうか。
また、彼女たちの母親は、これに同意したのでしょうか。
私には娘はいませんが、母親だったら、娘の代わりに自分がと思わないのでしょうか。
日本に帰ってから、この「性接待」そのものがなかったことにされ、皆のために身を犠牲にした女性たちが貶められる状況に、胸が痛くなりました。
むしろ、日本に帰国してからの方がつらかったという女性の言葉が、心に沁みました。
私は、危険な目に遭ったことも、ひもじい思いをしたこともありません。
けれど、今、この瞬間も、争いは世界中で起き、亡くなっていく方がたくさんいます。
黒川の女性たちのような、弱い立場の人たちが虐げられているという状況は、過去の話ではありません。
こんなに強烈に、見て見ぬふりをせず、向き合わなきゃと思ったのは、初めてです。
まず、乙女の碑に、お参りに行きます。
戦後80周年映画として現在暫定1位
タイトルなし(ネタバレ)
終戦時、満州開拓団を襲った悲劇・・・
太平洋戦争後半、貧農たちは満蒙開拓へ急き立てられるように海を渡った。
岐阜県黒川村の農民たちも、そんな集団のひとつだった。
開拓とは名ばかりで、既に開拓されてた土地を現地の人々から安く買い上げて農業をするのだ。
だが、終戦間際、ロシアの参戦により状況は一変する。
開拓団を守るべき日本の関東軍は知らぬうちに撤退。
土地を奪われた満州の人々が開拓団の集落を襲う。
身の安全を得るために開拓団が採った手段、それはロシア軍に守ってもらうかわりに、村の若い女性を差し出すことだった・・・
という太平洋戦争秘話。
犠牲になるも生き延びた女性たち、遺族たちの証言。
十数年に渡る取材・インタビューをまとめたドキュメンタリー。
事の陰鬱さとその後の対応は、いま振り返るべき重みがある。
このことについては「隠すべきこと」として、封印されてきた。
「なかったこと」にするよりも酷く、「あったこと」だが「忌むべきこと」としても封印。
犠牲になった女性たちの扱いは、帰国後の方が酷かった。
団長ほか、開拓団をまとめる立場の者たちが、生き延びるために若い女性たちを差し出すという決断をしたにもかかわらず・・・
この構図は、戦争についての責任を追及せずに、GHQ指導の元に戦後生活を得た日本そのものに重なる。
というわけで、描かれる内容は非常に重要である。
が映画作品としては、テレビの報道特番のような印象を受ける。
これは、同じようなショットや証言が繰り返されるからか。
それとも、本件を次代へ繋ぐ、という流れ・作品のつくり自体が綺麗事にみえるためか。
映画としては「惜しい」感じがしました。
いうなれば、ルポルタージュ本として、じっくり読みたかったなぁ、という感じなのだ。
事実
戦後80年 見るべき映画とはこの作品
仕事が休みだった平日。自宅から地下鉄に乗って映画の上映館がある渋谷に向かう。
電車の席に座ると、目の前になかなか素敵なマダムが一人。年齢は50過ぎか。僕よりは若いだろう。
その彼女をチラリと見て、ぼくは渋谷に向かう30分、電車に揺られた。
で、映画館に着き、上映までしばらく待っていたら、そのマダムが連れと一緒に隣にいた。ちょっとびっくりした。まあ、それはこの映画とは無関係の話。
この手のドキュメンタリーを見る人って、どういう人なんだろう。日本の戦争犯罪、戦争責任とかに関心のある「左」の人だろうか。きっとそうだろうな。
平日の昼間、予想外に客は入っていた、3割弱はいたかな。でも、ほとんどが60、70代の男女だった。僕もそのひとりだが。
ドキュメンタリー映画である。内容的には過去にテレビで放送されたり、ノンフィクションとして出版化もされたことである。新事実があるわけではない。
過去にNHKなどで放送されたものに比べると、彼女らの深刻な体験についてはマイルドな伝え方になっている、と感じた。
ただ、「性接待」を強要された人たちの証言だけでなく、戦後生まれの人たちが彼女らとどうかかわったか、という今日的視点が織り込まれ、考えさせる内容になっていた。
テレビ朝日の社員ディレクターによる作品だが、ミニシアターでの上映だけでなく、広くテレビでも見られてほしい内容だと思った。
にしても、彼女らのことを書いた「碑文」が参政党やら維新やら保守党やらの極右、歴史修正主義者らにペンキでもかけられないか、なんてことがなければいいけど。
映画「国宝」のレビューが、僕が書いた1本を含めて1500を超えているにのに比べると、本作はたったの15本のレビューしかない。
戦後80年。歴史を知り、そして考えないといけないのである。
せめて50、60のレビューがついてほしいものだ、と思う。
地下鉄の中で見た、あのマダムは映画を見て、どう思ったかな…。
自分が団長だったらどうしただろうか?
岐阜県白川町黒川から満州へ移り住んだ開拓団の、終戦後から2か月間にわたり「性接待」を強要された人たちについてのドキュメンタリー映画です。
軍隊が国民を守らずに逃げたという話は至るところで聞く話ですが、これは、開拓団が終戦後に、自分たちが土地を奪った満族の人々からの襲撃に対して、自決をせずに、ソ連兵に守ってもらう代償に、同胞の若い女性を差し出すという選択をしたというものです。
その選択により、開拓団の多くの人々は日本に帰って来ることができました。ところが、自分たちの負の歴史を覆い隠すために、緘口令を強いたり、村八分にしたりすることで、自分とは関係のないところで起こったこと、あるいはそんなことはなかったことにしようという意図で、戦後、その事実はずっと伏せられてきました。それが、2013年7月に行われた満蒙開拓平和記念館での語り部定期講演で、勇気ある二人の女性がこれについて証言したことをきっかけに、初めて公になりました。
人間の「業」というものの恐ろしさに、途中から涙を禁じえなかったです。「性接待」を強要された人たちのお孫さんがみな、勇気ある証言をした祖母のことを誇りに思っているのがとても印象的でした。
日本中、いや世界中の人たちに観ていただきたいドキュメンタリー映画であると思いました。
これを観ても、「歴史を書き換えた」とまたあの議員は言うのでしょうか?
自分が開拓団の団長だったら、どういう意思決定をしたのかとずっと考えています。
だんだん時間が経っていく。
大体混乱期には理不尽なことが起こりやすいが、黒川開拓団が第二次世界大戦終戦直後、満州から逃げられず、ロシアの支配下に置かれた時に何が起こったかを、具体的に語ってくださって、為になった。人身御供にされた元娘さんたちが「乙女の碑」ができて、少しだけ報われたように感じた。今はおばあちゃんとなった人たちも、心なしか表情がふっきれたように感じた。
まだ語られてない歴史が生存者が減ることで、だんだんなかったものになっていく。
映画を見た数日後、白川町黒川にある佐久良太神社に「乙女の碑」やその碑文を見に行ってきた。なぜ満州にいったのか、とか、満州からの引き上げについて詳しく書いてあった。
次の悲劇を起こさないために
隣県のことなので、黒川開拓団のことは以前に新聞記事か何かで読んだことがあった。
そのあとも、取材を続けこうして映画として残してくれたこと、何よりも取材を受けてきた当事者の方々、ご家族の方々に敬意を表したい。
あったことをなかったことにはできない。
あったことをなかったことにしたい人たちが生きている間、力を持っている間は、声をあげることができない。いや、声をあげても取り上げてもらえなかった。
いつの時代も犠牲になるのは、貧しいもの。
その中でもさらに弱いもの、女性や子供たちが犠牲になってきた。
日本に帰ってからの方が悲しかった。
利用しておいて誹謗中傷する男たち。
黒川だけの話ではない。
今も。どこかで同じようなことが起こっている。
「隠していたら、次の悲劇を起こしてしまう」
ご子息の言葉が心に響く。
あったことをなかったことにはできないと、
声をあげてくれた女性がいた。
その女性たちを支えた人たちがいた。
帰国後も、彼女たちのおかげで生きて帰れたこと、彼女たちのおかげで今の暮らしがあることに、感謝する人たちがいた。
乙女の碑を建てた人がいた。碑だけでは足らないと碑文を残そうとした人たちがいた。
亡くなった父たちの代わりに感謝し謝罪してくれる人たちがいた。
彼女たちのおかげで私たちが今ある、こどもがいると誇りに思ってくれる子や孫たちがいる。
次の世代へ伝えていかなければならないと思い、授業で取り上げている先生がいる。
こうして映画として残すことができた。
黒川は稀有な列だろう。
若い人たちだけでなく、多くの人たち、男たち、為政者の方々に是非観てほしい。
戦争の残酷さ・狂気・悪夢のドキュメンタリー映画
本まで買いました。
記録として残すことを望み語った女性たちの思いをつなぐ
語った女性たちの勇気と思いをつなぎ、映画として記録をまとめていただいた方たちに感謝します。国策で開拓団を送り込み、現地の人々から畑や家を奪った日本軍は、対ソ連軍の人柱として開拓民を見捨て、自分達だけ逃げました。棄民政策と決定権を持つ男たちの保身が、女性たちを見捨ててきました。二度と戦争を起こしてはならない、軍は人々を蹂躙することを忘れてはならない、と思います。
戦争を題材にした映画が続く
25年12月公開のペリリューはまだ先だが、それまでにこの夏は戦争をテーマした映画が続く。本作品はいきなりの衝撃作!
満州に行った人については、TV深夜ドキュメントや黒川開拓団碑文の新聞記事で知った気になっていたが、この映画を観て、知らなかった事実に圧倒された。
黒川開拓団のあった岐阜県のイオンで観たが、終わって観客席を見ると、先ほど映画に出ていた黒川開拓団遺族会会長がいるではないか。この方のお陰で岐阜県 白川町(旧 黒川村)の佐久良太神社に 開拓団 碑文が新たに建立されたのかと感慨深い。映像に出てた奥様も同席されていた。団長に「良い映画を有難うございます」と声かけされた観客もいた。
但し、岐阜県なので観客は多かったが、すべてシニア世代であった。
映画では学生時代に黒川開拓団を取材し、その後、男性教師となった人が女学生に黒川開拓団をテーマに授業する場面が収められている。学生は真剣に学んでいたが、残念ながら実際の映画館上映となると若い人が観に来ないのは惜しい。ナレーターの大竹しのぶは黒川のことを知っていたようで、それはそれで良かったと思うが、ナレーターを男性や女性のアイドルに依頼すれば少しでも広い世代の関心を集められるかもと思った。
黒川の語り部となった女性たちは子や孫たちに満州の事を隠さず話していたと言う場面があった。子や孫たちはそんな彼女たちを尊敬していたとのこと。若い人が観に来ないと書いたが、もし自分がその立場となったら若い人にも伝えられるかと自問自答する。よほど信念や自信がないと出来ないことで本当に稀有なことである。
歴史に残る映像となった。先人の苦労が報われることを祈りたい。
重いテーマだが観るべき作品
黒川開拓団が直面した命の危機と若き女性たちの受難の歴史。
何故開拓団は満州に送り込まれたのか?
何故彼らは侵攻してきたソ連軍将校に若い女性を差し出して陵辱させたのか?
彼女達に寄り添う者は居なかったのか?
現在の我が国で時折見え隠れする「弱い者を切り捨ててもいい」と主張する者達がもし力を持てば再び同じ過ちを繰り返すのではないか?
そんな思いを抱いてしまった。
出来れば男子高校生に観て欲しい、真の平和を実現する為に何が必要か、「ほんとうにたいせつなもの」を見出して欲しい。
【第二次世界大戦時、傀儡国家満州国に国策のため渡った岐阜県白川町黒川の開拓団で起きた性接待の事実を明らかにした強烈な反戦ドキュメンタリー。高齢になった被害女性達の声と、壮絶な生き様には涙が出ます。】
ー 今夏、戦後40年という事もあるからか、戦争映画が多数シネコンで上映される。戦争を知らない私たちにとっては、反戦思想を学ぶ事が出来てとても良い事だと思う。
今作もその一作である。-
◆感想<Caution!内容に触れています。>
・当時、貧しかった岐阜県白川町黒川人達は国策に乗り、開拓団として傀儡国家満州国に渡る。既に敗色濃厚で、軍隊は撤退しつつあったのに・・。劇中で語られるが、彼らは”人の盾”として派遣されたのである。
・現地民が住んでいたボロイ住居に入り(という事は、現地人から当然恨まれる。)、生活を始めるもあっと言う間に、敗戦濃厚のため現地人と、ソ連兵に怯える日々。
そこで、開拓団の男達が下した決断が、未婚の18歳以上の女性達をソ連軍の幹部に”性接待”の相手として差し出す事であった。
当時の事を克明に語る女性達の言葉が、哀しい。”お母さん”と泣きながらも、開拓団を護るために行わされた事。
・だが、もっと哀しかったのは命からがら戻った岐阜での、マサカノ日本人たちからの差別と偏見に満ちた態度と言葉だったという事実。
ある女性の手記には”日本に帰ってからの方が哀しかった。”とある。
証言をする女性の中には、顔を映させない方もいるのである。
ある女性は、岐阜の更に北部である、今は観光地のひるがの高原に移住して、酪農家として生きて来た。彼女の言葉”満州の事を思えば、辛くはなかった。”
■今作の途中から、50代の男性が登場する。彼は被害女性達の家を何度も周り、証言を得て、それまで像しかなかった黒川の鎮守の森に、岐阜県白川町黒川の開拓団で起きた出来事を克明に記した記念碑を作ろうと奔走するのである。
そして、漸くその碑が出来た時に、彼は涙を流しながら女性達に詫びるのである。彼が生まれる前の出来事なのに・・。凄い男性だと思う。立派だと思う。
彼の詫びの言葉を聞いて女性達の表情は変わるのである。
特に、それまで顔を出さずにインタビューを受けていた女性が、顔を出してくれたり、それまで笑顔が無かった女性に笑顔が戻ったり・・。
<今作のタイトル「黒川の女たち」の意味が分かったのは、最後半である。
被害者の女性達が生き永らえたお陰で、多くの子孫が出来、その中には3人の女性達の孫もいたのである。彼女達は祖母たちの生き様を知り、彼女達のお陰で自分達がいる事を知るのである。
一人の女の子の孫が幼い時に、祖母に書いた葉書に書かれていた言葉も、優しさに溢れていて、涙が出そうになった。
そして、彼女達は自分達の幼子を、被害者の女性達に会わせるのである。その時の被害者の女性の涙の笑顔も、実に沁みた。涙が出たよ。
今作は、第二次世界大戦時、傀儡国家満州国に国策のため、渡った岐阜県白川町黒川の開拓団で起きた性接待の事実を明らかにした強烈な反戦ドキュメンタリー映画である。
最後に印象的な言葉を記してレビューを終えます。
■次に生まれるその時は、平和な国に産まれたい。>
全43件中、21~40件目を表示