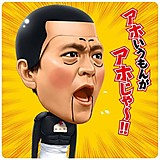大長編 タローマン 万博大爆発のレビュー・感想・評価
全21件中、1~20件目を表示
うーん
日が合わなくて、応援上映というとんでもない日にあたってしまった😅周りのノリには全くついていけず。挿入歌みたいな途中途中の歌を、なんでこの人たちは歌えるの?何回リピートしてるのって驚かされた。
万博と太陽の塔、月の石など、行きたくてしょうがなかったけど、大阪までなんか貧乏でそんな余裕のなかった小学生時代。太陽の塔は憧れで、今でもいけてないけど、あんな風に扱われて、とかは別に言わないけど。ストーリーとしては、ところどころで、昭和のニュアンスが散りばめられててクスッとしてしまったところもあったので、★1にしました。配信を待って見ようかなとも思ってましたが、配信だったら最後まで見なかったかな。
主題歌が素晴らしい
爆発だ、爆発だ、爆発だ、芸術だぁ♪
街に襲来する謎の奇獣達をでたらめ殺法で次々と撃破するヒーロー(?)タローマンのお話なのだが、先ず70年大阪万博の時代の荒っぽい映像や妙に説明臭いセリフや特撮技術が素晴らしい
そして舞台を大宇宙万博の控える2025年に移してからは秩序vsデタラメとなるのだが、まるで昭和のコンプラを無視していたバラエティ番組vs現代のコンプラ重視していたバラエティ番組みたいだった
残念なのが2025年世界でのタローマンが戦うまでが結構暇だったね
ちょいちょい場面の切れ目で登場する「タロォォウマァァァン♪」が変に癖になる
上映中ずっとスクリーンのサイズが小さい気がしていたが、まさか終盤にスクリーン上下の幕を捲り上げて敵奇獣を殴りまくるアイテムにする為にわざと小さく見せていたのはお見事!! っと岡本太郎も言っていました
結局、常識を守ってる奴には未来はない
始まりから終わりまで、徹底してバカバカしい。巨大な着ぐるみが暴れ回り、唐突に歌が挟まり、奇獣たちは意味不明な造形で「なんだこれは」と観客を振り回す。だが鑑賞後に残るのは単なる笑いではなく、岡本太郎の言葉と思想がじわりと腑に落ちていく不思議な感覚だ。
岡本太郎は「芸術は呪術である」と言った。芸術は美の飾りではなく、人の心を直接揺さぶり、世界の見え方を変えてしまう力を持つ。だから彼にとって芸術とは、理屈ではなく爆発であり、常識を壊す「でたらめ」の力だった。本作『大長編 タローマン 万博大爆発』は、その呪術的な作用を現代の観客に体験させる装置として機能している。
物語は1970年大阪万博と、そこから見た未来=2025年を重ね合わせて描く。万博は当時、科学と人類の進歩の祭典であり、同時に「でたらめ」の集合体だった。太陽の塔が象徴するのは、理解不能であるがゆえに人を圧倒する創造の力だ。映画に登場する奇獣もまた、理屈を超えた「でたらめ」の存在であり、観客に「なんだこれは」と叫ばせるための呪具である。
そしてタローマン自身の行動も、秩序立った防衛作戦や合理的思考を突き破る「でたらめ」そのものだ。未来を救うのは計算や計画ではなく、予測不可能な逸脱の力である。科学も芸術も社会の変革も、歴史を振り返れば常識破りの「でたらめ」からしか生まれていない。地動説も印象派も民主主義も、最初は世界から「なんだこれは」と嘲笑された。
観客はこの映画を観ているうちに、自らの常識を崩される体験をする。冗長だと感じる人もいるだろう。意味がわからないと戸惑う人もいる。しかし、その「わからなさ」「でたらめさ」こそが岡本太郎の真意であり、観終わった後に妙な感動として残る。バカバカしさを笑い飛ばすだけではなく、我々自身が秩序に安住しすぎてはいないかと突きつけられる。
結局、「なんだこれは」とは困惑ではなく、感動であり驚嘆であり、言葉にできない感情の爆発である。この映画は観客一人ひとりにその体験を強制する。そう考えれば、本作はただの怪作でも奇作でもなく、岡本太郎が生涯をかけて伝えた「でたらめに生きろ」というメッセージを最もわかりやすく体感させる、呪術的な芸術なのだ。
まさかのべらぼうな傑作!!
配信を一気見してハマったタローマン。
劇場版やるなら観るか〜、くらいのノリで観にいったらまさかの大満足だった!
普段はモブに毛が生えたくらいのCBGの面々が大活躍。特にカウボーイはめちゃくちゃヒーローしてた。
未来のCBG隊員の緑、いい動きしてるなーと思ったらタローマン中の人だった!
奇獣も負けてない!
正義の奇獣水差し男爵と、地底の太陽がべらぼうにいい味出してる!ソフビが欲しい!
そして今回のストーリーの骨太さよ!
タロウマンが失ったでたらめを取り戻す=人々が抑圧されたでたらめを取り戻す=〇〇がでたらめを受入れる、が全てリンクしてる。
カリカチュア化された過剰な『不適切』規制は2025年現代そのもの。
90分になっても全くテンポは悪くならず、終盤はまさかの8兄弟をぶち込んでの対明日の神話戦は激アツだき、いよいよ開いた口が塞がらなくなった!褒
タロウマンの映画でまさかこんなに満足すると思わなかったし、もっかい見に行きたい!
余談、パンフを観たら全力で買った方がいい。
監督の壮絶インタビューや、奇獣や登場人物が全員載ってる!
タロ〜マ〜ン〜
最初にサカナクションの山口さん出てきてビックリ。
冒頭シーンが4:3の画面だったので昔のテレビ番組のリバイバル上映なのかな?って思ってしまった。小さい頃に父のウルトラマンタロウのDVDとかをよく見ていて、流石にそれよりも昭和臭かったので作り物感があって、やっぱりそうゆう演出と分かった。ネットでググったらNHKで昔番組をやってたんや。
岡本太郎の格言が随所に出てきてて普通に勉強になった。「忘れるからこそ常に新鮮でいられる。そう岡本太郎も言っていた」。映画何回みてもほぼ初見な感覚で見れるから、これだけは実行できた笑笑。アイキャッチも良かったなぁ。
タロ〜マ〜ン〜♫
昔見た大阪芸大のダイコンフィルムの特撮見たくなった。
タイトルなし(ネタバレ)
まさかの今年の映画で上位に食い込んでくる程面白い作品だったとは!
最初の感想はストーリーちゃんとしてるんかい!でしたね。
2回見ると地底の太陽とかの細かい伏線とかもあったりして結構ちゃんとしてる。その上でべらぼうででたらめなのがすごい。
個人的にエランの顔が好きすぎる。常識人間一級の証明証みたいなホログラムで顔出てくるの毎回笑っちゃう。1人だけコマ撮り?ってくらいカクカクしてるのすごい。
あとエランの娘と一緒にいる先生ロボットみたいなのも好き。ビルみたいな塔を乗って鎖で繋いで動かしてるだけなのにめっちゃアクションするあれそんな動く訳なくて好きすぎる。そんな動く訳ないだろ。
明日の神話も映画の怪獣感あっていいし、でたらめ8兄弟もテンション上がった。テンペラー星人の時のウルトラ六兄弟まんまだろあれ。なんでタローマンで鳥肌立たなあかんねん。
何より星に帰っていたタローマン好きすぎる。2025年のタローマン本人やんけ。何助っ人ですよみたいな感じで出てきてんの?ほんと好き。
あとは存在しない記憶のタローブレスを使った変身シーン。あそこの山口一郎もはやホラー。
タローマンの世界に浸れるならストーリーは気にしない…
…つもりでしたが、毎回5分のテレビ版と比べて100分の劇場版は蛇足が多く間延び感が半端なくなかなか苦痛でした。
テーマはざっくり言うと「でたらめ」と「秩序」のバランスを社会と人間がどう保てばよいかという内容だったと思うのですが、このテーマが強調され過ぎでいささかクドい。
終始なにかにつけて、でたらめでたらめ…のオンパレードにはちょっと辟易しました。
テレビ版は5分間という限られた尺のせいで盛り込んだテーマがかえってクッキリ&スッキリと伝わってきたことを考えると、タローマンは劇場版にする必要はなかったように思える。(せめて60分程度?)
ちなみに長編ともなるとタローマンがどのようなキャラクターなのかよくわかります。岡本太郎のキャラなのでこれでよいかもしれませんが、野生的で奔放、知性があまり感じられず、ヒーローというよりもわがままな子供のような印象で、この点もあまり受け入れられなかった。
他に気になった点として、未来から来たサイボーグ(名前は忘れた)が70年代ではスムーズで華麗な動きを見せていたのが、2025年に戻ったとたんにC-3POのような、なんともぎこちない動きになってしまいなんとも違和感があった。(その違いについて上手く理由付けがされていると面白かったのだが)
それとテレビ版の女性隊員役の俳優さんが映画版では見られなくてそこが最も残念でした。
なんだこれは!タローマン!!
なんだこれは!
1週間経ってるのに映画館が満席!前の方数席しか残ってなかった!嘘でしょ!鬼滅とスクリーン間違ってない?
しかもタイトルが言い難い!(声に出して言ってみて下さい😊)
内容は余りにタローマン。万博と万博を繋ぐ105分のお祭りでした!
ものっすごい情熱を感じた。
メッセージ性が変に強いのもあの時代っぽい。
けど、正直、やっぱり105分は長く感じた。
70分くらいならなぁ。45分でならもっと評価したかな?
ほんと、「なんだこれは!」な作品だ!(褒め言葉)
#タローマン
なんだコレはっ❗️
事前にあまり情報を入れずに鑑賞。
始まってすぐ、まさに「なんだコレはっ❗️」です。
70年代の映像解像度、編集、台詞、岡本太郎テイストのキャラクターが、デタラメべらぼうな世界がくりひろげられます。
常識にとらわれて真面目に見てたら、この世界にはついて行けません。
ずっとニヤニヤ見ていたのに物語が進むにつれ、モラル、常識とデタラメ、べらぼうの対立は現代のホワイト社会の風潮を反映していて、不覚にも胸に刺さってしまいました。
終始このデタラメな世界に圧倒されて、気がつけば全ての登場人物が愛おしくなって、タローマンワールドにハマってしまいました。
帰り道には自然と「爆発だ♪爆発だ♫」と口ずさんででいましたとさ。
風来坊のキャラは「怪傑ズバット」のオマージュですかね。
健全な歴史改竄
岡本太郎
1911年生まれ
漫画家の父岡本一平と小説家の母かの子
の間で時代を考えれば全く互いに
好きな事をやる家族で自由奔放に育ち
絵は好きだったが何の為に描くのか
迷いながら東京美術学校で学ぶ中で
留学中本場で見たピカソの抽象画に
衝撃を受け戦後には
シュールレアリズムの大家
として突き進み1970年の大阪万博では
総合プロデュースを任されるなど
(実は1964年の東京オリンピック
のメダルデザインも任されている)
丹下健三ほか戦後を代表する
デザイナーとして地位を築く
有名なのは近鉄バファローズの
キャップのロゴをデザインした年
あの巨人のキャップより売れたというから
その世間への人気ぶりがわかる
交友関係も広くテレビ出演も
バラエティなど多岐にわたり
昭和生まれには
指圧の浪越徳治郎
発明のドクター中松と並び
「テレビでよく見る"三大"変なおじさん」
として記憶されている(勝手認定)
誰かさんが一時期名乗ってた
「ハイパーメディアクリエイター」
の正真正銘だったと言えるだろう
という岡本太郎が遺した
数多の芸術作品を奇獣とし
1970年当時放送されていた
というあるはずのない記憶で
特撮映画を作ろう
という謎発想で生まれた「タローマン」
遅れながら観に行ってきましたが
どうだったか
アクの強いノリに果たして
ついていけるのだろうかと
不安でしたが
監督の藤井亮氏
生年を見ると1年違いの同世代
解説する山口一郎氏も同世代
そう
自分も作り手も1970年の大阪万博
リアルで知らない世代なのです
太陽の塔などのモニュメント
しか知らない世代
過去を想像しながら
ある意味さぞ夢があった
イベントだったのだろうと
思いながら作ったんだな
という感じは
シンパシー覚えるところ
あって面白かったです
ちりばめられた岡本太郎の
あまりに多すぎるので書かないが
ある意味ひねくれで
ある意味ポジティブで
ある意味でたらめで
ある意味べらぼうな
格言がほぼセリフで現れ
「~と岡本太郎は言っていた」
「~と岡本太郎みたいな事言わないでください」
という言い回しがギャグになっている
(~とガ〇ダムがそう言っているってのみたい)
作りは前出のNHKのショート番組よろしく
特撮風仕立てでいきなり100分尺は
ムチャではないかと思ったが
やや長いかなと思いつつ
シナリオ自体はちゃんと映画らしく
なっていました
60分くらいでもよかったかもね
岡本太郎氏がこの映画を
観たらなんと言うだろうか
ただのオマージュで
創造性がないじゃないかと怒るか
なんだこれは!と喜ぶか
また想像にふけるもよし
よくやり切ったと思います
たまにはこういう映画もよき
抜群のセンス
美大生の抜群のセンスをひけらかされているような感じが延々続く。作っている人が一番楽しんでいる感じだ。でたらめと秩序が対立し、でたらめをよしとしているのだけど、真にでたらめな人や物は、でたらめかどうかなど気にしない。お題目を全編に渡って聞かされて続ける。高い美意識と抜群のセンスで統一された世界観で大変整っている。
大爆発
短編ドラマ10話を経てからの劇場版。
5分作品を105分は正気か?と思いましたが、でたらめな作風ならそこんとこ余裕かと思い鑑賞。
万博開催中に万博大爆発というタイトルを添えた製作陣に大拍手。
はっきりとしっかりと狂っている作品でした。
岡本太郎の名言を頼りにしながら進撃しまくり、昭和100年な事をいい事に時代を超えまくるとんでもねぇ作品でした。
初っ端から縄文人という怪人と戦うタローマン、縄文土器に感動して自分も街の一部を壊して使用しながら縄文土器作成に勤しむ様子は意味不明で面白かったです。
しかも色んな怪人が怒涛の勢いで参戦してくるんですが、そこはでたらめなタローマン、あり得ないくらいパンパパンとぶっ倒していきますし、なんなら怪人たちを活かして朝食作りに移行する肝の座りようが面白すぎました。
そこから未来のCBGのエランという人物が2025年からやってきて、タローマンの力を借りたいという感じなんですが、タローマンが素直に応じることはなく、連れて行こうとしたら変に暴れてみたり、対策をうったかと思ったら全部吹き飛ばしていったり、結局反対のことをすれば喜んで未来へ行ってしまうというでたらめさを見せつけてくれて中々にお腹いっぱいです。
未来に行ってからもタローマンのデタラメっぷりは相変わらずで、もうなんなら人間サイドが奮闘する描写が多いくらいサボりまくりなんですが、決めるところはしっかり決める、というか増殖したり意味不明なパワーアップしてみたりとやりたい放題で、オチの付け方すら水を差すようなおバカっぷりを爆発させていて笑いっぱなしでした。
70年代の特撮の表現が素晴らしく、当時を体験していない自分でもその時代にタイムスリップしたようなタッチで戦闘シーンやミニチュアをたくさんやってくれるので手作りな感じがヒシヒシと伝わってきて最高ですし、それにすら抗うようなタローマンのヌルヌルした動きも人間味がありつつ、程よく気持ち悪さも兼ね備えていてこれまた面白かったです。
タローマンがエンドロールを邪魔しまくるのでこんな大変な作品を作った製作陣のお名前が拝めないのが惜しいところですが、あのタローマンを仕向けたのは製作陣なのでなんとも言えないところです笑
一郎さんの解説パートもタメになるなぁと思いつつ、時折顔を出すタローマンオタクな一郎さんが微笑ましくも思えつつ。
5分尺でまた狂っているものを観せてくれるのかな〜と続編を今から待ち侘びている自分がいます。
皆さんせーの「なんだこれは!」チャンチャン。
鑑賞日 8/26
鑑賞時間 14:15〜16:15
ばーくはつだぁ、ばーくはつだぁ、ばくはつだ!
の歌と、映画泥棒みたいなタローマンの動きが後を引く味わいで、、、クセになるよね。それで★0.5プラス。
んで、岡本太郎の主張を繰り返し盛り込む努力と岡本太郎本人へのリスペクトで★0.5プラスかな。
作品そのものは別に悪くはなかった。そういう時代や特撮をなぞるスタンスは珍しくないしね。
一番引っかかったのは、岡本太郎が一番嫌っていたのが、
符牒
ってこと。パロディと呼ぼうが、オマージュと呼ぼうがあれはまさしく「特撮の符牒」だし、「70年代の符牒」だよね。そこは、大いに異論が湧いたなあ。これでも岡本太郎は読み漁ったしね。そこが最初から引っかかって、純粋に作品に没入できなかった、個人的には。
それに対立関係にある組織がどちらも「岡本太郎の作品群」なので、戦う理由がぼやけてしまっているのもマイナス。あの手の構成は善と悪がはっきりしてしる対立構造だからこそ、「善」側に感情移入できるわけだからさ。そこを「岡本太郎風」な視点で語ると、ちょっとねぇ、という感じ。
パンフは当然買ったけど、「昭和感」を出して「懐かしさ」も味わってもらおうっていうのがビシバシでてきてるのも、うーん。
岡本太郎は「誰にも受け入れられないもの」を創造することに意義があるっていってたんだから、映画との相性は良くないのかもね。エンタメと割り切れば観れるだろうけどさ、、、、
2025年度劇場鑑賞40作品目(41回鑑賞)
トゥーマッチ
で良いんだろうな。
NHKで放送された短編を見てて面白かったから見に行ったんだけど、物語とキャラクターが冗長で長く感じた。この特撮レトロ感でどこまで行けるか、チャレンジングな作品だった。
岡本太郎のコトバを繰り返すんだけど、せっかく良いこと言う〜なので、字幕もあるけどサッサか次のシーンに行っちゃうので1個くらいお言葉を持って帰りたかったな。
でも太郎さんもそこまで望んでじゃないか。いいのか。
最後分裂した明日の神話が巨神兵みたいに見えた。あんな柔らかい素材だったのね!!
渋谷駅でしみじみ観ました。カチコチだよね、本物は…
岡本太郎ファンにはたまらん
太郎の作品大好き!タローマン大好き!
冷蔵庫に太郎のお言葉マグネット貼っている自分には
むちゃくちゃはまった!
105分どうすんの?と多少心配していたが
べらぼうな登場人物や奇獸が終始ワラワラあーだこうだしていて
タローマン抜きでも話は進んで飽きさせない。
(と、言いつつ中弛み?眠くなるところも・・)
このギッタギタの昭和感は
もはや令和の今には新鮮すぎてセリフきいているだけでああ楽しい。
さらに3分に1度くらいの割合で太郎のありがたいお言葉がポンポン出てくるわ
あの作品この作品が奇獸として出まくるわ
音楽もはまるわ、そしてやはり主題歌、最高!
一郎さんもしっかり登場し、
楽しくて終始ニヤついてしまった。
ナンセンス系と見せつつ
ただ観ているだけで岡本太郎の哲学が五臓六腑に染みわたる
実はかなり、お得?な作品とも思える。藤井監督素晴らしい。
フランス人の一部にはハマらないかななと思っていたら、
映画祭に出品するらしいので反応が楽しみだ。
岡本太郎好きにはウケる?
サブいギャグの連発。
隣で恰幅の良い男性がブヒブヒ笑てたけど俺は全くおもろない。ストーリーも薄いし冗談で作った作品か?と思てまう。
わざわざ映画館で観るもんと違う。
良かった点は早川健(宮内洋)と少林寺木人拳の木人が出てきたところやな
岡本太郎は正義。
1970年の万博開催の日本、100年後の未来2025年から来た寄獣と未来兵士と、その時代の地球防衛軍CBGと、敵なんだか味方なんだかなタローマンの話。
2025年の昭和100年で開催される宇宙万博を絡め「秩序と常識な未来」の世界でタローマンの都合とワンパク感、CBG達のおふざけ、“岡本太郎は言っていた”なナレーションとセリフで見せてく。
ストーリーはちゃんとあるけれど、この昔っぽいナレーションと棒読みっぽくも聞こえるセリフの喋り方で何かストーリー入ってこない、入ってこないけどずっとふざけてる(笑)これだけは分かる!
デタラメな巨人タローマンのわんぱく感、人が乗ってる電車を持ち上げて電車ヌンチャク、敵とのバトル中に突然作り始めた縄文土器、合間に入る“岡本太郎は言っていた”というワードに笑い堪えるの必死だった(笑)
世界観になれてしまって少しウトついたけど楽しめた!てか岡本太郎はネタかと思ったら実在する方だったんですね。
でたらめの完成度
面白かった。テレビのタローマンが好きなら間違いない。
「うまくない」ように作っている風に「うまく」作っている、という無茶苦茶矛盾したことをすごい完成度でやっている。
はじめ、「えっ、劇場版なのに3:4の昔のテレビサイズなん?」って不満だったが、まさかそれが画面が大きくなる仕掛けの布石だったとは…。
「でたらめ」というか、これって単なるギャグじゃん…、といいたくなるシーンも多かったが、笑えたので問題なし。タローマンじゃないキャラのでたらめで笑えるところが多かった。
ただ、観てる側としては、作り手がねらってチープな画面とか、変な展開にしてることをわかってるので、その分少し冷静に観てしまうところもある。
ほんとうに真面目に作ろうとした作品が意図せず奇妙になってしまった方がやっぱり面白い。デスクリムゾンとか、MUSASHI -GUN道とか。
タローマンが何なのか全く知らなくて、これが本当に1970年代に作られた作品なんだとだまされて観た人だったら、もっと衝撃で、もっと楽しめたかも。
単に笑えるだけではなくて、ちゃんと岡本太郎の言葉が引用されてて学びも多い。この辺ちゃんとテレビのテイストを維持している。
とくに、万博の「太陽の塔」にこめられたメッセージはあまり知られていないので、2025年の万博をやっている今こそこの映画をやる価値がある。
全21件中、1~20件目を表示