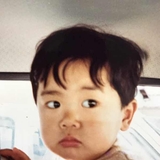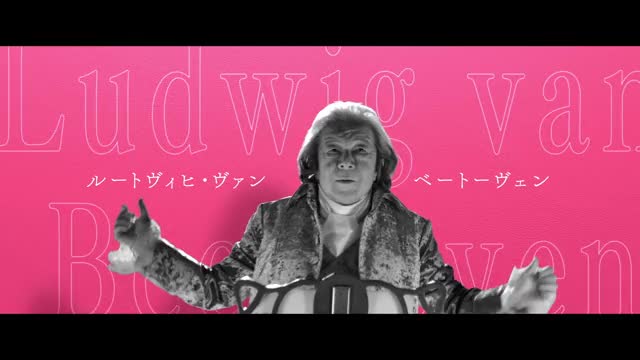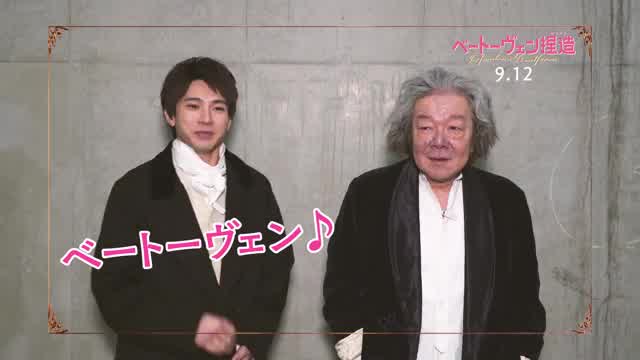ベートーヴェン捏造のレビュー・感想・評価
全61件中、41~60件目を表示
勝手に罠にハマった感じ…
最後の生徒のひとことを聞くために長々と交響曲を観させられていたようで…正直途中ウトウトしていたけどそれも踏まえてしてやられた感じが悔しくて面白い映画でした。
低予算ながら上手く纏め仕上げたと感じます
大昔、”アマデウス”を観たけども。この手の話はあれ以来でしょうか。
今日は、低予算ながら良くこんな面倒くさく難解な古典的イメ-ジになりがちな作品の「ベートーヴェン捏造」を見ました。
原作:かげはら史帆氏(ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく)
脚本:バカリズム氏
監督:関和亮氏
-------MC------
・ベートーヴェン役:古田新太さん
・シンドラー(忠実おバカ秘書)役:山田裕貴さん
・セイヤー(アメリカ人音楽ジャ-ナリスト)役:染谷将太さん
・ホルツ(晩年の秘書)役:神尾楓珠さん
・カ-ル(甥)役:前田旺志郎さん
--------------------
最初少し難解気味に人物相関が理解できず行くかと思われましたが
洋画で字幕だったら難しくなったでしょうけども、
そこは日本語 ある意味吹替(笑)。かつ登場人物が総て日本人顔。逆にこれで良いのかとは思いましたね。
会話や思ってる心内の心情理解は良く訳されてて分かりました。
この点はバカリズムさんの脚本の功績なのでしょうか。
決して過去作品風な おバカ路線には入らず、
あくまで原作ベ-ス?に忠実路線に徹したところは良かったと感じます。
”アマデウス”の時も感じたのですが、天才を描く時
どうしても内面をどう感じ どの様に切り出すのか表現が難しいと思うのです。
コミカル風に置き換える事でより人間らしく内面を描けたのではないでしょうか。
そういった点が評価かなと感じます。
洋画字幕で内容ベタで描かれてたら、BGMがクラシックですしね きっと熟睡してるだろうと思いました。
原作知りませんが、内容は非常に興味沸きました。
本気でドイツ、ウィ-ン、アメリカ合作で仕上げたら
中々?オスカ-狙えそうな作品素質では無いかと、そう思います。
(良かった点)
・あくまで学校の音楽教室内での 音楽の先生と生徒の話。
ココでの遣り取りが 決して総てを包み隠さずさらけ出す事(真実)が正しいわけでは無いとしているポイントが良い。セイヤ-が最後に取った行動がやはり善の行いとして取れるのではと思うのです。
確かに捏造したことはイケない事ですが、偉大なる音楽家を守り称えたかった訳で。親族内の事まで今更暴露する事がいいのかどうか。そう言う事ではないでしょうか。昨今のSNS問題を思うとそう感じます。
・誰を見てもクセ凄な役者陣。西洋の話なのに、キャスト全員日本人。
でも背景等はできる限り洋風仕立てで。
色々と画を工夫し普通なら金かかりそうな場面を低予算内で纏めているのが伺えます。その点は出来る事をやっているのがこちらにもその努力が伝わって来ます。
上手く纏めていったのかなとは感じました。
・俳優陣はメイン山田さんの頑張りどころ一筋って感じですかね。
あと、古田さんに染谷さんですね。悪乗りして無くて程々で良かったです。
(難点な点)
・脚本域の事ですが、時代を語るのに 18OO年~とか事前テロップ多過ぎと感じます。ちょっと技が感じられません。正確に描きたくてそうなったカモですが、荒くなっても良いと思います。観客はそんな数年毎の話は気にしてないと思います。
あくまで流れが大事で。それよりも その年代の時代象徴する背景的な物を同時に映した方がより一層印象を与えて分かりやすかったのではと思います。
ベ-ト-ベン楽曲がBGMでガンガン流れて
是非好きな人は
どうぞ劇場へお越し下さい!
評価できない。
しいて言えば
ベートベン以外は、おとしめられた。
そんな感じ。
劇中に出てくる、オーケストラは
ちょっとだけなのに感動した。
素直に音楽の力はすごいと思ったし
文化を好きになった。
言葉にすれば
すべておとしめられる
そんな重さがあった。
僕はのだめが好き。
飛んだら跳ねたりする女の子が
昔の偉人と対峙しながら
音楽を作っていく方が、豊かな音楽と思ってる
だから、子供にそんな重たいバトン
渡さないでと書いておく。
虚構と推し活のあいだで
歴史というものは、事実の積み重ねではなく、物語の積み上げである。そう思わせてくれる作品。ベートーヴェンを“孤高の天才”として後世に伝えた秘書アントン・シンドラーの「熱量」を題材にしている。だが、ここに描かれるのは単なる音楽史の豆知識ではない。もっと人間臭い、普遍的な物語だ。
◼️偶像化された“推し”
シンドラーはベートーヴェンを守ろうとしたのか、それとも利用したのか。答えは両方だろう。会話帳を改ざんし、伝記を脚色し、欠点を削ぎ落とした「理想のベートーヴェン」を組み立てた。それは、現代で言えばオタクが「推し」の黒歴史を隠し、SNSで完璧な偶像を作り上げる行為に近い。
「推し活」とは自己投影の営みである。推しを美化することで、自分もまた社会に対して存在を誇示できる。シンドラーにとってベートーヴェンは音楽の巨匠であると同時に、自分の人生を正当化するための最大の道具だった。
◼️日本人が日本人として外国人を演じる意味
特筆すべきは演出だ。古田新太が演じるベートーヴェン、山田裕貴のシンドラーをはじめ、登場人物は「日本人っぽさ」を隠そうとしない。つまり、映画は最初から“これは虚構だ”と開き直っている。
この潔さが効いている。観客はリアリティを疑う余地もなく、「歴史とは誰かのフィルターを通じて伝わる」というテーマに直撃される。舞台演劇的な虚構性が、そのまま映画のメタ構造を補強しているのだ。
◼️先生と生徒、そして観客
さらに構成が面白い。先生と生徒の対話パートで“史実”が語られ、再現パートで“虚構”が提示される。観客は理性と感情を行き来しながら、真実と物語の境界に揺さぶられる。
ラストの会話で「先生のような人が歴史を事実と異なる形で伝える」と生徒が指摘する。これはまさに観客への問いかけだ。歴史を“事実”として信じていいのか、それとも“物語”として受け止めるべきなのか。
◼️歴史はそもそも捏造である
吟遊詩人や琵琶法師が英雄を語った時代から、歴史は常に物語化されてきた。ナポレオンも、信長も、そしてベートーヴェンも同じだ。事実の断片を繋ぎ合わせ、社会が欲する形で脚色する。それを「捏造」と呼ぶか「物語」と呼ぶかは立場次第だ。
シンドラーの行為が暴かれたことで、ベートーヴェンは“神格化された天才”から“欠点も俗っぽさもある人間臭い天才”へと再評価された。むしろ、その方が私たちにとってリアルだし、魅力的ですらある。
◼️結語
『ベートーヴェン捏造』は、歴史をどう受け止めるかという人類普遍のテーマを、笑いと狂気とミステリーで見せる意欲作だ。そして観客は気づく。私たちの「推し」も、企業も、国家も、すべてはシンドラーのような“語り手”によって形作られた偶像なのだと。
結局、歴史とは「推し活」の最も壮大なバージョンにすぎないのかもしれない。
楽しんだ、ただバカリズムはやっぱりちょっと苦手
バカリズムはネタも脚本もあまり好みではないのですが、古田新太ベートーヴェンに抗えず鑑賞。
キャストで見る映画でした。山田裕貴さんは実は目元も声もややぼやっとしているので(ディスるわけではないです)、こういうちょっとずれた垢抜けない役のほうが合うのではないかと思いました。古田新太はザ・古田新太です。小澤征悦さんはセリフほとんどないけどいい。
原作未読ですが、音楽の先生が生徒に捏造を語り、その学校の先生役のみなさんが本編の各役としても出てくる仕掛けは、日本人が外国人役をとってつけたような背景で演じる、この作品への導入としていいアイデアだと思いました。
狂気のファンはその狂気の愛ゆえに、対象を誰しもに特別と思わせるだけでなく、自身を対象にとって特別な存在とも思いたがる。それを感じさせるストーリー。それをわかっていても不思議とシンドラーを応援する気持ちになってくるのは山田さんの力かもしれません。
総じて楽しめた作品です。
ただ、終盤の生徒とのやりとり。
本編ではシンドラーの先生が、セイヤーへの解釈が想像であることを指摘され「その方がドラマチックじゃないか」というシーンは本編とのつながり、表裏、人間の普遍性を表してとてもいいのに、それを受けた生徒の一言が私的にはやりすぎかな。
そこはわかったような顔でふっと笑うくらいの方が好みでした。それでも十分生意気な中学生です。すでに「先生の妄想ですよね」と言ってるんだから。
なのにわざわざ「先生みたいな人が真実を歪めてきたんでしょうね」(うろ覚え)とまで無自覚風にはっきり言わせちゃうのは、わかりやすくしたというより、これを面白いと思うバカリズム的性質なんだろうなぁと思います。なんというか、意地の悪さ。それもからっとしたタイプならいいんだけど、陰湿なやつ。それがバカリズム的毒といわれればそうなんですが、私はやっぱり少し苦手なのかもしれません。
キャストが豪華だ
にしても、イノッチが
コントの時のバカリズムそのもので笑った
無駄に豪華なキャスト。
お金かかってるね
子役の子、大きくなったねえ。
ベートーヴェンが指揮をしたコンサートシーン
短いながらも、凄く良かった
第九をちゃんと生で聴きたくなった
ふざけた作品かと思いきや…
シンドラーのベートーヴェン愛がハンパない。
もう神。シンドラーから見たベートーヴェンは神。
だから第九の初演でのベートーヴェンは神々しいのだ。
であるが故の伝記捏造に至ったシンドラーが主人公。
ドイツの話を全員日本人で演じる歴史ドラマに
なっているところが意外で秀逸。
バカリズムらしさはほとんどないのでは?と感じる。
むしろそれで良かったと思う。内容は硬派。
前半はベートーヴェンの秘書とし
て尽くすシンドラーが
描かれ、ベートーヴェンの本質的な姿も描かれていて、
割とシンドラーは酷い扱いを受けるにも関わらず
その愛情は変わることがない、その一途さがよくわかる。
後半はベートーヴェンの伝記を巡って、
誰が描くベートーヴェンの姿が本当なのか、
のミステリー調というよりも、
本当の姿ではなく神々しいベートーヴェンを描こうとする
シンドラーvs現実に忠実に描こうとするホルツら
他の人たち。
シンドラーの嘘に気づき、それをシンドラーにつきつける
セイヤーだが、シンドラーの伝記の嘘を暴く行動には
出ない。
という語りを、現代の音楽教師が生徒に対してするという
設定も良い。そこで歴史って、
書物に書かれていることが全部が本当ではないことを
あらためて痛感したし、その時々の権力者の都合によって
書かれたりするわけだから、そこは踏まえておかないとな
と思った。
だからシンドラーの思いもわからなくもない。
映像の世紀にならないと事実は伝わらないのだろう。
ただ、その余白というか想像の余地があるのが
歴史の面白さ、ロマンだと思う。
俳優は山田裕貴がバツグンに素晴らしかった。
染谷将太も登場シーンは少ないけれど存在感があって
良かった。
観るつもりは、無かった!
劇場のポイントが消えるので、時間帯がこの作品だけでしたので。脚本は、バカリズムか?えっベートーヴェンは古田新太?日本人がやるの?パロディ?内容は、しごく真面目でした。誰かの利の為に人は作られるんだ。
歴史的にもよくありますね。何を信じるべきか?
えらいさんの都合や民衆のそうであって欲しい。なかなか
考える作品だ。バカリズムやるね。
捏造=作者の想い
全体を通して、もっと殺伐とするような話をちょうど良く見やすい作品にしているところが、さすがバカリズム脚本という感じだった。
前半はベートーヴェンとシンドラーの関係をイジリも入れながら語っており、どう捏造していくのか楽しみにしていた。
後半からは各々がベートーヴェンについての書籍を書く中で、元々はベートーヴェンの狂信的な信者だったシンドラーが少しでもベートーヴェンを偉大な人物として描きたい理由が前半があったからこそより際立っていた!
色々な人の伝記があって、そこに書かれていることは全てが事実とは限らないとは大人になると分かってくるが、この作品を通して結局は誰かの目を通して書かれているということは、その人の考えが入ってしまうことがあることを、伝えたかったのではと自分自身も"勝手に"想像してしまった。(先生が最後に面白い方に話を予想していたように)
求めるのは真実か事実か
ルートヴィヒ・ファン・ベートーヴェン
(1770-1827)
ドイツの歴史上代表する作曲家
古典派からロマン派を発展させた
先駆者で影響を受けた作曲家は
数知れずの「楽聖」
その生い立ちは
テノール歌手ながら酒浸りの
父親によってスパルタ的に
音楽を仕込まれ10歳を前に
演奏会にも出演
ウィーンで会ったモーツァルト
をも「なんだこんなもんか」
と思ったほど
しかし20代後半には難聴を
患い自〇未遂もしながらも
音楽の情熱から活動を続けた
というベートヴェン
原作小説をベースに
いかに素晴らしかったかという
視点で伝記を執筆した元秘書
アントン・フェリックス・シンドラー
を主人公に彼が行った捏造改竄工作
どう行われたのか
何故行ったのかに迫った今作
どうだったか
まあいわゆる
以前観た「陰陽師0」でも出てきたが
実際に起こったことが「事実」
その人が信じているのが「真実」
というやつである
世間が英雄視している人物を
側近だった人物は果たして
家政婦に当たったり
息子カールを追い込んで自殺未遂
に追い込んだりした「事実」を
並べたらベートーヴェンの
名誉はどうなるか
皆が「真実」として信じたい
形に守り通すのが側近の
私の役目だとシンドラーは
「信者」としてスイッチが
入っちゃったのである
そりゃあ偉人研究というジャンル
がある以上ありもしなかった
事を並べてしまう捏造改竄は
もちろんいい事ではない
が「わからんでもない」
という気持ちにさせられる
そこには信者っぷりがウザすぎて
ベートーヴェンにクビになり
ホルツに秘書の座を奪われた
嫉妬などもあったと思うし
ホルツらはあいつの伝記は
デタラメだと新聞で批判の応酬
を繰り広げる中で
あっちが先に死んだらこっちの
勝ちみたいな変な勝負意識が
生まれてきたりする部分は
なんともリアル
(政治の話だって利害関係に
ある人間が死なないと
真相は出てこないとよく
言われます)
自分もしょっちゅう
Wikipedia鵜呑みにして
痛い目にあっております
結局ベートーヴェンの名誉を
護りたいシンドラーと違い
ホルツやシンドラーは
事実ベースで追いかけている
だけだから永遠に反りが
合わなくて当然なのである
マスコミが取材した事
(最近は取材すらしてるかどうか)
に自分らの論調に合うように
偏向報道するのと同じである
部分は現代と何も変わりがない
事実はよほどSNSの一般人の
投稿などで転がっている
それが都合が悪いから
マスコミは必死にSNSを
嘘だらけだと叩く
自分らが信用度を落として
コソコソSNSでネタ拾うのも
全然協力してもらえなくなった
からである
昨今の情報化社会
皆事実を知りたくなっている
風潮からは
シンドラーの感覚は理解されない
かもしれないが当時がどうだったか
というところ
ただちょっとくどくど長く
画面が飽きやすいかなと思う
ところもある
日本人キャスティングでやってる
とことか画面的には非常に
「舞台」っぽくなっているが
山田裕貴や染谷将太らの演技力も
あってそこはあまり気にならない
中学校の音楽室パートも
最初は面白い構成に感じたが
中学生が急に頭がよくなった
感じで不自然に感じるとこも
あった
ならシンドラーとあの音楽の先生で
いっそ転生的に話し合ってしまう
ファンタジー演出でも?
と少し感じたところ
でも悪くはなかったです
最後にこれだけは言いたいのは
ネットもなんもない19世紀の
偉人を称えるメンタルと
何でも調べれば真偽はどうあれ
誰でも手元に入る現代を
同じ目線で見るのは大間違いだと
いうことです
歴史には「真実」よりも「ストーリー」の方が大切なのかもしれない
演劇とは違って、映画の中で、日本人が西洋人を演じるとなると、違和感ばかりが先に立って、内容が頭に入ってこないことが多い。
その点、この映画では、日本の中学校で、音楽教師が生徒にベートーヴェンのことを話して聞かせるという体裁を取っているので、そうした違和感がほとんどなく、「この手があったか!」と膝を叩いてしまった。
内容的には、だらしなくて癇癪持ちのベートーヴェンと、融通が利かなくて空気の読めないシンドラーの交流が笑いを誘う序盤、ベートーヴェンの人生を巡って、伝記を捏造するシンドラーと、真実の姿を伝えようとする勢力との闘いが面白い中盤、シンドラーによる捏造を見破ったセイヤーが、シンドラーと対峙するというスリリングな展開に引き込まれる終盤と、三部構成のそれぞれに異なる味わいがあって楽しめる。
ここで、何と言っても異彩を放つのは、ベートーヴェンの伝記を捏造することが、世の中のためになると信じて疑わないシンドラーのキャラクターで、そこに浮かび上がるのは、罪悪感など微塵も持たず、自分は正しいことをしているのだという強い信念と、狂信者のような使命感と陶酔によって支配された人物像である。彼にとっては、何が「真実」なのかということよりも、素晴らしい音楽を作り出した人物は、素晴らしい人格者でなければならないという「ストーリー」こそが重要なのであり、確かに、歴史は、こうした人々によって作り出されてきたのかもしれないと思えるような説得力を感じることができた。
さらに、この映画で面白いのは、ラストの、セイヤーに関する音楽教師と生徒とのやり取りを通じて、教師が、シンドラーによる捏造を批判するどころか、それを支持していると思わせるところだろう。そこには、全ての「真実」を暴露することは、果たして「世の中の利」になるのだろうかという問いかけや、「真実」こそが「正義」だとするSNS社会に対する疑問といった、強いメッセージ性を感じ取ることができるのである。
その一方で、冒頭の「伏線」の部分等を使って、中学校のどの教師が、ベートーヴェンの物語の誰を演じているのかを、もっと分かりやすく説明してもらいたかったし、どこか憎めないキャラクターの古田新太が演じたせいか、ベートーヴェンが、それほど酷い人格の持ち主に見えなかったところにも、少なからず物足りなさを感じてしまった。
特に、ベートーヴェンの音楽家としての実像がよく分からなかったのは残念で、例えば、偉大な芸術家ゆえの傲慢さとか尊大さのようなものや、同時代の音楽家達への対抗心や嫉妬心のようなものが描かれていたならば、より生々しくて人間臭いベートーヴェン像を作り出せたのではないかと思えるのである。
ただし、実際に、そうしたことがなかったのであれば、それこそ捏造になってしまうのだが・・・
まさしく「憧れは理解から最も遠い感情だよ」が当てはまる
偏屈で暴力的で癇癪持ちで息子を束縛し監視するベートーヴェンを支えられるのは自分しかいないと思い込み迷惑な偏愛や理想を押し付ける秘書シンドラーの話。メンヘラとDV彼氏の組み合わせに似たものを感じた。
見たいものしか見ないシンドラーの姿や、自分の想像をあたかも真実かのように話す音楽教師の姿は良い教訓になったかも。
個人的に好きなのは、序盤のまだ拗れていない頃のシンドラーが大ファンで憧れのベートーヴェンに初めて会った時、心の中で言った感想が「小さくて小太り」とか「不潔」、「握手した時の手がぬるっとしてた」ってすごいリアルだったところ。理想と現実のギャップを見ても憧れは消えず、それどころか偏愛に変わったりベートーヴェンとの相性最高だと思ってたのはシンドラーだけだったりと、タイトルの名言がぴったりだと思った。
生徒と教師が話すシーンと、偉人の歴史を解き明かすシーンが交互にくる展開に似たものは歴史系のテレビ番組でよく見るし、もしかしたら映画館で観るほどのものではないかもしれない。
⭐︎3.3 / 5.0
9月12日(金) @映画館
ベートーヴェン捏造
---
ひたすら喋るだけの起伏の無さ+心地良いクラシックで終始睡魔に襲われる😪なんて批評は「利にならない」から止めておこうw
---
#movie 🎬2025
#備忘録
#ベートーヴェン捏造
#映画
#映画鑑賞
#映画レビュー
#映画好き
#映画好きと繋がりたい
#映画好きな人と繋がりたい
後半のミステリー調に変わっていくのは面白かった!!
きっかけ
バカリズム脚本ということで観に行く事に。
ベートーベンの知識はほとんどなし。
当方、原案となった「かげはら史帆さん」の「ベートーベン捏造」は読まずに観賞させてもらいました。
あらすじ
とある中学校の生徒が音楽室に筆箱を忘れた事でこの映画は始まる。
筆箱を取りに音楽室へ行くのだかそこには先生が…
先生はピアノを弾いている。第九だ。そしておもむろに話す。「ベートーベンを知っているか」っと。
ベートーベンには、秘書が歴代何人かおり、その中でも特に強烈、いや狂人的なキャラであるシンドラーの半生について先生は話し出す。
そして、先生の話は回想シーンになり映画のストーリーは進んでいく。
果たして、シンドラーの半生とは?どーいった思いでシンドラーは狂人となっていったのか?っといったところでストーリーが展開していく。
感想
バカリズムは日常の中にある異常、もしくは、異常な話の中に普通を混ぜ混むスタイルのコントが多く、HuluでやってたOLのドラマも観て、面白いな~と思ったので絶対観ようと思い観ました。
面白いなと思った事は回想シーンの舞台はウィーンやベルリンといったオーストリアとドイツなのに、海外の人やアニメーションを一切使わず全員日本人の役者でやっていた事。そして、それが違和感ではないこと。
また、脚本も現代日本の日常のようなテイストで物語が進んでいくので、ベートーベン、シンドラー、ホルツ(シンドラーのライバル。ベートーベンの晩年の秘書)、そしてセイヤー(シンドラーの虚言を暴こうとする人)の心境やシンドラーとの関係性が理解しやすく描かれており話が理解しやすかった。
冒頭でもお伝えしたが後半で出てくるセイヤーのパートは、これまでシンドラー目線で半生を描いていたのに、ミステリータイムに突入する。そして、闇が暴かれるのかどうなのか?そしてこの映画のストーリーの肝に繋がっていくのだが、ミステリーパートから肝部分への切換がスムーズにストーリー進行していて気持ち良かったし、おもしろかった。
さすがバカリズム!!
ただ、これって映画館で観る必要あるかな??って感じた。
オーケストラの演奏も序盤の方にベートーベンが指揮をするのだが、そこくらいなもので、後はシンドラーの半生を淡々と描いてる感じ。
疲れてたのもあって正直ちょっと寝た。
まとめ
僕的には主人公が19世紀ウィーンにタイムスリップして、そこから話が展開していくもんだと勝手にフライヤーを、観て想像してしまった事もあり、なんかハチャメチャ感が足りなく感じた。
また、感想でも言ったがオーケストラの演奏や臨場感溢れる演出などかないせいか、映画館で観る映画ではないと感じたしたし退屈になってしまった。
この作品、バカリズムや堀監督を好きな方にはキツい言い方をしてしまい申し訳ないが僕にはあわなかった。
最後にこの映画はベートーベン好きは勿論、ベートーベン論争を知ってる方、クラシック歴史に博識な方、原作のベートーベン捏造の本を読んでいる方にはこの映画が面白いと思うと感じた。
バカリズム作品
原作がついているので、純粋に「バカリズム作品」とは言えないのでしょうけれど、良くも悪くも「バカリズム」さんっぽいかなぁって、思いました。
バカリズムさんの作品は、結構支持する人もいて面白いと評判なのですが、全般的に自分はそれほど面白いと思えなくて、この作品も古田新太さんが出るということで見に行きました。見ていて、古田新太さんが「自分」っぽさ(世間の古田新太イメージ)を守って演じている感じがして、そこも面白みに欠けた感じでした。
ラストでは、「それって先生の想像ですよね」って身もふたもないことを言わせちゃったのは、いかにもバカリズムさんっぽいかなぁとは思いました。
とくに、ベートーヴェンを深堀したとか音楽の歴史を茶化して見せたわけでもなく、普通に始まり普通に終わった感じでした。
ただ、始めが「音楽室で先生と生徒がコーヒーを飲む間のお話し」になっているのですが、そこには無理があるなぁって感じました
失礼ですが、映画館で観るに値しない
俳優さんたちをはじめとしてこの映画に携わる人たちが一生懸命この作品を作ったことを承知の上で無礼な感想を書かせていただきます。
決してこの作品をバカにする意図はありません。
まず、
バカリズムさん脚本にしてはひねりも伏線もないストーリー
映画の雰囲気はふざけすぎてないけどコメディ感があり、ちょい役も有名俳優が演じているほど豪華キャスト。
しかし、コメディ感がある割にセリフの掛け合いがおとなしくキャストが豪華なだけに面白くなるのかなと期待してしまうがそこまで面白くならない
特に筆談のシーンは必然的にテンポが悪くなるのか、心の声のシーンも長く多い印象で今一つ笑えない
何より1番残念だったのは多分ほぼCGで作られた安っぽい街並み
総評して凝ったセットで作られた長くつまらないコントを見ているようだった
テレビのコント番組で見るならまだしも映画館で観るには値しないと感じた
この投稿を読んで気分を害した方がいらしたらすみません
変化してく真実。
音楽室へ忘れたペンケースを取りに行き「コーヒーでもどう?」と音楽教師に捕まりベートーヴェンの秘書をしたシンドラーの話を聞かされる生徒の話。
シンドラーの秘書時代、ベートーヴェンが亡くなってから伝記を書くまでを教師と生徒の語りを合間に挟みながら見せる。
先に書くとバカリズムさんの脚本は私の性格上苦手でドラマ作品はスルーしてきた、ってのもクドイ台詞回しが無理、無理だけど本作は映画だから観た~
秘書から始まり著者へとなり…偽り伝記で新聞を使っての論争からのベートーヴェンの伝記を新たに書こうと調べ始めた若者と見せるけれどストーリーが全く刺さらず眠い。
最初から最後までずっと眠かったけどラストの音楽室での先生と生徒の会話、生徒から「この話って先生の想像も入ってますよね」…「先生みたいな人がいるから真実が歪んで伝わるんですよね」と冷静に先生の話と先生を論破する生徒に吹き出しそうになった(笑)
真実を伝えることの「正しさ」とは
コメディを観に行ったはずが…何やら深いメッセージを受けた、不思議な作品でした。
過去の偉人の伝記などが正しいかどうかは日本でも話題になりますよね。不確かだからこそのロマンがあると思うし、新たな解釈で本が出版されたり、映画化されたり…。本作はそんな歴史の曖昧さをテーマにした作品。
思ったより真面目だなぁ、というのが正直なところ。いや、ベートーヴェンが生きている前半部分は結構笑いどころもあって、ちゃんとコメディしてたんですが、後半になるとなんだかシリアスな展開に。
本作は、後半のシンドラーの狂気とも捉えられる、敬愛するベートーヴェンの美化に奔走する姿こそが描きたかった部分だったかと思います。真実を全て語る必要があるのか?彼の評判を落とすような伝記を残しても誰の為にもならないのではないか?偉大なる音楽と共に偉大なる作曲家として評価されるべきではないか?シンドラーの暴走は倫理的な問いに発展していきます。
コメディとして観たら、もう少し笑いどころが欲しかったかな、とは思いますが、思いもよらぬメッセージ性はなかなか深いなぁと唸ってしまいました。
ラスト、生徒と先生の対話で終わるのも面白かったです。これは現代に通ずる普遍的な問題であると思わせてくれるオチでした😊
全61件中、41~60件目を表示