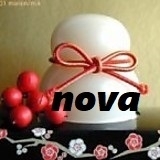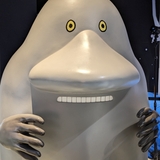おーい、応為のレビュー・感想・評価
全58件中、1~20件目を表示
応為の内面のドラマはあまりない、芸術家親子の日常系映画
タイトルロールは葛飾応為だが、終盤にはいつの間にか北斎の物語になっていた。
応為関連のエピソードの多くが断片的で、ただ日常を淡々とたどっているように見えたこと、そして永瀬正敏の北斎の方がキャラ・ビジュアル共に作り込まれている印象だったことがその原因だったように思う。
先によかった点から書くと、長澤まさみはとても魅力的だった。北斎の部屋でくつろぐ彼女の、着物の裾から覗く膝下の長くて美しいこと。江戸時代に本当にいたら周囲から浮くのではといらぬ心配が湧くほどのスタイルのよさ。そんな彼女が着流しのようにマニッシュに着物を着こなして強気な物言いをすると、独特の婀娜(あだ)な雰囲気がただよう。
ところどころで見られた、江戸のレンブラントとも呼ばれる応為の画風に寄せたような光と影のコントラストが美しい映像は、応為へのリスペクトを感じられてよかった。
ずっと美しかった長澤まさみの横で、老けメイクばっちりなだけでなく老いを段階的に演じ分けた永瀬正敏の演技力が際立った。
正直なところ、人間的な魅力も北斎の方が上手く描けている気がした。馬鹿にしていた長寿の煎じ薬(wikiによると茯苓(ぶくりょう)という生薬らしい)をしれっと常飲していたり、迷惑がっていた子犬のさくらを添い寝するほど可愛がるようになる様子は人間味があって微笑ましかった。愛する者の姿に死の影を見ることに耐えられないのか、病床の息子にも会いに行けなかった彼が、取材旅行から帰ると死んでいたさくらの墓の前で、肩を震わせる姿に胸が痛んだ。
パンフレットの年表と、以前見た「新美の巨人たち」の応為の回での情報を合わせると、応為が夫と離縁して北斎のもとに身を寄せた1820年、彼女は20歳位だったと思われる(厳密には生没年不詳)。長澤まさみの美しさと演技で、この時期の描写にはさほど年齢的な違和感はない。
ところがこの後、11年ほど時間が飛んだ場面で、北斎はがっつり加齢が進んでいるのに応為の顔はつるんとしたままなのを見てちょっとだけ「あれ?」と思った。
まあいいか、と思っていたら、時間の経過と共に北斎だけがさらに年を取っていき、応為は終盤で少し白髪が生えたもののお肌はツルツルなままで(北斎が亡くなった1849年、応為はアラフィフのはず)その落差に対する違和感が雑念になって気が散ってしまった。
もう少し、2人の加齢のペースを揃えてもよかったのではと思う。
また、応為に関するエピソードがどれも北斎の横に並べて語るにはインパクトが弱すぎる印象だった。
そして「自分の意思で父親の世話をしていた」と応為に語らせたことで、親子愛の話にはなったが応為の内面のドラマがさらに薄くなった気がした。
実際の応為の気持ちは当然わからないのでこの辺はもう完全に私の好みの話になってくるが、十分な才能を持ちながら天才である父の助手に甘んじざるを得ない人間の葛藤を描く方が人間描写としても面白いし、応為が女性だからこそ現代に通じるテーマ性も出てくるのにと考えてしまった。
まあ、私が勝手にそういう物語を期待して、蓋を開けたら日常系&親子愛の話で肩透かしを食らった、それ以上のことではないのかもしれないが。
あと、映画を観ている時は気づかなかったが、キャストは自分で浮世絵を描く練習をかなり重ねたそうだ。にもかかわらず、北斎が障壁画を描く時以外、吹き替えなしにここまで描くのだとびっくりするようなシーンはほとんどなかった気がする。障壁画のシーンも、実際は浮世絵指導担当の想定の3倍ほど長回しで撮って、その間永瀬正敏はずっと描き続けたらしいが、映画では最初の数タッチしか使われていない。
せっかく練習したなら、長澤まさみが、永瀬正敏が実際にここまで描いてるんだ!と驚けるような映像が見たかった。そのような映像は役柄のリアリティも向上させる。
パンフレットの浮世絵指導担当者インタビューには、「監督は欲張らず、見せきらない選択をされて、すごい」とあったが、いやいや見せてくれよ。もったいない。
うーん、残念
何を伝えたいのか、場面がコマ切れでストーリーがつかみづらい。
絵師のふしだらな日常を描きたかったのか、出戻り娘応為とだらしない父北斎との日々を描きたかったのか。
物語は長澤まさみの男勝りな演技と永瀬正敏の怪演に終始する。
著作権の関係もあるのだろうが、絵画ができあがるまでの流れと葛藤を期待しただけに、人間模様に脚光か当てられ過ぎて肩透かしを喰らった。
単調なため途中で居眠りしてしまった。
実在と空想の狭間
ずっと観たかった一作
が、Uターン転職したての週から公開だったため、バタバタしていて地元では逃してしまい…
なんとか観られるシアターとタイミングを探り、本日ようやくテアトル新宿で成就!
さて感想を…
まず前提として、葛飾応為は情報量が少ないミステリアスな存在
自分が知っているのも『奔放な性格』『だが筆は精緻かつ繊細』『旦那の絵にケチつけて勘当くらう』くらいのもの
よって、フィクションとしてならある意味どんな表現もできてしまう
それだけに万人に共通する応為像を”創る“のは非常に難しいのだろうということは理解できる
だが、そのためかやや物足りなさを感じてしまった
題材として取り上げられた作品がほとんどないのなら、いっそ当作で「葛飾応為とはこういう絵師だったんだぜ!」くらい大胆に描いてほしかった
もうひとつ残念な部分として、終始色彩が鮮やかすぎたこと
そのことで身近に感じられすぎたというか…時々まるで近所にいそうな錯覚に陥った
しかし全体的には良い作品だし、配役は最高だった
特に長澤まさみさんはドはまり役で、公開が決まった時から葛飾応為=長澤まさみが即シンクロしていたのだけど、その期待に見事に応えてくれた
そして永瀬正敏さんの幅の広さ
年齢的にどうなんだろう…と感じていた不安は序盤であっという間に払拭してくれた
脇を固める篠井さんも寺島さんも、大俳優なのに月明かりの如くさりげなく照らしており、さすがの一言
とにかく観賞後の今、葛飾応為という人物の魅力にますます取り憑かれたのは確か
ただ最後はあの言葉で締めてほしかったなあ
「筆1本あれば生きていける」
特別なことは起こらない、それがいい。
「百日紅」溺愛者の江戸文化好きなので「長澤まさみと永瀬正敏なら大丈夫だろう」と思って観た。今日までだったので焦った。
冒頭から最後までカッコいいジャズが鳴っていて、画面では江戸の人たちがただ生きている。フランス映画みたい。エンドロールで大友良英の名を見つけ声出そうになった「ですよねー!」って。
色男渓斎英泉、髙橋海人良かった。チャーミングで儚い感じよく出てた。もっと艶っぽいシーン観たかったな。
「百日紅」のエピソードがたくさん出てきて、その度に泣きそうになった。台詞そのままなんだもの。
いろんな絵師の人生があるけれど、北斎は一等幸せ者だったんじゃないかな。そう思える長澤、永瀬の親子だった。
期待しすぎた〜
その一言に尽きます。
葛飾応為が大好きで、長澤さんのビジュアルが美しくて、情報が出た時からものすごく楽しみにしていました。(眩の宮崎あおいさんは少し可愛らしすぎるなぁと思っていたので)
最低でも2回は見に行くだろうなと、ムビチケはとっておいたのですが、もう使わずに終わりそう。
「葛飾応為」の作品としてみるとこの評価になりました。
まぁでも長澤さんと永瀬さんのビジュアルだけはよかったので良しとします。
ファンの方には申し訳ないんですけど個人的には善次郎のイメージが違い過ぎるので、メインビジュアルは葛飾親子だけで良かったのになとは思います。善次郎がいてもいなくてもいいような位置付けだったので余計に。
事務所的に出さなきゃいけなかったとか客寄せのためなのかなとか大人の事情を勘くぐってしまいます。何せお芝居がなんというか…うーん……過大評価しすぎじゃないかなぁと。
全体的に…
お栄さんは仕事せずぶらぶらして煙管ふかしてる、何もしないくせにやたらと啖呵切って偉そう。北斎先生も耳障りなほど口が悪くやたらと怒鳴り散らしてる。(二人のこの描かれ方が一番悲しかった)
門人や版元が工房へ出入りする描写もなく、貧乏人が追われて次から次へと引っ越してるだけの、そんな印象。(沢山引越してたっていうのをやりたかったんでしょうけど)
津軽の侍のくだりいらんから絵師として北斎先生の弟子としてもっと北渓さんと善次郎と絡んでほしかった。男だったら確実に名を上げていたんですよ、彼女は。絵師としての葛藤をもっと見せてほしかったです。
もっと絵を、大画面で見せてほしかった。
晩年を描いたのに小布施を出さないのはなぜ?
お栄さんも同行した記録があったはず。
富士越龍図を描きながら息絶えたようにしたのは何故?(亡くなったのは数ヶ月後だったような)
お弟子さん達に見守られながら亡くなったと記憶していましたが。
応為の記録が少ないのは仕方ないにしても、北斎先生に関しても「ん?」と思うことばかり。
予算がなかったのでしょうか…。
見終わったあと口直しで眩と百日紅を読み返すぐらいには後味悪かったのですが、
ライティングとか映像の雰囲気自体はこだわりを感じて好きでした。
内容はどうであれ、長澤さんのビジュが美しく格好良かったです。あとパンフレットがかなり良かったです。
タイトルなし(ネタバレ)
やっと見れた
浮世絵師の世界観を粛々と描いてる
お栄は髷を結ってなくてかんざしでとめてるだけ着物も着流し風でそれでもそこはかとなく美しく寝転んでたら足がて出る所も色っぽくて着物が墨が付いてたり、足の裏が真っ黒だったりすごく現実味がある
足の指が女は上になるんだよて父である北斎にアドバイスしてた
弟?が盲目で母親と別に暮らしてるんだけど亡くなった時に魂だけ北斎と応為の住む長屋にきてた
お栄ちゃんも弟くんもものすごい北斎の事を尊敬してて慕ってて大好きでものすごい愛を求めてるんだね
俺について来ないでこんなじじいの世話をしないで自分の好きな事をしなさいと言われ泣きながら好きでやってるんだよてあの最後のセリフ震えた
天賦の才能を持ち、その道に邁進する者ならではの苦しみ
愛読する「百日紅」(杉浦日向子)が原作とのことで(実際はもう一冊あるが)見に行ってきた。
正直「百日紅」を読んだり、北斎についてある程度知っていなければ状況や人間関係が分かりにくいかもしれない。それらの説明は必要最低限、雰囲気から色々察しなければならないが、そういうのが好きな人には余計なノイズのない、どっぷり雰囲気に浸かれる映画と言えるのではないか。
個人的に印象に残ったのは、天賦の才能を持ち、その道に邁進する者ならではの苦しみ。
北斎はいつか絵の神域にたどり着きたいと長寿を願いながら、長く生きたら生きたで体の衰えにより絵のモチーフを把握しづらくなり、もう一度生まれ変わりたいと願う。末娘や弟子、犬にも先立たれる苦しみも味わう。
お栄は決して普通の女としての幸せを望まないわけではなかっただろうが、己の才能の乏しさと真摯に向き合わない夫にはきついことを言わずにはいられない。恋する初五郎に対しては同様のことをすまいとあえて彼の絵師としての欠点から目を逸らしている節があるが、「妹」呼びがトリガーになったのかきつい指摘をしてしまう。
これは北斎ゆずりの才能と気性を持っているのだから仕方ない。女として、小心者やノンデリの顔を立てて支えていくには才能がありすぎるし、気性も強すぎるのだ。こういうタイプは同業者の甘えや妥協を許せない。
善次郎に寂しくないのかと聞かれるが、たとえ一抹の寂しさはあったとしても、自分を封じて誰かのお内儀になるなんて人生、彼女には耐えられなかっただろう。結局、天賦の才能に恵まれようと全ての幸せを得ることなどできず、苦しくても寂しくても自分の最適解を選ぶしかないのだ。
演技に関してはやはり北斎役の永瀬正敏が圧巻。お栄の母親役の寺島しのぶの様々な感情がにじみ出る抑えの利いた演技も素晴らしい。「女はね、赤いものをつけるとやさしくなるものだよ」の台詞の時の、母親としての表情に目を奪われた。篠井英介の小唄の師匠もいい味を出している。
長澤まさみも荒々しい演技をしていても艶があり、魅力的だったが、津軽の侍に啖呵を切るところや、北斎に対し自分がどんな気持ちでこの道を選んだかと語るところはやや俗っぽく感じた。下手というわけではなく、この映画であればもう少し斜に構えた、抑えた演技の方が個人的には好みだった。
ところで「百日紅」が原作なら何故善次郎がお栄に粉をかけているのかと思ったが、パンレットの渓斎英泉の説明に「下あごを突き出したアクの強い美人画で個性を発揮」とあった。そういえばお栄もあごが出ていたか。必ずしもそこが結びついたとは限らないが、確かに二人の関係に少し想像が膨らんでしまう。
芸術家のカタログ
「おーい、応為」。言わずと知れた天才画家、葛飾北斎。その娘、葛飾応為。北斎が死を迎えるその日まで、様々なことでぶつかり合いながらも、生活を共にした。二人の日々を描いた映画。
この映画では、北斎と応為は対照的に描かれる。それは、人としても、画家としても。北斎は家にこもりきって、常に絵を描きつづける。対して応為は外に出て、気の向くままにふらふら歩き回り、ほとんど絵を描かない。二人を対象的に描くことで、そこに二つの芸術家像が現れる。実際、芸術家を二分しようとすると、この点で分けることが多い。映画の中には、ほかにも多くの画家たちが描かれる。売れっ子になる者や、道半ばで描くことをやめてしまう者、そして、描かれもしなかった、有象無象の画家たち。創作スタイルや生き方は画家の数だけある。これらを皮切りに、私はこの映画に、「芸術家の生態描写」を見出した。
それを最も強く感じたのは、応為が突如絵を描き始めるシーン。ではなく、その直前。それは祭りの夜、応為が気になっていた男性に、「妹のようだ」と、言われたシーンである。応為はその言葉を、「異性として、女として見ていない。」と、解釈したのだろう。そして、そのやりとりの直後、体感時間一分間以上の沈黙がつづく。それはもちろん、その情景描写や、心理描写のための間であることは間違いない。しかし、それだけではない。今思えば、「このシーンが、この映画の最も重要なシーンである。」と、製作陣が訴えかけてきているようにさえ感じた。そして応為は、翌日から人が変わったように、絵を描き始める。それは、フラれたことによるショックや、自暴自棄によるヤケクソの類ではない。
画家をはじめとする芸術家が、創作を行う際に必要なことは、大きく二つある。一つめは「孤独」である。これは常日頃から感じつづけている。そこに、二つめの「喪失」という名の起爆剤が重なると、大爆発を起こし、創作が動き出す。火とガソリンのようなものだろうか。これこそが、芸術家の重要な生態である。この映画は、この点を非常にわかりやすく描写している。
少し話が脱線するが、「芸術家は頭がおかしい」「気が狂っている」と、言われることがよくある。その原因のひとつは、前述した孤独と喪失。ある日、偶然この二つが重なったときに、「創作がうまくいく」と、気がつく。それに味をしめると、自ら孤独と喪失を求めるようになる。ついには、歯止めが効かなくなり、自ら追い詰められにいってしまう。その後は、容易に想像できるだろう。
話を映画に戻す。この映画は重要なシーンにおいて、必ず長い間をおく。それは昨今の映画とは、比べ物にならないほど長い。対して日々の生活のシーンはテンポがよい。それは引越しのシーンが多く、印象的に描かれいることに起因しているだろう。また、テンポの良さを感じる理由のひとつに、音楽がある。大友良英のキャッチーで、耳にのこる音楽。これを、それぞれのシーンと対応させることでパターン化され、映画全体が、音楽形式のように形作られている。繰り返しのシーンが多いこの映画では、実に効果的に使われている。場面の転換や、間と日々の生活の効果的な対比に、間違いなく音楽が一役買っている。しかし映画終盤、北斎の死が近づくにつれて、心理描写が増え、間が多く続く。中盤までテンポが良かっただけに、終盤は少しダレて、間延びしている感じは否めない。
最後に、私がこの映画で、最も評価しているのは、配役である。応為を演じた、長澤まさみ。北斎を演じた、永瀬正敏。この配役を決めた時点で、映画自体が失敗する可能性は、皆無に等しかっただろう。
才能と言う名の希望 ーあるいは災いー
応為(おうい)という画号を贈られていますが本名はお栄(おえい)さん
(ウキペディア調べ)
冒頭、お栄さんは嫁いだ先の絵師で夫の絵を「下手くそ!」と罵って大喧嘩!
そのまま家を飛び出してたどり着いた先は貧乏長屋の一室。
何がごみくずで何が必要な物か見分けがつかない様な所で
初老の男が一心不乱に絵を描いている。
男はお栄さんの実の父の天才絵師、葛飾北斎。
北斎はお栄さんに「お前のいる場所など無い」とつれない言葉。
そこには北斎の父としての娘を思う気持ちがこもっている事、
後半で良くわかるのですが、嫁ぎ先を飛び出して来た時には
聞きたくない言葉ですよね。
それでも行くあてのないお栄さんは北斎のそばで不貞寝を決め込む。
お栄さん、これからどうなるのかしら??
女っぽさ等ほとんど無く粗野なお栄さんだけど、
そこは演じる長澤まさみの実力と言うか滲み出るものと言うか、
決して下品ではなく、見ていたくなる微かな色気や恥じらい。
ぜひ映画館で見届けてくださいな。
で、
月に8回ほど映画館で映画を観る中途半端な映画好きとしては
比較的地味な映像が続く本作の中に
史実かどうかは知らないですが柴の子犬を取り入れたのは
時間経過を感じさせるのにとっても有効でした。
ちょっとしたユーモアシーンもあって
柴犬チーム、良い仕事してました(笑)
葛飾応為の作品を数年前の浮世絵展で観たことがあります。
光と闇のコントラストが見事な作品でした。
火事場で燃え上がる炎や蝋燭の灯に魅了されるお栄さんらしい。
映画の中では随所にその描写が織り込まれてましたね。
映画の中盤、寺島しのぶ演じる実の母から
「あんたは親父に似て絵も上手いが目も効くから」
それは、一種の才能であり、才能という名の災い〜
最初の夫の絵を下手くそ!とつい罵ってしまう。
男としては惹かれている大谷亮平演じる初五郎を
嫌いになりたくないから絵を観ないと頑なに拒む。
自分に言い寄ってくる高橋海人演じる善次郎のことも
その絵を多少なりと認めているから必要以上に
自分に入り込ませたくない。
目利きのお栄さんにとっては絵の良し悪しにどうしても引っ張られてしまう。
結局、お栄さんが心底、素晴らしいと思える絵を描けるのは
父である葛飾北斎以外にはいなかったのかもしれない。
そして、男尊女卑の時代にお栄さんの実力を真に認めてくれるのは
父である葛飾北斎以外におらず、北斎のそばにいる事でしか
お栄さんが絵を描き続け、認められる術が無かった〜〜。
悲しい〜〜とばかりも言い切れない。
娘への親心だけでは無く真の実力を認めて「絵師」として
お栄さんに「葛飾応為」と言う画号を与えた北斎。
東洋でも西洋でも名前すら残っていない素晴らしい芸術家は
おそらく山ほどいるのだろうから〜〜。
今年放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう」の蔦屋重三郎の全盛期と
お栄さんが実力を発揮し出した頃の年代差、多分10年とか20年程。
もうちょっと早くお栄さんと蔦重が出会えていたら〜
これは歴史好きの妄想ですね〜〜(苦笑)
動く浮世絵だなぁ
世界に名の知られる葛飾北斎とその娘、応為。
彼らがどのようにして名作を描きあげたか、その様子が垣間見られる映画。
生活に向き合うことなく、ただひたすらに描き続ける北斎(引っ越しばかりしていたエピソードも盛り込まれている)
江戸っ子らしい激しさと、描く対象を見つめる静かな眼差しを合わせ持つ応為。
その背景では急に降り出した雨の中大工たちが肩に道具箱をのせて走り出す。富士は朝日に照らされて赤く輝く。動く浮世絵だ。
絵を描き、絵の中に生きた親子。
全編を通してジャズのようなトランペットの音。江戸と西洋との出会い。日本の貴重な宝が海外に多く出ていってしまったことを心に浮かべながら音色に聞き入った。
静かに時は流れていく
「北斎のしわざ展」から北斎に興味を持ったところ。今やってるなら観ておこうと。
親子の時間が淡々と、大きな事があるわけでは無いが淡々と過ぎていく。じわっと沁みるような映画。最後、その後の応為がどうなったかわからない辺りが、彼女の生き方を表しているようで。
この親子に更に興味が湧いている。
芯のある女性
応為の日常を綴った映画ですが、応為は父である北斎を尊敬していたから、どんなに喧嘩してもなじられても出ていくことはなかったと思います。
ストーリーと関係ないですが、江戸時代に女性でも料理ほぼできなくて簡単な外食や持ち帰りで生活していたことに「ほぇ〜」となり、江戸時代は土葬だと思い込んでいたのでいたので火葬していたことにも驚きました!
髙橋海人さん演じる弟子の善次郎が二人の親子と終始違うテンションでいいアクセントで艶っぽくて眼福でした。
長澤まさみさんは所作が美しく、身体を先に向けて顔を少し遅れぎみに動かす仕草が(伝える力不足💦)美しかったです。
なんといっても北斎演じる永瀬さんが凄まじかった!年をとるごとに小さく見えて、晩年着物の襟元からあばら骨が見えて役作りに驚き惹き込まれました!
されどたくましい女性であった
天才女性画家。表にはあまり出てないが。。のフレーズで歴史映画を見に来てみたら。
エンタメだな、応為の視点でもなく、北斎の視点かと言われるとそんな風にもとれず。淡々と進む舞台のような作品にかんじた。
ただ、どうであれ、作品内にでてくる応為の
自分が選んだ、と言った言葉はそうなんだろうと現代の私に響くものがあった。
「自分の人生を生きるんだ」
応為というのは,大河ドラマ『べらぼう』で,くっきー!が演じている勝川春朗(葛飾北斎)の娘お栄のことです.葛飾北斎が出てくる映画はいくつかあり,先日観た『八犬伝』(2024年公開)にも,滝沢馬琴の友人として出てきてました.一方,応為をとりあげたドラマはありますが,映画は初めてかと思います.ちなみに,『八犬伝』で滝沢馬琴の妻役で出ていた寺島しのぶが,応為の母役で出ています.
とにかく,長澤まさみの魅力満載の映画でした。北斎役の永瀬正敏も素晴らしかったです.絵を描くことにしか興味のない、似たもの父娘の愛情物語というところでしょうか.
長澤まさみは,防虫剤のCMや『コンフィデンスマンJP』,『スオミの話をしよう』に見られるように,コメディエンヌとしてもっとも輝く持つ女優と思っていましたが,時代劇でも素晴らしいものがあります.
ときどき流れる,「哀愁漂うトランペットの響き」が効果的で心地よかったです.
ぼんやりと過ごすには良質な空間
特別、波乱万丈な展開や目を見張るシーンがあるようには思えなかったが、長澤まさみが和服姿でキセルをふかしているというのを観るだけでも、なにかしら浸れるものがある気がした。
セリフや展開に驚かされることはないものの、逆にいえば時代物で日常的な生活の時間が流れてゆくのを観れる機会は少ない。それを長澤まさみという画で観れるだけでも贅沢に思う。撮り方が綺麗で画面自体は見やすかった。
昔の時代だ、武士だちょんまげだ、と肩肘張らず、今も昔も人が暮らしているんだなぁと思える雰囲気。武士よりも絵師ならば現代にもある暮らしのため、身近な存在に思えた。異様な数の引越しなどの場面はちらほらとはあるものの、破天荒さが強調される作りではなかった。
葛飾北斎や描かれる絵のエピソード、というよりも長澤まさみによる応為の秀麗な映像の画が魅力的な作品だった。
余白を楽しむ映画
静かに淡々と葛飾応為と北斎親子の日常が描かれている映画。江戸の生活を覗いているようなタイムスリップしたような気分にもなる。
この親子に善次郎が加わることでクスッと笑えて淡々とした日常がパッと明るくなり犬のさくらも家族として大切な存在。引っ越しのシーンは何ともかわいく笑いを誘った。間を大事にしている会話や台詞がなく表情のみのシーンもある余白のある映画。登場人物の気持ちを考えながら、時には感情移入しながら見た。
応為と北斎を見ていると亡くなった父との2人暮らしを思い出す。後半、富士の麓の小屋で北斎が応為に好きなように生きろと話すシーンは応為の気持ちになり涙が止まらず。長澤さんの演技は圧巻。永瀬さんの表情に父を思い出した。
俳優陣の演技が素晴らしく淡々と描かれる江戸の生活と親子の日常に髙橋海人くんがフワッと現れ動きを出し篠井さんと寺島さんがさすがの演技力と存在感で江戸を感じさせてくれた。
長澤まさみさんの応為はかっこよく滲み出る色っぽさと美しさが素晴らしい。永瀬正敏さんの存在感と年を重ねていく演技は圧巻。髙橋海人くんが軽さの中に少しの影と色っぽさがあり自然な演技がとても良かった。
応為、北斎、善次郎が長屋でそばを食べながら話すシーンが印象に残り、見終わると無性にそばが食べたくなった。
当時の日常の飾らない美しさたっぷり、音楽もよし
めちゃくちゃ長く書いたレビューが消えてしまった
取り急ぎ、
長澤まさみは圧巻の美しさ、といっても派手なキラキラしたものではなく、着崩した暗めの着物や煙管を吸う姿、蕎麦をすするところなど日常の飾らなすぎる姿から見える美しさ。どこを切り取っても絵になる。人生に迷っているところから自分のやりたいことに気づいて突き進んでいくストーリーをその日常生活の中から感じ取る映画。
ジェットコースター的なストーリー性は皆無だがなるべく実際の応為や北斎から離れないで作り上げたと思われ、観る人一人一人が自分の人生と照らし合わせて考えることができる。周りから理解されるかどうかではなく自分の生き甲斐を突き進む人生を見せてもらえる。
北斎の永瀬正敏は決してかっこよく描かれていない北斎だが絵の道を突き進んだ職人感が滲み出ている。長澤まさみとダブル主演だと思う。圧巻。
善次郎の髙橋海人は色気がすごい。初めはかわいい舎弟でストーリーに笑いをもたらしてくれるが経験を積んだのか年数が経過したあとの善次郎は余裕と色気がたっぷり。応為がどうなるのか心配になるほど。彼のストーリーも見てみたい。この映画の大事なスパイス。
他の役者も味わい深くて、まぁそれは人選時点で分かるかな。さすが。
セットや小物、犬や市井の人々の動きなどの詳細も凝っていて、細かいところもじっくり見たくなる。
それから音楽が素晴らしい。
雰囲気のあるちょうどよく気の抜けた、しかし時代劇時代劇していない音楽がとても合っていて、起伏のあまりない映画の中で素晴らしいアクセントになっている。
総じて、人生に思いを馳せる見応えある良い日本映画。好きなことを見つけたら突き進むのもよい。犠牲になることも他人から理解されないこともあるかもしれないが突き進む道もあるよ。
葛飾北斎の事全然知らない
髙橋海人くん出てるから、観に行かなきゃなーって思ってて、シネリーブル池袋でやっていたから、株主優待券使って観てきた。
そんな程度の動機で観に行ったから、葛飾北斎に画家の娘がいたことも全然知らない状態で、どんな話しかもよくわからず観に行ったけど、良き作品。
喧嘩をしながらも、父の北斎を師匠として尊敬している娘が、父にずっと寄り添っていて、父も娘の才能を認めていて…ほっこり心地よかった。
葛飾北斎って、あんな昔であんな長寿だったんだ。しかも絵を描きながら死ぬって、全うしてるな。
好き嫌い分かれそう
ドラマチックではなく、芸術天才肌の不器用な親子愛のドキュメンタリー
全体的に淡々としている
あと、唐突に女性が上裸になるシーンがある
(そこに海人くんはいないのでご安心を)
かいつまんで言うと
かいつまんで言うと婚家で同じく画家の旦那の絵をボロクソけなして北斎の家に出戻ってから、北斎が亡くなるまで約30年寄り添った娘の日々を綴ったもの、出て来るエピソードは
ほぼ「百日紅」(エンディングにも参考文献として「百日紅」出ていたし)個人的に思ったのは長澤まさみの髪型、下ろした姿も含めて現在なら違和感ないが、江戸末期なら違和感ありありだなと。あと、近年の邦画としては珍しくオッパイが丸出しのシーンがあったのにビックリした。それだけ!!
全58件中、1~20件目を表示