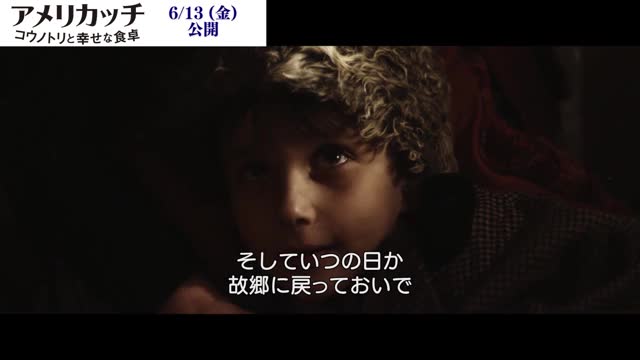「力なき者の処世術」アメリカッチ コウノトリと幸せな食卓 かばこさんの映画レビュー(感想・評価)
力なき者の処世術
子供がたったひとり、衣装箱に入れられ船積みされて、よくぞアメリカまで行きつけたものだ。その後どうやって生き延びたのか。チャーリーは運がいいのか悪いのか。
個人がどうあがこうとびくともしない大きな力に翻弄され続け、せっかく移住できたアメリカから希望を抱いて故郷のアルメニアに戻ってきたと思ったら、たった一度の「親切」がとんでもない不幸を招くおそろしく理不尽な目に遭わされるが、チャーリーはあまり抵抗しないし嘆いたりもせず、なすがままに流れに身を任せ周囲に逆らわず生きていく。抵抗も嘆きも無駄だと知っているからか。
逆らわずその場になじんで何かしら「楽しみ」を見つけて生きていく。
それが、チャーリーが身に着けた、力なき者の処世術なんだろう。
当初チャーリーに意地悪してサンドバックにして楽しんでいた職員たちもいつの間にか親しくなって、刑務所なのにその辺の職場のよう。
チャーリーが房の中でいろいろ仕掛けを施して住みやすく改善、向かいの夫婦観察を楽しむあれこれを整えているところはたくましくて笑ってしまった。
踏みつける人がいれば、助けてくれる人がいて、それが人生。
でも、助けてくれる人がいないかタイミングが悪いかで、終わってしまう人生もいくつもある。
覗かれていた側が、カギのありかを教えてくれたことに感謝するか、覗かれていたことに嫌悪感を持つかで、チャーリーの運命は変わったはず。
しょせん、人生は運なのだろうか
「運」のように見えるが、チャーリーの日ごろの行いが引き寄せた、めぐりあわせのように思える。
刑務所の所長ドミトリーは妻のソナに頭が上がらないが、彼女はどういう立場なんだろう。
いい人でよかった。
チャーリーは結局アメリカには戻らず、故郷アルメニアに留まり、家族、同胞に囲まれてにぎやかな食卓を囲むという、夢に見た幸せを手にしたようで、彼の幸せが心から嬉しかった。
アルメニアという国の複雑な事情とソ連によるでたらめな統治を描きつつ、コウノトリのように、自由に空を飛んで自身の居場所を決められたら、という願望と、高いところなら呆れるくらいどこにでも巣を作り居場所にしてしまうコウノトリのように、どこであろうと自分なりの居場所と楽しみを見つけてそこで生きていける人が幸せに近いという、シンプルかつ普遍的なことが描かれていた映画だったと思います。
コウノトリには、私が知らない宗教的な意味合いもあるのかも。当時のソ連では宗教は禁じられていたことでもあるし。
エンドタイトルで流れていた曲がとてもよかった。
インドの楽曲のようであり、バラライカのような楽器も聞こえる、独特で耳に残る曲調と、民族衣装に身を包んだ演奏者たちがとても良く、アルメニア音楽をもっと聴いてみたいと思いました。