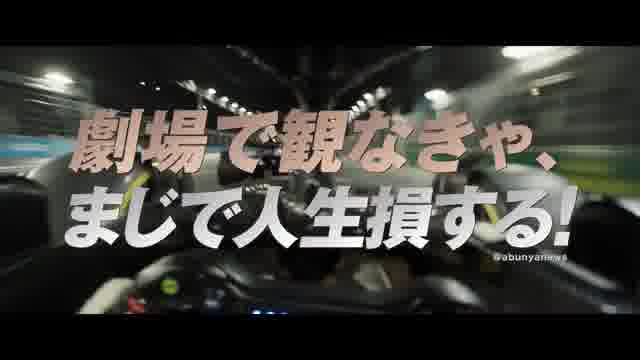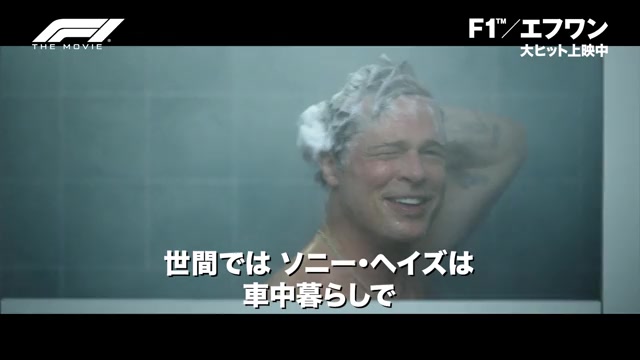「Appleの矜持とブラッド・ピットの歳の重ね方」映画「F1(R) エフワン」 こひくきさんの映画レビュー(感想・評価)
Appleの矜持とブラッド・ピットの歳の重ね方
観終えた瞬間、まず感じるのは「単なるレーシング映画ではない」という事実。ジョセフ・コシンスキー監督の手腕によって映像と音響は極限まで研ぎ澄まされ、観客はまるでサーキットのピットウォールに立っているかのような没入感を味わう。スクリーンに映し出されるレースシーンは、単なるスピードの誇示ではなく、機械と人間の緊張関係を映像の限界まで引き延ばした実験である。ここに「最高のレーシング映画をつくる」というAppleの強い意志と、映像産業における存在感を刻印したい矜持が透けて見える。
Appleはこの作品を、単なるIP消費型のエンタメ作品ではなく、自社ブランドの「体験価値の拡張」として提示している。実際、撮影技術やサウンド設計にはApple的な哲学が反映されており、ハンス・ジマーの音楽が物理的な音圧とデジタル的な緻密さを兼ね備え、観客に「劇場でしか成立しない体感」を強制する。Apple本社を舞台にしたプロモーション映像でティム・クックが登場し、Apple本社の屋根をテストコースにしてF1マシンで疾走することにGOサインを出す演出も含めて、この映画は「Appleが映画に本気で取り組む」宣言そのものだ。
もちろん物語自体は、過去の挫折からの復帰、若手との師弟関係、弱小チームの再建という、既視感のある枠組みに収まっている。だが、その「ありきたりさ」が逆に観客の理解を助け、複雑なF1の世界に慣れていない層にも容易に感情移入させる仕掛けとして機能している。専門的なレース戦略や技術描写を突き詰めれば突き詰めるほど門外漢を遠ざけるのがこの題材の難しさだが、そこをあえて“定型の物語”に託すことで、映像と演出の斬新さをストレートに響かせる。要するに「映画的リアル」と「スポーツ的リアル」の折り合いをつけた作品だ。
そして何より驚かされたのは、ブラッド・ピットの存在感である。トム・クルーズが『トップガン マーヴェリック』で若さを保ちつつ限界に挑戦する姿を体現したのに対し、ピットは年齢を隠さず、その重みを役に昇華させている。無理に若作りすることなく、皺や疲労を背負ったままステアリングを握る。その姿がむしろ“めちゃくちゃかっこいい”のだから驚嘆せざるを得ない。彼の演じるソニー・ヘイズは、過去の栄光に縋る亡霊ではなく、年齢を受け入れた上でなお速さを追い求める生身の人間であり、その在り方こそが観客の心を打つ。クルーズが「永遠の若きヒーロー」を演じ続けるのに対し、ピットは「歳を重ねたからこそ輝くヒーロー」を体現した。これはキャリアの差異ではなく、ハリウッドにおける二つの“歳の取り方の美学”を示している。
総じて『F1(R) エフワン』は、物語の新奇性よりも体験そのものを価値に変換した作品だ。映像と音響の革新性、Appleの戦略的意志、そしてブラッド・ピットの成熟した存在感が三位一体となって、「レーシング映画の新しい基準」を打ち立てている。ストーリーの平凡さを補って余りある迫力と説得力がある以上、この作品は今後長らく「スポーツ映画の到達点」として語られることになるだろう。
かくかくしかじかレビューへの共感&コメントありがとうございます。
私のレビューを高評価して頂きありがとうございます。
かくかくしかじかのレビューが見つかりませんでしたので、
こちらに返信コメントします。
何と言っても『描け、描け』というセリフが印象的でしたね。
学生時代に担任の先生によく、お前らは考えて行動している。失敗を恐れるな。行動しろ。考えるのはそのあとにしろ』とよく言われていたんでその時が蘇ってきました。永野芽郁が大変だった時期だったので、彼女へのエールだとも感じました。大泉洋ってなんでも熟す役者ですが、
本作の先生役も適役でした。
では、また共感作で