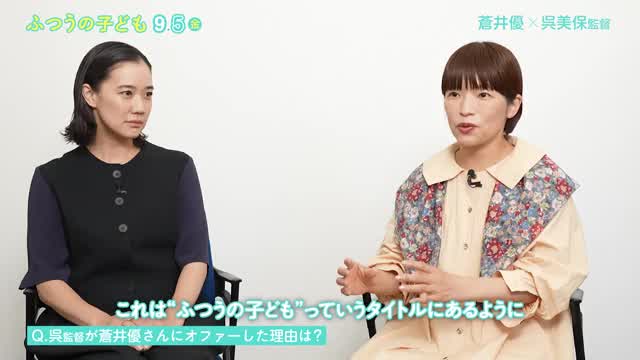ふつうの子どものレビュー・感想・評価
全141件中、81~100件目を表示
主人公の子のトボけた感じが良かったですね(^-^)
呉美保監督作品。
昨年見た『ぼくが生きてる、ふたつの世界』は私の中では映画館で見たベスト1でした。
この映画は、映画館で予告を見ていてみたいと思っていた。
ほとんどのシーンが子役が出てくるシーン。
主人公の子のトボけた感じが良い。
予告を見て、コメディチックで子供の淡い恋心を描いた映画なんだろうと思っていたら違っていた。
環境問題に興味を持つ女の子に恋心を抱くというところまでは想定通りだったけど、それから大胆な行動に移って行く。
えっ、小学生がココまでって感じがしながら見ていた。
純粋に環境問題意識からの行動じゃなく、三者三様の理由があっての行動。
それには親の存在なかも絡んでの展開。
心温まる映画というより、今の社会風刺的な映画であったように思う。
お母さん役の蒼井優、瀧内公美、良かったです。
蒼井優は久しぶりに見て気がした。
私的にはもっと子供目線で純粋な世界を描いて欲しかったかな。
あの主人公の子役のトボけた感じを活かす展開がもっとあったように思った。
親と子供の関係は千差万別。
いろんな親がいる中で、いろんな子供が育っていくというのが分かる映画でした。
瀧内公美が捲ってきた
ずっと観てる間、もう一息マジックというかスパイスが欲しいと思ってたところに瀧内公美が捲ってきた。どういう親なんだろう。バリキャリ路線ではあるが、男の子ってそうだもんねなどのちょっとオバサン掛かったニュアンスも堪らない。前日知らないおばさんに飲み屋で子供を育てるのがいかに大変かを聞かされたのでなおさら染みる。自分が学校に呼び出されるなんてシチュエーションになったらテンション上がりすぎて楽しくなっちゃうな。キタキターって。不思議なトーンのクラスメートが気になっていたが長峰というらしい。意図的に何を言ってるか分かりづらいハイテンションなキャラクターなのだが、この子が特に今後が楽しみ。とにかく不思議な雰囲気だ。私の従姉妹がルック含めて小さい頃こんな雰囲気だった気もするのでどこか懐かしい気持ちにもなる。子供の演技の面白さがほかの作品と比較してやっぱり素晴らしい。
小学生あるある。
唯士くんの淡い切ない気持ち!
お父さんの不在
とまでは言えないとしてもその存在感の薄さ、軽さということが印象に残りました。唯士のお父さんはママに比べたら0.75くらい、陽斗のお父さんはママに比べたら0.5かそれ以下。心愛のお父さんはゼロ。離婚しているのかもしれません。お父さんたちはどうしちゃったんだろうと思うけど、これが現在のリアルな姿、でしょうか。
最後の会議室のシーン、ふだん教室ではいばってる陽斗は泣いてばかり。唯士も頼りない。でも、追い詰められて途中、意を決する姿は凛々しい。心愛は一人、逃げない、投げ出さない、ひとのせいにしない、言い訳もしない。映画をこの上なく心地よいものしているのは、監督の信頼と希望を示すこのシーンのおかげかと思います。
How dare you!
子どもたちの人間関係と日常をメインに、ありそうな問題をいくつも、フラットな視点でうまく詰め込んである構成が素晴らしい。
地球温暖化は待ったなしの喫緊の問題で、無関心な方がどうかしているんだが、日本人はほんとに危機意識が薄い。それどころか危機感を募らせる人たちを奇異の目で見たりする。
小学4年生の女の子・心愛は、それを真剣に考え、周囲の啓発を試みる。
クラスメイトはそんな彼女に引いて遠巻きにするが、彼女にハートを射抜かれた普通の男の子唯士は、彼女に好かれたい一心で温暖化について学び始める。子供らしく杜撰であからさまな作戦に笑ってしまうが、そこにクラスの問題児の陽人も加わり、3人だけの秘密結社ができる。心愛が陽人に魅かれているようで唯士は気が気ではない。
最初のうちは3人の子供らしい行動力を微笑ましく見ていたが、だんだん笑えなくなってくる。人様の家に勝手に入り込んで好き勝手し放題、ライバルの出現に対抗意識を燃やして行動がエスカレートする。ライバルとの競争とか自己顕示欲のほうに目的がずれていき、環境問題よりそっちが重要になって、テロリストもどきの行動に走る。その昔の過激派組織の成長過程のよう。
また、「牛肉を食べない」など、ひとつの象徴的な事柄をかたくなな教義にしてしまうところは、宗教のようでもある。
視野の狭い未熟な人たちの集団が陥りがちな、極端に走る傾向が描かれており、これを見せるところがすごい。
そして、How dare you! と、大人が子供から糾弾されているようだとも思いました。
心愛は、一番身近な大人である自分の母親のありさまから「大人全般」はこんなものだと思い込み、大人全般に絶望し怒りを抱えて、テレビで見た環境活動家の少女の言葉に同化するくらいの共感を覚えたんだろうとは思う。
でも、我々大人は無意識に、良くないなと分かっていることでも、あきらめつつ結果的に容認しているようなところがある。また、極力責任は人任せにしたい。
担任教師は、責任回避ファースト。子供に寄り添ったり深入りすることを放棄しているよう。なので無神経な発言も目立つ。「誰が最初に言い出したのか」は、関係者全員いるところで聞いたらダメなのでは。
とはいえ、そもそも、子どもたちの不始末に、何で教師が責任を問われるのか、子育ては家庭の責任ではないのか。先生が、持つべきでない責任を回避するのは当然だという気もする。そうでなくては自分自身を守れない。
3人の「犯行」がバレて学校に親が呼び出されるが集まるのは母親だけ。
陽人のところは父も来たが、完全部外者の体で下の子供の世話要員に徹している。
3家庭とも子育ての責任を母親のみに負わせて父親は不在か他人事のようにしか子育てに関わらない。
母親たちにはそれぞれ問題があるように見えるが、一緒くたではない。
唯士の母は頭でっかちかもしれないが、少なくとも将来を見据えて子供の幸せを願って試行錯誤している。他の二人の母は、自分に都合の良い子供像に沿ったありよう以外は認めない。大事なのは自分で、子供自身に良いようにとはまるで考えていない。それぞれの子供の態度に、それぞれの親の子育てが如実に表れていた。
牧場に謝りに行く途中で陽人が度々泣き崩れてしゃがみ込むのは、卑怯者な自分にやりきれなさが募ったからだろう。子供社会では「卑怯者」は何より嫌われる。アウトロー的でちょっとカッコいい雰囲気の「問題児」が「卑怯者」に大幅格下げで、今後の学校における自分の居心地を考えて絶望したかも。こういう子供にしたのは親であることは一目瞭然だ。
そして、心愛がかわいそうで胸が痛くなる。くやしさに涙をこぼす姿に、私も悔しさでいっぱいになった。生まれて10年も経っていない子供であるがゆえに視野が狭く考えは極端になりがちだが、オトナ相手に堂々と、ひるむことなく、理路整然と自分の主張を言えるのは大したものだ。「出る杭は打たれる」が激しい日本の社会、この子がつぶされることなく成長できるような世の中にするのも大人の役目じゃないだろうか。
大人たちが自分の責任を真面目に考えて、世の中が良くなるよう実行に移すことは、大人たちにとってもいいことなのだ。
唯士には、自己肯定感がすくすく育っているよう。親の愛情を疑わず安心して子供でいられる幸せな子供に見える。見かけはイケてないが、心愛とちゃんと言葉を交わして自然に人間関係を築ける力が備わっているよう。
親は、子供の人間形成に決定的に影響するのだとつくづく感じる。親ガチャは確かにあるのだ。
こんど本を貸してあげるね、とにっこり笑いあう心愛と唯士に、本来の子供らしさを見て微笑ましかったです。心愛は、あの修羅場でちゃんと言うべきことを言い、自分を好きだと言った唯士の気持ちがうれしかったと思う。
「大事件」を経験して、3人は、それぞれ葛藤し、成長の足掛かりにできたらいいなと思いました。
子役たちの演技が驚異的。自然でまるで演技なんかしていないよう。特になんかとぼけた普通の子どもの嶋田鉄太くんが素晴らしい。全員が天才なんじゃない!?
ムカつく大人たちを演じた俳優さんたちも好演。
特に担任ののらりくらりの風間俊介と、不快感ともにMAXな陽人の母(名前が分かりません)と心愛の母瀧内久美の、思わず「黙れ」と言いたくなるような嫌な奴演技が大変堂に入ってました。
そして、監督・呉美保、脚本・高田亮、恐るべし!
自身の子供の頃もそうだったけど、子供って本当に『浅はか』だよなぁ ...
子どもは面白くて深い
子どもの主観にかなり立脚していて、自然と子どもの頃の気分になって見入った。子どもは新鮮で振り回されるけど将来の希望だなと思った。子役は勿論、蒼井優、風間俊介、瀧内公美が各々微妙な役回りを流石の演技。特に瀧内さんの役どころはスカッとした。日経夕刊のシネマ万華鏡の紹介(これを読んで観に行くことにした)や、パンフレットの川内三郎氏の解説などとても参考になった(クラスメート皆さんの自己紹介とかも良い)。
無邪気なエコテロリスト
普通は難しい
答えは無限な第二次自己中心的行動期
突貫小僧を思い出しました‼️
純粋でまっすぐな子供たちによる、矛盾だらけの大人社会への挑戦‼️二酸化炭素の排出による地球温暖化を危惧する小学生の女の子、彼女に好意を抱き、気に入られたいために同じく地球温暖化に興味を抱く男の子、そしてお調子者のガキ大将・・・‼️とにかく子役たちの演技、表情が素晴らしい‼️主役の三人はもちろんなんですが、主人公の男の子に好意を寄せ、一緒に駄菓子屋で買い物をする女の子が特に可愛いですね‼️すぐ大人になっちゃうんだろうな・・・‼️そんな三人の子供たちによる子供なりの抵抗‼️手作りの「車に乗るな」チラシを駐車場の車に片っ端から貼り付けていったり、お肉屋さんへのロケット花火攻撃、そして牧場の牛を逃がしてあげたり・・・‼️そんな子供たちの姿を躍動感たっぷりに、テンポ良く描いた微笑ましい秀作ですね‼️さりげなく社会問題も盛り込み、ラスト、犯人(?)である三人が親と共に集められた席上での女の子の外国語での涙の訴えまで、私は小津安二郎監督も「生まれてみたけれど」を思い出しました‼️いつの世も子供たちの純粋な瞳と好奇心、探求力は物事の本質を鋭く突き刺しますね‼️
期待を裏切らない瀧内さん
ごくごくふつうの男の子が、好きな女の子と仲良くなりたい一心で、特に興味もない環境問題に取り組むお話。
主演の男の子は『LOVE LIFE』で亡くなった息子役の子だったのね。ドキュメンタリーでも観ているかのような自然な演技。
環境に関する啓蒙的な映画だったのかとザワザワしたけれど、3人のやってることが、SNSとかでよく見かける環境活動家のそれと同じようなことだったり、How dare youを多用するあたり、ちょっと活動家をいじってるな。
でもさすがに肉屋と牛はやり過ぎ。大人なら逮捕されてる。
案の定、やり過ぎて大問題になってしまうわけだけど、はるとは自分でけしかけといて卑怯だし、その母親は若干モンペ気味。三宅さんは全く悪いと感じてない地獄のような会議室の中、満を持して登場の瀧内さんが、もはや誰の味方してるのか分からない暴れっぷりで、ごっそり掻っ攫っていきました。
それに対するふつうのお母さん、蒼井さんの小声の「もう黙って」も良かった。
その後がどうなるか気になる終わり方も好き。
現代版禁じられた遊び
ってか。ウシの出没地点とか三者三様のお母さんとか、グレタトゥーンベリにちょっとイラッとする気持ちとか、面白い作品にしようという努力は大いに感じられた。
反面、焦点は絞り切れずに終わった感。いきなりモテ期到来してもね・・最近の子どもは基本的に弁が立つねェ。
子役たちの演技力に脱帽
以前より映画館でこの映画の予告を観て「面白そうだなぁ」と思い、公開2日目に監督の舞台挨拶含めて鑑賞しました。
まず子役達の演技が素晴らしいです。
監督も仰ってましたが、「ふつうの子ども」と言うタイトルだけあって、変に演技慣れしていない本当に普通の学校にいそうな子達をオーディションで選んだとの事で、それが見事に子ども社会のリアルさを表現出来ていてとても良かったです。特に主演の唯士君は表情だけで感情を上手く魅せていて、つい唯士君の言動に見入ってしまいました。あと個人的には唯士君と仲の良いメイちゃんもとても好きなキャラでした♪
テーマは「社会的問題」と「子供社会」の2つあり、一見相反しそうな両テーマですが上手くストーリーで結び合って最後まで目が離せない作品でした。予告を観て気になった方は是非観てください。オススメです♪
なかなか持っていかれる
全141件中、81~100件目を表示