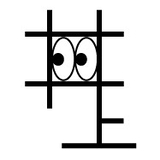ルノワールのレビュー・感想・評価
全209件中、121~140件目を表示
中途半端
期待し過ぎたわけではない。カンヌ出品だけど賞を取ってはいない時点で、「まあ、だいたいこんな映画やろな」と、ある程度出来の良し悪しは想像していた。何より、今誰より注目している河合優実が出演して、リリーさんも出ているということで、めちゃ良いということはなくても料金の価値はあるやろうと判断して鑑賞。
観た感想はまさにその通りという感じ。他の方も投稿しているように、何が描きたいのかイマイチ焦点が絞れておらず、いろんなエピソードを次から次から流して、数うちゃ当たる的なショートフィルムの連打みたい。1本の映画としてはなんとも中途半端。主役の女の子の演技は悪くないが、いかんせん脚本が弱く、観ている方が感情移入できるだけの魅力に欠ける。明確な個性がなく、メインテーマ(?)である(と思ってた)「父親が亡くなることを経験して大人へ成長すること」もあまり描かれていない印象で、80年代にこだわる理由も不明。結局すべて雰囲気だけ、そこそこきれいな映像だけで乗り切っただけみたいな。いかにもカンヌでは好まれそうな題材とは思うが、やはりそれだけで賞を取れるほど甘くない。
ただ、ショートフィルム連打の中で白眉だったのは河合優実演じる未亡人のエピソード。ほぼひとり語りしているだけなのに映像が浮かんで、ここだけ別の作品みたいな感じで強烈に印象に残り、演者の格の違いを感じた。そもそもこのエピソードは丸ごとカットしてもストーリーに影響ないのだが、これがなかったら星ひとつ減ってると思う。
深堀りや考察好きの映画ファンなら好意的に、「あのシーンにはこういう意味がある」とか「このシーンが良かった」といろんな感想を出すと思うし、それは映画の楽しみ方のひとつですが、まずその前に「ああ、いい映画だった。見ごたえがあった」と思えることが第一かなと。
大人の境目ってどこなんでしょうね。
そこはかとなく欧州風
あまり事前知識が無い状態で鑑賞。いきなり主人公がアレだったのでまさかと思いつつ、しばらくどっちどっち?と疑うワタシ。その後もあくまでおっさんがついて行けるレベルの(ここ大事)混濁を散りばめてそこはかとなく欧州風。クレジットで判明、フランス資本も入った合作で編集や音楽など多くのメインスタッフが非日本人でポストプロダクションも多国籍。どこまでが早川監督の味なのかもはや分かりません。しかし全体に心地よいすっ飛ばし方でしたー。パンフ買ってしまったけど未読、何か新しい情報がわかると良いのだが。
鈴木唯ちゃん、ちょっとインティマ心配。事務所は河合優実坂東龍太同様、本作の製作にも名を連ねる鈍牛倶楽部の様です。
主人公11歳女子の目線で見えた, 周囲の人々 とくに大人たちの物事...
主人公11歳女子の目線で見えた, 周囲の人々 とくに大人たちの物事.
父は癌の末期, 母は多忙で苛々が募り.
両親や, 学校など友人らのまわりで日々が過ぎ.
この女子, 飄々としたような, 繊細なような, 掴みづらく. 両側面ともあるんでしょう.
時代はどうも80年代のよう
超常現象ブーム, ウォークマン, 子供による親殺し事件,
学級のマスゲームで YMO "Rydeen" が使われたような当時.
主人公目線で諸々が描かれ,
結論や見え方が画一的にならず, 言語化もされず.
そういう見え方, 心当たりは多々あります.
私的にも, かつて見た諸々の出来事に, いちいち理由や結果を追求してはいないですし.
途中で聞こえたオペラ的な歌 Klaus Nomi "Cold Song"
とてつもなく冷たく感じました. 凍り付いて死ぬような歌詞をもつ歌ですしね.
生死観 - この女子, 学校の作文で "寝ている間に何者かに絞殺" や "孤児になりたい" と書いたり, 物語上の父が実際に余命わずかであることと, 辻褄が合うような.
そういう意図かはわかりませんが.
題目の画家ルノワールさんは, 劇中で話題には挙がりますが, 意味を深く持つものではない様子.
絵画のレプリカ販売が盛んだった, 当時はそういうこともありましたしね.
当時, 絵画の展示を見学に出掛けたら, 終盤で販売員さんらに囲まれて逃げづらくなった... なんて販売手口もありましたね. ルノワール, ラッセン, エバハートとか.
童心を思い出すような, 澄んだ心を持っていた頃もあったねえと感じるような.
そのままで美化も劣化もされてない,この年代,この世代のリアル.
切なくて温かくて, 耳と胸が少し痛くなる, 鑑賞体験でした.
大人でも子どもでもない大切な時間。
少女を中心に見える世界と”死“を考える大人たち。
揺れ動く心と当時の世間の空気感がとてもよく描かれています。
残酷な一面を持つ子どもと傷つく父を優しくかばう大人が同居しているのが面白い。
”死“を迎え自身に湧き上がる感情や故人への想いが彼女の成長を垣間見えるのが良かったです。
普通の人間にはわからんわ!
まずタイトルの「ルノワール」
フランスの印象派の画家。分からなかった。この映画が印象派?ルノワールっぽい作品?普通の人間には分かりません。
何を言いたい、何を見せたいとずっと観ていて考えても分からなかった。
父親がガンで死ぬまでの話。事件は起きるが、だから何だと感じる。「PLAN75」は増える老人の問題への警鐘を鳴らして、皆に考えてもらいたいみたいな芯があっての観て良かったと感じたけど、これは何したいのか普通の人間には全く不明でした。
こういう作品がカンヌ対策を施したものなら、カンヌ映画祭に出す作品は観てもしゃあないと思うしかないと感じました。
人が死ぬと泣く
「こちらあみ子」を思い出しながら観ていた。あちらのあみ子も、この映画のフキのように周囲と溶け込めていなかったが、関わり合っていた。こちらのフキは、家族とも学校でもどこか世間と隔たりがある。だけど、それを苦にはしていないようだ。というか、そういう感情を持っていないのか?そんな、無感情というか、冷めているというか、愛想なしというか。無垢であり、残酷であり、無遠慮であった。だけどむしろ、だからこそ観察者としての視点で世間と距離を取っているようにも思えた。感情がないと言っておきながら、半面、瑞々しいほどの感性を内包してるようにも見えた。
そして周りの大人たちが、はた目にはどこにでも居そうでいながら、ひと癖もふた癖もある。言い換えればちょっと嫌なところや弱いところを皆抱えている。だけど、そんな大人の集合体こそが、リアルな世間なのだろう。
おそらく、友人宅の引っ越しとか、母親の秘めたる内面とか、描かずとも察することで味わえる、じんわりと面白味を感じる深みのある作品であることは間違いないが、そこを不満と思う人もいるだろう。だけど自分としては嫌いではない。ただ、配役として先生役はどうなのか。どうみても定年過ぎにしか見えない。父親役のリリーフランキーもどうなのか。あの風貌で小学5年生の父親って無理がないか。いや待てよ、もしかしたら結婚が遅く50歳を過ぎてからできた子宝だと想定したら、なるほどこの映画の空気もさらに楽しめるかも知れないな。そして、「人生って素晴らしくて素晴らしくて素晴らしくて、いつか終わるもの」この言葉が妙に引っかかって、離れない。たぶん僕は、フキが夢の中で踊っていたような快楽と厭世観のごちゃ混ぜになった気分で、この映画の世界にふわふわっと翻弄されているのだろう。
フキは「イリーヌ」のような人生を歩むのか?
カンヌ映画祭の「ある視点」部門でカメラドール(新人監督賞)の次点に選考された、『PLAN 75』の早川千絵監督作品ということで、『メガロポリス』を差し置いて観に行きました。
リリー・フランキー、石田ひかり、河合優実、中島歩、そして、フキ役の鈴木唯といずれも確実な演技をしています。特に、鈴木唯はあと10年もすると、キミスイで鮮烈な印象を残した浜辺美波のように、朝ドラの主役になるんだろうな、と思いました。
初っ端から画面の陰影が強烈な印象を残すのですが、谷崎の『陰翳礼賛』にあるような日本的な美学を表現していて、それがカンヌ映画祭で評価された理由のような気がしました。
ストーリーとしては、起伏が激しかったり、大どんでん返しがあるというものではなく、思春期の少女らしい、何にでも興味を持つけど飽きっぽいところや、神秘的なものや死に関心をもって、ときとして思いついたことを行動に移してしまう、危うげな少女の日常を描いたものです。
細部にわたって緻密に計算されて作られた作品であると感心しましたが、一度観ただけではわからなかったところがいろいろあり、極めて難解な映画であると思いました。
「お引越し」???
少女が見つめていたもの
小学5年生の眼から観た大人と呼ばれる人間たちの行動はときに滑稽です。
不思議な事象を超能力と面白がったり、
小学生の書く作文に過剰に反応してみたり、
子どもの泣き顔を集めた動画を観賞してみたり、そんな夫との死別を淡々と受け止めてみたり、
素敵な家族として体裁を整えてみたり、
見えない何かを信仰してみたり、
電話で気の合う人を探してみたり、
懲りずに誰かを好きになってみたり。
たとえ、自分の親であっても理解に苦しむことがあります。
死を覚悟したような佇まいながら、仕事のことを考えながら病床を過ごしたり、何かにすがるように足掻く様子を見せたり。
そんな夫よりも仕事や段取りを優先させてみたり、その職場では言動を問題視されてみたり。
それでいて父母ともに、どこか奥深い場所で家族のことを考えていたり。
そんな大人たちが紡ぐ「社会」と呼ばれる環境を、少女はまっすぐに冷静に見つめながら上手に泳いでいきます。それは楽しんでいるようにも見えましたし、その眼はトランプの模様と数字を見透かすような眼差しでした。そして、どちらが大人なのか?と思えるような姿勢でした。
いろんな人間に出会い、多様な経験を積むことでたくましい大人になっていく未来が予想されるような締めくくりでした。
いつの時代の設定かとか気にならない空気感でしたが、途中YMOの「ライディーン」が流れた瞬間、小学校でこの曲をバックに行われた縄跳び大会が思い出されて一気に昭和に引き戻されました。
純粋、爽やか、冷徹に大人の価値観、固定観念を揺さぶる
タイトルの意図は不明だが、
映像が、光と影のコントラスト強く、やや粗めの質感も手伝って、
絵画的な見方、鑑賞の仕方を求められているようで面白い。
それは、全編にわたって一応の話の流れはあるけれど、セリフの無いシーンが多く、
観る人それぞれで心情を想像してくださいというようなスタンスからも感じた。
内容については、
子供の純粋な心、強い眼差しが、大人の矛盾や勝手な都合を冷徹に炙り出し、
生死も含めた固定観念や価値観に揺さぶりをかけてくるのが面白い。
物語の時代を数十年前に設定しているのは、
胡散臭い迷信や他人に依存してしまうそんな大人の弱さ、情けなさを強調する
キーアイテムが豊富なのが理由だろうか。
ラスト近くに女の子が手を振るシーンは、
まさしく相米監督の”お引越し”のオマージュのようで
少女の成長の暗示に対して、思わず”おめでとう”と言いたくなりました。
とてつもなく味わい深い作品
早川千絵監督による映画『ルノワール』は、1980年代の日本を舞台に、11歳の少女・フキのひと夏の体験を、繊細かつ静謐なタッチで描き出した傑作である。
とはいえ、この作品は単なる少女の成長譚ではない。物語は直線的な時系列で語られるのではなく、相米慎二監督の映画「お引越し」をはじめ様々な作品からの引用、断片的で印象的なカットの連なりによって進行する。そこに見られるのは、日本の80年代にさまざまな表現領域で取り入れられたポストモダン的アプローチ、すなわち脱構築的なサンプリング、カット&リミックスの手法だ。
ビデオテープ、ロリコン文化、超能力、狼男、怪しげな民間療法……。こうした時代の記号の羅列が濃密に織り込まれ、80年代という時代の空気が再現される。そしてその中に、言葉では語りえない感情や傷が、ひっそりと浮かび上がってくる。この手法は、ジャン=リュック・ゴダールが80年代に行った映画言語の解体と再構築にも呼応しているようにも思える。
なかでも特筆すべきは、フキの「抑圧された哀しみ」が、劇中で直接語られることがないという点だ。フキは語らない。だがその沈黙の豊かさを、早川監督は映像と音の配置によって丁寧に、精緻に語っていく。それは「物語」ではなく、「構造そのものが語ってしまう」という、極めて現代的で冷徹な視点がある。
それはまさに早川千絵という作家の映像表現の真骨頂である。
——と、ここまでやや理屈めいたことを書いてきたが、後半、あの雨のシーン以降、フキの喪失と愛と哀しみが、ぐっと押し寄せてきて、涙が止まらなくなった。
名場面が幾重にも折り重なる、宝石箱のような映像体験。ぜひ劇場で、味わってほしい。
タイトル回収って言葉知ってる?
少女の視点で日常の風景を描く
カンヌのときに話題になっていたので、「どんな作品?」と興味が湧いた。
200館弱の上映で、思ったほどの公開規模ではなかったので、「どこでもいつでも見れる」わけでは無かったが、観賞スケジュール調整最優先作品として観てみた。
【物語】
舞台は1980年代後半、ある夏の郊外の街。多感で想像力豊かな11歳の沖田フキ(鈴木唯)の日常が描かれる。
会社員の父親沖田圭司(リリー・フランキー)は会社でそこそこの地位まで来ていたが、現在はがんに侵され、入退院を繰り返し、本人、家族とも快方の希望を持てない状況で日々過ごしている。家計を支える母親詩子(石田ひかり)は、会社では部下の指導をパワハラ扱いされ、家庭でも仕事でもストレスを抱えていた。
ふきはそんな大人達に囲まれながらも、周囲に押し潰されることもなく、自分の世界を生きていた。
【感想】
思ってたのとはちょっと違った。
メリハリの利いた感動ストーリーを好む人は肩透かしかも知れない。俺も観る前はもう少し物語らしい物語がある作品かと思っていたのだが、日常描写系の作品だった。少女の身の回りで起きる様々なことは、直面する少女にとっては大事件も含まれるが、他人事として大人が見れば「良くある話」ばかりだ。
それらの出来事が少女の目にどう映り、少女がどう受け止めていくかを描いた作品と言っていい。 そういう意味で、フキの言動のリアリティーがポイントになって来るが、鈴木唯は子供が持つ、可愛らしさ、純粋さ、多感さ、小憎たらしさ、危なっかしさを好演している。 つまり、特別な少女ではなくて、どこにでもいる11歳の等身大の少女がそこにいた。
確かに話題になった鈴木唯の好演は認めることができ、出来の悪い作品とは思わないのだが、俺的には心動かされる作品ではなかったかな。
ちなみに題名のルノワールだが、ルノワール画の特徴をググってみたら、「鮮やかな色彩と軽やかな筆致で、人物や日常の風景を生き生きと描いた」と出て来た。なるほど、そういうところを目指したのかと、納得。
「ナミビアの砂漠」と「かぞかぞ」を足して水で割ったような
冒頭にゴミに出す為に紐で梱包された「FOCUS」と「FRIDAY」が登場して終わりの方で鵜飼いを映したシーンがあるので「FRIDAY」で刊行された昭和59年以降の岐阜が舞台なのは分かる。当時の小道具を集めるのは大変だったろうな、とは思った。登場したビデオがVHSだったので「ふてほど」で昭和61年の小川家にあるデッキみたい。ベータを使うのはSONYがスポンサーでないとダメなのだろうか?「カムカム」のように「ノストラダムスの大予言」を登場しなかったが主人公はオカルト番組のファンなのが当時らしい。それと郵便受けに入った伝言ダイアルのチラシを使うシーン。いいと思ったところはここだけ。
しかし内容は主人公の小5の女の子と両親(主に母親役の石田ひかり)との間で作品内の視点が何回も変わる上に抽象的で分かりにくいシーンが多過ぎる。これで河合優実との共演が8回目という中島歩の役どころが「ナミビアの砂漠」と同じ精神科のカウンセラーだ。石田ひかりの夫の訓覇圭プロデューサーが制作統括の1人だった「かぞかぞ」ではマルチの福地桃子と七実の亡父役の錦戸亮が登場するシーンも見ていて楽しいのに「かぞかぞ」くさいシーンが非常に陰気臭い。事務所が売り出したい女の子を「RoOT」の2人に加えて河合優実が出演した「17才の帝国」と「かぞかぞ」のプロデューサーの奥さんを組ませた映画に見える。
鈍牛倶楽部が制作に関わった映画でも河合優実が主演の「ナミビアの砂漠」は分かりにくいが許容範囲に入っても金子大地が所属するアミューズが制作して堀田真由が主人公の「バカ塗りの娘」のような鑑賞出来る映画を制作してほしい。
内容を知らずに見ると寝る羽目になります
”PLAN 75”の監督だから、なにか問題提起した作品だろうくらいの予備知識で観たら・・・あれれ
小六の女の子の日常と家庭の話がずーっと続いて終わった
ただの、思春期前の女の子が少しだけ成長しただけの作品でした
観客席からは、かなりの寝息が聞こえる
多分、同じように内容を知らずに来た人が多数だったんでしょう
日曜日の昼下がりの映画館、かなり人が入ってたんですがね
はい、知らずに入った自分も悪い
でも、この手の映画は数あれど、こんなにつまらないのは珍しい
理由を考えてみました
①女の子が子供すぎる
もう少し大人になりかけの色気がないと、思春期へのムンムンとしたオーラが出ない
足が長くて、これから肉が付いて女性になっていくんだろうけれど、この子はまだ子供
顔にも色気がない
カッパみたい
この体型なら、同じ子役出身の夏帆が子供だったらなあなんて、思いました
②子供が意外に残酷で合理的なのは、人生経験の無さから来るイメージの欠如です
実際、娘に聞いたら、お父さんより飼い猫が死ぬ方が悲しいんだと(笑)
今回は父親の死をきっかけに、布団の中で少し涙が出た
普段からいるはずの人が居なくなった寂しさくらい
つまり、ものすごく初歩的な感情の動き
とても、映画で語るような話しではありません
演技も下手なら、テーマもつまらなすぎる
演出も感動とは程遠い
だから、とーてもつまらない
③ご都合主義
監督が女性だから、残酷な結果を避けたんだろうけどね
都合よく危険をすり抜けて、めでたしめでたしでは、文科省の教育ドラマかっつーの
もっと傷付いてこその映画です
やってはいけない事をすれば、それなりの危険が伴い、フィクションだからこそ、その残酷さを見せる事ができるんです
それに、変態ロリコン男が坂東龍太って
ファンが怒りますよ
ついでにいうと、朝の連ドラで好感度を上げた中島歩が女癖の悪い男役ででてます
それに、なんなん?
何かと言うと不倫不倫
不倫出しときゃ、問題提起してるとおもってるのかな
同じパターン、2回出してるしね
監督の頭の中が単純すぎる
④今の日本状況を知らなさすぎる
日本は安全で、ほとんどの人がいい人だと思ってるんかな
甘々な人だ
問題提起するなら、そこなんだよ
外国人を悪くいうつもりは無いけど、今の日本は古き良き日本では無い
外国と思った方がいい
お父さんは女子トイレに入れないから、女の子をトイレにひとりで行かせれば、待ち構えた人さらいにトランクに放り込まれて誘拐される
学校にひとりで行かせられる時代ではなくなっている
家に鍵をかけないでもドロボウに入られない時代は終わりました
実際、そういう田舎の新興住宅地に住んでいるんですが、人を信用していてか、オープン外構ばかりです
心配なので、うちだけ柵をつけて門を付けましたが、そんな我が家で車のイモビライザーが鳴りました
盗難防止対策は必須ですが
5人組の強盗に押し込まれたら、日本家屋なんて、どこも対処出来ない
香港みたいに、ドアの前に鉄格子をつけないとくらせない時代がやってくる
外国人が法を犯しても、なぜか不起訴になるのは何故?
沖縄の米軍だけじゃないんですよ
なんて、理不尽な事がおこりまくっている
もちろん、父親が死んだ事に同調して、女の子を抱きしめる英語教師のような、いい影響もあるにはある
でも、日本にとって害のある風習だらけです
女の子が夜にフラフラ出回って何も無いのがおかしい時代です
ということで、この映画、なんなん?
となるのは当然ではないでしょうか
寝んかっただけマシでしょ
あ、エンディングの歌だけ良かった
あれ、誰のなんて歌かな
人生は一度きり
先を見るだけじゃなくて、今を楽しみましょうみたいな歌詞
この歌だけで、0.5ポイントアップです
永遠に色褪せない少女の絵には、フキなりの大人への抵抗が示されていたように感じた
2025.6.23 一部字幕 MOVIX京都
2025年の日本映画(122分、G)
父の死に直面する11歳の少女を描いた青春映画
監督&脚本は早川千絵
物語の舞台は、日本のとある地方都市(ロケ地は岐阜県岐阜市)
闘病中の父・圭司(リリー・フランキー)と、彼を支える母・詩子(石田ひかり)との間に生まれた11歳のフキ(鈴木唯)は、どこからか手に入れた「子どもたちが泣いているビデオ」を見ていた
見終えた彼女はそれをマンションのゴミ捨て場に捨てに行くものの、そこで不審に思える住人と遭遇した
その後、フキはその男に襲われて殺され、死んだことを実感していない彼女は自分の葬式を目のあたりにしてしまう
だが、一連のこの事柄はすべてフキの想像で、課題の作文だったことがわかる
彼女はこの作文以外にも「孤児になったら」という題名で作文を書き、担任の戸田先生(谷川昭一朗)を困らせていた
母も学校に呼ばれるものの「先生は暇なのかしら」と毒を吐き、「たかが作文じゃないの」と吐きすてた
その後、父の容態は悪化し、入院せざるを得なくなる
当時の日本では末期癌に対する治療は限定的で、父は海外の医療誌などを引っ張り出してきて主治医を困らせていた
ある日のこと、同じマンションの住人・北久里子(河合優実)と遭遇したフキは、彼女の部屋に入れてもらうことになった
フキは超能力とか催眠術に興味を持っていて、見様見真似で久里子に催眠術をかけていく
すると彼女は、夫が奇妙なビデオを隠し持っていたことを告白し、それを見つけて以降、夫を見る目が変わってしまったと告げた
また別のある日には、英語塾で一緒になったちひろ(高梨琴乃)の三つ編みに興味を示し、友だちになって、彼女の家に招かれることになった
ちひろの家は裕福なようで、母・梨花(西原亜希)はケーキを出してくるものの、父・淳(大塚ヒロタ)の無言の圧に苛まれ、ケーキを買い直しに出掛けてしまう
フキはこの夫婦に不穏なものを感じていたが、別の日にかくれんぼをしていた時に、大事にしてそうな箱の中から「別の女の人と一緒にいる父の写真」、「その女の人が赤ん坊を抱いている写真」などを見つけてしまう
フキはそれとなくちひろが見つけるように仕向け、それが原因かはわからないものの、彼女は遠くに引っ越すことになったのである
映画は、淡々と大人たちの裏の顔を知っていくフキが描かれ、父の死によって動いていく大人の世界というものを体感していく
母は早々に知人に葬式の相談をしているし、死んでもいないのに喪服を部屋に出していたりする
父の会社の同僚(中野英樹&佐々木詩音)も「もう復帰はできないだろう」と考えていた
さらに、母は研修先で出会った男・御前崎(中島歩)の妻・貴和(宮下今日子)が手がけている健康食品を大量に買い込んだり、占い師(天光眞弓)に「恋をしている」と言われて浮き足だったりもしていた
フキは超能力の本で得た知識で母と男を引き離そうと考え、ある術のようなものをかけていく
映画のタイトルは「ルノワール」で、これは劇中でフキが父のために買う絵画のレプリカのことで、購入したものは「イレーヌ・カーン・ダンヴェール嬢」と呼ばれるものだった
ルノワールの作風とか、彼にまつわることが映画と関連しているというふうに捉えがちだが、おそらくは「少女の絵」というところに意味があるのだと思う
この絵は「少女の絵」としては最も有名な作品で、ある伯爵の8歳の長女を描いたものだった
前述の変わりゆく大人たちとは対称的な存在であり、変わらないものとしてのメタファーであると思う
父から見れば「変わらないフキ」であり、フキから見れば「変わらない私」であり、父の死によって変わっていく大人たちへの抵抗にも思える
父の死後は彼女の家に絵が飾られることになるのだが、これは変わらぬ父のメタファーになるのだろう
あの絵を見るたびに思い出すのは、11歳だった時に過ごした父との時間であり、その思い出は色褪せることはない
そう言った想いをフキなりに表現したものが、あの少女の絵であり、直接的な意味を避けるために「ルノワール」というタイトルにしたのかな、と思った
いずれにせよ、少女期に感じたことがテーマになっていて、あの時期の彼女には「大人の感じているもの、発しているもの」を敏感に感じ取る力があったのだと思う
それによって、見たくない部分も見てしまうことになり、いずれは自分が身につけてしまう大人の事情というものを先取りしているようにも見えた
あの絵があることで、フキなりに抵抗を見せていたことがわかるのだが、いずれはそう言ったものも変わってしまうのだろう
でも、父が存命中に動き出す必要はないので、いささか心が離れているとしても拙速に思えたのだろう
そう言った感覚が当時の監督にあって、それを印象的な映像に作り込んだのかな、と感じた
かなりふわっとした映画
ちょっと期待し過ぎたのはカンヌコンペ作品だからだろう。予告編から相米慎二の『お引越し』味があちこちにみえたが、『こちらあみ子』の森井監督もそうだけどこの世代への圧倒的な影響力を感じつつ、早川監督としては前作『PLAN75』からまた大きく舵を切ってきたなあとある意味期待もあった。
『こちらあみ子』に比べても思ったよりスケッチ映画で、そのスケッチの一部分の、特に浦田秀穂の被写体に迫っていくところのカメラやロケ地の抜けの景色の良さがかなり魅力的ではあるものの、それが一向に連続性を持ったカタルシスに向かっていかない。どう繋がるかと思って前半観ていたら、ああこれはスケッチで終わらせるんだな、と思い、淡さの良さは感じつつ、映画としては物足りない。かつ描かれているエピソードのひとつひとつがかなり弱い。弱いのでスケッチにするしかなかったのではという気もしてくる。
おそらく監督の幼年期を彩る超能力番組、キャンプとYMO、テレクラ、両親の関係、すべてがゆらゆらとして不安で心をどこに置いていいかわからない感覚のエピソードがほぼ単発。そしてそれらがだいたい淡いというより薄い。そして面白みがない。主人公もいい子でも悪童でもない。主要登場人物はみんな両面がある。それはいいのだけどだからどうなんだ、というところに向かないふわっとした映画だった。が、『PLAN75』よりはいい。
実験してみる世代
2025年。早川千絵監督。小学校5年生の感受性鋭い少女が、末期がんを患う父、キャリア志向の母、できたりできなかったりする友人、などと触れながら、表面的ではない彼らの本心を見抜いたり挑発したりして大人になっていく、奇跡のようなひと夏の話。
少女は催眠術や透視術にはまり、父親が新興宗教的なものにはまっているあたりに時代感覚が現れている。80年代後半の時代設定は見ているうちになんとなくわかってくるが、監督自身の世代と同じようだ。笠松競馬場が出てくるから岐阜県なのだろうが、だとするとあの印象的な川は長良川か木曽川か。
しかし、重要なことは時代や地域ではなく、少女が催眠術や透視術のテレビや本にはまったときに、自分でやらずにいられないことの方だ。伝言ダイヤルの番号を知ったら電話をかけずにいられないし、同年代の少女の三つ編みが気になったらその髪に触らずにはいられないし、友人の父の浮気写真を見つけたらそれを友人に見つけさせずにはいられない。そして、その危険と隣り合わせの好奇心によって、少女は人間の奥深さを知り、あやうく少女趣味の浪人生の餌食になりかけ、友人ができ、その友人が遠くに引っ越していくきかっけをつくることになる。死期が近い父親に向ける視線も、悲しみよりも好奇心の方が強く、その視線によって、表面的な情緒的関係とは別の関係(透視術の成功)を父親との間に築いている。そしてどうやら母親とはそうした関係にはならないらしい。好奇心旺盛な実験精神によって世界と触れ合っていく少女のあやういひと夏を見事に形象化している作品。
ルノワールは画家の父親の方を指すと作品内で言及されているが、息子の映画監督の方を意識していないわけがないと思わせる広々とした端正な画面と落ち着いた展開。
全209件中、121~140件目を表示