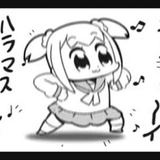ルノワールのレビュー・感想・評価
全209件中、21~40件目を表示
映画でなくては表せない生の凹凸
【ルノワール】
初めての長編監督作『PLAN 75』でカンヌ映画祭のカメラドール(新人監督賞)をいきなり受賞した早川千絵監督の第2作です。
11歳の少女フキが覗き見る大人の世界を小さなエピソードを織り重ねながら描いた物語。一緒に観た我が家の妻も僕も観終えてから
「相米慎二監督の『お引越し』(1993)の世界だね」
と、全く同じ思いを抱きました。恐らくその影響は受けているのでしょうが決して物真似ではなく、紛れもない2025年の映画でした。『PLAN 75』の様な強いストーリーがある訳ではないのですが、フキの目に映る社会、そして自分自身の危うさが繊細ながらも明瞭な凹凸感で展開します。一つ一つは小さなお話なのかも知れませんが、言葉にしない眼差しや表情・間が、僕自身にもあったかも知れない、そして今も抱えているであろう「生の苦み」の様な物を緩やかに浮かび上がらせます。ストーリーを言葉で説明しただけでは何も伝わらない、これこそ映画の世界です。
何より、フキ役の鈴木唯ちゃんが素晴らしい。子供だけれど何もかもを見透かした様な眼差し。不満だけれど不安な表情。よくぞこんな子供を見つけて来たものだと驚きました。
物語の組み立ても巧みです。冒頭でいきなり「なんじゃこれ?」と思わせて観る者を一気にお話の中に引きずり込みます。そして、物語と直接関係のないライディーン(YMO)のダンスを観る者の脳裏に強烈に刻み込むのです。これも監督の周到な計算なんだろうな。僕は大好きです。
明らかな目的が
昭和末期の家庭を覗き見するような怖さ
劇中に出てくる国鉄のカレンダーによれば舞台は1987年。途中、中学生が両親と祖母を殺害した事件(1988年)のニュースも出てくる。テストで平均点を下回ったらお小遣いナシという子育て方針の家だったとか。
そのような昭和末期の、「真面目を極めた末に正気を保てなくなっている」家庭が描かれる。リリー・フランキー演じる父は末期のがん。看病と家計のため孤軍奮闘する母を石田ひかりが演じている。この家庭のほころびを11歳のフキちゃん(鈴木唯さん)の視点で残酷に暴く。
このお母さんが印象的で、父の死を見越して葬式や喪服の準備までしている。「私は先のことまで考えているのよ」とフキに言い訳するが、必死であるがゆえにどこか空洞化してしまった価値観を体現しているようだ。
父の病室に部下が律義に訪れるけれど、後で「もう職場に帰ってこないだろう」と陰口を囁く。フキちゃんが習い事に通う英会話教室では丁寧なおもてなしが意地悪さを際立たせる。人間関係の儀礼がまだ生きていて、でも形骸化しているところがリアル。
しかし、残念ながら肝心のフキちゃんにキャラクターの核のようなものが感じられなかった。映画『こちらあみ子』のような奔放な個性でも、『夏の終わりに願うこと』『aftersun』のような父の死を予感する少女の感性でもない。ただ大人の痛々しさを暴く「眼」の役割だったのだろうか。
ラストでフキのテレパシーごっこにつきあう母。鋭敏な少女ではなく、老獪な母こそ、この映画を通じて成長した勝者だったかもしれない。
構成について、起承転結のはっきりした映画が見たいわけではないが、今作は「転」のあとにまた「承」が続くような場面が気になった。描く順序を変えても大差ないのでは、とも。何度か「ここで終わり?」と思いながら観てしまったのは、相性が合わなかったということだろう。
無題
まず、なぜ主人公フキはおかっぱあたまの大きめのシャツに半ズボンなのか。
最後まで理由が見えてこない。
80年代の思い出を連ねただけに見えてしまうシーンの連なり、
「死」に対しての、フキの、恐怖や不思議、興味などの話なのかと思いきや、その辺りは冒頭のみで、そのあとは薄らいでいくし、
子供から見た大人たちの不思議やおかしさ、その影響によるやりきれなさ、そして成長、という話でもない。
予告で使われていた大型客船のシーンも、予告用でしかない。
色々きつかったです。
考えるな、感じろ的昭和原風景
「カンヌノミネート」
哀しみを背負いながら生きていく
酷暑の中の平日休み、観そびれてたルノワールを鑑賞してきた。
難解でシュールな作品なのかと想像していたが、予想とは違っていた。
人は哀しみを背負い、感情と折り合いをつけて生きていく。
作家性の強い、抽象的な作品なのかと想像して鑑賞したが、人間が生きていく日常と、必ず訪れる死を誇張する事なく描いた作品であった。
もうその時が訪れるであろうとする、闘病中の父への子供からの視点。
父を失う恐怖心や哀しみではなく、不思議な感覚。
ありのまま出来事を受け入れ、時間は経っていく。
ダイヤルQ2で出会った男。
仕事をしながらも旦那の闘病を支える妻。
思い通りにいかずの八つ当たりや、感情の逃げ道のような恋心。
癌になりながらも仕事復帰を目指し、怪しい団体に投資して希望を託すものの願いは叶わず、最後の親子の時間に過ごす競馬場。
その競馬場の切なさ。
人は哀しみを背負いながら生きていく。
そして教科書通りには生きてはいけない。
寄り道はきっとある。
切ない寄り道かもしれない。
それは人間だから。
だけど人の死は必ず訪れるもの。
人生は一度きり。
そんな哀しみも背負いながらも、人生を楽しく充実させるべき。
他者の死から自らの生を感じる作品であった。
そこはかとないユーモア
いつもの映画館 久々
祝日だけど月曜日なので会員サービスデーだと
監督の前作がよくて楽しみにしていた一作
上映が今日までだったので滑り込み
一言でいうと
背伸びしがちな小5の少女が
大人の世界に触れるという物語かと
で両親を含むその大人たちが
必ずしも善人ではない
で少女も決して純心無垢ではない
友達に父親の浮気の写真を見つけるようにしむける
オラが勝手に期待しているセオリーを裏切る
そういうところが監督の狙いなのかもしれない
今書いていて整理したらそういうことかと
ただ好みではない
なんだかエピソードがツギハギというか
あまり必然性を感じなくて
石田ひかりのエピソード
パワハラの研修に行ってどうしてそうなるのか
手相見のエピソードもうーん
河合優実のエピソードって何
冒頭シーンとつながっているのか
そもそも誰だっけ
心理学男のくだり
橋からオヤジが連れ帰る
現実と夢のシーンが整理されずに
出されるような居心地の悪さがいくつかあった
もう少し説明があってもいいような
前作と共通するそこはかとないユーモアは感じた
中島歩のシーンとか喪服のシーンとか
まぁ他の人のレビューを早く読みたい系だな
フロントライン でっちあげといい流れで来ていたが
小休止だな
終了後は炎天下の市役所前ベンチ
何とかギリギリ日陰を見つけた
缶ビール2本と自作弁当
どうやら猛暑日だったようだ
出鱈目
少女の不穏な視点でみた不穏な世界
評判以上 子どもをうまく捉えていた
なんだか聞こえてくる口コミが悪く、見る気が失せていたのだが、観てよかった!
監督の撮りたいものが撮れた作品だと思う。
それに応えた役者さんたちも素晴らしい。
序盤から最後まで目が離せずのめり込めた。
なんだかんだ色々あるけど、自分にとって良い映画ってのはそういうとこが大事だと思ってる。
小5らしさ、死や悲しみへの疑問、好奇心、無邪気な悪気。かなりリアルに描かれていたと思うし、演じる相手へ投げかけるようなフキの視線もとても素晴らしかった。こちらへも投げかけられていたと思う。
映画というスクリーンでみる作品として頭一つ抜けている作品だと感じた。
河合優実さんとの共演シーン、恐ろしく完璧じゃなかったか?あのテンポ、空気感。他人と自分の境界。色んなものが詰まっていて痺れました。
スクリーンで観ることができて良かった。
個人的新人賞です。いいものみれたなー
フキの視点
人間として逃れられない
身内の死の現実を目の前にして
薄情にも滲み出てくる人間の本質の数々。
子供だが大人になりかけ、危うさも
ありつつ、どこか冷静。
あの相手を覗きこむ仕草と表情は
はっとする。
どう受け止めたら良いのか、処理すれば
良いのか、少女の一夏の経験が
凝縮している。
彼女の目線でフキの考え。
子供の頃の自分を思い出す
人間くささも感じる映画。
微かな幼少期のにおい
自分の話でもあるようでないような。でも、確かにあの時に感じた記憶を呼び戻す様な作品であった。
突然、何かを触りたくなったり、意地の悪い事をしてみたり、やってはいけないことをやってみたり。
大人の返事に、ハキハキと大きな声で答えたり。
大人の言う事を聞いてはいて、一見は意思疎通が取れている様に見えて、そこにはいないと言うなんとも危うい状態を見事に表現されていたと感じた。
自分も親として振り返ってみると、この映画で出てくる人物達の様に、本当に身勝手で自分のことしかつくづく考えていないなとこの映画観て思い直した。
(父、母、不倫相手、その妻、友達の親、同じ病室のばぁさん、アイツ!)
誰かの為などと言い訳ならべて、子供を自分の思い通りにしようとする姿。頭が痛かった。。。
子供を一人の人間であると捉えて接しよう、でないと寂しさの余りに一線を越えてしまうのかもしれない。ちゃんと、聞いて、見て、向き合おうと思えた作品でした。
最後、フキが少し成長した姿となり寂しい様な、でも母を見る目は子供の様な。カードの答えは合っていたのか合っていなかったのか。私は、カードの答えは合っていたのではないかと思う次第です。
11歳に戻って観てみたい。
大人にとっては大したことの無い出来事かもしれないけど、フキにとっては全てが刺激的で、知らずにはいられない。その好奇心のみで真っ直ぐに行動してしまう子供らしさや、だけど11歳という少し大人に近づいてきている部分もあって、しっかり人を見ているので空気を読むこともできる部分に、子供から大人への成長する過程の葛藤を感じた。なんでこんなことを?それはなに?みたいなシーンや行動も多かったと思うが、それが11歳のフキからの視点であり、大人になってしまった私たちには素直に受け止めれないのだと思うとすこし寂しさもあったり。
だから、11歳に戻ってもう一度観てみたい。そうすると感じ方も共感できる部分も増えるのでは無いかと思った
近未来から過去まで命の尊厳を撮る
カンヌに出してるプラン75の監督が作った少女の成長を描いた作品くらいを前提知識として観に行ったが、作中でも終わっても思ったのがこれは人の命の尊厳をテーマに作った作品と思えた。戦争談や映像見たり飼ってる魚で死んだものを何気なくすくうシーンがあったり、これは私だけ思ったことかもしれないがキャンプファイアーの火の粉が空襲に思えた。
質疑で監督はああ答えたが恐らく空襲に模したものだと思う。そして父の死をあまりにあっさり報告するからなぜウソを言うのだろうと思ってしまった。
フキをあのようにとったのには考え有っての事だろう。もっといろんな経験をして成長をと思ってたから力石以上に強烈な死に思える。そして船でのダンスは私は生きてるのよと訴えかけたように取れた、波のカットを入れたのはルノワールだけに北斎を意識してるのではないだろうか。
「ストーリーが明確でなくても楽しめる早川千絵監督作品」
小学五年生の少女フキが主人公。つまりこの映画は、少女の視線から描写されている。少女がある事柄をわかる、知ることは、事柄の全体像ではなくある断片に限られていく。「なんとなくわかる、知る」というイメージだ。だからこの映画には明確なストーリーはない。なぜならフキの視線の断片の寄せ集めだからだ。
フキが置かれている家庭環境の断片が二つの作文にあらわれる。超能力、催眠術、カード当て、テレビから得た情報の断片をうけてフキはやってみる。ただ不思議な描写が入り込む。夫を亡くした女性にフキが催眠術をかける。催眠術がきいているのかいないのかわからないが、女性は自分の思いをストレートに語るシーンのみがストーリーになっている。なぜなら彼女は大人であり物事の全体像をはっきりと把握できるからだ。
少女と大人の区別を明確にし、なおもフキの断片を描写していく。少女同士の遊び。何かを見つけたフキ。この遊びにフキの残酷性の断片を見る。伝言ダイヤルにはまり、大人の誘いに軽々とのってしまう危うさと未熟さの断片。病院でルノワールの絵を見つめるフキの断片。ガン末期の父の病室に飾られるルノワールの絵の断片。父親が一時帰宅したとき、父が部屋を開けると母の喪服がつるされ準備されていたのを見た瞬間、フキは電気を消し部屋を閉める優しさの断片。母がなんとなく浮気している男の周りを自転車でぐるぐる回り無視して走り去る断片。父が亡くなっても覚悟をしていたからたんたんとし、ルノワールの絵をはずして自分の部屋に飾り、父のことは忘れないという優しさの思いのこもった断片。
この断片の数々がフキの記憶となり人間形成の一部になる。様々な大人の断片を見て経験して、やがて物事の全体を把握できる大人に成長していく。しかしはっきりわかるということは、幸せと結びつかないこともいずれ知るだろう。
様々な断片を見てきたフキが、いつか光り輝く青空の下、クルーズ船上で満面の笑顔で踊っている姿を想像する断片。未来に希望を持っているフキに、よしと思った。
「語られぬ感情、映し出される世界」
「ルノワール」|早川千絵監督作品
映画館で鑑賞
早川千絵監督の新作『ルノワール』は、一人の少女の視点を借りて、時代と社会を鋭く見つめる異色の作品である。舞台は1980年代、少女の目を通して映し出されるのは、家庭や社会の中で静かに進行していく歪みや違和感の数々だ。だがこの映画は、決してセンセーショナルに問題を暴いたり、分かりやすい感動に収束したりする作品ではない。
主人公の少女・フキは、ごく淡々とした表情で、どこか達観したように世界を眺めている。彼女の行動は時に挑発的でさえあるが、それは言葉に置き換えられることなく、意味を明かすこともない。ただ、そこにある事実や現象に静かに反応するのみだ。その沈黙が、逆に観る者に多くを語りかけてくる。
印象的なのは、登場人物たちが抱える苦悩や不和が、あくまで“描かれる”ことに留まり、“解決”や“癒し”へとは向かわない点である。日常の中に潜む重さや、愛情のすれ違い、不意に訪れる破綻──それらは物語の中で特別な扱いをされることなく、ただ静かに通り過ぎていく。感情を爆発させる場面も、明快なメッセージもない。むしろ、判断を保留するまなざしが貫かれていることが、この作品の核心と言えるだろう。
フキは、常に一歩引いた距離で周囲を観察する。だがそれは無関心ではない。彼女なりのやり方で、身の回りに起きる出来事と向き合い、対峙している。その姿勢は、私たち観客にも静かな問いを投げかけてくる──「世界をどう見るのか」「何を感じ、どう振る舞うべきなのか」。
作品の終盤、ある楽曲がエンドロールに重なって流れる。それは単なる救済のメッセージではない。むしろ、混沌とした現実の中でも、私たちには人生を選び直す力があるのだと、そっと背中を押してくれるような優しさに満ちている。
ここにあるのは、“悲しみの物語”ではなく、“悲しみの中でも生きていくこと”を描いた映画なのだ。
『ルノワール』は、物語のわかりやすさやカタルシスを求める人には、ややとっつきにくく映るかもしれない。だが、この作品が本当に提示しているのは、「人生の観察者」としての視点。何が正しく、何が間違っているのかを断定しないまなざしで、社会や人間を見つめるその姿勢こそが、今の私たちに最も必要な“まなざし”なのかもしれない。
全209件中、21~40件目を表示